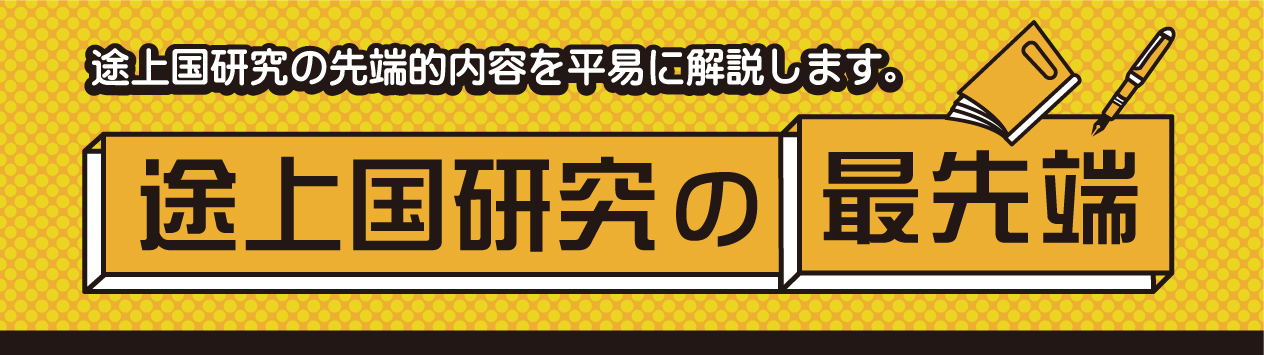IDEスクエア
コラム
第66回 所得が中位以上の家庭から保育園に通うと知的発達が抑えられます――イタリア・ボローニャ市の場合
Daycare use at age 0-2 had negative impacts on intellectual capacity of children from upper half wealth class in Bologna
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00053561
2023年1月
(4,499字)
今回紹介する研究
Margherita Fort, Andrea Ichino, and Giulio Zanella. 2020. “Cognitive and noncognitive costs of day care at age 0-2 for children in advantaged families.’’ Journal of Political Economy, 128 (1) January: 158–205.
高まる保育ニーズ
政府が「すべての女性が輝く社会」を目指しているなか、「保育園落ちた、日本死ね」とブログに投稿し、保育のために退職する羽目になった女性のことが国会で取り上げられたのは2016年2月末。7年経って「待機児童」数は劇的に減ったが、一部地域では0-2歳児を中心に「待機児童」が数多くいる1。今でも保護者はどうすれば保育園に入ることができるかを考えて保活をしている。もちろん、保育園に通うことが家庭にとって最善の選択と考えていることだろう。こうした選択は男女の労働参加が進む国では増えている。OECD各国の保育園就園率は上昇傾向にあり、日本でも0-2歳児は16.2%(2005)→ 32.6%(2018)となった。
でも、保育園に通うと知的発達が妨げられるかもと言われたら、保活中の保護者はたじろぐのではないだろうか。今回紹介する研究の著者たちは、イタリア・ボローニャ市のすべての公立保育園のデータを使い、0-2歳児での保育園通園が家庭保育に比べて知的能力(8-14歳時点)に与える効果を推計した。すると、保育園に応募した家庭のうち、所得上位半分の家庭の子どもは、通園によって家庭保育よりも知的能力が減ることが判明した。所得下位半分の子どもには負の影響はなかった。著者たちは、所得上位半分の家庭では家庭保育の質が良好であるため、保育園保育の質は相対的に見劣りし、通園が子どもの知的発達にとって損失となる、と解釈している2。
データ
著者たちはボローニャ市から2001-2005年に保育園の0-2歳児クラスに応募した全員のリストと応募書類に記載された情報、そして、各園の入園者と通園日数を入手している。これにより、誰がどの園をどの順番で希望し、どの園から入園許可が出て、どの園に何日通ったかが分かる。応募書類には住所、学歴、年収、就労状況を示すので、各家庭の社会経済背景や通園距離も分かる。これらに加え、著者たちは2013-2015年に応募者に調査への招待状を送り、知的能力を計測した。応募者リストには6575世帯9667人の子どもが記載されており、うち、招待状送付は効果推計に適した(後述)1383世帯、調査応諾は444世帯であった。知的能力はIQに加え、ビッグ5と呼ばれる5因子(開放性、誠実性、外向性、協調性、神経症傾向)を計測した。
入園選考方法と推計方法
ボローニャ市の入園選考方法は日本の自治体における選考方法と似ている。入園希望者は障害の有無などのカテゴリによって優先順が決められる。本研究では両親が就労中のカテゴリのデータを用いている。この両親就労カテゴリにおいて、子どもは経済的余裕を示すFA指数(family affluence index、所得などから計算)によって順位付けされる。一方、保護者は優先順位を付けた希望園リストを自治体に提出し、自治体は集計して各園について入園を許可するFA指数の上限値(入園カットオフ値)を決める3。
保護者には入園カットオフ値を予想できない。保護者からすれば、入園カットオフ値はランダムである。言い換えれば、入園カットオフ値の周辺では、自分が入園カットオフ値よりも下にいる(入れる)か上にいる(入れない)かはランダムなので、入園許可があたかもランダムに割り振られていると見なせる。つまり、入園カットオフ値の周辺で局地的に入園許可実験をしているようなものだ。このような状況で入園が可能になったときに子どもの知的発達に変化があるとすれば、入園によって知的発達が変化したという因果関係として特定できる。
入園カットオフ値の周辺だけに限定して推計するこの方法は、回帰不連続デザイン(regression discontinuity design: RDD)の局地ランダム化(local randomization)という4。著者たちは入園カットオフ値がランダムであることを注意深く検証し、カットオフ値が前年値とほぼ無相関であることや、カットオフ値を正確に予測して家計が所得を減らしたりする操作をすると発生するFA指数特定値への家計数の集中がないことなどを確認している。その上で入園許可は入園カットオフ値の周辺でランダムと判断し、著者たちは10年以上経ってからカットオフ値の周辺の入園希望者1383世帯に調査招待状を送り、入園許可者と入園非許可者の知的能力平均値の差を入園許可の効果(治療意図による効果、intention-to-treat effect)として示している。
推計結果
調査招待に応じた444名の元入園希望者は保育園に通うとIQが4.8%、開放性が8%、協調性が6.8%減り、神経症傾向が5.1%増えた。ジェンダー差が顕著で、この結果は主に女子に与えた効果を反映したものであり、男子に与えた効果は統計学的にゼロであった。著者たちは女児の知的発達が男児よりも早いという先行研究を根拠に、相対的に質の低い保育の影響は発達がより先鋭な女児に多く現れたのではと解釈している。
先行研究との対比
発達心理学では、保育園は知的発達に負の影響があると以前から指摘されていた(Belsky and Steinberg 1978; Belsky 1988, 2001)。家庭保育の質が子どもの知的発達に正の影響があることも指摘されてきた(Hart and Risley 1995; Rowe and Goldin-Meadow 2009; Cartmill et al. 2013; Gunderson et al. 2013)。よって、本論文で示されたショッキングな負の効果も、実は驚くには当たらない。一方、経済学分野では保育園通園が知的発達に対して正の効果があったとする推計もある。ノルウェイ(Drange and Havnes 2019)、ドイツ(Felfe and Lalive 2018)、日本(Yamaguchi, Asai and Kambayashi 2018)を扱った研究である。ただし、経済学分野でもカナダを対象に負の効果(Baker, Gruber and Milligan 2008)を見出しており、効果は正負混在している。
カナダ(Kottelenberg and Lehrer 2017)や日本の研究では、経済的に困窮している家庭の園児には正の効果があったとも指摘されており、この点は負の効果が所得の高い層に限定されていた本論文と整合的である。推計結果を家庭保育の質の高低で理解する本論文の解釈も、家庭の富裕度で効果の違いを見出した先行研究と整合的である。
なぜか――メカニズム
保育園への通園で知的発達が抑えられるのは、信頼する大人との質の高い一対一の接触が減るから、と著者たちは解釈している。保育園で子どもと大人は多対一で接触する。大人は、学んでいることが対象特殊か一般性を持つか簡単に教えることができる。子どもが大人を信頼していると、子どもは素直にその教えを受け取り、対象特殊か一般性を持つか試行錯誤せずに済むので学びの効率が良い、という説である(Csibra and Gergely 2009; 2011)。これが正しいとすれば、1. 一対一の接触が多く、2. その質が高く、3. 子どもが大人を信頼しているときには、知的能力が発達しやすい。逆に、保育園に行くことで3つの条件のうち1つでも欠ければ、子どもの知的発達は抑えられる。
信頼できる大人との質の高い一対一接触というメカニズムが背後にあることを直接示す証拠は本論文にない。しかし、正の効果が計測されたノルウェイ、ドイツ、日本の園児/保育士の比率は0歳児で3:1であり、イタリアの4:1よりも少ない。1歳児以降はノルウェイとドイツは3:1に留まる一方、日本では1-2歳児クラスは6:1、3歳児クラスは20:1、イタリアは1-2歳児クラスが6:1なので、日本は例外として、保育園通園の知的発達に与える正の効果が示された国では一対一の接触が多い5。そして、所得の低い家庭ほど保育園の負の効果が観察されないことは、保育園保育は低所得の家庭保育よりも質が低くないという想定と整合的である。3. の大人を信頼しているかどうかは傍証すらないので未確認である。
信頼できる大人との質の高い一対一接触にはある程度の根拠がある一方、今まで論者が示してきた他のメカニズムはいずれも弱点があって、今回の結果を説明するのは難しいことを著者たちは示している。列挙すると、
- 保育園での感染症罹患(なぜ女児だけ負の影響か?)
- 通園すると保護者が育児に関心を持たなくなる(なぜ女児だけ負の影響か?)
- 母親との接触の減少(なぜ女児だけ負の影響か? ボローニャのデータで家庭保育者は母親以外が半分程度なので、家庭保育でも母親に接していない子どもは多い)
- 保育園で男児が多いと活発ゆえに女児への世話が薄まる(園児性比率を推計で考慮しても結果に変化なし)
- 母乳育児が減るから(母乳育児は保育園利用日数と相関なし)
である。
著者たちの解釈は、現状では反駁されていない数少ないメカニズムの1つである。ただし、国ごとに制度や保育士配置数以外の保育内容が異なり、さらに、各研究で推計方法・識別仮定の信頼性も異なるため、知的発達への効果推計結果にこれらの差違が影響している可能性もある。文献全体のまとめとして主な原因を保育士配置数に帰して良いのか、慎重になるべきかもしれない。また、保育園は家庭にはない社会経験を得られる長所があるのに、開放性や協調性などの社会性に関わる知的能力の発達が家庭保育より劣るという結果は意外である。今後、なぜそうなるかを示す保育内容などにも踏み込んだ研究が待たれる。
途上国への示唆
人的資本投資が個人だけでなく国を豊かにする決定打だとすれば、本研究は保育園が整備されていない途上国にも示唆がある。たとえば、インドでは農村にも保育園機能を持たせるようになったが、筆者が10年以上前に垣間見たのは、狭い屋内に小さい子どもが多数収容され、保育者の老婆が子どもに対し棒を使って躾ている姿だった。もちろん、現在の代表的な保育風景と言うつもりはないが、中等以降の教育、英語による教育、STEM教育が強調されるなか、今でも乳幼児保育の優先順位が低いのは変わっていない。保育施設や保育士の能力の貧弱さはそれを物語っている。もしも、認知能力(IQ)と非認知能力(ビッグ5など)を高めたいのであれば、中等以上の教育よりも、保育園の質を高めることに予算を使う方が容易で社会的収益率も高いかもしれない。若年人口が多い途上国こそ、本研究と同じ視角での知見の積み上げが望まれる。
参考文献
-
Baker, Michael, Jonathan Gruber, and Kevin Milligan. 2008. “Universal Child Care, Maternal Labor Supply, and Family Well‐being.” Journal of Political Economy 116 (4): 709–45.
- Belsky, Jay. 1988. “The ‘Effects’ of Infant Day Care Reconsidered.” Early Childhood Research Quarterly 3 (3): 235–72.
- ———. 2001. “Emanuel Miller Lecture: Developmental Risks (Still) Associated with Early Child Care.” The Journal of Child Psychology and Psychiatry 42 (7): 845–59.
- Belsky, Jay, and Laurence D. Steinberg. 1978. “The Effects of Day Care: A Critical Review.” Child Development 49 (4): 929-49.
- Cartmill, Erica A., Benjamin F. Armstrong, Lila R. Gleitman, Susan Goldin-Meadow, Tamara N. Medina, and John C. Trueswell. 2013. “Quality of Early Parent Input Predicts Child Vocabulary 3 Years Later.” Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (28): 11278–83.
- Cattaneo, Matias D., and Rocío Titiunik. 2022. “Regression Discontinuity Designs.” Annual Review of Economics 14: 821–51.
- Csibra, Gergely, and György Gergely. 2009. “Natural Pedagogy.” Trends in Cognitive Sciences 13 (4): 148–53.
- ———. 2011. “Natural Pedagogy as Evolutionary Adaptation.” Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 366 (1567): 1149–57.
- Drange, Nina, and Tarjei Havnes. 2019. “Early Childcare and Cognitive Development: Evidence from an Assignment Lottery.” Journal of Labor Economics 37 (2): 581–620.
- Felfe, Christina, and Rafael Lalive. 2018. “Does Early Child Care Affect Children’s Development?” Journal of Public Economics 159: 33–53.
- Gunderson, Elizabeth A., Sarah J. Gripshover, Carissa Romero, Carol S. Dweck, Susan Goldin-Meadow, and Susan C. Levine. 2013. “Parent Praise to 1- to 3-Year-Olds Predicts Children’s Motivational Frameworks 5 Years Later.” Child Development 84 (5): 1526–41.
- Hart, Betty, and Todd R. Risley. 1995. Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children, Paul H. Brookes Publishing.
- Kottelenberg, Michael J., and Steven F. Lehrer. 2017. “Targeted or Universal Coverage? Assessing Heterogeneity in the Effects of Universal Child Care.” Journal of Labor Economics 35 (3): 609–53.
- Rowe, Meredith L., and Susan Goldin-Meadow. 2009. “Differences in Early Gesture Explain SES Disparities in Child Vocabulary Size at School Entry.” Science 323 (5916): 951–53.
- Yamaguchi, Shintaro, Yukiko Asai, and Ryo Kambayashi. 2018. “How Does Early Childcare Enrollment Affect Children, Parents, and Their Interactions?” Labour Economics 55: 56–71.
著者プロフィール
伊藤成朗(いとうせいろう) アジア経済研究所 開発研究センター、ミクロ経済分析グループ長。博士(経済学)。専門は開発経済学、応用ミクロ経済学、応用時系列分析。最近の著作に「南アフリカにおける最低賃金規制と農業生産」(『アジア経済』2021年6月号)、主な著作に“The effect of sex work regulation on health and well-being of sex workers: Evidence from Senegal.”(Aurélia Lépine, Carole Treibichと共著、Health Economics, 2018, 27(11): 1627-1652)など。
注
- 厚労省の「待機児童」数の算出方法に問題があり、入園可能性が上がると「待機児童」数は増えるため、受け入れ可能児童数が増加しても「待機児童」数が必ずしも減らないことはよく知られている。
- 公立保育園に行かない子どもは家庭保育ではなく私立保育園に行っているかもしれない。しかし、ボローニャは公立保育園の質が高いと見なされているために、私立保育園は僅かしか存在していない、と著者たちは述べている。
- 日本の自治体で見られるように、兄や姉が通園していると入園許可を得やすい、ということはないので、入園許可が育児負担の高い家庭に集中して知的発達に影響する、という可能性はない。
- 最も頻用される局地線形回帰を使うRDDと違い、局地ランダム化はカットオフ値の前後でスコア(FA指数)と介入後の結果(入園後の知的能力)に相関がない、つまり、自己選抜がないという仮定が追加して必要である(Cattaneo and Titiunik 2022)。
- Yamaguchi, Asai and Kambayashi(2018)は保育士配置基準が6:1である2.5歳時点での保育園通園の効果に着目し、自治体の保育カバー率(受け入れ可能人数/該当年齢人口)と親の教育年数との交差項を操作変数として推計、サンプル全体で言語能力への正の効果を計測している。なお、ボローニャ市内での保育士配置数の違いやその効果を観察することは難しい。なぜならば、多くの園で配置基準ぎりぎりで遵守していて、各園で違いがあまりない可能性が高いためである。仮に、各園の保育士配置数に十分な差があったとしても、知的発達には園の運営方針という観察できない要因も影響し、同時に運営方針は保育士配置数にも影響するので、質の高い運営方針の園は知的発達も高く保育士配置数も多くなる。このとき、「保育士配置数と知的発達の関係」には運営方針も影響しているため、「保育士配置数が知的発達に与える効果の因果関係」と解釈することはできない。
- 第1回 途上国ではなぜ加齢に伴う賃金上昇が小さいのか?
- 第2回 男児選好はインドの子供たちの発育阻害を説明できるか
- 第3回 子供支援で希望を育む
- 第4回 後退する民主主義
- 第5回 しつけは誰が?――自然実験としての王国建設とその帰結
- 第6回 途上国の労働市場で紹介が頻繁に利用されるのはなぜか
- 第7回 絶対的貧困線を真面目に測り直す――1日1.9ドルではない
- 第8回 労働移動の障壁がなくなれば一国の生産性はどの程度向上するのか
- 第9回 科学の世界の「えこひいき」――社会的紐帯とエリート研究者の選出
- 第10回 妻の財産権の保障がHIV感染率を引き下げるのか
- 第11回 飲酒による早期児童発達障害と格差の継続――やってはいけない実験を探す
- 第12回 長期志向の起源は農業にあり
- 第13回 その選択、最適ですか?――通勤・通学路とロンドン地下鉄ストライキが示す習慣の合理性
- 第14回 貧困者向け雇用政策を問い直す
- 第15回 妻(夫)がどれだけお金を使っているか、ついでに二人の「愛」も測ります
- 第16回 先読みして行動していますか?――米連邦議会上院議員の投票行動とその戦略性
- 第17回 保険加入率を高めるための発想の転換
- 第18回 いつ、どこで「国家」は生まれるか?――コンゴ戦争と定住武装集団による「建国」
- 第19回 婚資の慣習は女子教育を引き上げるか
- 第20回 産まれる前からの格差――胎内ショックの影響
- 第21回 貧困層が貯蓄を増やすには?――社会的紐帯と評判
- 第22回 農業技術普及のキーパーソンは「普通の人」
- 第23回 勤務地の希望を叶えて公務員のやる気を引き出す
- 第24回 信頼できる国はどこですか?
- 第25回 なぜ経済抗議運動に参加するのか――2010年代アフリカ諸国の分析
- 第26回 景気と経済成長が出生率に与える影響
- 第27回 消費者すべてが税務調査官だったら――ブラジル、サンパウロ州の脱税防止策
- 第28回 最低賃金引き上げの影響(その1) アメリカでは雇用が減らないらしい
- 第29回 禁酒にコミットしますか?
- 第30回 通信の高速化が雇用創出を促す―― アフリカ大陸への海底ケーブル敷設の事例
- 第31回 最低賃金引き上げの影響(その2)ハンガリーでは労働費用増の4分の3を消費者が負担したらしい
- 第32回 友達だけに「こっそり」やさしくしますか? 国際制度の本質
- 第33回 モラルに訴える――インドネシア、延滞債権回収実験とその効果
- 第34回 「コネ」による官僚の人事決定とその働きぶりへの影響――大英帝国、植民地総督に学ぶ
- 第35回 カップルの同意を前提に少子化を考える
- 第36回 携帯電話の普及が競争と企業成長の号砲を鳴らす――インド・ケーララ州の小舟製造業小史
- 第37回 一夫多妻制――ライバル関係が出生率を上げる
- 第38回 イベント研究の新しい推計方法――もう、プリ・トレンドがあると推計できない、ではない
- 第39回 伝統的な統治が住民に利益をもたらす――メキシコ・オアハカ州での公共財の供給
- 第40回 なぜ勉強をさぼるのか? 仲間内の評判が及ぼす影響
- 第41回 戦争は増えているのか、減っているのか?
- 第42回 安く買って、高く売れ!
- 第43回 家族が倒れたから薬でも飲むとするか――頑固な健康習慣が変わるとき
- 第44回 知識の方が長持ちする――戦後イタリア企業家への技術移転小史
- 第45回 失われた都市を求めて――青銅器時代の商人と交易の記録から
- 第46回 暑すぎると働けない!? 気温が労働生産性に及ぼす影響
- 第47回 最低賃金引き上げの影響(その3)アメリカでは(皮肉にも)人種分断が人種間所得格差の解消に役立ったらしい
- 第48回 民主主義の価値と党派的な利益、どっちを選ぶ?――権力者による民主主義の侵食を支える人々の行動
- 第49回 経済的ショックと児童婚――ダウリーと婚資の慣習による違い
- 第50回 セックスワーク犯罪化――禁止する意味はあるのか?
- 第51回 妻が外で働くことに賛成だけど、周りは反対だろうから働かせない
- 第52回 競争は誰を利するのか? 大企業だけが成長し、労働分配率は下がった
- 第53回 農業技術普及のメカニズムは「複雑」
- 第54回 女の子は数学が苦手?――教師のアンコンシャス・バイアスの影響
- 第55回 マクロ・ショックの測り方――バーティクのインスピレーションの完成形
- 第56回 女性の学歴と結婚――大卒女性ほど結婚し子どもを産む⁉
- 第57回 政治分断の需給分析――有権者と政党はどう変わったのか
- 第58回 賄賂が決め手――採用における汚職と配分の効率性
- 第59回 いるはずの女性がいない――中国の土地改革の影響
- 第60回 貧すれば鋭する?
- 第61回 貿易自由化ショックとキャリア再建の男女格差――仕事か出産か
- 第62回 最低賃金引き上げの影響(その4)――途上国へのヒントになるか? ドイツでは再雇用によって雇用が減らなかったらしい
- 第63回 貧困からの脱出――はじめの一歩を大きく
- 第64回 大学進学には数学よりも国語の学力が役立つ――50万人のデータから分かったこと
- 第65回 インドで女性の労働参加を促す――経済的自律とジェンダー規範
- 第66回 所得が中位以上の家庭から保育園に通うと知的発達が抑えられます――イタリア・ボローニャ市の場合
- 第67回 男女の賃金格差の要因 その1──女性は賃金交渉が好きでない
- 第68回 男女の賃金格差の要因 その2――セクハラが格差を広げる
- 第69回 ジェンダー教育は役に立つのか
- 第70回 なぜ病院へ行かないのか?──植民地期の組織的医療活動と現代アフリカの医療不信
- 第71回 貧困層向け現金給付政策の波及効果
- 第72回 社会的排除の遺産──コロンビア、ハンセン病患者の子孫が示す身内愛
- 第73回 家庭から子どもに伝わる遺伝子以外のもの──遺伝対環境論争への一石
- 第74回 チーフは救世主? コンゴ民主共和国での徴税実験と歳入への効果
- 第75回 権威主義体制の不意を突く──スーダンの反体制運動における戦術の革新
- 第76回 紛争での性暴力はどういう場合に起こりやすいのか?
- 第77回 最低賃金引き上げの影響(その5) ブラジルでは賃金格差が縮小し雇用も減らなかったが……
- 第78回 なぜ売買契約書を作成しないのか? コンゴ民主共和国における訪問販売実験
- 第79回 国際的な監視圧力は製造業の労働環境を改善するか? バングラデシュのラナ・プラザ崩壊のその後
- 第80回 民主化で差別が強化される?――インドネシアの公務員昇進にみるアイデンティティの政治化
- 第81回 バングラデシュのラナ・プラザ崩壊のその後(2)――事故に見舞われた工場に発注をかけていたアパレル小売企業は、事故とどう向き合ったのか?
- 第82回 児童婚撲滅プログラムの効果
- 第83回 公的初等教育の普及、それは国民を飼い慣らす道具──内戦による権力者の認識変化と政策転換
- 第84回 先生それPハクです──なぜ実証研究の結果はいつも「効果あり」なのか?
- 第85回 教育の役割──教科書は国籍アイデンティティ形成に寄与するのか
- 第86回 解放の甘い一歩
- 第87回 途上国の医療・健康の改善のカギは「量」か「質」か
- 第88回 人種扇動的レトリックの使用と国家の安定性──ドナルド・トランプの政治集会が黒人差別に与えた影響
- 第89回 都合が良ければ「民主的」、そうでなければ「非民主的」──政治的行動に対する知覚バイアスを探る
- 第90回 融資金を夫から遠ざけることができたらマイクロファイナンスの効果が大きくなるかもしれない
- 第91回 インドのグラム・パンチャーヤトから学ぶ地方自治体の規模が公共財供給に与える影響
- 第92回 ルールにはルールを──シナリオ実験が示す社会規範を形成する法律の力
- 第93回 産まれたらすぐ現金給付を
- 第94回 売買春市場から人身売買をなくすことのできる規制とは?
- 第95回 少数民族政党が民主主義を守るとき
- 第96回 バングラデシュのラナ・プラザ崩壊のその後(3)――途上国で労働法制の実効性を高めるには?
- 第97回 目に見える汚職は氷山の一角――コンゴ民主共和国、交通警察内部の汚職システム
- 第98回 石油の採掘権は誰の手に?地元企業 vs. 多国籍企業
- 第99回 生成AI ―― 労働生産性への効果
- 第100回 統治できない地方議員たち―― インドの小規模都市に見る手続き知識の重要性
- 第101回 貿易アクセスへの断絶は社会を不安定化させるか?――清朝・大運河の閉鎖と騒乱
- 第102回 組織の成果を最大化する報酬体系をシエラレオネのコミュニティ保健プログラムから考える