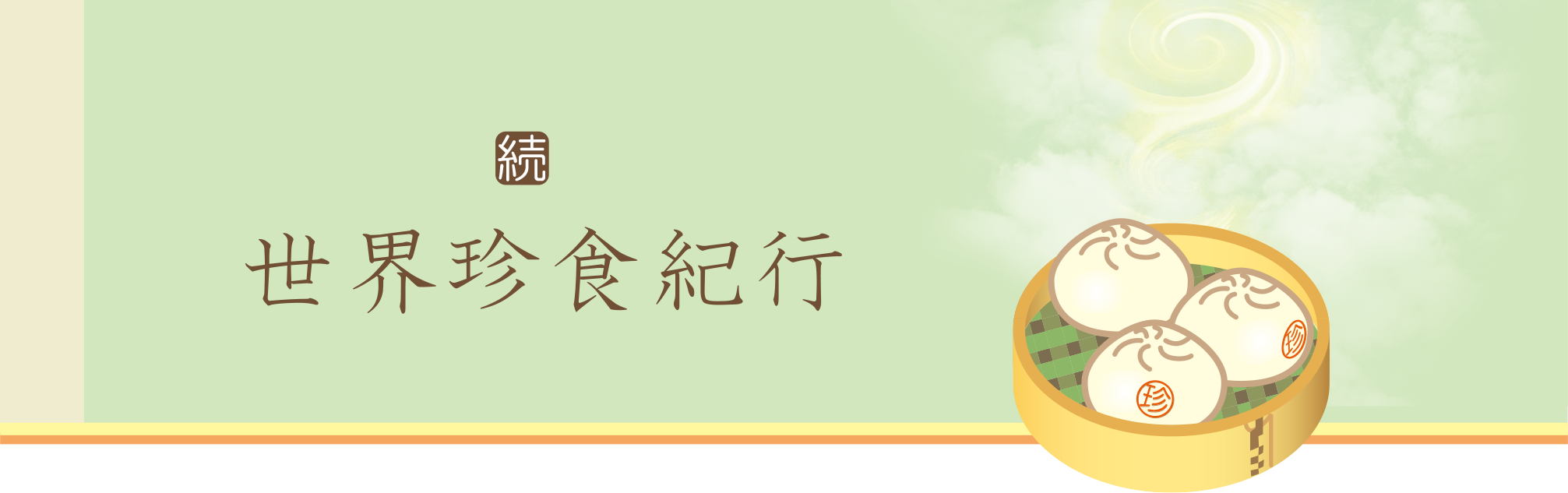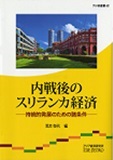IDEスクエア
コラム
第12回 モルディブ――食べても食べてもツナ
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00050927
2019年5月
(1,665字)
インド洋に浮かぶ高級リゾートなんでしょう?
インド洋に浮かぶ高級リゾートの国モルディブ、というとさぞかし贅沢な光景・水上コテージでトロピカル・ジュースなどを飲みながら新鮮な魚介類や南国の果物を堪能している、と想像されるのではなかろうか。確かに非日常を演出しているリゾート島ではそうなのだろう。
モルディブは、リゾートホテルのある島と住民島を分けており、住民島ではリゾート気分は味わえない。特に仕事で訪れる首都マレはリゾートとかけ離れている。まずマレは小さい。楕円形の島で最も長い、島の東西を結ぶ直線道路は2キロに満たない。そこに12万人が住む。ギュウギュウだ。珊瑚礁の島で地盤の強度が十分でないため、高層ビルの建築がすくないので圧迫感はないものの、道は狭く、車とすれ違う際に歩行者は壁に張り付かなければならない。
そしてモルディブは食材の多くを輸入に依存している。そのため、物価は総じて高い。マーケットに行けばモルディブ産の野菜や果物もあるが量は多くないし、大分傷んでいるようにも見受けられる。しかし魚市場や魚加工品、特にカツオやツナ(マグロ)の加工品は豊富だ。

現地の美味しいものを求めて
そんな食材に恵まれない環境の中でも絶対に「現地の美味しいもの」はあるはず、と短い滞在中、「現地の美味しいもの」を探し求めた。隣のテーブルでスパゲティとかステーキを食べている人には目もくれず。アジ研職員の習性のようなものだ。
インタビュー先で何種類ものいろんな形のお茶菓子を提供してくれた時は心が躍った。インドに留学していたことのある先生は、インド的なマシンガントークを炸裂させながらも、我々にお茶とお茶菓子を猛烈に進めてくる。こちらも食べる気満々だ。

まず一口、中身はツナかカツオのフレークとココナツ。ぺろりと平らげて、メモを取りながらもう一つ。中身は魚のフレークとココナツ。形と中身の調合がいささか違うかな。まさかね、と思いつつ三つめもトライ。やっぱり魚のフレークとココナツ。食べても食べてもツナだった。
主食ならきっと、と期待してレストランに入り、ガルディアというローカルフードを注文すると、白いご飯、ツナの切り身が入った透明なスープ、それに少しの生野菜と揚げたツナの切り身が添えられたものが出てきた。これもツナか。なんとまあシンプルで直球なことか。
こうしてモルディブで数日過ごした。狭い首都だったし、土地勘を養うために時間の許す限り徒歩でアポ先を巡った。たまたまとても暑い時期だった。おかげで一気に毛穴が開いたようで、布団に入ると自分の身体からツナのにおいがしているような気がした。
再チャレンジ
モルディブでツナ尽くしに打ちのめされた私は、スリランカを訪れた際にモルディブ料理屋に立ち寄ってみた。モルディブでは食材が少ないから、ローカルフードはあんなにシンプルなんだろう。隣国スリランカでモルディブ人が集まるモルディブ料理屋ならきっとスリランカで得られる豊富な食材を用いてカラフルなガルディアが食べられるのではないか、と推測・期待したのだ。
結果は……カフェ風のこぎれいなレストランで出てきたのはモルディブで食べたのとほとんど同じガルディアだった。

一応、誤解のないよう付け加えておくと、きっと現地の美味しいものはあるのだと思う。滞在期間が短いとか、レストランの選択を誤ったなどの理由で出会えなかっただけで。そう信じている。
写真の出典
- 写真1~3:筆者撮影。
著者プロフィール
荒井悦代(あらいえつよ) 。アジア経済研究所地域研究センター動向分析研究グループ長。著作に『内戦終結後のスリランカ政治――ラージャパクサからシリセーナへ』アジア経済研究所(2016年)、『内戦後のスリランカ経済――持続的発展のための諸条件』(編著)アジア経済研究所(2016年)など。
- 第1回 バングラデシュ――食らわんか河魚
- 第2回 クウェート――国民食マチブースと羊肉のはなし
- 第3回 ラオス――カブトムシは食べ物だった
- 第4回 タイ――うなだれる大衆魚・プラートゥー
- 第5回 トルコ――ラクの〆は臓物スープで
- 第6回 台湾――臭豆腐の香り
- 第7回 カンボジア――こじらせ系女子が食べてきた珍食
- 第8回 インドネシア――1本のサテがくり出す衝撃の味
- 第9回 中国四川省――肉食の醍醐味
- 第10回 ベトナム――「元気ハツラツ」じゃなかったハノイの卵コーヒー
- 第11回 ブラジル――「ツンデレの果実」ペキー
- 第12回 モルディブ――食べても食べてもツナ
- 第13回 フィリピン――最北の島で食す海と人の幸
- 第14回 タンザニア――ウガリを味わう
- 第15回 アメリカ――マンハッタンで繰り広げられる米中ハンバーガー対決
- 第16回 ニュージーランド――マオリの伝統料理「ハンギ」を食す
- 第17回 イギリス――レストランに関する進化論的考察
- 第18回 南アフリカ――「虹の国」の国民食、ブラーイ
- 第19回 デンマーク――酸っぱい思い出
- 第20回 ケニア――臓物を味わう
- 第21回 モンゴル――強烈な酸味あふれる「白い食べ物」は故郷を出ると……
- 第22回 インド――幻想のなかの「満洲」
- 第23回 マグリブ(北アフリカ)――幻の豚肉
- 最終回 中国――失われた食の風景
- 特別編 カザフスタン――感染症には馬乳が効く
世界珍食紀行(『アジ研ワールド・トレンド』2016年10月号~2018年3-4月号連載)
- 第1回「中国――多様かつ深遠なる中国の食文化」
- 第2回「ベトナム――食をめぐる恐怖体験」
- 第3回「気絶するほど旨い?臭い!――韓国『ホンオフェ』」
- 第4回「イラン――美食の国の『幻想的な』味?!」
- 第5回「キューバ――不足の経済の食」
- 第6回「タイ農村の虫料理」
- 第7回「ソ連――懐かしの機内食」
- 第8回「エチオピア――エチオピア人珍食に遭遇する」
- 第9回「多人種多民族が混交する国ブラジルの創造の珍食」
- 第10回「コートジボワール――多彩な『ソース』の魅力」
- 第11回「デーツ――アラブ首長国連邦」
- 第12回「ペルー ――アンデスのモルモット『クイ』」
- 第13回「ミャンマー ――珍食の一夜と長い前置き」
- 第14回「『物価高世界一』の地、アンゴラへ――ポルトガル・ワインの悲願の進出」