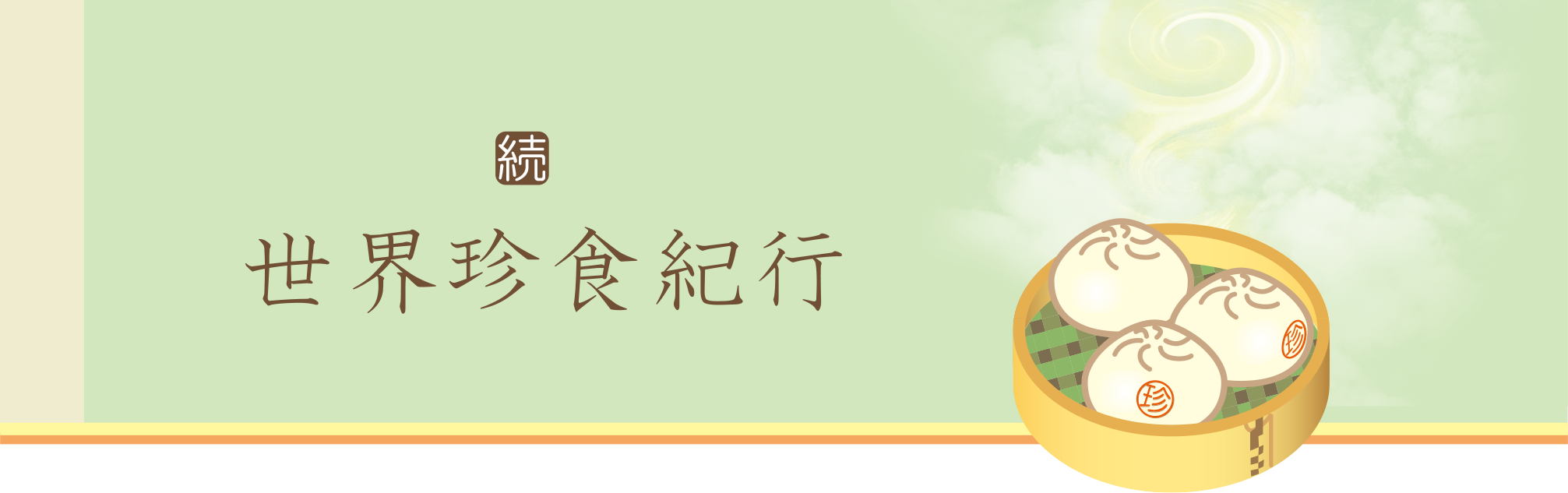IDEスクエア
コラム
特別編 カザフスタン――感染症には馬乳が効く
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00052122
岡 奈津子
2021年4月
(2,188字)
「カザフスタンの住民は、もうみんな感染したんじゃないかな」。
首都ヌルスルタンに住む筆者の友人は、昨年の夏、新型コロナウイルス感染症で10日ほどの入院を余儀なくされた。いまも倦怠感や気分の落ち込みなどに悩まされているそうだ。彼女の職場では同僚の多くが感染し、コロナが原因で家族を亡くした知り合いも少なくないという。
2021年4月初めの時点で、カザフスタンの人口あたりの感染者数は日本の4倍強だ。しかし現地からの話を聞くと、実態はこの数字以上に深刻なのではないかという気がする。住民全員が感染したというのは誇張だとしても、筆者の知人・友人のなかにも自分自身や家族が感染して闘病した、という人がぞろぞろいるからだ。
パンデミックが猛威をふるうカザフスタンで、いま改めて注目されているのが、遊牧民に飲み継がれてきた伝統的飲料である。古来、カザフ人のあいだでは、サウマルと呼ばれる搾りたての馬乳、それぞれ馬とラクダの乳を原料とする発酵酒であるクムスとシュバットが、健康と長寿をもたらす飲み物として親しまれてきた。酒といってもクムスとシュバットのアルコール度数は低く、子どもにも飲ませることができる。

滋養に富んだこれらの飲料は、新型コロナウイルス感染症の予防や発症後のリハビリに効果があるといわれ、買い求める人が急増している。カザフスタンの専門家によれば、サウマルとクムス、およびシュバットは、健康維持に不可欠なビタミン類や微量元素を豊富に含んでいるほか、腸内フローラ(細菌叢)のバランスを保ち、腸内の免疫細胞を活性化する作用があるという。
ただし、これらの飲み物は新鮮さが命だ。なかでもサウマルは、搾乳後2、3時間以内のものでないと効果が期待できないといわれている。しかし、ブームに乗じて荒稼ぎしようとする悪徳業者もいるようで、メディアでは、古くなったり水で薄めたりしたものを買わされ、それを飲んで体調を崩したという苦情も伝えられている。
筆者が初めてクムスに挑戦したのは、たしかアルマトゥのバザールだった。そのときのクムスはにおいがきつくて酸味も強かったため、すっかり苦手意識を持ってしまった。そのせいでしばらく敬遠していたのだが、あるとき勧められて飲んでみたら思いのほか美味だった。最初に飲んだクムスは発酵しすぎていたのかもしれない。それ以来クムスへの抵抗感はなくなったものの、筆者はさらっとしたシェイクのような舌触りで、酸味がさわやかなシュバットのほうが好みである。
馬乳酒は中央アジアやモンゴルのほか、世界各地で愛飲されているが、その伝播については興味深い逸話がある。ヨーロッパに初めてクムスを伝えたのは、第二次世界大戦後、捕虜としてカザフスタンの収容所に捕えられていたドイツ人だった。彼の名はルドルフ・シュトルヒ。重い結核を患い収容所から追い出されたシュトルヒは、生死の境をさまよっていたところをカザフ人家族に助けられ、サウマルとクムスのおかげで健康を回復したという1。
カザフの伝統的飲料の効果を自ら体験したシュトルヒは、帰国後、馬牧場を開き、ヨーロッパ初のクムス生産工場を作った。さらに彼は馬乳を凍結乾燥し、栄養成分を維持したままパウダー状に加工する技術の開発にも成功した。現在、シュトルヒの娘と、その夫ハンス・ツォルマンが経営するツォルマン・シュトゥーテンミルヒ社は、馬乳とクムスだけでなく、馬乳を原料とする食品やスキンケア製品なども生産・販売している。
カザフスタンとドイツを結びつけるこの逸話には、今世紀に入ってからの続きがある。カザフ人のカドゥルベク・メイラムベコフは、かねてから馬牧場を持ちたいと考えていた。2012年にロンドンを訪問した際、彼はスーパーで偶然クムスを見つけた。てっきりカザフスタンからの輸入品だと思ったら、それはドイツ製であった。驚いたメイラムベコフはすぐさまドイツに向かい、ツォルマンと面談したという。その後、メイラムベコフが起こしたユーラシア・インヴェスト社は、ツォルマン・シュトゥーテンミルヒ社の技術を用い、サウマルやラクダの乳を加工した製品の生産を行っている。
シュトルヒがもし生きていたら、コロナ禍のいまこそサウマルとクムスを飲むべきだ、と力説したに違いない。
写真の出典
- Bakhyt Ashirbaev氏提供。
著者プロフィール
岡奈津子(おかなつこ) アジア経済研究所新領域研究センター・ガバナンス研究グループ長。PhD in Politics and International Studies. 近著に『<賄賂>のある暮らし――市場経済化後のカザフスタン』白水社(2019年)、"Changing Perceptions of Informal Payments under Privatization of Health Care: The Case of Kazakhstan," Central Asian Affairs 6(1): 1-20, 2019など。
注
- ユーラシア・インヴェスト社のウェブサイトによる。ツォルマン・シュトゥーテンミルヒ社のウェブサイトでは、シュトルヒとカザフ人牧夫の出会いについては触れられていない。
- 第1回 バングラデシュ――食らわんか河魚
- 第2回 クウェート――国民食マチブースと羊肉のはなし
- 第3回 ラオス――カブトムシは食べ物だった
- 第4回 タイ――うなだれる大衆魚・プラートゥー
- 第5回 トルコ――ラクの〆は臓物スープで
- 第6回 台湾――臭豆腐の香り
- 第7回 カンボジア――こじらせ系女子が食べてきた珍食
- 第8回 インドネシア――1本のサテがくり出す衝撃の味
- 第9回 中国四川省――肉食の醍醐味
- 第10回 ベトナム――「元気ハツラツ」じゃなかったハノイの卵コーヒー
- 第11回 ブラジル――「ツンデレの果実」ペキー
- 第12回 モルディブ――食べても食べてもツナ
- 第13回 フィリピン――最北の島で食す海と人の幸
- 第14回 タンザニア――ウガリを味わう
- 第15回 アメリカ――マンハッタンで繰り広げられる米中ハンバーガー対決
- 第16回 ニュージーランド――マオリの伝統料理「ハンギ」を食す
- 第17回 イギリス――レストランに関する進化論的考察
- 第18回 南アフリカ――「虹の国」の国民食、ブラーイ
- 第19回 デンマーク――酸っぱい思い出
- 第20回 ケニア――臓物を味わう
- 第21回 モンゴル――強烈な酸味あふれる「白い食べ物」は故郷を出ると……
- 第22回 インド――幻想のなかの「満洲」
- 第23回 マグリブ(北アフリカ)――幻の豚肉
- 最終回 中国――失われた食の風景
- 特別編 カザフスタン――感染症には馬乳が効く
世界珍食紀行(『アジ研ワールド・トレンド』2016年10月号~2018年3-4月号連載)
- 第1回「中国――多様かつ深遠なる中国の食文化」
- 第2回「ベトナム――食をめぐる恐怖体験」
- 第3回「気絶するほど旨い?臭い!――韓国『ホンオフェ』」
- 第4回「イラン――美食の国の『幻想的な』味?!」
- 第5回「キューバ――不足の経済の食」
- 第6回「タイ農村の虫料理」
- 第7回「ソ連――懐かしの機内食」
- 第8回「エチオピア――エチオピア人珍食に遭遇する」
- 第9回「多人種多民族が混交する国ブラジルの創造の珍食」
- 第10回「コートジボワール――多彩な『ソース』の魅力」
- 第11回「デーツ――アラブ首長国連邦」
- 第12回「ペルー ――アンデスのモルモット『クイ』」
- 第13回「ミャンマー ――珍食の一夜と長い前置き」
- 第14回「『物価高世界一』の地、アンゴラへ――ポルトガル・ワインの悲願の進出」