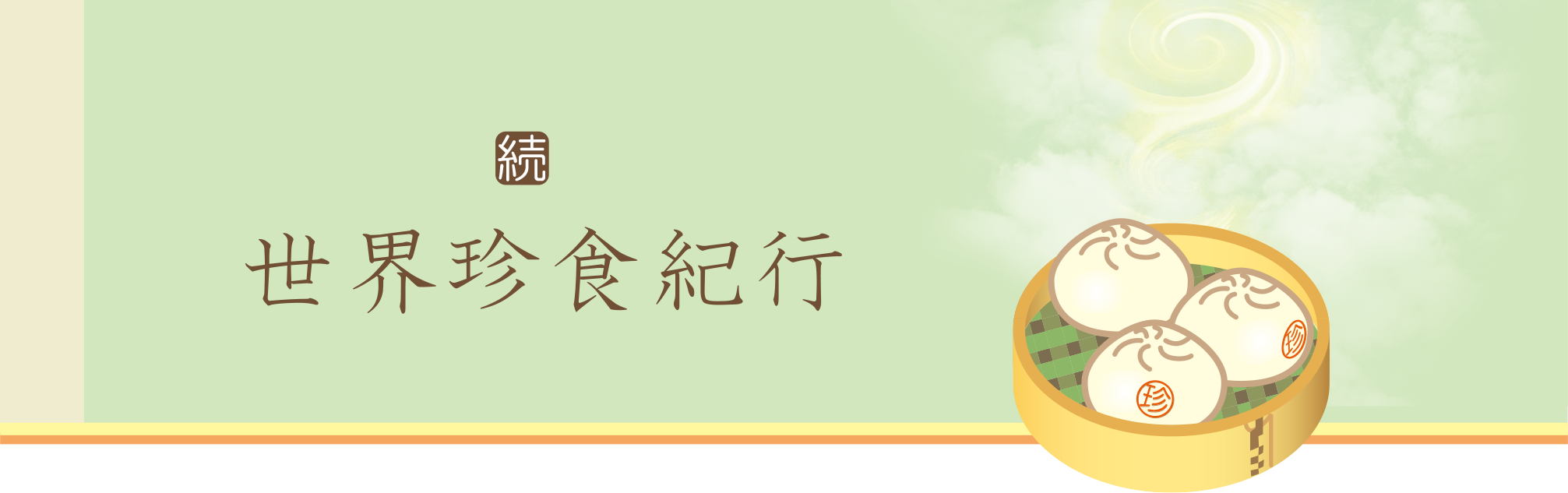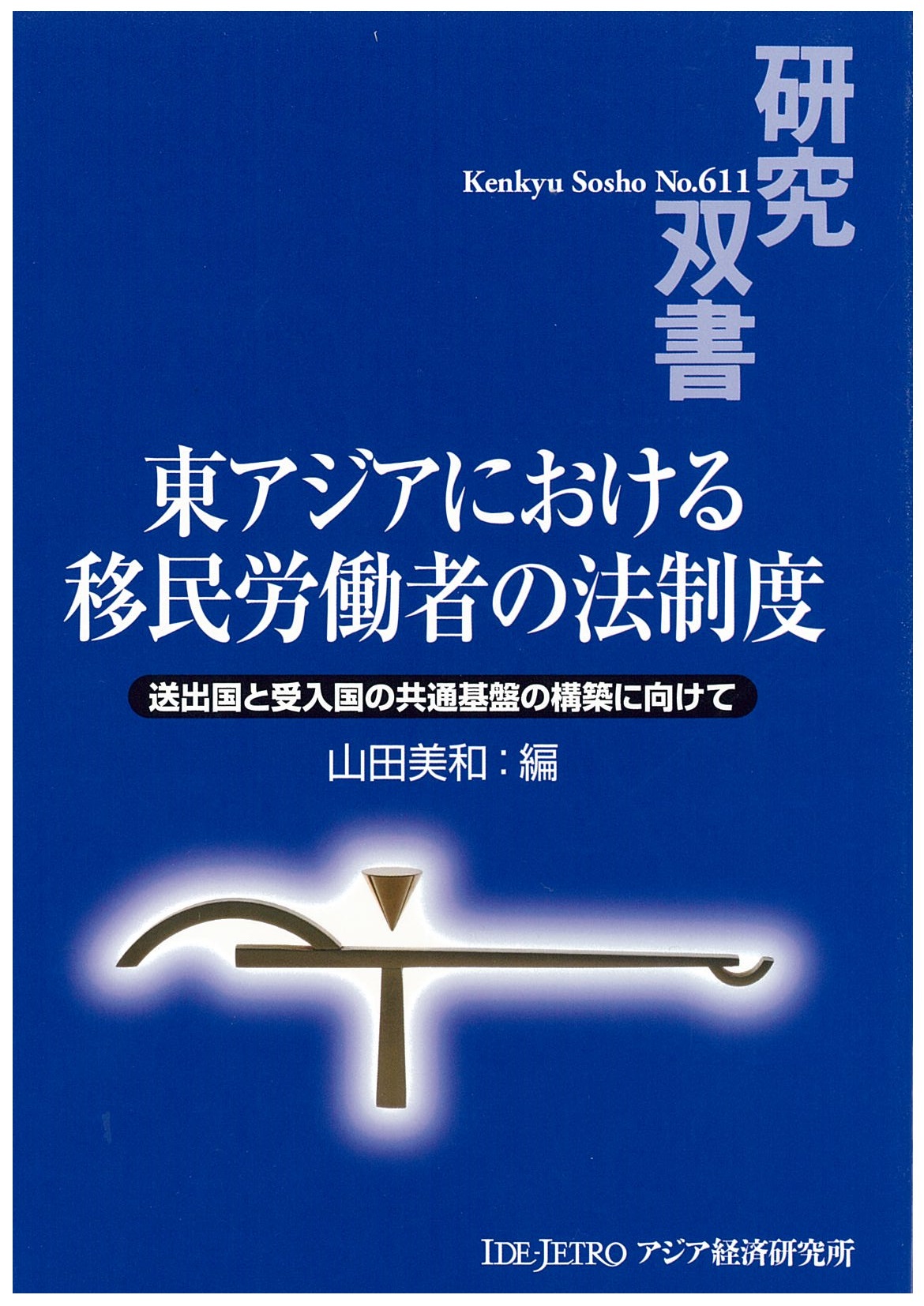IDEスクエア
コラム
第7回 カンボジア――こじらせ系女子が食べてきた珍食
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00050659
2018年12月
10年くらい前の私は、珍食グルメに対して比較的貪欲でオープンだった。なぜなら、「気持ち悪い」と言って拒絶することへの反発心があったからだ。その背後に、多感な高校生のころの出来事があった。ある夏の日、同級生のとてもかわいい女子がセミを気持ち悪がってその存在を全否定している姿を、周りの人びとが温かい目で見守っていた場面に居合わせた。その少し前に、私がゴキブリを気持ち悪がったところ、男子たちに白い目を向けられた(ように感じられた)事態とのあまりの違いに、私は傷ついた。その結果、何かを「こじらせた」私は「私は気持ち悪いなんて言わないわ」とばかりに、ほぼヤケになってさまざまなものを食べてきた。筆者がフィールドにしているカンボジアでも、拒絶せずに食べてから判断するということを実践してきたつもりだ。そのなかで、私の日本の友人の大半が「気持ち悪い」という反応をするであろう3つの珍食グルメについて紹介したい。
プノンペンから小一時間ほどのところにある街スクンはタランチュラ(蜘蛛、現地ではアーピン)で有名である1。付近に止まる観光バスには、売り子たちがこぞって蜘蛛を売りにくる。2007年頃、一緒にドライブ旅行を楽しんでいた現地の友人の都会育ちの妹(当時中学生)が「食べたい」とねだるものだから、一緒に食べてみた。悪くはなかったけれど、これを好きだという人たちがもっとも美味しい部分だと評する蜘蛛のお尻の丸い部分のモサモサとした食感がどうにも好きになれなかった。もう一度食べる機会があったが、やはり理解できず、その後一度も食べていない。
同じく2007年頃、プノンペンでお世話になっていたメイドさんが、「今日のご飯は特別よ」と笑顔で出してくれたのが、山盛りの蟻とハーブの炒めもの(大振りの羽蟻入り)だったときは、一瞬たじろいだ(写真1)。動揺は隠して満面の笑みで「ありがとう」と言いつつ、多めのご飯に蟻数匹とハーブとを載せてかきこんだ。米とハーブの味と、プチッという食感しか覚えていない。もう一度、蟻の味を実感しながら食べてもいいとは思っているが、あんなにたっぷりの蟻料理にはその後出くわしていない。当時の日記には、現地の友人から「そんなに頻繁に食べるものではないけれど、半年に1回くらいは食べる」「コンポンチナン州に行ったとき、ほとんど毎日蟻だった」という証言を得たとあったので、その気になれば「次」があったのかもしれない。しかし、こちらもまた、10年以上食べていない。
孵化直前のアヒル卵は、唯一「おいしい」と人に勧めることができる(写真2、3)。フィリピンやベトナムでも食されていて、カンボジアではポンティアコンと呼ばれる。夕方になると「熱々のポンティアコンだよー」という声が聞こえてくる。卵のてっぺんをコンコンとノックしながら小さな穴をあけ、スプーンで少しずつ中身をいただく。たっぷりのハーブと、塩コショウにライムを絞ったものをあわせる。羽になりかけの物体が見えたりすると、食べにくいかもしれない。しかし、卵と肉の中間のような味なので、おいしくない理由がない。初めて食べたとき、一気に5個平らげてしまったことを覚えている。しかし、この卵ですら、最近めっきり食べる機会が減ってしまった。
若かりし頃の心の傷のおかげで、さまざまな食材に挑戦する機会に恵まれてきたことは確かだが、そろそろ無理せずに食べたいものを食べてもよい年ごろになってきたのかもしれない。「食べない」ということは、必ずしも相手の食文化を否定することを意味しないのだから。そう言いつつ、出張先のカンボジアで頻繁に和食を選ぶようになった自分が、何か大事なものを忘れつつあるような気もする。いま、もし目の前に、蟻の炒め物が出てきたら、私は果たして笑顔で食べることができるのだろうか。



著者プロフィール
初鹿野直美(はつかのなおみ)。地域研究センター動向分析研究グループ。おもな著作に「カンボジアの移民労働者政策――新興送出国の制度づくりと課題」(山田美和編『東アジアにおける移民労働者の法制度――送出国と受入国の共通基盤の構築に向けて』アジア経済研究所 2014年)、「きこえるのは誰の声――ラタナキリ州の先住民と土地問題を支援する人たち」(青山和佳・受田宏之・小林誉明編著『開発援助がつくる社会生活――現場からのプロジェクト診断(第2版)』大学教育出版 2017年)など。
注
- タランチュラ料理については、近年乱獲で数が減っているのではないかとの報道もある。
- 第1回 バングラデシュ――食らわんか河魚
- 第2回 クウェート――国民食マチブースと羊肉のはなし
- 第3回 ラオス――カブトムシは食べ物だった
- 第4回 タイ――うなだれる大衆魚・プラートゥー
- 第5回 トルコ――ラクの〆は臓物スープで
- 第6回 台湾――臭豆腐の香り
- 第7回 カンボジア――こじらせ系女子が食べてきた珍食
- 第8回 インドネシア――1本のサテがくり出す衝撃の味
- 第9回 中国四川省――肉食の醍醐味
- 第10回 ベトナム――「元気ハツラツ」じゃなかったハノイの卵コーヒー
- 第11回 ブラジル――「ツンデレの果実」ペキー
- 第12回 モルディブ――食べても食べてもツナ
- 第13回 フィリピン――最北の島で食す海と人の幸
- 第14回 タンザニア――ウガリを味わう
- 第15回 アメリカ――マンハッタンで繰り広げられる米中ハンバーガー対決
- 第16回 ニュージーランド――マオリの伝統料理「ハンギ」を食す
- 第17回 イギリス――レストランに関する進化論的考察
- 第18回 南アフリカ――「虹の国」の国民食、ブラーイ
- 第19回 デンマーク――酸っぱい思い出
- 第20回 ケニア――臓物を味わう
- 第21回 モンゴル――強烈な酸味あふれる「白い食べ物」は故郷を出ると……
- 第22回 インド――幻想のなかの「満洲」
- 第23回 マグリブ(北アフリカ)――幻の豚肉
- 最終回 中国――失われた食の風景
- 特別編 カザフスタン――感染症には馬乳が効く
世界珍食紀行(『アジ研ワールド・トレンド』2016年10月号~2018年3-4月号連載)
- 第1回「中国――多様かつ深遠なる中国の食文化」
- 第2回「ベトナム――食をめぐる恐怖体験」
- 第3回「気絶するほど旨い?臭い!――韓国『ホンオフェ』」
- 第4回「イラン――美食の国の『幻想的な』味?!」
- 第5回「キューバ――不足の経済の食」
- 第6回「タイ農村の虫料理」
- 第7回「ソ連――懐かしの機内食」
- 第8回「エチオピア――エチオピア人珍食に遭遇する」
- 第9回「多人種多民族が混交する国ブラジルの創造の珍食」
- 第10回「コートジボワール――多彩な『ソース』の魅力」
- 第11回「デーツ――アラブ首長国連邦」
- 第12回「ペルー ――アンデスのモルモット『クイ』」
- 第13回「ミャンマー ――珍食の一夜と長い前置き」
- 第14回「『物価高世界一』の地、アンゴラへ――ポルトガル・ワインの悲願の進出」