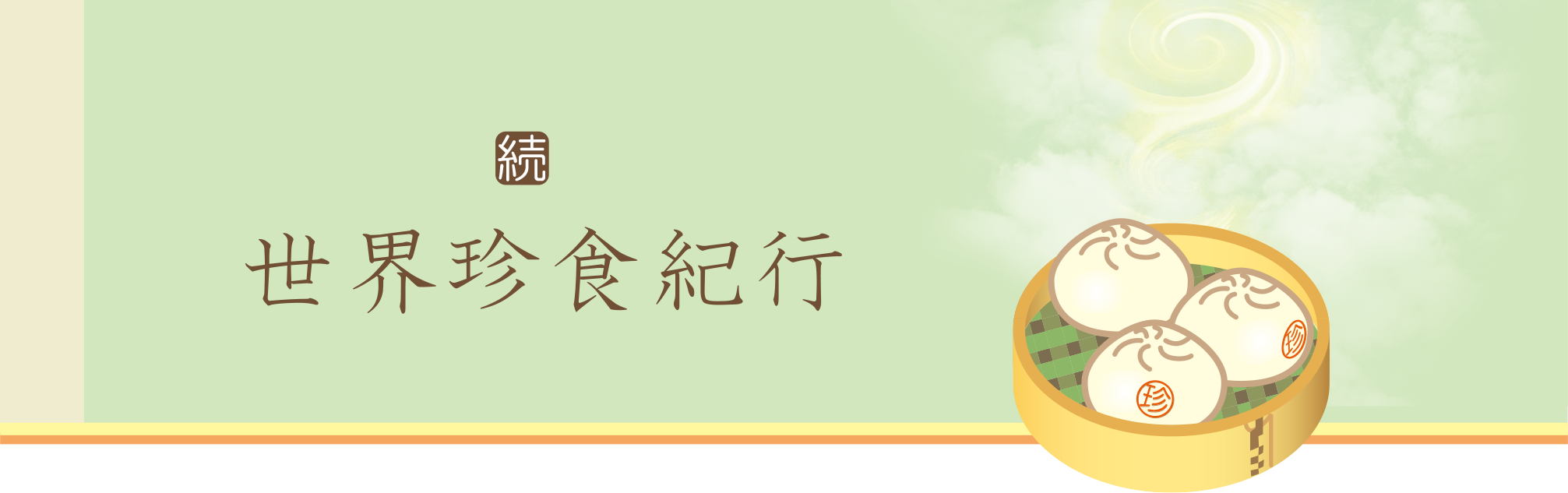IDEスクエア
コラム
第20回 ケニア――臓物を味わう
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00051537
岸 真由美
2020年1月
(1,734字)
筆者の故郷は奥羽山脈の麓に近い山形の農村だ。実家は農家である。小さいころ、実家では卵をとるために鶏を、乳を搾るためにヤギを、食肉用にウサギを飼育していた。歳を取って卵をうまく産めなくなった親鶏は絞めて食用にした。料理方法はいたってシンプルで、頭と足以外の部位を適当にぶつ切りにして、醤油で煮込むだけである。肉の部分だけでなく、臓物も余すところなく調理する。筆者はひも、きんかん、レバーが好きだった。ももや背の骨の髄も美味しかった。さすがにヤギは法律で禁止されているため自宅でと殺することはなかったが、ウサギは鶏と同じように調理して、特に冬に食卓にのぼった。ウサギの臓物を食べた記憶はあまりないが、頭蓋をうまく外して食べる脳みそが格別な味だったのを覚えている。こうした経験が影響したのだろう。筆者は今も肉より臓物が好きである。
2012年に1年ほどケニアの首都ナイロビに滞在した。この時よく食べた肉料理にニャマ・チョマとニャマ・カアンガがある。ニャマは「肉」、チョマは「焼く」の意味で、ニャマ・チョマは焼肉のことだ。カアンガは「炒める」の意味で、ニャマ・カアンガは「肉炒め」だが、日本人の感覚で言うと炒めものより炒め煮に近いかもしれない。調理する肉はヤギや牛、鶏などである。食堂では、ニャマ・チョマなら好きな部位をキロ単位で選んで注文する。そうするとお店の人が炭火で焼いて、一口サイズに切り分けて出してくれる。これをシンプルに塩と、好みでピリピリ(輪切りの唐辛子)をつけていただく。日本なら焼肉で主食のご飯をほおばるが、ケニアではトウモロコシの粉をお湯で練ってつくるウガリと一緒に食べることが多い(ウガリについては本連載第14回、粒良麻知子「タンザニア――ウガリを味わう」を参照)。ニャマ・カアンガは肉をトマト、玉ねぎ、ニンニクなどと一緒に炒めたものだ。ナイロビの食堂では、カアンガは主食・付け合わせの野菜と一緒にワンプレートで出てくることが多い。


ちなみに臓物は正肉よりリーズナブルなのでお財布にも優しい。牛マトゥンボなら1キロあたり250〜350ケニア・シリングほどで、ナイロビのシティマーケットのほか、大きなスーパーで売られている。街の食堂でもマトゥンボのカアンガは250〜300シリングほどで食べられる。1ケニア・シリングはおおよそ1円。円換算ならワンコインでお釣りが来る。ケニアを訪れる機会があれば是非試してみてほしい。

写真の出典
- すべてナイロビにて筆者撮影
著者プロフィール
岸真由美(きしまゆみ) アジア経済研究所図書館ライブラリアン。サブサハラ・アフリカに関する蔵書構築を担当。
- 第1回 バングラデシュ――食らわんか河魚
- 第2回 クウェート――国民食マチブースと羊肉のはなし
- 第3回 ラオス――カブトムシは食べ物だった
- 第4回 タイ――うなだれる大衆魚・プラートゥー
- 第5回 トルコ――ラクの〆は臓物スープで
- 第6回 台湾――臭豆腐の香り
- 第7回 カンボジア――こじらせ系女子が食べてきた珍食
- 第8回 インドネシア――1本のサテがくり出す衝撃の味
- 第9回 中国四川省――肉食の醍醐味
- 第10回 ベトナム――「元気ハツラツ」じゃなかったハノイの卵コーヒー
- 第11回 ブラジル――「ツンデレの果実」ペキー
- 第12回 モルディブ――食べても食べてもツナ
- 第13回 フィリピン――最北の島で食す海と人の幸
- 第14回 タンザニア――ウガリを味わう
- 第15回 アメリカ――マンハッタンで繰り広げられる米中ハンバーガー対決
- 第16回 ニュージーランド――マオリの伝統料理「ハンギ」を食す
- 第17回 イギリス――レストランに関する進化論的考察
- 第18回 南アフリカ――「虹の国」の国民食、ブラーイ
- 第19回 デンマーク――酸っぱい思い出
- 第20回 ケニア――臓物を味わう
- 第21回 モンゴル――強烈な酸味あふれる「白い食べ物」は故郷を出ると……
- 第22回 インド――幻想のなかの「満洲」
- 第23回 マグリブ(北アフリカ)――幻の豚肉
- 最終回 中国――失われた食の風景
- 特別編 カザフスタン――感染症には馬乳が効く
世界珍食紀行(『アジ研ワールド・トレンド』2016年10月号~2018年3-4月号連載)
- 第1回「中国――多様かつ深遠なる中国の食文化」
- 第2回「ベトナム――食をめぐる恐怖体験」
- 第3回「気絶するほど旨い?臭い!――韓国『ホンオフェ』」
- 第4回「イラン――美食の国の『幻想的な』味?!」
- 第5回「キューバ――不足の経済の食」
- 第6回「タイ農村の虫料理」
- 第7回「ソ連――懐かしの機内食」
- 第8回「エチオピア――エチオピア人珍食に遭遇する」
- 第9回「多人種多民族が混交する国ブラジルの創造の珍食」
- 第10回「コートジボワール――多彩な『ソース』の魅力」
- 第11回「デーツ――アラブ首長国連邦」
- 第12回「ペルー ――アンデスのモルモット『クイ』」
- 第13回「ミャンマー ――珍食の一夜と長い前置き」
- 第14回「『物価高世界一』の地、アンゴラへ――ポルトガル・ワインの悲願の進出」