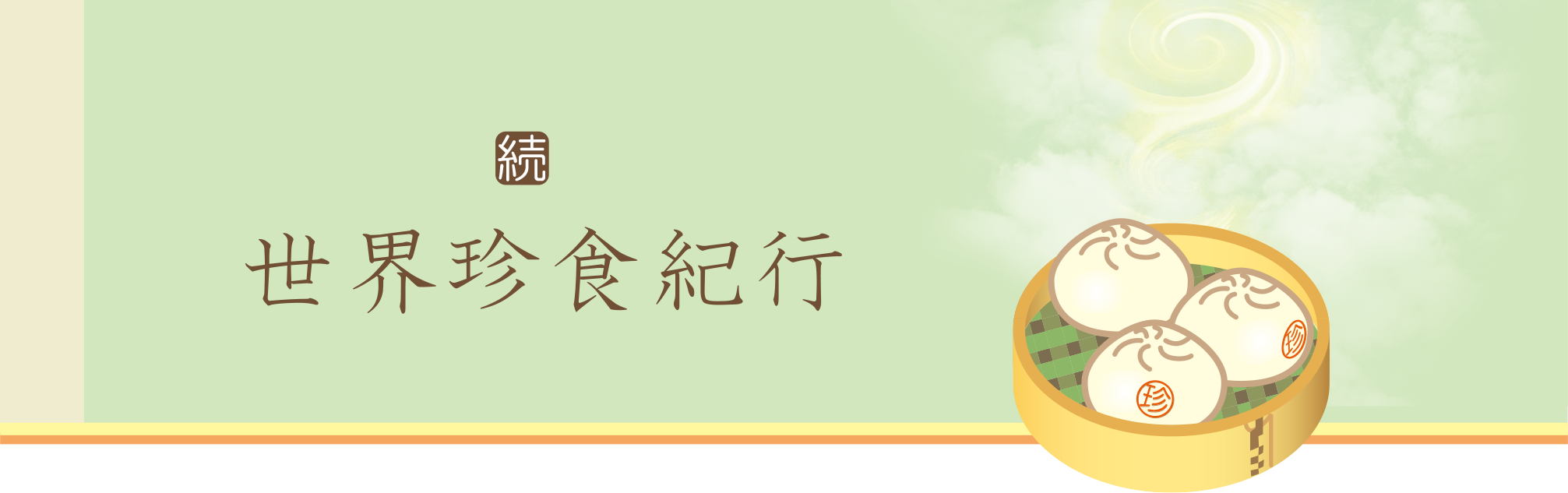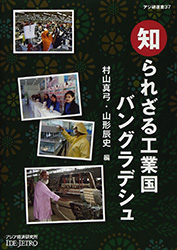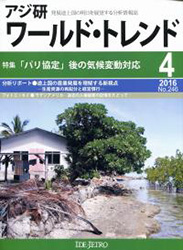IDEスクエア
コラム
第1回 バングラデシュ――食らわんか河魚
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00050356
山形 辰史
2018年4月
バングラデシュは川の国である。「川」というより「河」と書く方が適切だろう。内陸部に行っても、向こう岸が見えないほどの大河がある。河の中州が島になっていて、人が住んでいるし、中洲全体が行政区になっていることもある。
日本で川魚といえば小ぶりであるが、バングラデシュの河には大きい魚もいる。河でも海からの逆流があるようで、バングラデシュの国魚であるイリシ(IlishまたはHilsa)は河に住むがニシンの仲間である。
1998年、私が初めてバングラデシュに行ったとき、バングラデシュ研究ではすでに名を成していた同僚の村山真弓氏にダッカのベンガル料理店に連れて行かれた。「これがバングラデシュ人が大好きな魚なんだよー」と勧められたイリシのカレーを食べたときに、とてもおいしいとは思えなかった。脂ぎっていたし、骨が多かったので、食べどころがないような気がしたのである。自分は2000年に1年間、バングラデシュで研究することを決めていたのだが、「これが美味しいとされている料理だとするならば、俺のバングラデシュ生活はどうなってしまうのだろうか」と暗澹たる気持ちになった。
人は、自分が何を食べているかわからないと、おいしさを味わえないものではないだろうか(自分の勝手な仮説です)。イリシがニシン系だとわかったら、なーんだニシンなんだから脂ぎっていても骨が多くても当たり前じゃないか、と思えるようになった。しかし歳のせいか、やはり脂ギトギトは苦手である。
しかしバングラデシュの一般食のカレーは脂ギトギトなどしていない。庶民は脂ギトギトしたカレーなど高くつくから、それを薄く延ばして水っぽいカレーを食べるのである。そのぐらいの方が私にはちょうど良い。
そして何といっても一番うまいのは炊き立ての米の飯である。バングラデシュでライスを頼むと、一膳いくらとかいうのではなく、大皿で提供されて、食いたいだけ食わしてくれる。それでまず、いい匂いのするご飯だけを食べる。それだけでもうまい。その次に、野菜でご飯を食べる。野菜は、ジュートの葉であるホテイアオイとか、オクラとか、ジャガイモとかが定番である。そしてその次に魚カレーだ。ご飯を改めて器に盛って、その上から魚カレーをかける。私の好きな魚は、現地でルイ(Rui)と呼ばれる鯉の類の魚である。これはだいたいどんな食堂でも用意している。ルイの方がイリシより淡白であっさりしている。ルイもイリシも胴体を輪切りにして出されるか、あるいはその半身が出される。小麦粉をまぶしていったん揚げて、そのうえでカレーで煮るようである(料理法に詳しいわけではない)。そして、魚カレーでもご飯がまだ残ってしまったら、最後にダルと呼ばれる豆スープでお腹を仕上げる。満腹である。最後に練乳入りミルクティーで昼食を締めくくる。


手前は小魚カレーの一部で、真ん中にあるのがルイの輪切りの半身である(同上)。
バングラデシュで外国人が「魚が食べたい」というと、「外国人は川魚が苦手だろう」とバングラデシュ人が忖度して、海水魚のマナガツオ(Pomfret)が供されることが多い。しかし通常のレストランで生のマナガツオを用意しているわけではないので、冷凍のマナガツオを解凍して用いることになる。言っては悪いが、これが概して不味い。
ルイとイリシに加え、多くの店で供されやすいのが「小(チョト)魚(マーチ)」である。いわゆる雑魚であろう。日本人には慣れ親しんだ小魚の味がする(写真の小魚カレーを参照)。その他、筆者が比較的多くの店で食することができた魚の中で好んでいるのはコイ(Koi)という名の魚である。これは日本語ではキノボリウオと呼ばれ、通常の皿に載る程度の大きさである。小ぶりだが身が締まっている。この他、南部のボリシャルを訪れた際、ご当地の特産品としてシン(Shing)という魚を紹介された。「貧血に効く」という。素人目には、細身のナマズに見えた。
バングラデシュで焼き魚が供されることはないが、筆者は日本から安価な焼き網を持って行って、市場で買った魚をしばしば焼いて食べていた。「これは鯵に似ているな」と思える魚は、焼いたら鯵の味がしたものである。このことから名前はどうあれ、見かけの似ている魚は、味も似ているのではないか、と思う。カレーであれ何であれ、皆様是非、バングラデシュの河魚を堪能されたい!!
著者プロフィール
山形辰史(やまがたたつふみ)。ジェトロ・アジア経済研究所開発研究センター研究員。経済学博士。専門は開発経済学、バングラデシュ経済。バングラデシュ関係の著作として、『知られざる工業国バングラデシュ』(共編著)ジェトロ・アジア経済研究所(2014年)、「バングラデシュの気候変動対応」『アジ研ワールド・トレンド』(2016年4月号)、「バングラデシュ、テロ起こした若者たちの世界観」『Yomiuri Online』(2016年7月8日)がある。
- 第1回 バングラデシュ――食らわんか河魚
- 第2回 クウェート――国民食マチブースと羊肉のはなし
- 第3回 ラオス――カブトムシは食べ物だった
- 第4回 タイ――うなだれる大衆魚・プラートゥー
- 第5回 トルコ――ラクの〆は臓物スープで
- 第6回 台湾――臭豆腐の香り
- 第7回 カンボジア――こじらせ系女子が食べてきた珍食
- 第8回 インドネシア――1本のサテがくり出す衝撃の味
- 第9回 中国四川省――肉食の醍醐味
- 第10回 ベトナム――「元気ハツラツ」じゃなかったハノイの卵コーヒー
- 第11回 ブラジル――「ツンデレの果実」ペキー
- 第12回 モルディブ――食べても食べてもツナ
- 第13回 フィリピン――最北の島で食す海と人の幸
- 第14回 タンザニア――ウガリを味わう
- 第15回 アメリカ――マンハッタンで繰り広げられる米中ハンバーガー対決
- 第16回 ニュージーランド――マオリの伝統料理「ハンギ」を食す
- 第17回 イギリス――レストランに関する進化論的考察
- 第18回 南アフリカ――「虹の国」の国民食、ブラーイ
- 第19回 デンマーク――酸っぱい思い出
- 第20回 ケニア――臓物を味わう
- 第21回 モンゴル――強烈な酸味あふれる「白い食べ物」は故郷を出ると……
- 第22回 インド――幻想のなかの「満洲」
- 第23回 マグリブ(北アフリカ)――幻の豚肉
- 最終回 中国――失われた食の風景
- 特別編 カザフスタン――感染症には馬乳が効く
世界珍食紀行(『アジ研ワールド・トレンド』2016年10月号~2018年3-4月号連載)
- 第1回「中国――多様かつ深遠なる中国の食文化」
- 第2回「ベトナム――食をめぐる恐怖体験」
- 第3回「気絶するほど旨い?臭い!――韓国『ホンオフェ』」
- 第4回「イラン――美食の国の『幻想的な』味?!」
- 第5回「キューバ――不足の経済の食」
- 第6回「タイ農村の虫料理」
- 第7回「ソ連――懐かしの機内食」
- 第8回「エチオピア――エチオピア人珍食に遭遇する」
- 第9回「多人種多民族が混交する国ブラジルの創造の珍食」
- 第10回「コートジボワール――多彩な『ソース』の魅力」
- 第11回「デーツ――アラブ首長国連邦」
- 第12回「ペルー ――アンデスのモルモット『クイ』」
- 第13回「ミャンマー ――珍食の一夜と長い前置き」
- 第14回「『物価高世界一』の地、アンゴラへ――ポルトガル・ワインの悲願の進出」