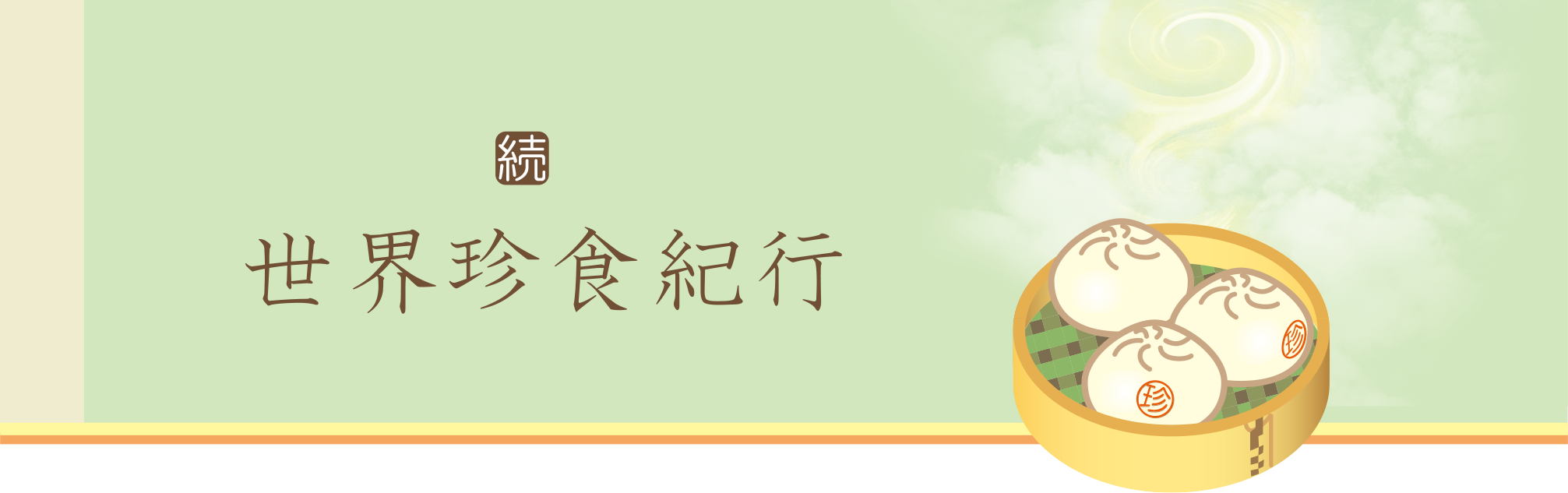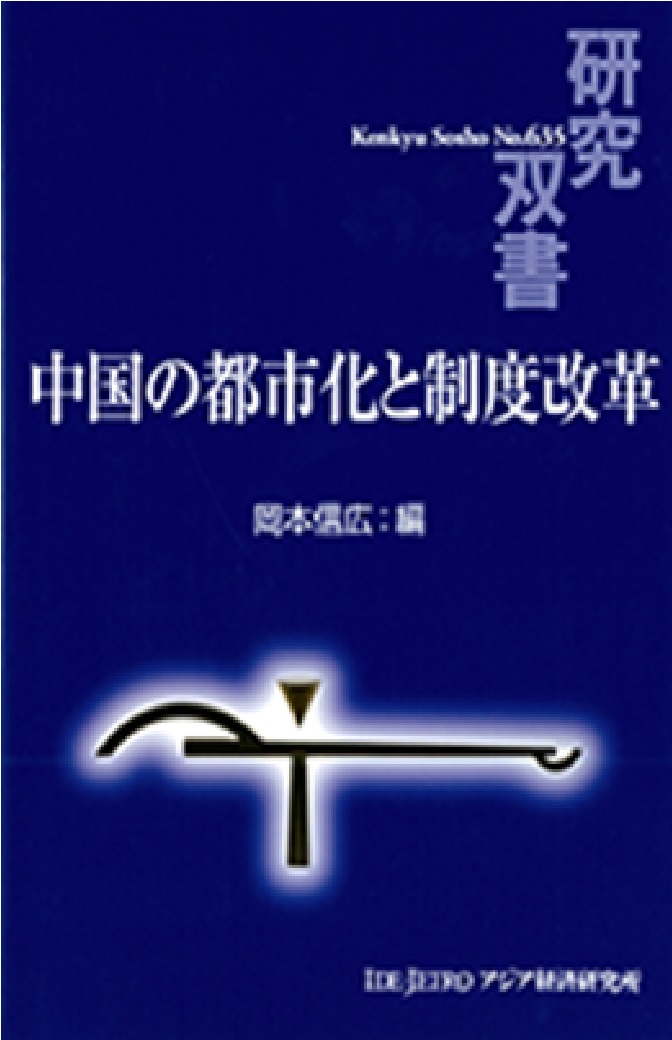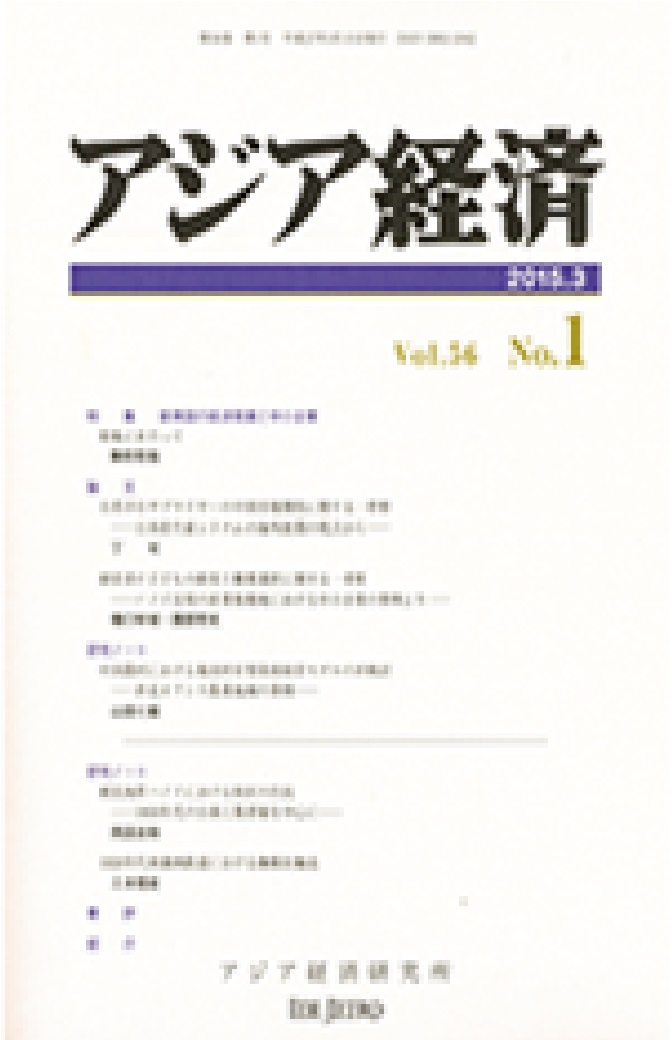IDEスクエア
コラム
第9回 中国四川省――肉食の醍醐味
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00050719
2019年2月
(2,295字)

写真右上のQRコードで電子決済も可。
昨冬訪れた四川省成都は西南部の四川盆地に位置し、古来天府の都と呼ばれる肥沃な土地柄である。畜産も盛んで、肉のなかでは特に豚の脂身の多い部位や内臓類が好まれる。年間を通して曇天が多く湿度が高いため、夏は蒸し暑く冬は比較的温暖だがじめっとした冷気に包み込まれるような寒さである。このような気候風土のため、夏は食欲を刺激し冬は体を温める「麻辣(マーラー)」(山椒と唐辛子のしびれるような辛さ)と呼ばれる味付けが、四川料理を特徴づけるものとなっている。ただ辛いだけでなく、豆板醤や搾菜などの発酵食品を多用した奥行きのある味わいが特徴で、代表的な四川料理の麻婆豆腐、回鍋肉、担々麺などは日本でも有名だ。
四川といえば火鍋も忘れてはいけない。成都のレストランの3軒に1軒は火鍋屋という都市伝説を聞いたことがあるが、実際筆者は一週間の滞在中2回食べたのであながち間違いではないかもしれない。なお、火鍋は鍋料理全般を指す中国語なので辛くないものもあるが、成都や重慶と銘打っていれば真っ赤な麻辣スープがメインであることはまず間違いない。日本で鍋の季節といえば冬だが、友人曰く成都では夏でも汗をダラダラ流しながら火鍋を囲むそうだ。暑さ(熱さ)に耐えられなくなると多くの男性はシャツをまくり上げて腹を出したり、あるいは上半身裸になったりしてなおも食べ続けるのだという。
友人が連れて行ってくれた火鍋屋では、薄切り肉、野菜、豆腐などお馴染みの具もあるが、猪脳花(豚の脳)、腰花(豚の腎臓)、鴨腸(カモの腸)、毛肚(牛の第三胃)などの内臓が大人気だった。日本では珍しい鴨腸は一見太めのミミズのようだが、切り開いてあるので箸でつまむときし麺のような形状になる(写真2)。毛肚や鴨腸は食感を残すため火を通し過ぎてはならず、「七上八下」1(箸でつまんだまま7、8回上下させスープにくぐらせること)がコツだという。引き上げると鴨腸は元の半分くらいの長さに縮んでおり、表面が滑らかで噛むと弾力があり美味である。


成都の小吃(シャオチー)と呼ばれる軽食の類も有名である。その一つである麻辣兎頭(ウサギの頭の唐辛子煮)を、街角の屋台で買ってみた2。トレーの上に、拳より一回り小さい兎の頭が積み重ねられている。渡されたビニール手袋で掴みまじまじと観察すると、細長い顔に落ち窪んだ小さな眼窩、二本の前歯が確かにウサギであることを生々しく物語っている(写真3)。
どこから食べたものか分からず頬のあたりに噛り付くも、ほとんど肉がなく硬い頬骨に自分の歯が空しくぶつかる。しかも、舌先に残った煮汁が辛すぎてしばし悶絶する。気を取り直して手で頭蓋骨を分解していくと、頬骨の内側に僅かに赤身の肉が見つかった。結局その他に発掘できた可食部は舌くらいで、脳や目玉も食べられたのかもしれないが技術の限界により断念した。肉は牛と鶏の中間のような味で悪くないが、正直言って手間の割になんとも食べでがない代物である。
しかし、これは無粋な外国人の感想である。地元の人々は指と舌と口を巧みに使い、上手く兎頭を食べるという。そこでふと、大の魚好きだった筆者の祖母が、良い魚が手に入ると目玉の周りのゼラチン質から内臓に至るまで、じつに美味しそうにきれいに平らげていたことを思い出した。これと全く同じことではないか。筆者がしばらく忘れていた、五感を動員して生き物を丸ごと味わい尽くすという愉しみが、まだここではしっかりと生き残っているのである。ここでようやく、兔頭を食べる醍醐味を(頭では)理解できたような気がした。


著者プロフィール
山田七絵(やまだななえ)。アジア経済研究所新領域研究センター研究員。農学博士。専門は中国農業・農村研究。最近の著作に、岡本信広編『中国の都市化と制度改革』(第5章担当。アジア経済研究所、2018年)、「中国農村における集団所有型資源経営モデルの再検討――西北オアシス農業地域の事例」(『アジア経済』第56巻第1号、2015年)。
写真の出典
- 写真1-3:2018年12月、四川省成都にて筆者撮影。
注
- 数え方にもよるが、冷静に考えると数が合わないような気もする。中国のインターネット上でも議論されているが、結論は出ていないようだ。厳密さより語呂の良さを重視したとみたほうがよいかもしれない。
- 中国の年間ウサギ肉消費量は世界の30%、このうち四川省が70%(約2億匹に相当)を占める。欧州では食用にならないウサギの頭や鶏の足の多くは中国に輸出されており、中国で消費されているウサギの頭の約5分の1は輸入品である(「中国人一年啃掉5億個兔頭 進口占五分之一」『四川在線―華西都市報(成都)』2014年7月23日)。
- 第1回 バングラデシュ――食らわんか河魚
- 第2回 クウェート――国民食マチブースと羊肉のはなし
- 第3回 ラオス――カブトムシは食べ物だった
- 第4回 タイ――うなだれる大衆魚・プラートゥー
- 第5回 トルコ――ラクの〆は臓物スープで
- 第6回 台湾――臭豆腐の香り
- 第7回 カンボジア――こじらせ系女子が食べてきた珍食
- 第8回 インドネシア――1本のサテがくり出す衝撃の味
- 第9回 中国四川省――肉食の醍醐味
- 第10回 ベトナム――「元気ハツラツ」じゃなかったハノイの卵コーヒー
- 第11回 ブラジル――「ツンデレの果実」ペキー
- 第12回 モルディブ――食べても食べてもツナ
- 第13回 フィリピン――最北の島で食す海と人の幸
- 第14回 タンザニア――ウガリを味わう
- 第15回 アメリカ――マンハッタンで繰り広げられる米中ハンバーガー対決
- 第16回 ニュージーランド――マオリの伝統料理「ハンギ」を食す
- 第17回 イギリス――レストランに関する進化論的考察
- 第18回 南アフリカ――「虹の国」の国民食、ブラーイ
- 第19回 デンマーク――酸っぱい思い出
- 第20回 ケニア――臓物を味わう
- 第21回 モンゴル――強烈な酸味あふれる「白い食べ物」は故郷を出ると……
- 第22回 インド――幻想のなかの「満洲」
- 第23回 マグリブ(北アフリカ)――幻の豚肉
- 最終回 中国――失われた食の風景
- 特別編 カザフスタン――感染症には馬乳が効く
世界珍食紀行(『アジ研ワールド・トレンド』2016年10月号~2018年3-4月号連載)
- 第1回「中国――多様かつ深遠なる中国の食文化」
- 第2回「ベトナム――食をめぐる恐怖体験」
- 第3回「気絶するほど旨い?臭い!――韓国『ホンオフェ』」
- 第4回「イラン――美食の国の『幻想的な』味?!」
- 第5回「キューバ――不足の経済の食」
- 第6回「タイ農村の虫料理」
- 第7回「ソ連――懐かしの機内食」
- 第8回「エチオピア――エチオピア人珍食に遭遇する」
- 第9回「多人種多民族が混交する国ブラジルの創造の珍食」
- 第10回「コートジボワール――多彩な『ソース』の魅力」
- 第11回「デーツ――アラブ首長国連邦」
- 第12回「ペルー ――アンデスのモルモット『クイ』」
- 第13回「ミャンマー ――珍食の一夜と長い前置き」
- 第14回「『物価高世界一』の地、アンゴラへ――ポルトガル・ワインの悲願の進出」