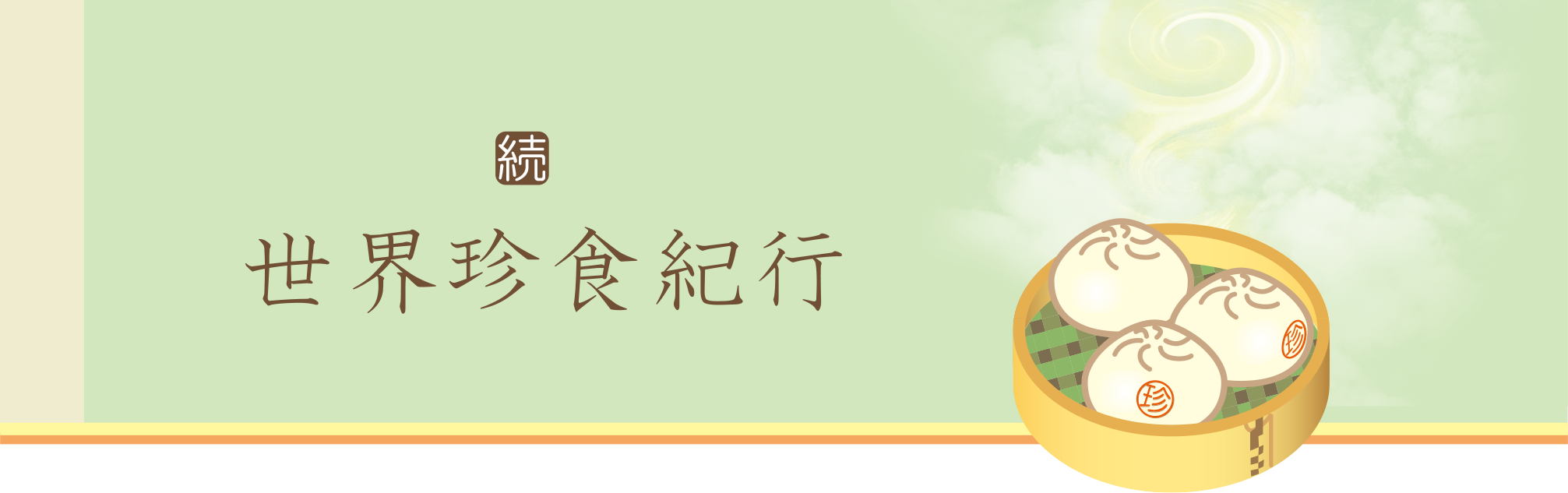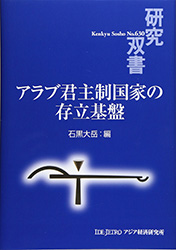IDEスクエア
コラム
第2回 クウェート――国民食マチブースと羊肉のはなし
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00050373
2018年5月
湾岸アラブ諸国の「珍食」とは、強いて言えばラクダ肉だろうか。クウェートでは、イラク国境への道沿いで食肉用に放牧されたラクダとふれあったり、部族代表議員の選挙キャンペーンで選対本部の置かれたテントに若いラクダが繋がれているのを目撃したことはあるのだが(選挙戦終盤に屠って集会参加者に振る舞い、気勢を上げるという)、筆者にはいまだにラクダ肉を口にする機会がなく、至極残念である。
そこで代わりと言っては何だが、ここではクウェートの国民食であるマチブースを取り上げたい。マチブースとは、ご飯(インディカ米)の上に鶏肉、羊肉、または魚がどんっとのっかった見た目をしており、油で炒めた玉ねぎとニンニクにターメリック、クミン、カルダモン、シナモンなど香辛料を加えたベースに、メインの具材となる肉や魚と水、米を加えて作る炊き込みご飯の一種である。多少の製法や材料は異なるものの、見た目は南アジアのビリヤニーとほとんど違わない(と思う)。似たようなものが近隣国ではカプサ、マンディーと呼ばれているが、料理に疎い筆者には、未だにマチブースとの違いが判然としない。とはいえ、アラブ料理といえばピタパンとケバブ(シャワルマ)のイメージしかなかった身には、湾岸アラブ諸国で主食ばりに米が食べられているのは、珍食とは言えないまでも、案外意外と感じたものだ。アラブと言いながら、食文化には歴史的な海上交通を通じたインドとの繋がりが色濃くあらわれているのが興味深い。

マチブースはのせる具材によって鶏(マチブース・ディヤーイー)、羊(マチブース・ラハム)、魚(マチブース・サマク)の3種類がある。お手頃なのは鶏だが、客人のおもてなしやハレの日の食事には、やはり羊がメインになる。バーレーンでは魚(近海で獲れるマハタの一種で、ハムールと呼ばれる)でもてなされることもある。基本は大皿に盛られたものをそれぞれが取り分けて食べるのだが、地元料理を謳うレストランでは1人分からでもサーブしてくれる。ひとりでは食べきれないほど量が多いのは、もとがもてなしの食事なので残して下げてもらうのがマナーだからなのだろう。留学中、毎日の寮の食事に出てくるマチブースは正直不味かったが、クウェート人の友人宅でいただいた、母親お手製や東南アジア出身の家政婦の手によるもの、外国人コックが調理した郷土料理レストランのもの、選挙キャンペーンでの饗応や結婚式でのビュッフェなどでのケータリングなど、いろいろな機会でマチブースをそれなりに美味しくいただいた。それなり、というのは、筆者に限らず出汁とうま味に長じた日本人には、大味なので何か物足りなさを感じて飽きがきてしまうからであろう。最大の問題は、出汁となる羊肉の品質にあるのではないかと筆者は見ている。
うまい羊肉はうまい。それがわかったのは2006年にシリア北部のアレッポを訪れた時のことである。適度の降水量があるので羊は自然の青草を食んで育っているのだろう。生肉(クッベ・ナーイエ)も臭みがなく、躊躇なく平らげることができた。シリア産の羊肉は、わずかではあるがクウェートにも輸出されているらしい。アラビア半島において羊は遊牧民の代表的な家畜であるが、国民のほとんどが都市住民化したクウェートで流通している羊肉の大部分は、オーストラリアからの輸入ものである。断食月(ラマダーン)や犠牲祭で羊肉の需要が高まる時期に、オーストラリアから出港した船の中で、生きた羊が劣悪な環境におかれ、動物虐待だと問題視するニュースが流れるのは恒例である。
クウェート人もうまい羊肉を食べたいのは同じらしい。地産地消がブームなのか、新たに国産ブランド羊肉をつくろう、という動きがあるようだ。サウジアラビアとの国境に近い南部の、かつてのオアシス地域では、現代的な農場が広がり、その一角で牛や山羊と一緒に羊が飼われている。農場は地元流通大手が手掛けており、生産物は自社店舗で試験的に販売しているそうだ。いずれ美味しい地元産羊肉でもてなされてみたいものである。


著者プロフィール
石黒大岳(いしぐろひろたけ)。ジェトロ・アジア経済研究所地域研究センター研究員。学術博士。専門は比較政治学、中東湾岸諸国の政治参加と社会変容の研究。最近の著作に、『アラブ君主制国家の存立基盤』(編著)ジェトロ・アジア経済研究所(2017年)。
- 第1回 バングラデシュ――食らわんか河魚
- 第2回 クウェート――国民食マチブースと羊肉のはなし
- 第3回 ラオス――カブトムシは食べ物だった
- 第4回 タイ――うなだれる大衆魚・プラートゥー
- 第5回 トルコ――ラクの〆は臓物スープで
- 第6回 台湾――臭豆腐の香り
- 第7回 カンボジア――こじらせ系女子が食べてきた珍食
- 第8回 インドネシア――1本のサテがくり出す衝撃の味
- 第9回 中国四川省――肉食の醍醐味
- 第10回 ベトナム――「元気ハツラツ」じゃなかったハノイの卵コーヒー
- 第11回 ブラジル――「ツンデレの果実」ペキー
- 第12回 モルディブ――食べても食べてもツナ
- 第13回 フィリピン――最北の島で食す海と人の幸
- 第14回 タンザニア――ウガリを味わう
- 第15回 アメリカ――マンハッタンで繰り広げられる米中ハンバーガー対決
- 第16回 ニュージーランド――マオリの伝統料理「ハンギ」を食す
- 第17回 イギリス――レストランに関する進化論的考察
- 第18回 南アフリカ――「虹の国」の国民食、ブラーイ
- 第19回 デンマーク――酸っぱい思い出
- 第20回 ケニア――臓物を味わう
- 第21回 モンゴル――強烈な酸味あふれる「白い食べ物」は故郷を出ると……
- 第22回 インド――幻想のなかの「満洲」
- 第23回 マグリブ(北アフリカ)――幻の豚肉
- 最終回 中国――失われた食の風景
- 特別編 カザフスタン――感染症には馬乳が効く
世界珍食紀行(『アジ研ワールド・トレンド』2016年10月号~2018年3-4月号連載)
- 第1回「中国――多様かつ深遠なる中国の食文化」
- 第2回「ベトナム――食をめぐる恐怖体験」
- 第3回「気絶するほど旨い?臭い!――韓国『ホンオフェ』」
- 第4回「イラン――美食の国の『幻想的な』味?!」
- 第5回「キューバ――不足の経済の食」
- 第6回「タイ農村の虫料理」
- 第7回「ソ連――懐かしの機内食」
- 第8回「エチオピア――エチオピア人珍食に遭遇する」
- 第9回「多人種多民族が混交する国ブラジルの創造の珍食」
- 第10回「コートジボワール――多彩な『ソース』の魅力」
- 第11回「デーツ――アラブ首長国連邦」
- 第12回「ペルー ――アンデスのモルモット『クイ』」
- 第13回「ミャンマー ――珍食の一夜と長い前置き」
- 第14回「『物価高世界一』の地、アンゴラへ――ポルトガル・ワインの悲願の進出」