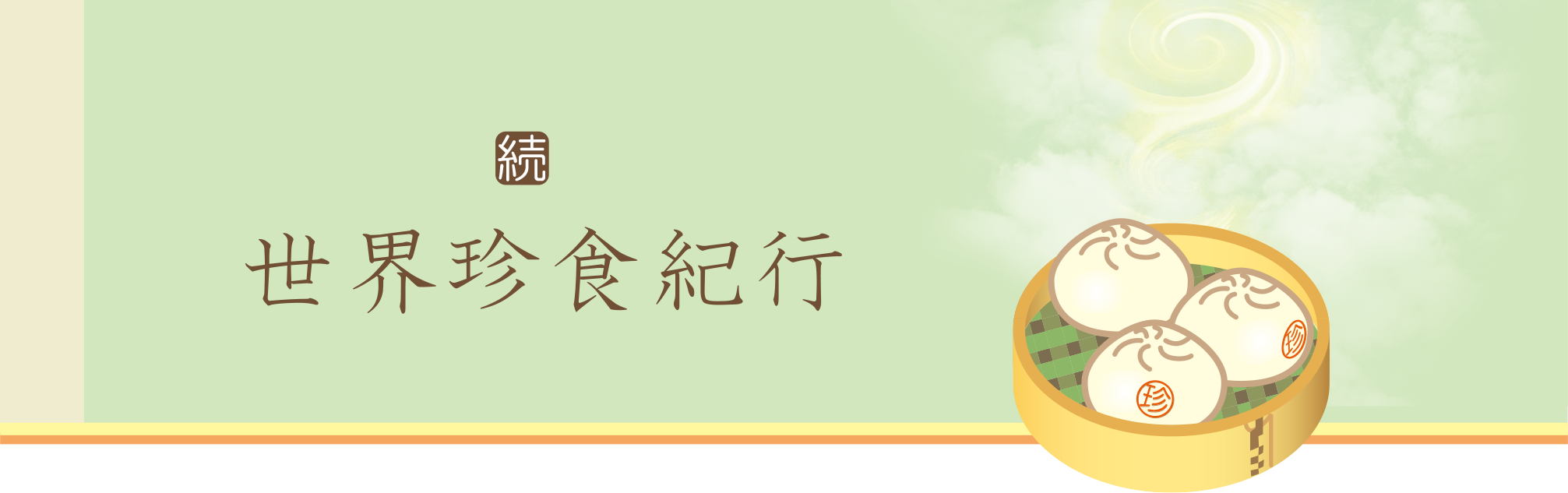IDEスクエア
コラム
第14回 タンザニア――ウガリを味わう
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00051446
2019年7月
(2,016字)
タンザニアでは、食事を終えた人が水道で手にこびりついたウガリを爪でこすり落としているのを見ることがある。それを見た外国人は「スプーンで食べればいいのに」と思うかもしれない。しかし、日本人が白いご飯を箸で食べるのと同じように、ウガリは手で食べて味わうものである。
基本的なウガリはメイズ(白いトウモロコシ)の粉を熱湯に入れて練って固めたもので、国によって呼び名は違うが、タンザニアをはじめ東南部アフリカで食べられている伝統的な主食である。タンザニア人はウガリを肉(牛肉、鶏肉、山羊肉など)や魚を焼いたり揚げたりしたものやトマトのスープで煮込んだもの、豆の煮物、青菜の炒め物、サラダなどと一緒に食べる。

製粉したメイズを使った白いウガリにはあまり味がないが、独特の粉の風味がある。タンザニア人は乳児の頃から、ウガリと同じ粉で作ったウジという粥を飲んでおり、その味に慣れているが、日本人には馴染みのない味である。筆者は初めてウガリを食べた時には珍しさから「これなら食べられる」と思ったが、その後、自分から進んで食べることは少なかった。タンザニアでは日本のような米(ただしタンザニア人が作るご飯には少量の塩と油が入る)も一般的に食べられていたので、主に白いご飯を食べていた。しかし、博士課程の研究の現地調査で、タンザニア最大の都市であるダルエスサラームの一般家庭に1年間泊めていただき、その家で作られるウガリを毎日のように食べていたら、いつのまにか、あたり前に食べられるようになっていた。ウガリの味に慣れたからだが、食べ方を習得したからでもある。
ウガリを食べる前には必ず手を洗う。レストランや一般家庭では、店員か家政婦がぬるま湯を入れた水差しと洗面器を持ってきて、手を洗わせてくれる。ローカルな食堂の場合、近くに水道があることが多いので、そこで手を洗う。
肝心のウガリの食べ方であるが、まずウガリの白い塊から、右手の親指、人差し指、中指で、一口で食べられる量をちぎって手のひらにおき、何度か転がし握りながら、団子を作る。最初はウガリが手につき、粘土をこねているような感覚になるが、思い切って握る。筆者の経験では、ここでしっかりウガリをこねると粉っぽさがなくなり、なめらかな餅のような質感になる(ただし餅のようにはのびない)。そして、ウガリの団子の真ん中に浅い溝を作り、指先に移動させ、それをスプーンのようにしておかずをすくって食べる。つまり、ウガリは食べる人の右手の中で完成し、スプーンの役割を担うのである。ウガリと汁物の主菜は手にくっつき、爪と指の間にも入るが気にしない。むしろ、くり返し食べているうちに、手にウガリがついてこそ食べているという実感がわくようになってくる。
写真の出典
- Chen Hualin "Ugali with beef and sauce," via Wikimedia Commons( GNU Free Documentation License, Version 1.2)
著者プロフィール
粒良麻知子(つぶらまちこ)。アジア経済研究所地域研究センター研究員。Ph.D. (Development Studies)。専門はタンザニア政治、比較政治学、開発学。最近の著作に、"Presidential Candidate Selection and Factionalism in Five Dominant Parties in Sub-Saharan Africa." IDE Discussion Paper No. 745(2019年)、「タンザニアの優位政党の大統領候補選考と派閥政治」、『アフリカレポート』55:79-91(2017年)など。
- 第1回 バングラデシュ――食らわんか河魚
- 第2回 クウェート――国民食マチブースと羊肉のはなし
- 第3回 ラオス――カブトムシは食べ物だった
- 第4回 タイ――うなだれる大衆魚・プラートゥー
- 第5回 トルコ――ラクの〆は臓物スープで
- 第6回 台湾――臭豆腐の香り
- 第7回 カンボジア――こじらせ系女子が食べてきた珍食
- 第8回 インドネシア――1本のサテがくり出す衝撃の味
- 第9回 中国四川省――肉食の醍醐味
- 第10回 ベトナム――「元気ハツラツ」じゃなかったハノイの卵コーヒー
- 第11回 ブラジル――「ツンデレの果実」ペキー
- 第12回 モルディブ――食べても食べてもツナ
- 第13回 フィリピン――最北の島で食す海と人の幸
- 第14回 タンザニア――ウガリを味わう
- 第15回 アメリカ――マンハッタンで繰り広げられる米中ハンバーガー対決
- 第16回 ニュージーランド――マオリの伝統料理「ハンギ」を食す
- 第17回 イギリス――レストランに関する進化論的考察
- 第18回 南アフリカ――「虹の国」の国民食、ブラーイ
- 第19回 デンマーク――酸っぱい思い出
- 第20回 ケニア――臓物を味わう
- 第21回 モンゴル――強烈な酸味あふれる「白い食べ物」は故郷を出ると……
- 第22回 インド――幻想のなかの「満洲」
- 第23回 マグリブ(北アフリカ)――幻の豚肉
- 最終回 中国――失われた食の風景
- 特別編 カザフスタン――感染症には馬乳が効く
世界珍食紀行(『アジ研ワールド・トレンド』2016年10月号~2018年3-4月号連載)
- 第1回「中国――多様かつ深遠なる中国の食文化」
- 第2回「ベトナム――食をめぐる恐怖体験」
- 第3回「気絶するほど旨い?臭い!――韓国『ホンオフェ』」
- 第4回「イラン――美食の国の『幻想的な』味?!」
- 第5回「キューバ――不足の経済の食」
- 第6回「タイ農村の虫料理」
- 第7回「ソ連――懐かしの機内食」
- 第8回「エチオピア――エチオピア人珍食に遭遇する」
- 第9回「多人種多民族が混交する国ブラジルの創造の珍食」
- 第10回「コートジボワール――多彩な『ソース』の魅力」
- 第11回「デーツ――アラブ首長国連邦」
- 第12回「ペルー ――アンデスのモルモット『クイ』」
- 第13回「ミャンマー ――珍食の一夜と長い前置き」
- 第14回「『物価高世界一』の地、アンゴラへ――ポルトガル・ワインの悲願の進出」