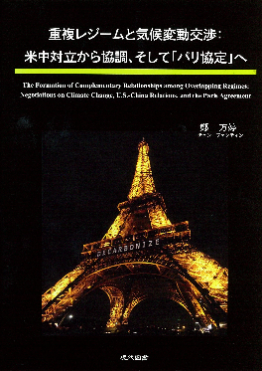IDEスクエア
コラム
目標13 気候変動に具体的な対策を――「カーボン・ニュートラル」に向けて何ができるのか?
Goal 13 Climate Action: what can be done towards carbon neutrality?
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00052898
鄭 方婷
Fang-Ting, Cheng
2022年1月
(4,583字)
気候変動対策と「カーボン・ニュートラル」
「目標13:気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」は、気候変動の深刻化を防ぐだけでなく、すでに発生している自然災害などにも対処する必要があるということも意味しています。とりわけ近年、気候変動は世界各地に影響を及ぼしており、熱波、干ばつ、豪雨、巨大台風といった異常気象と強い関連性があることから、差し迫った脅威として「気候クライシス(危機)」とも呼ばれるようになっています。目標13には具体的に気候変動の最大の要因であるとされる温室効果ガスの排出を減らすこと、つまり「緩和策」と呼ばれる行動と、深刻化する状況への対策として防災や減災を含む「適応策」が含まれています。
国際社会も対応を迫られており、2015年には国連気候変動枠組条約の第21回締約国会議(COP21)において、「パリ協定」が採択されました。パリ協定では、「緩和策」として温室効果ガスを削減することで「今世紀末までに産業革命以降の気温上昇を摂氏2度未満、できれば1.5度に抑える」という目標が盛り込まれています。これに基づき、各締約国は5年ごとに温室効果ガス削減計画の提出と更新を義務づけられています。
パリ協定の履行は目標13の達成に不可欠で、さらに対策は急いで行わなければなりません。これを科学的に示しているのが、2018年に国連の専門家組織である「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)によって作成された特別報告書です。この報告書では、2030~2052年に地球の平均気温が産業革命前に比べて1.5度上昇するという予想に基づき、今世紀末に予想される極端な気候リスクを回避するには「2050年前後の時点における温度上昇を1.5度以下に抑える必要がある」とし、パリ協定よりもさらに野心的な目標を実現する必要性を世界に訴えています。また同報告書には、「2050年に1.5度以下」を実現するためには「地球全体で温室効果ガスの実質的な排出量をゼロにし、2050年以降も実質排出量がゼロより少ない状態を維持しなければならない」と記されています。この背景には、「早急に」排出量を削減する対策を開始しなくてはならないという考えがあります。
地球全体で温室効果ガスの実質的な排出量をゼロにすることを「カーボン・ニュートラル(炭素中立)」といいます。二酸化炭素(CO2)、メタン、一酸化二窒素、フロンなど様々な温室効果ガスのなかでも排出量が圧倒的に多く、気候変動に最も大きな影響を及ぼすのが人間の社会経済活動によって発生する人為起源のCO2です。このため、カーボン・ニュートラルは、狭義では「人為起源のCO2について、排出量と吸収(もしくは除去)量が同程度になるよう調整することで、大気中の炭素濃度を一定に保つ取組み」です。
人為起源のCO2の多くは発電プロセスや燃料の使用などエネルギーの生産過程で放出されています。CO2の排出を制限するためには、電気自動車のような低排出量の交通手段を選択するといった身近なものから、太陽光発電、風力発電などCO2を排出しないクリーン・エネルギーの普及、大気中に放出される前、もしくは既に放出されたCO2を回収して地下や海中に貯留する炭素の回収・利用・貯留技術の開発、CO2の吸収源である森林の面積拡大まで、多様な分野・規模で対策をとることが可能と考えられています(写真1)。

環境保護エリアに位置しており、著名な観光地にもなっている。
また、前述のIPCCは2021年8月にもうひとつ重要なレポートとなる「第6次評価報告書」を発表し、人間の活動が気候変動に与える影響を「疑う余地がない」と初めて断定して、1.5度上昇が前回2018年の特別報告書で指摘していたよりも10年早まると分析しました。さらに最新の科学的知見として、カーボン・ニュートラルの達成が遅れた場合、今世紀後半には地球の平均気温が2度弱上昇する可能性もあると警告しています。世界各国の「温室効果ガスの実質排出ゼロ」の達成手段や期限については今なお不透明な部分が多く、積極的なカーボン・ニュートラルの取り組みがなければ、気温上昇を「1.5度」あるいは「2度」に抑える目標が達成されない可能性があるとの指摘も出ています。
このような状況を受け、EU、中国、アメリカなど主要排出国は近年相次いで2050年を期限とするカーボン・ニュートラルの目標を打ち出しています。その数は現在130カ国以上に及ぶなど、大きな潮流となっています。
実際に2021年11月に閉幕した国連気候変動条約の第26回締約国会議(COP26)(写真2)では、CO2より温室効果の高いメタンを2030年までに2020年の水準から30%削減、あるいはCO2排出の多い石炭火力発電を段階的に廃止するといった提案が多くの国の賛同を得るなど、カーボン・ニュートラルの具体的な達成方法についての議論も始まっています。次のセクションでは、主要各国のカーボン・ニュートラル目標と、その達成に向けた取り組みを詳しくみていきましょう。

主要排出国による2050年「カーボン・ニュートラル」目標
カーボン・ニュートラルの先駆者はやはり欧州連合(EU)です。EUは、2019年には既にカーボン・ニュートラルを宣言しています。翌2020年6月には欧州の新たな気候変動対策となる「ヨーロピアン・グリーン・ディール」を正式に発表し、カーボン・ニュートラル宣言により具体性を持たせて対策を強化しました。
また新型コロナウイルス感染症によって経済が大きな打撃を受けた後、回復が本格化してきた2021年7月には「欧州気候法」を成立させています。この法律には、2030年に1990年比で温室効果ガスの排出量を55%削減する目標とそのための政策パッケージ「Fit for 55」が盛り込まれるなど、EUの気候変動対応での本気度が表れた積極的な内容となっています。
一方、現在世界最大の温室効果ガス排出国である中国は2020年9月、「2030年までにCO2総排出量を頭打ちにさせ、2060年のカーボン・ニュートラル実現に努める」という新たな約束を公表しました。この目標は、向こう5年間の中国全土の開発計画で経済施策に対しても拘束力を持つ「第14次五カ年計画(2021~2025年)」に盛り込まれています。
また、世界第2位の排出国であるアメリカでは、2020年大統領選挙の結果を受けて脱炭素・気候変動対策が再び脚光を浴びています。バイデン大統領は2021年の就任後、早速「2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロとすること」を優先的な政策として正式に打ち出しました。4月下旬にはオンラインにて中国、EU、日本など40カ国の首脳が参加した「気候変動に関する首脳会議」を主催するなど、トランプ政権で縮小した国際交渉での外交的主導権を取り戻そうとする動きもみられます。なお、アメリカは同会議を開く直前に自国の排出削減目標を発表し、2030年に温室効果ガス排出量を2005年比で50~52%削減すると約束しています。
主要排出国の一員である日本も、近隣の中国、韓国に続き、2020年10月にカーボン・ニュートラルを宣言しました。これは上記アメリカ主催の気候サミットに合わせて設定された目標で、全体の温室効果ガス排出量を2030年に2013年比で46%削減するという内容です。これに伴い、発電プロセスで温室効果ガスを放出しない再生可能エネルギーが全体に占める割合を36~38%に引き上げるなど、電源構成(発電に利用される火力や原子力、各種再生可能エネルギーなどの内訳)の調整も行われています。
しかし、すべての国が現時点で発表している削減目標を計画どおり実行しても、2030年時点での排出量は2010年の水準よりも13.7%増加するという試算が新たに発表されるなど、カーボン・ニュートラルの達成は非常に厳しい現実に直面しています。2030年の中期目標、さらには2050年の長期目標を達成するには、今よりさらに野心的な目標を打ち出すだけでなく、将来的には大気中のCO2を回収・利用・貯留するなど科学技術を積極的に利用する必要に迫られると考えられています。
「カーボン・リーケージ」への対策
脱炭素を進めるにあたっては懸念もあります。温室効果ガスの排出規制が厳しい国において生産活動や投資が縮小し、その結果として温室効果ガス排出量が減っても、生産活動が規制の緩い国に移転し、別の国で生産活動や投資が拡大して温室効果ガス排出量が増加する、ということが起こりえます。いわゆる「カーボン・リーケージ(炭素の漏れ)」の問題です。
EUは、カーボン・リーケージの可能性を念頭におき、新たな規制を始めています。前述の政策パッケージ「Fit for 55」の発表に合わせる形で、EUは「炭素国境調整措置」、あるいは「国境炭素税」とも呼ばれる規制案も公表し、世界中から注目を集めました。これは、EU域内の事業者が炭素国境調整措置の対象製品を域外から輸入するにあたって、生産過程で排出された炭素の量に応じて関税などの形でEUと「同等」の負担を課す措置となっています。同等の負担とは、当該製品がEU域内で製造された場合にEU排出量取引制度に基づいて課される炭素価格を指します。炭素国境調整措置は予備段階として2023年から報告制度がスタートし、2026年からは本格的な導入と共に支払いが義務化されることになっています。
この措置導入の目的は、主にカーボン・リーケージのリスクを低減することにあり、特に製鉄、セメント、アルミニウム、電力などリスクの高い産業が対象となっています。今後はEU主導の下で、WTOルールとの整合性をとりながら、多国間、または二国間貿易交渉を通じて詳細に検討・議論される予定です。
SDGsの役割とは
IPCCの第6次評価報告書が指摘するように、気候変動は今後も深刻化し続ける公算が大きく、これを食い止める、もしくは遅らせるには、人類による努力が不可欠です。特にCO2排出の多い化石エネルギーへの依存から脱却することは最も緊急性が高いのですが、世界全体では依然、削減に向けた努力が不足しています。
そのなかでEUは、一歩踏み込んだ積極的な対応で世界をリードしています。その最新の対応策は、ただEU域内に炭素税を導入するだけでなく、貿易活動を通じて域外にも適用し、広く低炭素化を促そうとするものになっています。多くのグローバル企業はすでに、今後の競争力を保つためにカーボン・ニュートラルや脱炭素のコミットメントを宣言し、国内外にある部品の提供元、輸出先など製品の生産・販売過程にかかわるすべての事業者に対して排出削減など対策の強化を求めています。
このように、カーボン・ニュートラルがもたらす社会の脱炭素化は、各国・地域の気候変動対策の実施、それに伴う事業者の対策を含め、これから本格化していくでしょう。しかし、気候変動への対策を行うのは政府や企業だけではありません。ターゲット13.3で挙げられているように、メディアや教育機関、そして様々な団体による市民や学生などへの啓発と教育活動を通じ、社会全体が気候変動の緩和策と適応策に取り組んでいく必要があります。
さらに学びたい人へ――IPCCによる科学的知見が国際交渉に与えた影響
「今世紀末までに世界平均気温の上昇を産業革命前に比べて摂氏2度より十分低く、摂氏1.5度未満に抑える努力をする」ことは、2015年のCOP21で合意・採択された「パリ協定」に記されていて、現時点において気候変動の深刻化を防ぐための最終目標です。この最終目標の設定にあたり、温室効果ガス排出量の増加による気候変動の進行状況や、「1.5度」と「2度」の気温上昇がもたらす被害の予測に関して精密な科学的知見を提供したのはIPCCです。IPCCは、人類が引き起こす気候変動の現状、その影響と評価を行うことを目的として国連環境計画と世界気象機関によって1988 年に設立された国連の専門家組織であり、これまで数回にわたり評価報告書を発表しています。これらの報告書においては、確実に起きている気候変動とそのインパクトが科学的エビデンスに基づいて指摘されており、国際交渉過程にも多大な影響を及ぼしてきました。
これまでの気候変動の国際交渉においては、中国やインドなどの途上国は、気候変動を引き起こした責任が主にアメリカやEU、日本といった先進国にあると主張し、一方の先進国側は、この数十年で著しい経済成長を成し遂げた途上国こそ問題を大きく深刻化させた責任があると反論してきました。双方の主張は長い間平行線をたどり、先進国と途上国の両方を含む主要排出国が取るべき行動について、なかなか結論に至りませんでした。
しかし、IPCCの予測モデルは時間の経過とともに確実に精度が向上しており、近年では、より厳しい未来を提示する結果が報告されています。これにより、主要排出国にかかるプレッシャーが年々強くなっているだけでなく、以前のような途上国と先進国との間の強い対立構造にも変化が見られるようになりました。IPCCの報告書がパリ協定を合意に導く要因のひとつとなったと言っても過言ではありません。
パリ協定で合意された最終目標を実現するには、すべての国の努力によって可能な限り温室効果ガスの総排出量を削減しなければなりません。今後も主要各国をはじめ、世界全体での脱炭素の動向を注視していく必要があるのです。
写真の出典
- 写真1 筆者撮影
- 写真2 UNclimatechange, UNFCCC_COP26_2Nov21_WaterClimateCoalition_Kiara Worth-10.(CC BY-NC-SA 2.0)
参考文献
- European Commission. (2021) Fit for 55: delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality. Brussels, July 14, 2021.
- IPCC. (2018) Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp.
- IPCC. (2021) Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
- Tanaka, Katsumasa and Brian C. O’Neill. (2018) “Paris Agreement zero emissions goal is not always consistent with 2°C and 1.5°C temperature targets.” Nature Climate Change 8, pp. 319–324.
- 鄭方婷(2013)『「京都議定書」後の環境外交』三重大学出版会。
- 鄭方婷(2017)『重複レジームと気候変動交渉:米中対立から協調、そして「パリ協定」へ』現代図書。
著者プロフィール
鄭方婷(チェンファンティン) アジア経済研究所新領域研究センター法・制度研究グループ研究員。2019~21年6月に海外研究員として台湾・台北に滞在。専門は国際関係論、国際政治学、地球環境問題、グローバル・ガバナンス論。主な著作に、『「京都議定書」後の環境外交』(三重大学出版会、2013年)、『重複レジームと気候変動交渉:米中対立から協調、そして「パリ協定」へ』(現代図書、2017年)などがある。
【連載目次】
おしえて!知りたい!途上国とSDGs
- 第1回 激論!SDGsってなに?(前編)――SDGsは途上国の開発に役立っているの?
- 第2回 激論!SDGsってなに?(後編)――私たちにできることは何があるの?
- 目標1 貧困をなくそう――「正義」の問題として
- 目標2 飢餓をゼロに――現在と将来の世代に十分な食料を供給する
- 目標3 すべての人に健康と福祉を――必要な保健医療サービスを誰もが受けられる世界へ
- 目標4 質の高い教育をみんなに――何をすべきか
- 目標5 ジェンダー平等を実現しよう――すべての女性が能力を発揮できる社会に
- 目標6 安全な水とトイレを世界中に――水とつながる多様な課題
- 目標7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに――経済発展に役立つエネルギーを取り戻せ
- 目標8 働きがいも経済成長も――働きやすく、生きやすい未来に向けて
- 目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう――多様性に富む持続可能な経済社会の実現に向けて
- 目標10 人や国の不平等をなくそう―― 世界を支配する「象」を倒せるか
- 目標11 住み続けられるまちづくりを――市民ひとりひとりを大切にする安全な都市とは
- 目標12 つくる責任、つかう責任――循環型社会ってなに? ごみ問題から考える国際協力
- 目標13 気候変動に具体的な対策を――「カーボン・ニュートラル」に向けて何ができるのか?
- 目標14 海の豊かさを守ろう――ハイブリッドな実施手段の活用
- 目標15 陸の豊かさも守ろう――東南アジアのアブラヤシと私たちの消費生活
- 目標16 平和と公正をすべての人に――制度はどこに?
- 目標17 パートナーシップで目標を達成しよう――持続可能な開発に向けてグローバルなパートナーシップを活性化する
- SDGsのここってどうなの?――SDGsの専門家に聞いてみた