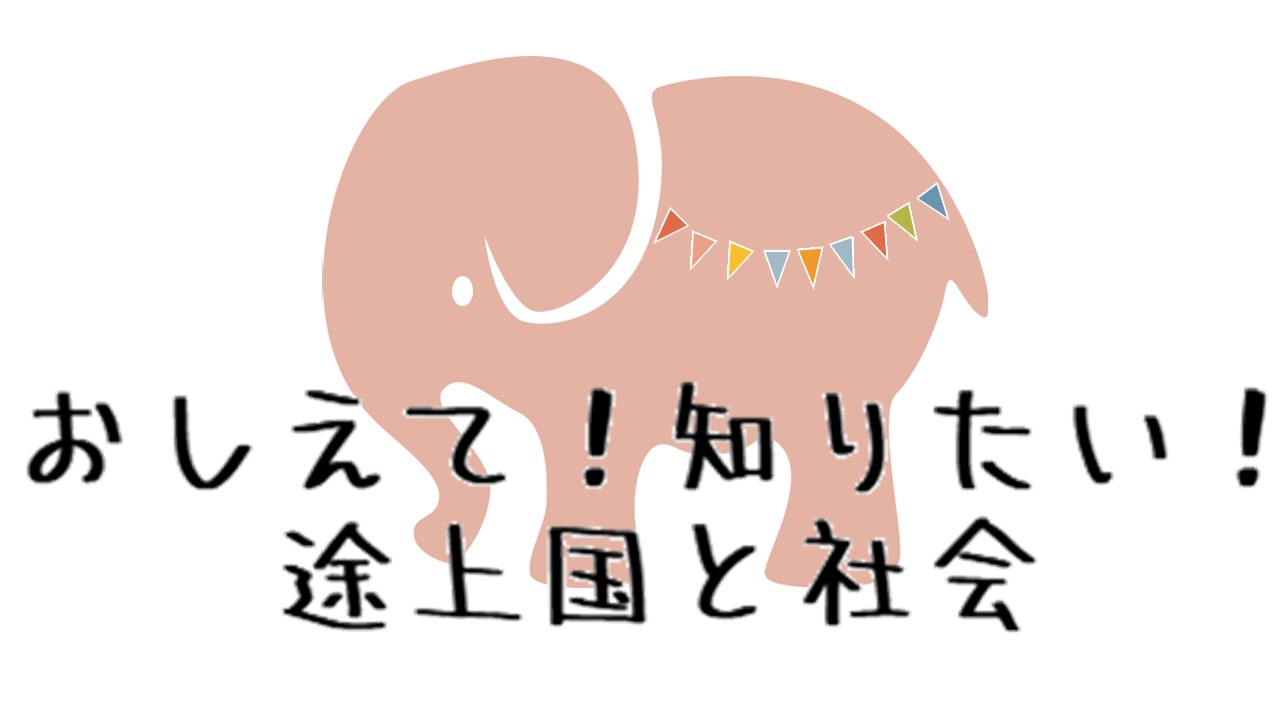IDEスクエア
コラム
第22回 途上国の経済成長を支えているのはどんな産業ですか?
Which Industries Are Driving Economic Growth in Emerging Economies?
PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001554
2025年11月
(2,374字)

産業と一言で言っても、農業から製造業、サービス業までいろいろあるし、最近は途上国でもICT(情報通信技術)産業が発展しているみたい。経済成長を支えているのは一体どの産業なんだろう?
はじめに
私たちの生活は、さまざまな種類のモノやサービスを生産・消費することで成り立っていますよね。そこでまずは、経済を構成する産業を整理しておきましょう。産業は、なにを、どう生産するのかを基準にして、つぎのように分類することができます。
- 第一次産業:農業、林業、漁業など
- 第二次産業:鉱業、製造業(工業)、建設業など
- 第三次産業:運輸業、卸売・小売業、飲食業、金融業、情報通信業など、幅広い分野のサービス業(第一次・第二次産業以外の全産業とすることもあります)
第一次・第二次産業はかたちのあるモノを生産し、第三次産業はかたちのないサービスを提供しています。
製造業とサービス業の発展
どの産業も経済成長に貢献していますが、日本をはじめとした多くの国で、製造業やサービス業の急速な発展が長期的な経済成長を支えてきました。人類の歴史を振り返ると、はじめは農業が経済活動の中心でしたが、まずは製造業が、つぎにサービス業が新たな中心になることで、産業構造が変化してきました。言い換えると、製造業やサービス業によって生み出される付加価値(生産額から原材料費などの費用を引いたもの)の総額や、これらの産業の就業者数が、経済全体のなかで大きな割合を占めるようになっていきました。つまり、新しい産業がつぎつぎに生まれるような変化こそが長期的な経済成長を支えている、とも言えます。
製造業の急速な発展(工業化)は、18世紀半ば(日本の江戸時代中期)以降のイギリス産業革命によってはじまりました。工業化の波は、まず、欧米や日本に広がり、第二次世界大戦後、韓国やタイなどの北東・東南アジア諸国をはじめとした多くの途上国にも広がりました。工業化が進む場合、はじめに、繊維工業や食料品工業などの軽工業が発展する傾向があります。さらに進展する場合、金属工業や化学工業、機械工業 (自動車、家電など) といった重化学工業や、機械工業のなかの情報通信技術(ICT)製造業(パソコン、スマートフォン、半導体など)といった先端技術製造業が発展する傾向があります。途上国は、賃金の安さを活かした生産から、資本や技術が必要な生産へ、製造業の中心を変化させることで、長期的な経済成長を実現できるようになります。
しかし、あらゆる国が容易に工業化を実現できるなら、途上国の成長問題はそもそも存在しません。途上国は、先進国の資本を受け入れたり、技術を導入したりすることで、急速な工業化を実現できるかもしれませんが、一方で、豊富な資本や技術を持つ先進国の工業製品が途上国市場にあふれることで、工業化の芽が摘み取られてしまう恐れもあります。このことも一因となって、インドネシアやインドなどの東南・南アジアの国や、アフリカや中南米などの多くの途上国の産業構造に対して、工業化が未熟な段階で停滞する「早すぎる脱工業化」を問題視することがあります。これに陥ると、工業化を通じた雇用創出や技術蓄積が十分に進まない可能性があります。
つぎに、サービス業の急速な発展は、まず、1970年代以降の先進国で起き、その後、多くの途上国でも起きました。サービス業は、各産業の発展によって、より大規模な流通や資金調達が必要になったり、所得水準の向上によって外食や娯楽、情報通信の消費が活発になったりすることで発展します。また、ICTの発展によって、ソフトウェアやシステムの開発をはじめとしたICTサービス業が誕生しました。インドのように、今後さらに工業化する可能性もありますが、ICTサービス業の急速な発展が、経済成長のけん引役の一つになってきた国もあります。このような技術変化によって、サービス業が主導する経済成長の可能性にも注目が集まっています。

写真は、運転が部分的に自動化したバス。
産業構造が変化する要因
それでは、産業構造はなぜ変化するのでしょうか? 経済の中心が農業から製造業やサービス業に移行する場合で考えてみましょう。
まず、需要面から見た要因として、所得の増加による、消費の変化があります。人間は一般に、所得の増加に合わせて食べる量をどんどん増やせるわけではありませんし、高級な食材を買うようになったとしても、それ以上に工業製品やサービスの消費を増加させる傾向があります。つまり、所得の増加にともなって消費支出に占める食料費の割合が低下します(エンゲルの法則)。その結果、第一次産業以外の産業が急速に発展することになります。
つぎに、供給面から見た要因として、技術の変化による、必要な労働力の減少があります。農業の生産性が向上すると、農業従事者が兼業したり、一部の農業従事者が農業を辞めて他の産業に移動したりしても、これまでと同量かそれ以上の農産品を生産できる可能性があります。もし生産量が減ると(ここでは輸入を考えないものとします)、価格が高騰し、人々の生活が苦しくなったり、価格高騰が他の産業にも波及することでモノやサービスが売れなくなったりする恐れがありますから、農業の生産性向上は、製造業やサービス業の発展の条件になっている、とも言えます。
おわりに
さまざまな産業が存在するので、経済成長との関係は複雑ですね。さらに、政府が打ち出す政策・制度や、外国とのあいだの貿易・投資も、各産業の発展に影響を与えるため、一層複雑になります。経済学ではさまざまな条件下の影響が研究されていますので、興味が湧いたらぜひ学習してみてください。その際、将来の仕事として興味のある産業を中心にすえて、各産業がどう関係しながら、私たちの生活全体を支えているのかを調べてみてください。そして、狩猟採集による自給自足からはじまった人類の経済活動が、どんな変化をたどりながら今のすがたになったのか、さらに、今後どこへ向かうのか、その歴史的展開と未来をぜひ探究してみてください!
写真の出典
- 2024年に千葉県柏市で筆者撮影
回答者プロフィール
木村 公一朗:アジア経済研究所 主任研究員。企業の競争が、産業発展や産業構造変化を通じて、経済成長にどのような影響をあたえているのかを研究しています。関連する自己紹介動画はこちらにあります。また、このコーナーでは、「第3回 研究テーマは何ですか? なぜそれにしたんですか?」と「第7回 途上国についてどのように調べたらいいですか?」にも回答しました。興味が湧いたらぜひご覧ください!
- 第1回 途上国の企業が先進国に進出することもあるのですか?
- 第2回 ベトナムの文化や習慣で驚いたことや尊敬していることはありますか?
- 第3回 研究テーマは何ですか? なぜそれにしたんですか?
- 第4回 途上国の縫製工場に女性が多いのはなぜですか?
- 第5回 発展途上国と先進国を分ける基準って何ですか?
- 第6回 発展途上国が先進国になるには何年かかりますか?
- 第7回 途上国についてどのように調べたらいいですか?
- 第8回 なぜアフリカでは紛争が多いんですか?
- 第9回 発展途上国で食料に困っている人はどれくらいいますか?
- 第10回 途上国に外国企業が工場を作ると、その国の発展につながるのですか?
- 第11回 発展途上国の支援のために私たちができることって何でしょう?
- 第12回 途上国に援助すると、日本にとってどんないいことがあるのですか?(高校生、兵庫県)
- 第13回 現地での一番の収穫は何ですか?
- 第14回 「アジア連合」ってないんですか?
- 第15回 地球温暖化をめぐり途上国は先進国と対立しているのですか?
- 第16回 途上国はどのように治安を改善しているのですか?
- 第17回 開発途上国は気候変動にどのように対応しているのですか?
- 第18回 歴史認識は途上国の政治や社会にどのような影響を与えていますか?
- 第19回 なぜ社会主義国で格差が生じるのですか?
- 第20回 どうしたらウクライナに平和が戻りますか?
- 第21回 途上国の水不足問題について教えてください
- 第22回 途上国の経済成長を支えているのはどんな産業ですか?