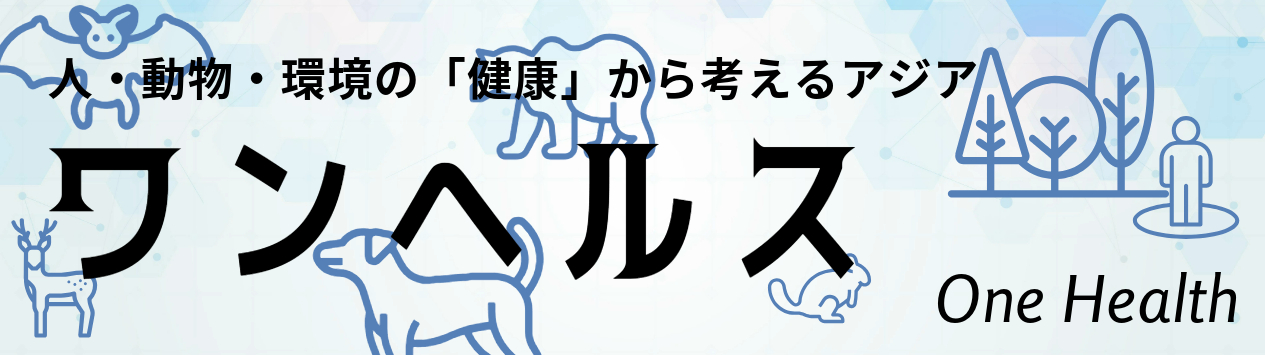IDEスクエア
コラム
第4回 ベトナムのワンヘルス・アプローチ──理想と現実のギャップ──
One health approach in Vietnam: Gap between ideal and current situation
PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001383
2025年5月
(4,669字)
ベトナムはパンデミック対応の優等生?
2003年1月の重症急性呼吸器症候群(SARS)と同年12月のH5N1鳥インフルエンザ(以下、H5N1)の流行時以来、ベトナム政府は、世界保健機関(WHO)、国際獣疫事務局(OIE/WOAH)、国連食糧農業機関(FAO)などの国際機関や先進国の援助機関、NGOなどと積極的に連携し、その後発生したパンデミックに対応してきた。これを、ベトナム共産党の一党支配を正当化するためのパンデミックの政治利用とする批判はあるものの、ベトナムにおける国際社会との連携や、国際的なガイドラインに沿った情報開示や感染防止の姿勢には、高い評価がなされてきた1。
とはいえ、その結果として、ベトナムでパンデミックの発生、拡大が抑えられたのかというと、実はそうではない。H5N1は、2003年から2008年にかけて6回にわたり拡大し、その間に数千万羽の鶏が殺処分され、経済的な損害はインドネシアに次ぐ規模であったと言われている。家畜の感染症としては、2019年1月からアフリカ豚熱(African Swine Fever: 以下、ASF)が流行し、600万頭が殺処分されている。また、COVID-19の流行も2021年半ばまではその抑制に成功していたが、2021年半ばからは、近隣のアジア諸国と比べても大規模な拡大を経験することとなった。
このような政府の取り組みに対する海外からの高い評価と実際の感染抑制のパフォーマンスの低さのギャップがベトナムでなぜ生まれるのだろうか。それは、中央集権的な政治・行政体制のあり方に加え、1990年代以降の市場経済化がもたらした急速な経済発展の過程に起きた家畜飼育の拡大とサプライチェーンの複雑化に関連している。
ワンヘルス・アプローチの取り組み
ベトナムは、東南アジアでは最も早くセクター横断的なワンヘルス・アプローチに取り組み始め、感染症対策を講じるための組織的枠組みづくりに着手した。SARSの流行から3年後の2006年、26の国内外の省庁や機関が参加する「鳥および人インフルエンザに関するパートナーシップ」(Partnership on Avian and Human Influenza: PAHI)という組織が設立された。このように政策策定のための枠組みづくりを省庁横断的に、そして海外の機関も巻き込んで行っていることが、ベトナムの感染症対策に対する海外からの高い賞賛の理由である。その後PAHIは「ワンヘルス・パートナーシップ」(One Health Partnership for Zoonoses: OHP)へと名称を変え、この組織が感染症の予防、拡大防止対策の計画策定を主導してきた。OHPが運営するOne Health Viet Namというウェブサイトでは、毎年国際機関などと連携してOHPが開催する、さまざまなセミナーや国際会議が紹介されている。
H5N1の対策を担った農業・農村開発省の畜産局がOHP設立を主導したという出自ゆえ、OHPは「マルチセクター・アプローチ」を謳いながらも、実際の主な関心事項は、人獣共通感染症や家畜の感染症対策にある。2022年に公布された現行のワンヘルス「マスタープラン」では、感染症対策の柱として、幅広い情報発信、農家や畜産物サプライチェーンの当事者たちへの啓発、知識の浸透、対話の促進に加え、データ共有、早期警報システムの導入といったシステムづくりまで幅広くリストアップされている。さらに、明確に具体的な政策転換の必要性が示されている項目として、「小規模家畜飼育に対する規制」という方向性を打ち出している。小規模の家畜農家の数を減らし、「工業的な」大規模飼育を奨励することで、人間の人獣共通感染症への暴露のリスクを減らし、食の安全を促進できるとしている。
問題は、ワンヘルスのマスタープランが、家畜飼育や畜産物サプライチェーンの現状を変えることができるのかという点である。ベトナムは中央集権的な体制のもと、中央政府が政策を策定し、地方政府や地方の社会団体などがその実施を担うという、トップダウンの役割分担がはっきりしている。OHPが示す方向性は、あくまでも国際機関等のガイドラインに沿ったものであり、それが実情に合っていない、あるいは地方政府による効果的なアクションにつながらないことが感染抑制のパフォーマンスの低さに関連している。
感染リスクの高い家畜農家
上述の「マスタープラン」が目指す「小規模農家の規制」という方向性は、家畜の感染症が「伝統的」な小規模経営の農家で起こりやすいため、「近代的」(あるいは「工業的」)な飼育に転換すべしというものである。しかし、この「伝統的」「近代的」という二項分類は、ベトナムの現状を見誤らせる。ベトナムでは、経済成長に伴い食肉生産と消費が急拡大しているが、この成長を支えてきたのは、伝統的でも近代的でもない、市場経済化開始後の1990年代以降、比較的新たに家畜飼育を始めた中規模の農家なのである。ベトナム農村では伝統的に、主たる農作物であるコメの生産に加え、1〜2頭の豚、鶏なら10羽程度を飼育する家計経営が行われていた。家畜は祭事に供されたり、急な出費が必要な際に販売されたりしてきた。一方、市場経済化後に増加してきたのは、豚であれば数十頭、鶏ならば百羽を超える数を専用の畜舎で商業的に飼育している中規模な家畜飼育農家である。
そして、これら中規模な農家こそが家畜の感染症発生・拡大の高いリスクを抱える層である。伝統的な飼育方法は開放型(豚小屋は人のトイレと併設、鶏は敷地内放し飼い)であるため、外部からのウイルス感染に対して脆弱ではあるものの、飼育個体数が少なく飼育密度が低いため、大規模な感染拡大や経済的な損害のリスクは低い。一方、近代的な大規模農家は、閉鎖型の専用畜舎で飼育しているため、ウイルスに暴露するリスクは低い。対して、多くの中規模農家の場合、伝統的な飼育方法の農家に比べると家畜の集中度は高く、閉鎖度・隔離度は低い。大規模農家のほとんどは企業との契約により、企業が指定する配合飼料を家畜に与え、企業が提供する獣医サービスを受けるという徹底した「バイオセキュリティ管理」を行っているが、中規模農家は、ワクチン接種、家畜の健康状態の管理、家畜/ヒトあるいは別種類の家畜同士の接触の回避などを、自らの知識と経験で行わなければならない。

多様で複雑な畜産物サプライチェーン
感染症のもうひとつの感染源は、畜産物のサプライチェーンであるが、ベトナムの畜産物サプライチェーンは非常に多様で複雑であり、すべてを網羅する感染対策は困難である。タイのCPグループなどの外資も含め、多くの大規模食品企業が畜産物サプライチェーンに参入しており、これらの企業は、生産(主に大規模農家に委託生産)から加工、流通まで一貫した、インテグレーション型のサプライチェーンを構築している。ただし、これらの企業が供給するのは、主にスーパーマーケットや専門の小売店(都市部では「安全食品」を売りにする小売店が増えている)向けの食肉、加工肉であり、供給量はまだ限られている。ベトナムでもスーパーマーケットは増えているものの、大企業のサプライチェーンに組み込まれていない農家や商人などが形成する地場サプライチェーンの存在は大きく、経済成長や都市化とともに、さらに多様化、複雑化の度合いが増している。
まず、豚についてみると、農家が豚を屠畜(とちく)することはほぼないため、多くの農家は屠畜業者に豚を売ることになる。そして、屠畜業者から小売業者や飲食店、消費者に売られ、その間の取引の間に中間商人が入る。小売業者は市場や小規模店舗、飲食店も屋台からレストランまでさまざまな形態がある。また、屠畜した枝肉をどの段階で食用サイズの豚肉や臓物などに加工するかも流通ルートにより異なっている。
鶏の場合、食肉用の鶏は大別すると「有色鶏」と呼ばれる在来種と外来種である「白色鶏」の2種類があり、さらに卵や雛鳥も取引されるため、サプライチェーンはさらに多様である。食用肉については、大企業によるバイオセキュリティ管理レベルの高いサプライチェーンで供給されるのは白色鶏であるが、商業的に飼育された鶏の72%は小・中規模農家により飼育され有色鶏が占める。有色鶏だけをとってもその地場サプライチェーンはより複雑である。いわゆる「地鶏」の種類も多く、販売先も市場、販売店、屋台、レストランなど多様である。また、結婚式の料理に有色鶏は欠かせないため、結婚式業者(主に個人事業主)向けの鶏の特別なサプライチェーンも存在する。

枝肉を仕入れて店内で小分けにしている(ハノイ市、2023年12月)
行動変容は可能か
豚344万世帯、鶏783万世帯という飼育農家世帯数の規模(2016年時点)に鑑みれば、短期間のうちに小・中規模の家畜農家を退出させ、家畜市場をインテグレーション型のサプライチェーンに集約させることは困難である。そのため、現在は、政府や国際機関、NGOなどがヘルスワーカーを派遣して、情報発信や啓発活動、教育・訓練を行い、小・中規模農家や地場流通業者の意識を向上させ、行動変容を促すというのが主要な感染症対策となっている。
しかし、H5N1流行時やそれ以降の家畜農家の行動を研究する人類学者たちの研究2 では、個々の農家や商人への働きかけで行動変容を促すことの難しさが指摘されている。外部者が科学的な知識として語る感染症の脅威やその原因、解決策と、農民や商人たちの経済的、社会的、文化的なコンテクストのなかで認識するそれらとのギャップが存在するからである。たとえば、政府がH5N1を新たな対策が必要な脅威と喧伝する一方で、農家は、これまでにも経験した数多くの感染症のひとつ(家禽の感染症の種類は多い)と認識し、旧来の対策の徹底が重要と捉えていた。また、農家が感染症予防の知識を得たとしても、周りの人たちに対して、家畜との接触を制限したり、「正しい」行動を要求したりすることが経済的、社会的に受容されないケースも多い。たとえば、ベトナム農村では、来訪した高齢者に手洗いを要求することが失礼に当たるといった社会慣習が存在する場合もある。また、外部からの働きかけで意識が変わり、行動が変容したように見えても、それが必ずしも持続的なものになるとは限らない。事実、H5N1の第2波以降の感染拡大時には、家畜の人からの隔離や家畜のハノイ中心部への持ち込みの禁止といった移動制限の措置は、途中から徹底されなくなっていた。
国際的な公衆衛生の専門知識に照らすと、多くの途上国の現状はあるべき理想の姿とは程遠く、それは、経済的、社会的な特徴が感染拡大の「原因」であり対策実行のための「障壁」になっているから、と捉えられがちである。そのため、「正しい」情報の提供や教育を通して農家や商人、屠畜業者ら個人の行動変容を促すことが重要という結論になる。しかし、彼らの行動はローカルな経済構造や家畜産業全体の構造、社会関係に規定されており、「正しい」情報が彼らの行動を変容させるとは限らない。現状の家畜農家や地場サプライチェーンの当事者たちが経済的、社会的に受容可能な方策(たとえば伝統的な感染症対策の再評価やインセンティブの設定など)や、個人の行動変容以外の対策(たとえば早期警報システムの導入など)をより強化した多面的なアプローチがワンヘルス戦略の実践には求められているといえるだろう。
付記
本コラムは『アジアのワンヘルス──人・動物・環境をめぐるリスクとガバナンス──』(アジア経済研究所、2025年2月)の刊行をふまえて社会科学的な観点からアジアのワンヘルスをめぐる課題について解説を行っていきます。第4回は第6章「ベトナムの家畜市場と人獣共通感染症対策──ワンヘルス・アプローチの実現と課題──」(147~166ページ)をもとにしています。詳しくは同書(オープンアクセス)をお読みください。
※この記事の内容および意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。
写真の出典
- 写真1 荒神衣美撮影
- 写真2 筆者撮影
著者プロフィール
坂田正三(さかたしょうぞう) アジア経済研究所地域研究センター主任調査研究員。専門はベトナム地域研究。主な著作に「ベトナムの家畜市場と人獣共通感染症対策──ワンヘルス・アプローチの実現と課題──」大塚健司編『アジアのワンヘルス──人・動物・環境をめぐるリスクとガバナンス──』アジア経済研究所(2025年)、International Trade of Secondhand Goods: Flow of Secondhand Goods, Actors and Environmental Impact.(共編著)Palgrave Macmillan(2021年)など。
注
- S.E. Davies. 2012. “The International Politics of Disease Reporting: Towards Post Westphalianism?” International Politics, Vol. 49, Issue 5. 591–613.
- N. Porter. 2012. “Risky Zoographies: The Limits of Place in Avian Flu Management.” Environmental Humanities, Vol. 1, No. 1. 103–121.