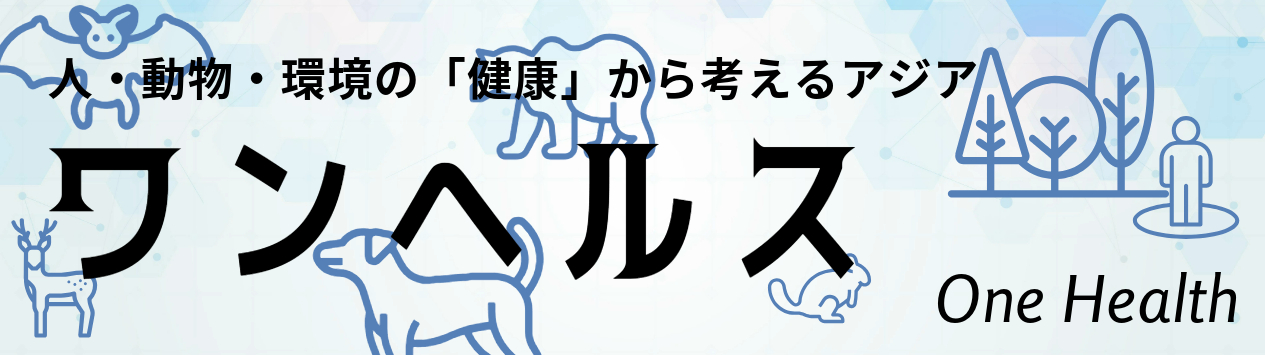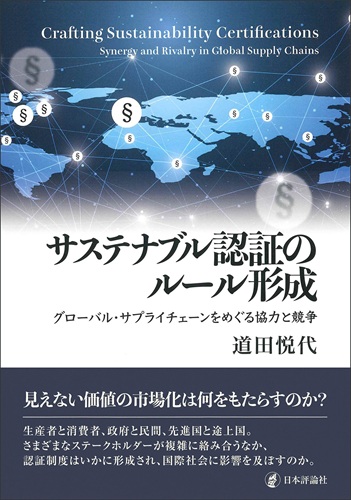IDEスクエア
コラム
第2回 森林保全は人・動物・環境の健康にどのような役割を果たすのか?
What is the role of forest preservation in one health?
PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001328
道田 悦代
Etsuyo Michida
2025年3月
(3,822字)
森林とワンヘルス
過去60年を振り返ると、地球上の土地の三分の一が改変された。そして、土地改変は森林破壊によって行われてきた。2000年から2018年の間の森林破壊の90%は、畜産を含む農業に関連するといわれている。森林は温室効果ガスを吸収するためのシンクとして、また天然林や原生林は生物多様性の保全の対象となってきた。とりわけ、途上国における農地拡大や都市化が、森林破壊の重要な要因である。森林破壊のスピードが急激なのがアフリカである。アジアでは過去に比べると森林減少のスピードは減速している。近年の森林破壊の原因は人為的な土地改変だけではない。気候変動による乾燥などの影響もあり、世界各地で森林火災が多発しており、さらなる森林破壊を引き起こしている。
森林は、温室効果ガスの吸収や生物多様性の維持など環境だけでなく、人や動物の健康に大きく関係してきた。例えば、エボラ出血熱や新型コロナウイルス感染症、ダニ媒介性脳炎、そして後で述べるニパウイルス感染症などの人獣共通感染症の多くは、森林に棲むコウモリや哺乳類などの野生動物が宿主となり、感染症の原因ウイルスを媒介している。
人獣共通感染症の経路
森林破壊が感染症に与える影響の経路は、病原体の媒介や宿主となる種の関係性の変化などもあり、複雑である。このため、森林破壊が人獣共通感染症の広がりに与えるメカニズムは十分に解明されていない。しかし、これまでにわかってきたこともある。人獣共通感染症のウイルスが野生動物から人に広がる経路で解明されたものをみてみよう。ひとつは、野生動物が棲む森林が破壊されて、野生動物が人里に近づくことでおこる。このメカニズムは、森林破壊とエボラ出血熱の関係でみられている1。まず、農業やアグロフォレストリー(森林農法)による森林破壊や、経済開発に伴う道路の敷設で森林の分断化がおこる。すると、そのような環境に適応しやすいオオコウモリの個体数が増加する。個体数が増え、生息地域を広げたオオコウモリが、人間の居住地域に棲むようになった結果、接触がおこる。人間も動物も生産性が高い肥沃な土地を利用するため、そこで人獣の活動地域に重複がおこると感染を引き起こす契機となるというものである。
別のメカニズムは、森林減少により生物多様性が減少し、これまで生存していた生物種がいなくなることでおこる。それまでいた生物種に代わり、病原体の宿主となりやすいコウモリやネズミなどの種がとってかわることで、コウモリやネズミから人に感染が広がる2。いずれにしても、感染症ウイルスの広がりには、森林に棲む野生動物と人との接触が関係するため、接触機会を減らすことが重要と考えられる。
ニパウイルスの事例
ニパウイルス感染症は、高熱が出て脳が腫れるなどの症状が出る感染症である。これまでマレーシア、シンガポール、インド、バングラデシュなどで多くの感染者が発生した。1998年にマレーシアで発生したケースでは、265人の感染者と105人以上の死亡者がでた。この感染症の宿主は完全には解明されていないが、コウモリが宿主の一つといわれている。
マレーシアで発生したニパウイルス感染症の研究によると、森林地域に生息するコウモリなどのニパウイルスが家畜のブタに繰り返し感染したことが感染拡大につながったといわれている3。一方、インド・ケララ州では2023年に、直近5年で4度目のニパウイルス感染症の発生が起こり、5名が死亡した。ケララ州では、宿主のコウモリのすみかや食用となる果物の木が森林破壊等により減少したことで、コウモリが人里近くに生息域を広げたことが原因と考えられた4。
ニパウイルスは予防するためのワクチンもなく、感染からの防御が最も重要となる。ケララ州でのニパウイルス感染症への対策では、すみかとなる森林や果物の木の保全が必要であると提言されている。しかし、土地の管理の意思決定は州政府だけでなく複数の行政組織や民間土地所有者が行っており、保護政策を実施することは困難を伴う5。民間の土地利用者は、保全のコストが補償されなければ土地開発をすすめる可能性もある。
農地の開発や土地利用変化の多くは開発途上国でおこっており、感染症の発生源となっている。このため、とりわけ途上国での対策が必要であるが、開発の必要性と開発がもたらす感染症リスクをどのようにバランスさせるかが課題である。対策には、農業活動や都市化の状況、そして感染症のリスクをモニタリングすることが必要である。ケララ州はニパウイルス感染症を受け、いくつかの対策を行った。まず、感染発生を早期に検知するモニタリングシステムを構築し、早期対応を行う体制を作った6。そして、感染症対策として、世界銀行やアジアインフラ投資銀行が資金を拠出する枠組みが設置されるなど、国際機関との協力も行われている。しかし、土地改変が続くなか、十分な対策が行われているとはいえない。
人獣共通感染症と住民の役割
感染症が野生動物や人間に広まるリスクを低減するには、人間と野生動物の接触機会を減らすような政策や行動変容が必要である7。そして、感染予防のためには住民の意識も重要な役割を果たすと考えられている。ケララ州の住民に対し、コウモリはもちろん、落ちた果実はコウモリの唾液で汚染されている可能性があるので、食べないよう教育している。一方、マレーシアでは豚とコウモリが接触しないような措置が必要と考えられる。バングラデシュでは、コウモリの分泌物に汚染されたナツメヤシの樹液を飲んだことがニパウイルス感染症発生の原因となっている。このように、個別の感染発生事例について、生態系や宿主、政策、そしてウイルスについてより多くの研究や調査が必要である。それを踏まえて、地域によって異なる対策と、住民へのメッセージが必要となるだろう。
感染症の予防は現地だけの課題ではない。途上国の生産地域に与えるグローバル化の影響は、これまで検討されてきた8。森林にかかわる土地利用変化の一部は、海外に輸出されて消費される農産物によって引き起こされている。例えば、マレーシアの土地利用変化には、パーム油(写真)など日本を含む多くの国で消費される農産物の生産がかかわっている。このため、ワンヘルスへのアプローチとして、生産国での施策だけではなく、輸出される農産物が森林破壊を引き起こすことを防ぐための消費者側での施策が必要である。

森林の遷移と接触管理
森林の利用状況も踏まえ、人との接触管理の政策も必要となる。異なる経済発展段階の国での接触管理の方法はさまざまである。途上国が経済発展する過程では農業が振興され、農地拡大や人口増加に伴う森林減少が進む。しかしその後、開墾に伴う限界費用の小さい耕作地が利用された後は、開墾が難しい土地が残されており、森林破壊が抑制される可能性がある。また、経済発展がすすみ、農業部門から工業部門へと労働者が移動する二重経済を経て、工業部門が発展する。すると、相対的に農業よりも工業、サービス業に従事するほうが人びとにとってより高い所得が得られるようになる。農業や林産物に生計を依存する割合が減ると、森林破壊のスピードを低下させる要因となるだろう9。
さらに、森林の環境価値やレクリエーション価値などが高まると、森林保護活動や植林が行われる。森林の価値が高まると、森林面積が拡大する10。多くの先進国では森林面積の回復がみられている11。このように森林は減少局面も回復局面もある。
森林の遷移の局面によって、また社会経済の状況により、人獣共通感染症を予防するワンヘルスの施策は異なるだろう。森林が減少する局面では、人が森林を侵食することによる感染を防ぐ方策が必要である。例えば、木材や農産物の経済的価値が高いことにより森林破壊が進行する場合には、その森林保全を食い止める規制措置や、保全を促す補助金の提供などが有効だろう。途上国で対策を行う場合には、森林破壊を伴う農業生産によって生計をたてる人びとへの対策が必要となろう。
一方、森林が回復する局面では、動物が人の居住地域に移動して接触が増えることを防ぐ施策が必要である。日本でも、市街地にイノシシやクマが出現し、共存のありかたが課題となっている12。このような段階では、森林が人獣共通感染症の予防に果たす役割について、住民に対する情報提供や教育などが重要である。
グローバルな取り組み
森林保全にかかわるさまざまな施策はこれまでも気候変動枠組み条約や生物多様性条約、また各種国内法や民間の取り組みなどで行われてきた。しかし、ワンヘルスの分野では検討が始まったばかりである。森林破壊を防止するためには、住民がどのように森林とともに暮らし、土地利用を行ってきたのか、また住民の生計が森林にどうかかわるのかなどの理解が欠かせない。そしてその理解に基づく社会的施策の導入が必要となる。しかし、人獣共通感染症の発生を抑制したり、野生動物と人の接触管理を行う目的での森林にかかわる国際・国内施策、そしてその社会実装についてはまだ十分検討が行われているとはいえない。長期的な計画が必要となる森林管理と経済開発との関係において、どのように将来の人獣共通感染症を予防し接触管理を行うのかについて、社会科学的な見地からのエビデンスをもとにした研究の必要性は高まっている。
※本コラムは、『アジアのワンヘルス──人・動物・環境をめぐるリスクとガバナンス──』(アジア経済研究所、2025年2月)の刊行をふまえて社会科学的な観点からアジアのワンヘルスをめぐる課題について解説を行っていきます。第2回は第3章「森林とワンヘルス」(49~73ページ)をもとにしています。詳しくは同書(オープンアクセス)をお読みください。
※この記事の内容および意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。
写真の出典
- 筆者撮影
著者プロフィール
道田悦代(みちだえつよ) アジア経済研究所新領域研究センター主任調査研究員。博士(経済学)。環境と貿易、環境規制、サステナビリティと基準認証について研究している。近著に、道田悦代(2025)『サステナブル認証のルール形成──グローバル・サプライチェーンをめぐる協力と競争』日本評論社。
注
- J. Olivero, J.E. Fa, M.Á. Farfán, A.L. Márquez, R. Real, F.J. Juste, S.A. Leendertz and R. Nasi. (2020). “Human Activities Link Fruit Bat Presence to Ebola Virus Disease Outbreaks.” Mammal Review, 50(1): 1-10.
- R. Gibb, D.W. Redding, K.Q. Chin, C.A. Donnelly, T.M. Blackburn, T. Newbold and K.E. Jones. (2020). “Zoonotic Host Diversity Increases in Human-Dominated Ecosystems.” Nature 584(7821), 398-402.
- J.R.C. Pulliam, J.H. Epstein, J. Dushoff, S. Abd Rahman, M. Bunning, A.A. Jamaluddin, A.D. Hyatt, H.E. Field, A.P. Dobson and P. Daszak. (2011). “Agricultural Intensification, Priming for Persistence and the Emergence of Nipah Virus: A Lethal Bat-Borne Zoonosis.” Journal of the Royal Society, 9(66): 89-101.
- S. Sivadasan, R. Jain, D.J. Nelson and R. McNeill. (2023). “Nipah Virus Outbreak Renews Calls to Protect Bat Roosts.” Reuter, Oct. 30.
- 同上。
- T.S. Anish. (2023). “Nipah Virus Is Deadly: But Smart Policy Changes Can Help Quell Pandemic Risk.” Nature, 622(7982): 219.
- World Bank and FAO. (2022). Reducing Pandemic Risks at Source: Wildlife, Environment and One Health Foundations in East and South Asia.
- 赤嶺淳 (2014). 「環境問題とむきあう──モノ研究からマルチ・サイテット・アプローチへ」『地域研究』14(1)、139-158ページ.
- A. Angelsen and T.K. Rudel. (2013). “Designing and Implementing Effective REDD+ Policies: A Forest Transition Approach.” Review of Environmental Economics and Policy, 7(1): 91-113.
- T.K. Rudel, O.T. Coomes, E. Moran, F. Achard, A. Angelsen, J. Xu and E. Lambin. (2005). “Forest Transitions: Towards a Global Understanding of Land Use Change.” Global Environmental Change, 15(1): 23-31.
- R.C. Estoque, R. Dasgupta, K. Winkler, V. Avitabile, B.A. Johnson, S.W. Myint, Y. Gao, M. Ooba, Y. Murayama and R.D. Lasco. (2022). “Spatiotemporal Pattern of Global Forest Change Over the Past 60 Years and the Forest Transition Theory.” Environmental Research Letters, 17(8), 084022.
- 藤田香(2025).「日本における中山間地域の変容と『鳥獣―人』の接近」大塚健司編『アジアのワンヘルス──人・動物・環境の健康をめぐるリスクとガバナンス』アジア経済研究所。