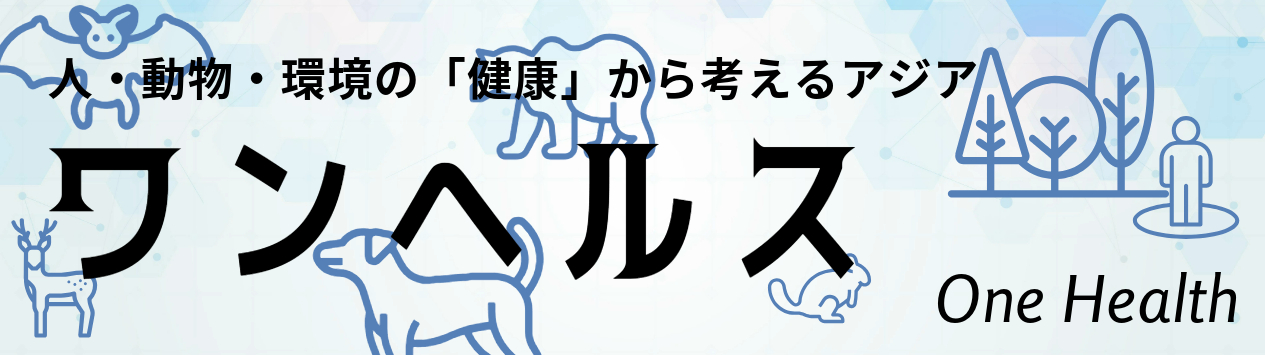IDEスクエア
コラム
第7回 パンデミック条約とワンヘルス
The Pandemic Treaty and One Health
PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001506
2025年9月
(3,589字)
ついに採択されたパンデミック条約
今年5月に世界保健機関(WHO)の第78回年次総会でパンデミック条約が採択された。この条約の目的は、今後パンデミックが発生した際に情報を迅速に共有し、ワクチン、検査薬、治療薬、防護具を各国間で平等に分配するとともに、感染症に対応できるような専門知識をもった人材を育成することである1。この条約の合意に至るまで、世界各国による協議は3年以上にわたった。協議は2021年に始められ、当初は2024年の採択を目指していたが、合意に至らなかったため期日が1年間延長された。今年の年次総会では賛成124票、反対0票、棄権11票で採択された。長きにわたる交渉をけん引したのは政府間交渉会議 (INB)という組織で、各国政府の代表などが任意で参加できる。日本政府の代表はINB の前副議長を務めるなど、積極的に協議に関わってきた2。
パンデミック条約が採択された意義は大きい。まず、ワンヘルスを基本概念と位置づけていることに注目したい。ワンヘルスとは、感染症などが人だけの問題ではなく、ニワトリ、ウシ、ブタなどの産業動物、コウモリ、サル、ネズミなどの野生動物、そして周囲を取り巻く環境と深く関連しているという考え方である。この点についてはより詳しく後述する。
さらに、その採択のタイミングも重要である。2025年はCOVID-19が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態 (PHEIC)」の指定から解除されて2年経つ。ジカウイルス感染症やエボラウイルス感染症など、過去のアウトブレイクでもみられたように、感染症への関心は一般の人びとやドナー、政府関係者のなかでも次第に薄れていってしまう。そのため、パンデミック条約のような国際的な枠組みは、熱が冷める前に制定しなければ、各国の優先事項は他のことに移り、合意のチャンスを失う可能性がある3。今回は、内容の詳細に合意できず最終的に採択されない、という残念なシナリオを免れたのだ。
また、パンデミック条約は健康問題に関する史上2つ目の国際条約である4。1つ目は2005年に発効されたたばこの規制に関する枠組条約だ5。感染症に関しても条約という形式で国際社会が合意に至ったことにより、罰則などは生じなくても社会的責任が生まれ、感染症対策の重要性が忘れ去られるということは防げるかもしれない。

2025年にジュネーブで開催された第78回世界保健総会(WHO総会)にて
コロナの教訓を次に生かす
パンデミック条約が生まれた背景には、COVID-19への対応で浮き彫りとなった課題がある。2023年に発表された条約の草案では、世界のCOVID-19への対応は「破滅的な失敗」(catastrophic failure)だったとされ、「各国間、地域間で起きた不平等を深く懸念して」条約の合意に至った、と記されている6。例えば、アメリカやヨーロッパなどの高所得国がワクチンを安定的に確保し接種するなか、アジア、アフリカ、南米の途上国がワクチンを入手できなかったことがあり、その状況は数の限られたワクチンを自国に囲い込む「ワクチン・ナショナリズム」や「ワクチン・アパルトヘイト」7と表現された。そうした状況を回避するためには、あらかじめ、ワクチンや治療薬など、感染拡大を阻止する鍵となるものの分配を製薬会社と取り決めたり、途上国がこれらにアクセスできるようなシステムを作ったりすることが必要だ。条約では製薬会社が緊急時にパンデミックの原因となっている病原体のワクチンや治療薬の製造量の20%を目安にWHOに提供し、それらが速やかに途上国などに送られるとされている。
また、感染症が急に拡大すると、医療従事者や感染症のモニタリングをする機関(保健所や国の研究所)の専門家に過度な負担がかかる。そのため、緊急事態に対応できる医療システムの構築、それを円滑に稼働させて国民の健康を守る専門家の育成も課題だ。条約ではこれらの医療従事者や感染症の専門家の人材確保、育成、離職防止の一環として、感染予防の徹底、男女の賃金格差を含む雇用に関する差別の撤廃、緊急対応の際に起こりうるハラスメント、怪我、障害、死亡事故などの防止といった職場での安全性の確保などを求めている。
パンデミック条約に盛り込まれた「ワンヘルス」
さて、パンデミック条約にはたびたび「ワンヘルス」という用語が盛り込まれており、条約の本文にはその定義を含め6回登場する。ワンヘルスとは「人、動物およびエコシステムの健康の均衡を持続可能的に保ち、最適化するための調和的、統一的なアプローチ」である8。パンデミックを引き起こす感染症の多くは、動物と人との間で感染する「人獣共通感染症」である。例えば、日本でも発生する鳥インフルエンザやデング熱も人獣共通感染症に分類される。他にもコウモリ由来のエボラウイルス感染症やラクダ由来の中東呼吸器症候群(MERS)などがある。このため、パンデミック対策を考えるときにワンヘルスの概念を持つことが必要だ。具体例としては、酪農の現場では野生動物が動物舎に入らないようにすること、野生のサルやコウモリを食する地域ではそれに替わるタンパク源を導入すること、ウシ、ラクダ、ヤギなどの生乳は必ず殺菌処理をすること、そして動物をと殺したり、糞尿を処理したりする際には手袋やマスク、ゴーグルなどを着用することなどが挙げられる。
これまでの感染症対策では、人の健康を動物や環境と結びつけることは稀だったが、人だけを対象とするパンデミック予防ではなかなか成果が上がらなかった。なぜならば、人・動物・環境が接するインターフェイス(境界)で人獣共通感染症が発生するからだ。例えば、野生動物が生息する森林が伐採されることにより動物が人の住む地域に侵入してきたり、人口過密な街で排泄物を適切に処理できない環境で病原体を運ぶ動物が繁殖したり、劣悪な過密飼育によりニワトリなどの産業動物にストレスがかかり、病原体が動物の体外へ排出されやすくなったりすることによって、病原体が動物から人に感染する確率が上がる。
今回採択された条約では、人獣共通感染症は環境、気候、社会、経済など、人を取り巻くさまざまな要因で発生することを認め、各国で次のような活動をするよう求めている。
- 国の既存の状況に合わせてワンヘルスの政策や枠組みを作る
- ワンヘルスの考え方に基づく教育や研修を行う
- 公衆衛生分野と農業分野が連携して感染症のサーベイランス(監視・追跡)を行う
- 病原体を迅速に検出するためのラボの機能(設備、人材、ラボ同士で情報共有を行うネットワークなど)を強化する
なお、協議に携わった関係者によると、パンデミック条約の最終合意に至るまでに、ワンヘルスをいかに取り入れるかは争点の一つだったそうだ。例えば、国によりパンデミック対策に使える資金や法律、そして感染症を取り扱う公衆衛生のシステムが大きく異なるため、ワンヘルスをどの程度政策などに取り込むことを義務付けるか、そしてワンヘルスの教育を必要とする場合、途上国などに資金面でのサポートがあるか、などが挙げられる。実際に採択された条約には「必要に応じてワンヘルス・アプローチを用いる」といった表現を弱めるような記述が垣間見える。つまり、各国の行政組織の構造(ワンヘルスには医療、農業、環境を司る行政組織の緊密な連携が必要)や資金、人材などといった状況に合わせて、ワンヘルスの概念のもとパンデミック対策が行われるという点での合意にとどまった。
また、条約のワンヘルスの定義に注目すると、その内容は2022年にワンヘルス高等専門家パネル(OHHLEP)という専門家委員会が発表したものよりも人間中心的である。つまり、人と動物と環境の健康を調和的に捉えてその均衡を保つのではなく、人のパンデミックを予防し対応するために、二次的に動物の健康と環境を考える必要がある、というニュアンスだ。
ともあれ、ワンヘルスがパンデミック対策の基本的な概念として国際条約に全面的に組み入れられるのは今回が初めてであり、草の根運動から始まったワンヘルスという概念が徐々に世界の政府機関などに認められ、そして条約において一定の位置づけがなされたことは大いに評価できる。
今後の展望
パンデミック条約は5月20日に採択されたばかりだ。これからは、病原体の情報共有についての文書(パンデミック条約の附属書)が引き続き協議される予定だ。今後の課題としてはパンデミック条約の実効性、そして条約に示された各国の活動を支える資金源の確保などが挙げられる9。各国政府の国際連携に対する姿勢が変わったり、新たな国際社会の課題が現れたりするなか、この条約はCOVID-19で培った教訓を未来につなげるための第一歩となった。これから先、再びパンデミックが発生した際にこの条約の真価が試される。
付記
本コラムは 『アジアのワンヘルス──人・動物・環境をめぐるリスクとガバナンス ──』(アジア経済研究所、2025 年 2 月)の刊行をふまえて今後数回にわたり各筆者が社会科学的な観点からアジアのワンヘルスをめぐる課題について解説を行ってきました。第7回は第2章「ワンヘルスのグローバルな動向──草の根運動から国際条約へ」(31~47 ページ)をもとに、最新のパンデミック条約の動向を追記しています。詳しくは同書(オープンアクセス)をお読みください。
※この記事の内容および意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。
写真の出典
- ©WHO / Christoper Black
著者プロフィール
戸上絵理(とがみえり) 獣医師。ジョンズ・ホプキンズ大学ブルームバーグ公衆衛生大学院、博士課程研究員。アジア、アフリカなど開発途上国における人獣共通感染症や、感染症対策における信頼構築、リスク認知、人材育成などについてワンヘルスの視点から研究。著作に「ワンヘルスと新型コロナウイルス感染症──パンデミックで注目される人、動物、植物、環境の繋がり」(『日本の科学者』通巻646号、2021年)、「コロナ時代に必要なワンヘルス・アプローチとは──『1つの健康』を目指す世界の取り組みから学ぶ」(『共生社会システム研究』15巻1号、2021年)など。
注
- WHO. “Intergovernmental Negotiating Body to Draft and Negotiate a WHO Convention, Agreement or Other International Instrument on Pandemic Prevention, Preparedness and Response: Report by the Director-General.” 2025.
- 注1参照。
- P. A. Villarreal, A. Gross and A. Phelan. “The Proposed Pandemic Agreement: A Pivotal Moment for Global Health Law.” Journal of Law, Medicine & Ethics. 53(S1): 55–58. 2025.
- WHO. “World Health Assembly adopts historic Pandemic Agreement to make the world more equitable and safer from future pandemics.” 2025.
- 外務省「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」2024。
- WHO. 2025(注1参照)、WHO. “Zero Draft of the WHO CA+ for the Consideration of the Intergovernmental Negotiating Body at Its Fourth Meeting.” 2023.
- B. M. Meier, J. B. De Mesquita and C. R. Williams. “Global Obligations to Ensure the Right to Health: Strengthening Global Health Governance to Realise Human Rights in Global Health.” Yearbook of International Disaster Law Online 3: 3–34. 2022; WHO. “Director-General’s opening remarks at Paris Peace Forum Spring Meeting – 17 May 2021.” 2021.
- 戸上絵理「ワンヘルスのグローバルな動向──草の根運動から国際条約へ──」.大塚健司編『アジアのワンヘルス──人・動物・環境の健康をめぐるリスクとガバナンス──』アジア経済研究所、31-47、2025。
- The Lancet. “The pandemic treaty: a milestone, but with persistent concerns.” The Lancet. 405(10489): 1555. 2025.
(2025年10月7日 誤字修正)