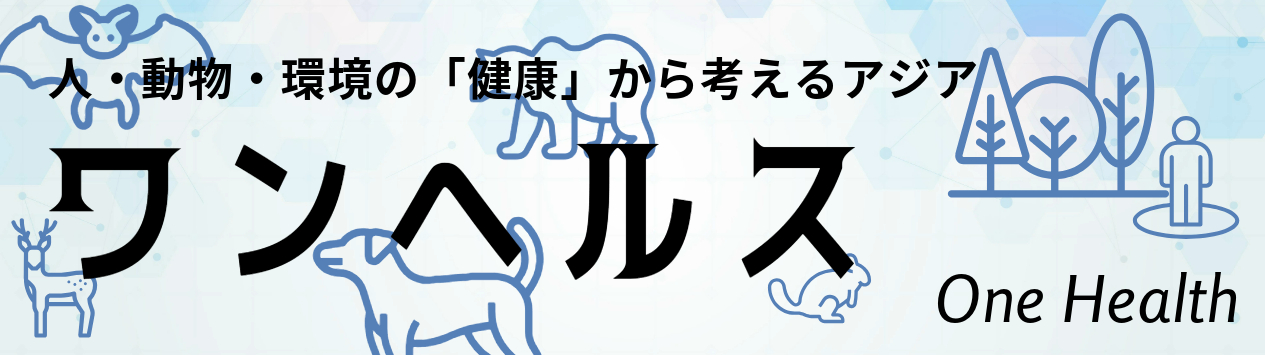IDEスクエア
コラム
第3回 ラオスのフィールドから考える人・野生動物・開発
People, Wildlife and Development - a Field Report from Laos
PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001378
2025年4月
(4,291字)
私たちの日常生活と地域社会に生きる人々
路上でひっきりなしに走っている車、大きな紙コップ入りのコーヒー、オフィスの入口においてある消毒用のエタノールなどの日常よく見かけるこれらのものは、新興感染症の発生に関連しているかもしれない。これは決して大げさな言い方ではない。車のタイヤを作るための天然ゴム、紙コップを作るためのパルプ、エタノールを作るためのキャッサバは、いずれも日本から遠く離れているどこかの森林を「消費」した産物となる。私たちの日常生活を維持するために、天然ゴムやユーカリのプランテーション、キャッサバの畑がつくられ、たくさんの森林は破壊された。これと同時に、地域の生態系も改変され、生物多様性の減少につながることが懸念される。
こうした開発の結果によって、森林に頼って生活を営んでいる地域の住民が十分な食物をとれなくなり、森林に生息している野生動物は餌場を失い、人間や動物はともに餓える状態に追い込まれかねない。そして、森林の減少によって、人間と野生動物のインタラクション(さまざまな形での接触や接近)の機会は増えてきている。私たちの日常生活を維持するためのプランテーション開発が作り出したこのようなシナリオは、新興感染症の病原体がスピルオーバーする(動物から人間に乗り移る)温床の形成に寄与するとされている1。
では、天然ゴムなどの工業用プラーテンションは、いったいどれほど森林を「消費」しているのだろうか。筆者の主な研究対象地域の東南アジア大陸部のデータを見てみよう。国連食糧農業機関(FAO)の報告2によれば、1990年から2010年の20年間に、プランテーション開発によって、同地域の森林面積は、106万平方キロメートルから89万平方キロメートルまでに減少した。言いかえれば、この20年間に日本国土面積の46%に相当する森林がプランテーションになってしまったことを意味している。
ラオスにおける筆者の調査対象地域であるサワンナケート県セポン郡は、まさにプランテーション開発による森林減少の代表的な地域の一つと言える。2010年代の初頭から現在まで、筆者は10数回にわたってフィールド調査を行ってきた。この10数回の調査で森林が天然ゴムやユーカリのプランテーションになっていくのを見てきた(写真1)。例えば、同地域でユーカリ(パルプ材)のプランテーションを経営しているD社が公表したFSC-FM認証(森林管理協議会―森林管理認証)資料によると、同社はサワンナケート県で1万5000ヘクタールのユーカリ・プランテーションを経営している(2024年7月現在)。この面積は東京都23区の約4分の1に相当する。これらの土地の多くは、地元の住民が主な生業である焼畑を営むための休閑林であった。

焼畑休閑林を失った住民は二つの局面に直面することになった。第一に、現在所有している焼畑の休閑期間を短縮せざるをえなくなることである。第二に、狩猟・採集の場としての焼畑休閑林を失ってしまうことである。第一の局面は、焼畑収量の減少や除草時間の延長を意味する。第二の局面では、山菜や野生動物の肉など副食の獲得は難しくなる。こうした変化の結果は、地域住民のコメ不足の状況、および栄養状態からある程度うかがうことができる。
筆者がプランテーションの開発に囲まれているKL集落で実施した調査によれば、同集落における約半分の世帯は新米収穫前2~3カ月前から、コメ不足の状況に陥ってしまうことがわかった。そして、約25%の成人は、世界保健機関(WHO)が定義している栄養状態の優れていない低体重や中・重度痩せの状況にある(BMIボディマス指数<18.5 kg/m2)。これはプランテーションから雇用労働の機会を得ているより恵まれている集落の状況であり、プランテーションから離れているAN集落おいては、低体重以下の成人男女はそれぞれ51%と33%に達している。こうした結果から、FSC-FM認証制度が求めている地域コミュニティの利益の尊重と保護の達成にはほど遠いと言える3。一方、住民の栄養状態が優れていないことによって、新興感染症の病原体のスピルオーバーのリスクが大きくなりかねない。
食物としての野生動物とプランテーション開発
2002年から2003年にかけて発生したSARS(重症急性呼吸器症候群)の時のハクビシン、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の震源地とされている海鮮市場の野生動物売り場は、いずれも野生動物の食用と関連していると報告されている4。筆者の調査対象地域の住民にも、野生動物を食用する習慣が見られる。COVID-19の初期にウイルスのキャリア(宿主)として疑われていたタケネズミ、およびその後SARS-CoV-2(COVID-19を引き起こす病原体)のキャリアとして推定されているコウモリは、いずれも筆者の研究対象地域の住民たちの食材である。
筆者の研究グループがある集落で実施した食事日誌調査から、食材としての野生動物の重要性をうかがうことができる。1万3934回の食事記録から、野生哺乳類動物が登場したのは774回で、約5.5%を占めた5。数字的にそれほど大きくないかもしれないが、日常的にもち米と唐辛子ディップ(「チェオ」──生トウガラシをつぶし、塩やライムなどであえたもの)を中心に食生活送っている人々にとって、野生動物の料理は重要な動物性タンパク源となる。ほかの代替の肉がないかぎり、野生動物の食用を禁止することで、かえって現地の住民の健康に大きなネガティブの影響を与えるに違いない。
一方で、地域社会におけるこうした野生動物の肉は決して安全とは言えない。ラオスの研究者が実施した全国調査によると、フードマーケットの野生動物の売り場、および道端で販売された359頭の野生動物のうち、5分の1程度の74頭はレプトスピラ(急性熱性疾患であるレプトスピラ症を引き起こす人獣共通感染細菌のこと)陽性であった6。言い換えれば、これらの野生動物の販売、調理、および食用をする人は、なんらかの病原体に感染するリスクがある。
では、どのようにすれば、代替的に安全な肉の食材を地域の住民の食生活に入れることができるだろうか。簡単に言えば、市場から適量の肉を買えば、より健全かつ健康な食生活を送れるようになる。しかしながら、前節で述べたように、主食のコメですら十分に確保できない人々にとって、肉を買うのはかなり贅沢な話となる。食肉の購入は、プランテーション開発から現金収入を得られている人々に限られている。
一方で、プランテーション開発は、野生動物の生息分布を変え、人間と野生動物が接触する機会を増やす可能性がある。土地利用変化とニパウイルスのキャリアであるコウモリの生息分布の関連性に関する研究によると、地域住民は集落の周辺にコウモリの餌となる果物を栽培した結果、もともと集落に遠く生息しているコウモリが、人間の集落の周辺に移動し、ニパウイルスのスピルオーバーにつながったとしている7。
筆者の調査対象地域のセポンでも、同じような傾向は観察されている。もともと陸稲の焼畑農耕を中心として生活を営んでいる住民たちは、土地の収益性を求め、バナナなどの換金作物を栽培するようになった。そして、バナナ畑に現れたコウモリを捕獲しているという話は、筆者の聞取り調査中によく聞くことである。野生動物の餌場になれない天然ゴムやユーカリのプランテーション、消えつつある森林、そして人間の周辺で作られた餌場となる果樹園や食料となる作物の畑といった急速に変化している生態系は、野生動物が人間の集落に接近する機会を増やし、人と動物の間に病原体がより移動しやすい環境を作り出している。
誰のための開発?
2024年初めごろから、先に述べたD社のウェブページを確認すると、FSC-FM認証の計画に関する文書が頻繁に更新されるようになった。計画を読んだ限り、持続的に森林を利用するための計画、および地元住民の利益に配慮する文言も明確に書かれている。しかし、2024年3月に筆者が現地調査を行った際に、この計画に関連する動きは観察できなかった。一方で、FSC-FM認証の計画を打ち出したと同時に、年間80万トンのパルプ生産規模から120万トンの生産規模まで増やす事業拡大計画も発表している。事業の拡大は、ユーカリ・プランテーションの面積をさらに拡大する必要があることを意味する。研究対象地域の森林は、さらにこの開発で「消費」され、住民の副食生産地の機能はますます低下してしまう。前記の食事日誌のデータを読むと、総計1万3934回の食事記録のなかに、5402回(39%)は森林に由来するタケノコ、野草、両生類・爬虫類、および野生哺乳類などがみられた(写真2)8。森林からそれらの副食をとれなくなると、栄養素摂取量の低下あるいは購入食品の増加につながる。十分な雇用機会に恵まれていない状況のなか、森林の急速な減少は、一部住民の栄養素摂取量の低下、そして栄養状態の悪化につながりかねない。

(左からそれぞれ両生類、げっ歯類、キノコ、アリの卵、唐辛子)(2024年3月)
こうした開発構図のなかで、プランテーション開発を主導する企業は、安い生産原料によって多くの利益を得ていると考えられる。ラオスの地元の政府はそれなりの税収を得られているだろう。そして我々消費者は安価な工業製品を得ることができている。では地元の住民は、何を得ているのだろうか。失った土地、失った森林、生活の不安定化などしか挙げられない。こうしたシナリオは、新興感染症の病原体のスピルオーバーのリスクを高めることになり、決して開発企業、地元の政府、そして我々消費者と無関係ではない。まだ完全に解明されていないが、開発のどこかの段階で食用のための野生動物が森林から持ち出され、これらの動物による病原体のスピルオーバーによって引きこされたと考えられているCOVID-19のパンデミックはまさにその事例の一つになる。開発により得られた利益は、平等かつ適切に地域の住民に届けば、人々のウェルビーイングの向上につながる。FSC-FMなどの組織が推奨している持続可能な森林利用を行えば、企業、政府、消費者の利益にもなるであろう。
D社のFSC-FM認証計画はまだ実際の行動に反映されていないが、計画の公表から地域生態系の保護や地域住民の文化や利益への尊重などの意識は少しずつ高まっているといえよう。近い将来に、こうした意識の向上が、開発活動の変化につながることを期待したい。
付記
本コラムは『アジアのワンヘルス──人・動物・環境をめぐるリスクとガバナンス──』(アジア経済研究所、2025年2月)の刊行をふまえて社会科学的な観点からアジアのワンヘルスをめぐる課題について解説を行っていきます。第3回は第7章「熱帯アジアの地域社会における開発・生業転換と新興感染症リスク──ラオス・サワンナケート県セポン郡の事例──」(167~193ページ)をもとにしています。詳しくは同書(オープンアクセス)をお読みください。
※この記事の内容および意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。
写真の出典
- すべて筆者撮影
著者プロフィール
蒋宏偉(しょうこうい) 国立環境研究所リスク健康領域特別研究員。博士(保健学)。専門は人類生態学、環境保健学、人文地理学、東・東南アジア地域研究、エコヘルス。主な著作に“Association between physical activity and activity space in different farming seasons among rural Lao PDR residents,” Tropical Medicine and Health 49: 73(共著、2021年)、“Factors contributing to the pre-elimination of malaria from Hainan Island, China, 1986–2009,” American Journal of Tropical Medicine & Hygiene 109(5)(共著、2023年)、Population Dynamics and Livelihood Changes of Small-Scale Societies in Laos, International Perspectives in Geography (IPG, volume 22)(共編著)、Springer(近刊、2025年)など。
注
- J.H. Ellwanger and J.A.B. Chies 2021. “Zoonotic Spillover: Understanding Basic Aspects for Better Prevention.” Genet. Mol. Biol. 44: e20200355.
- FAO 2010. Global Forest Resources Assessment 2010: Main Report. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2024 年11月8日最終アクセス)
- FSC 2023. FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship (version 5-3), Bonn: Forest Stewardship Council.(2025 年1月9日最終アクセス)
- C. Milbank and B. Vira 2022. “Wildmeat Consumption and Zoonotic Spillover: Contextualising Disease Emergence and Policy Responses.” Lancet Planetary Health 6(5): E439-E448.
- 佐藤廉也・蒋宏偉・西本太・横山智 2023. 「ラオス中部における焼畑民の食料獲得戦略──食事日誌の副食材料データ分析から」『E-journal GEO』18(2): 309-323.
- P. Nawtaisong, M.T. Robinson, K. Khammavong, P. Milavong, A. Rachlin, S. Dittrich, A. Dubot-Peres, M. Vongsouvath, P.F. Horwood, P. Dussart, W. Theppangna, B. Douangngeum, A.E. Fine, M. Pruvot and P.N. Newton 2022. “Zoonotic Pathogens in Wildlife Traded in Markets for Human Consumption, Laos.” Emerg. Infect. Dis. 28(4): 860-864.
- C.D. McKee, A. Islam, S.P. Luby, H. Salje, P.J. Hudson, R.K. Plowright and E.S. Gurley 2021. “The Ecology of Nipah Virus in Bangladesh: A Nexus of Land-Use Change and Opportunistic Feeding Behavior in Bats.” Viruses 13(2): 169.
- 注5を参照。