IDEスクエア
コラム

第1回 カンボジア語――出会いに支えられた語学習得への道
Cambodian: the path to language acquisition supported by encounters
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00053532
2022年12月
(4,763字)
なぜカンボジア?
「なぜカンボジアを勉強しようと思ったの?」――。
私が東京外国語大学のカンボジア語専攻に入学して以来、自己紹介をするたびに十中八九この質問が投げかけられてきた。
当初はしっかり伝えたいという思いが強く、聞かれるたびに一生懸命説明していたが、あまりに頻繁に聞かれるため、疎ましい気持ちも抱きつつ答えるようになっていた。カンボジア地域研究を生業にするようになり、研究の起点にまつわるエピソードを話す機会は今後も様々な場面で求められるであろう、とようやく観念しつつある。
前置きが長くなったが、私が大学でカンボジアを学ぼうと思ったきっかけは、紛争後社会の復興に関心があり、かつ特定の地域の言語を習得し、地域を深く理解しながらその事象を考えてみたいと思ったことにある。せっかくなら、その地域の言葉も学んで取り組みたいと思っており、語学からしっかり学べる環境がないか探していたところ、東京外国語大学のパンフレットでカンボジア語専攻の説明に目を奪われた。うろ覚えで恐縮だが、「カンボジア語、カンボジアの文化や社会を研究している人は世界的にも少なく、第一人者になれます」といったことが書かれていた。
調べてみると、カンボジアは1991年のパリ和平まで内戦や虐殺の時代を長く経験しており、まさに紛争後の社会復興の真っただ中にあった。そしてカンボジア語をみっちりと学べる大学は日本では東京外国語大学のみで、その希少性に強く惹かれ、受験した。無事に合格し、意気揚々と入学したわけだが、待っていたのはカンボジア語漬けの毎日だった。
怒涛のカンボジア語学習の日々
カンボジア語専攻では、入学式後、授業初日までの間に1泊2日のオリエンテーション合宿という、専攻の教員と新2年生とともに新1年生が親睦を深める機会があった。
たしか1日目の夕食後、先生がおもむろに新1年生へ本を1冊配ってくれた。なんだろうと見てみると、『カンボジア語入門』であった。入学するまでカンボジア語を見たことがなかった私は、「なるほどこれがカンボジアの言葉か」と思うや否や、「これが教科書です。2日後の授業初日に単語テストをするので第1章で扱われる単語を覚えてきてください」といわれた。多分そこにいた全員が「文字も習っていないのに単語テストをするなんて無茶苦茶だ」という気持ちになったと思う。
つまり、2日後までに文字を暗記し、さらに単語が書けるようになってきなさいという指示だったのだが、カンボジア語を見たこともない学生に出す課題なのか……という衝撃を抱えて帰路についたことをよく覚えている。しかもこの教科書を2カ月で学び、そのあとは民話を読むという。1からカンボジア語を始めて2カ月後に民話が読めるようになるということもにわかに信じられなかった。カンボジア語を学び始めるという感慨に浸る間もなく、帰宅早々文字の暗記を始めた。それが私のカンボジア語との出会いであった。
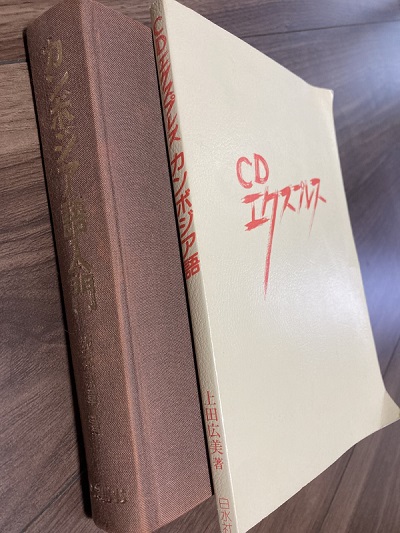
文法をしっかり学びたい人向け。『エクスプレス』は改訂されており、入門書としておすすめ。
オリエンテーション合宿の2日後の初回授業、本当に単語テストがあった。しかも、ディクテーションだった。文字と意味だけ暗記していても当然解けず、発音も理解していないと書けない。カンボジア語には「有気音」と「無気音」があり、たとえば「パ」と発音する文字には有気音の「Pha」と無気音の「Pa」で異なる文字が当てられる。さらに、同じ「Pha」も2種類の文字があり、単語によって使われる文字は異なる。文字列を暗記していたからといって、お目当ての単語を正確に書けるわけではないという訳だ。さて、その単語テストの結果がどうだったかというと、まさかの満点だった。
先生曰く、これまで初回テストで満点をとった学生はいなかったということで、驚いたとおっしゃっていたが、自分も相当驚いた。この「初回テスト満点」はその後2年間ほど続く怒涛のカンボジア語漬けの日々(確か1週間に5コマ~6コマあった記憶がある)を励ましてくれるお守りになった。
文字とその配列を覚えていないと辞書を引くのも大変なのだが、最初の段階で懸命に覚えたおかげで、速く辞書を引くこともできるようになり、新しい単語のオンパレードだった民話もそれなりに楽しく読めた(課題の量が多くて大変だったが)。カンボジアから交換留学で来ている学生やカンボジア人の先生との交流も楽しく、大学卒業後もカンボジアと関わる仕事をしたいなと思い始めた。
カンボジアにどっぷり浸かれる仕事はないかと考えていると、外務省にカンボジア語専門職があるとわかり、そこを目指そうかと思ったりもした。そのような思いを抱きつつ、大学4年生の夏からカンボジアの王立プノンペン大学へ1年間交換留学に行った。
留学先での4つの出会い
2009年9月に私のカンボジア留学が始まった。留学先では人生の転機となる4つの出会いがあった。第一が「カンボジアにいる第二の母」と呼ぶ方との出会いだ。当時カンボジアに留学するカンボジア語専攻の学生は、専攻の先生の紹介でホームステイすることになっており、私も首都プノンペンのオルセーマーケット近くのお宅にホームステイすることになった。上は80代のおばあちゃんから下は2歳の子どもから成る大家族とそこに間借りしている母子世帯、そして5人近く住み込みのお手伝いさんがいるお宅で、とても賑やかだった。
そのお宅の大黒柱が60歳近い女性で、家族や親せきから「マエ・トム」と呼ばれていた。マエ・トムは非常に真面目で、責任感が強く、チャーミングで、毎晩カンボジアのテレビを見ながら話し、様々なところへ連れて行ってもらった。多くの時間を過ごしたということもあるが、マエ・トムが話す内容はほとんど聞き取れ、私が伝えたいことも正確に理解してくれた。
日本でそれなりにカンボジア語を学んできたという自負はあったものの、いざ留学してみるとなかなか伝わらないこともあり、忸怩たる思いを抱いていたが、マエ・トムと話すことで自信を取り戻すことができた。
第二が、生涯の友との出会いである。当時私は王立プノンペン大学の第2キャンパスにある史学科に留学していた。留学前、紛争後の社会復興のなかでも、紛争の時代をその後いかに教育するのかについて関心をもっていた。そのため、カンボジアの大学でどのような歴史教育がなされているのか知りたく、史学科に留学した。そこではアメリカ人教員によるアメリカ史以外は、当然ながらすべてカンボジア語が教授言語だった。日本でもカンボジア人教員の授業はすべてカンボジア語で行われていたが、それはあくまで日本人を対象とした易しいカンボジア語だったことを留学で身をもって知った。
授業中飛び交うカンボジア語がまったくわからず、愕然とした。授業初日に出会い、隣の席へ誘ってくれた友人がいなかったら、早期に挫折していたであろう。その友人はマエ・トム同様にとても真面目で、かなりの苦労人なのだが、持ち前の明るさとユーモアでたくましく生きる人だった。面倒見がよく、たびたび学生寮でご飯をご馳走してくれたり、一緒に勉強をしてくれたりした。留学を終えた後もカンボジアで調査をするたびに、助手のように手伝ってくれ、そのおかげで得られた資料や機会がなければ、研究を続けてこられなかったのではないかと思う。彼女の結婚式では友人代表のスピーチも任され、カンボジア語で笑いもとりつつ、お祝いの言葉が伝えられたのも良い思い出である。

トゥクトゥク(三輪バイク)で通学していた。通学途中によく肉まんを買って頬張った。
第三が、研究仲間との出会いである。当時のカンボジアには研究のために長期滞在していた大学院生や外務省のカンボジア語専門の研修生がおり、偶然全員女性であった。私自身、カンボジアへ留学するまで若手研究者はもとより、東京外国語大学以外のカンボジア研究者と接点がなかったこともあり、留学中に若手研究者の方々と出会えたことは幸甚であった。
年齢も近かったので、一緒に勉強会をしたり、日本カンボジア研究会のカンボジア例会で研究発表をしたり、私自身が研究の道を志すきっかけをくれた。政治学、人類学、考古学と専門もバラバラであったが、彼女たちから聞く研究の話は私のカンボジアを視る目を大きく広げてくれ、カンボジア語を流ちょうに操り調査研究を進める姿に大変刺激を受けた。
最後に、研究テーマとの出会いである。紛争後社会における歴史教育に関心をもち、留学したと述べたが、留学当時、人口の4分の1にあたる170万人近い国民が亡くなった民主カンプチア時代の体制指導者に対する裁判が進行していた。留学も終わりに差し掛かった2010年7月、第1事例となったS-21強制収容所元所長カン・ケ・イウの初審の判決結果が出された。
35年の拘禁刑判決が出されたのだが、そのニュースをマエ・トムと一緒に聞いている際、穏やかなマエ・トムが激しく怒った。「あんなに人々を酷い目に遭わせたのに35年の拘禁刑だなんて許せない。最高刑の終身刑にするべきだ」――。
マエ・トム自身、民主カンプチア時代に厳しい生活を余儀なくされ、度々命の危険に晒され、夫を亡くしている。「最近は若い人たちに民主カンプチア時代の経験を話しても、『そんなの信じられない』と言われてしまう」と嘆いてもいた。カンボジアでは過去にどのような歴史教育がなされてきたのか、改めて強い関心をもつとともに、紛争や虐殺といった甚大な被害を国民に強いた時代をどのように教えるのかという問題は次世代だけでなく、それを経験した世代にとっても重要な問題であることを強く認識した。
その後、教育青年スポーツ省の書庫で埃まみれで雑然と置かれていた教科書群から古い歴史教科書を発掘したり、公文書館や国立図書館などで独立以降に出版された歴史書などを渉猟したりするとともに、過去の歴史教科書の執筆者の方々へのインタビュー調査も実施した。これらはカンボジア語の読み・聞き・話すの能力を総動員して行った訳だが、とくにインタビュー調査では、歴史を書くことの難しさに関する話し手の微妙なニュアンスも聞き取ることができ、通訳を介してでは得られにくいであろう経験もできた。
このように調査を続けるなかで、研究関心は紛争後社会から、歴史叙述とそれを取り巻く政治や社会へと移り、近現代カンボジアにおいて人々の歴史認識に影響を与える歴史叙述や歴史教育が幾度かの体制転換を経ていかに変容してきたのか、という研究テーマをもつようになった。留学中にマエ・トムと裁判について語り合った経験が、カンボジアの人々の認識を考えるうえで、歴史教育や歴史叙述が看過できない問題という理解に至り、新たな研究テーマを獲得する貴重なきっかけとなった。
カンボジア語とともに生きる
大学進学以降、現在に至るまであらゆる場面にカンボジア語があった。もはや欠かせない人生の一部である。オリエンテーション合宿で教科書をもらったときは、そのようなことは微塵にも思わなかった。ここまで長い間カンボジア語を続けてこられたのは、学習を始めてから出会った多くの人たちのおかげであることは間違いない。彼ら彼女らはカンボジア語を始めなかったら出会わなかった人たちであり、カンボジア語を学ぼうと決心してくれた自分に「よくやった!」と言いたい。
現在様々な動機でカンボジア語を学んでいる人たちのなかには、文字や発音、聞き取りなど様々に苦労している人も多いかもしれない。あくまで私の経験からだが、煮詰まる場面では、励まし、刺激をくれる友人が身近にいると心強い。拙いカンボジア語でも会話が成立するというのは大きな励みになり、流ちょうに話す友人の姿に憧れ、奮起もするだろう。少なくとも私はそのような存在に支えられ、カンボジア語学習を続けてこられた。そして幸い現在もカンボジア語を使って研究を続けている。
【好きなフレーズ】
ធ្វើល្អបានល្អ ធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់
「善き行いをすれば良い結果になり、悪しき行いをすれば悪い結果になる」
仏教の「善因善果、悪因悪果」を指すカンボジア語なので、カンボジア独自の諺という訳ではないが、ホストマザーのマエ・トムが繰り返し言っていた言葉。留学中を懐かしむとともに、自分を律するうえでも大事にしているフレーズ。
※この記事の内容および意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。
写真の出典
- すべて筆者撮影
参考文献
- 坂本恭章 1989.『カンボジア語入門』大学書林.
- 上田広美 2020.『ニューエクスプレスプラス カンボジア語』白水社.
著者プロフィール
新谷春乃(しんたにはるの) アジア経済研究所 地域研究センター研究員。博士(学術)。専門はカンボジア地域研究。博士課程ではカンボジアの歴史叙述に関して研究。現在はカンボジアの政治やメディアの研究に取り組んでいる。


