猪俣 哲史 研究者インタビュー
「世界の”お宝”、アジア国際産業連関表」
国際産業連関分析の研究に入られたきっかけは?
わたし、アジ研に入るまで産業連関分析って全然知りませんでした。大学ではどちらかといえば純粋理論が好きで、実証分析はほとんどやらなかったのです。理由は簡単で、数字を見るのが嫌いだったから。で、アジ研に入って、当時の上司にどんな研究をしたいか聞かれて、「なるべく数字を見なくてすむ研究がいいです」と答えたら、<修行のために>って逆に統計部に配属されました。産業連関分析とはそれ以来の腐れ縁です。まだ続けているのが自分でも不思議です。
産業連関表でどんな分析や予測ができるのですか?
経済というのは様々な産業のネットワークによって構成されています。だから、ある産業で起こった変化は、そのネットワークを通じて経済全体へ伝わっていきます。
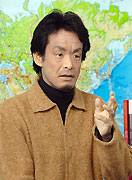
このように、一つの産業に対する需要の変化が、産業どうしの需給関係を通じて経済全体へ広がっていきます。ちょうど、小石を池に投げ入れたとき水面に生じる波紋のイメージですね。産業連関分析では産業連関表というデータを使って、この変化の深さと広がりを測ることができます。
最近では生産分析に加えて、雇用問題や環境問題への応用が進められています。さらに、アジ研の国際産業連関表を使えば、国境をまたいだ変化の広がりを見ることができます。経済統合の問題などへの応用が期待されています。
アジ研では1974年度からアジア諸国の統計機関と協働でこのプロジェクトを実施しており、この分野では先導的な役割を果たしてきたわけですね?
国際産業連関表は各国の産業連関表をつなぎ合わせて作ります。ところが、パーツとなる各国のデータは統計概念や推計手法が結構マチマチで、それらを連結するには一つの基準に沿ってデータのすり合わせを行う必要があります。そこで、アジ研が音頭をとって各国の統計機関と議論を重ね、統一基準を作ったり、調整のために必要なデータを集めたりしています。
また、これまで共同研究機関の統計専門家はもっぱら表の作成のみに注力していましたが、最近では、国際産業連関表の応用分析にも興味を持ってくれるようになりました。これも、アジ研が国際ワークショップなどで各国のモーチベーションを上げていく努力を積み重ねた結果だと思います。
昨年は欧州の大学や国際機関で連続講演を行いましたが、反響はいかがでしたか?
講演自体はかなり大きな反響を呼んだのですが、逆にかえって反省させられましたね。聴講者の反応がほとんど「こんなすごいデータがあったんだ」といった “お宝発見”的な感じだったので、言い換えれば、わたし達がこれまで、どれだけ海外発信を怠ってきたかということです。海外へのマーケティングは今後の大きな課題だと思います。
わたしの知る限り、『 アジア国際産業連関表 』は世界でも唯一無二の国際産業連関表です。もっともっといろんな人に知ってもらい、使ってもらいたいです。
今後の抱負をお聞かせください。
とにかく、変化に対して常に貪欲でありたいですね。技術の蓄積ももちろん大切ですが、どんどん新しいことにチャレンジしたいです。いま、産業連関分析が改めて注目されているので、うまいこと波に乗ってやろうと企んでいます。
(取材:2009年2月)

