採用・募集情報
研究者インタビュー
吉﨑 日菜子(2024年入所 地域研究センター アフリカ・ラテンアメリカ研究グループ)
担当国ガーナを初訪問

入所から1年近く経ちましたが、この間どのような業務(研究活動)に従事してきましたか?
この1年は、アフリカでの調査や研究の経験がない私にとって、今後アジ研でアフリカ研究を行うための準備期間だったといえます。具体的には、担当国であるガーナの報道や関心のあるテーマの先行研究などを読み、担当国や研究テーマへの理解を日々深めています。
それ以外に、アジ研の定期刊行物である研究雑誌『アフリカレポート』の編集委員会幹事として、編集委員長のもとで掲載予定の原稿のチェックや編集委員会の開催補佐を担当しています。また、他の編集委員の方々とともにアフリカに関連する本や論文の資料紹介を年2回執筆しています。アジア担当の研究者と異なりアジア動向年報の執筆がない一方で、これらの業務はアフリカ担当ならではといえます。
特に印象に残った業務(研究活動)には何がありますか?
やはり現地への訪問は印象に残っています。ありがたいことに今年度は、現地調査研修でエチオピア、現地調査(現調)でガーナを訪問できました。
現地調査研修とは入所歴の浅い職員を対象とした制度です。私は先輩研究員のエチオピア現調に同行し、聞き取り調査や家計調査のパイロットサーベイに立ち会いました。アフリカへの渡航経験がほとんどない私にとって、この研修は現調の進め方を学ぶだけでなく、アフリカ地域の人々の暮らしぶりを知る貴重な機会となりました。
また、1月には担当国であるガーナで現調を行いました。この現調では、シンクタンクや大学等でヒアリングを行い、2024年12月の大統領選挙の後の情勢を探るとともに、研究者とのネットワーキングを図りました。今回は私にとって初のガーナ訪問だったため、当時取り組んでいた『アフリカレポート』時事解説(「ガーナ新大統領が掲げる24時間経済政策と背景にある経済課題」)の執筆にあたり、同国の実情についてより明瞭なイメージをもつことができました。また、現在関心があるインフォーマル労働者の状況を探るべく、労働組合関係者との面会や市場および周辺コミュニティの視察も行いました。現地の知り合いも少ない中で一から現調を計画するのは簡単ではありませんでしたが、コミュニティの訪問等における人々との何気ない会話から彼らの暮らしぶりを知り、担当国への理解を深めることができました。

首都アクラ中心と郊外を結ぶ道路の整備が進行中

初のガーナ料理のレッドレッド(Red Red)、ボリュームがあって美味しい
2年目(2025年度)にはどのような業務(研究活動)に従事する予定ですか?
2年目は先輩研究員が主査となる研究会に参加し、より本格的に研究活動をスタートする予定です。なお、アジ研の研究会は毎年秋ごろに次年度の研究課題案を募集し、その後審査を通じて採択の可否が決まります。とくにアジア動向年報を担当しない場合、それに代わる成果物が必要となるため、研究会を通じた論考や論文の執筆が重要となります。
所属予定の研究会のテーマはアフリカにおける都市部の労働市場と、個人的に研究実績がないものの関心のあった内容なので、これからどのように研究を進めるか考えつつ、現在は担当国の同テーマに関する情報や先行研究を集めています。
工藤 太地(2024年入所 地域研究センター 動向分析研究グループ)
入所初年度の活動を振り返って
今年度の業務は、アジア動向年報の原稿執筆と「IDEスクエア——世界を見る眼」の記事執筆の二つでした。入所して最初の5か月間はアジア動向年報執筆の準備として、担当国の新聞報道の取りまとめを行い、毎月一回、研修担当の先輩研究者に報告しました。
アジ研に入所してからパキスタン担当になりました。それまでインドやバングラデシュの調査は行ってきましたが、パキスタンには行ったことがなく、現地事情も全く分からない状態でのスタートでした。入所後からパキスタンの新聞を読み始めたのですが、最初の1~2か月はその内容が全く頭に入ってきませんでした。文章としての意味はとれるものの、現地社会に関する基礎知識がないので、報じられる人物や団体・組織、起こっている出来事の重大さなどが分からず、記事全体として理解できた感覚がありませんでした。また、記事を読み解くには、それまでの経緯を把握する必要もあるため、過去の新聞も遡って読んでいました。そのため、一日中新聞しか見ていないのに、一日分の報道すら読み切れない日もありました。この時期はかなり大変でした。
先輩研究者への報告は、1~2か月の間に起きた内政・経済・外交の特筆すべき出来事をまとめて発表するというものでした。まとめといってもそれなりの深さが求められ、先輩研究者からの質問やコメントに対しても対応できるように準備しました。この作業を5か月ほど続けたおかげで、その時々で何が重要な問題なのかを判断できるようになったと思います。2025年1月からアジア動向年報の原稿を書き始めましたが、それまでの報道の取りまとめの経験が非常に役に立ちました。この一年で現地報道を整理して理解する力をある程度、習得できたのではないかと思います。

建国の父ジンナーのモニュメント(パキスタン・カラチ)
IDEスクエアの「世界を見る眼」に総選挙後のパキスタン政治を解説する記事が掲載されました。
毎回の報告内容の中から関心のあるトピックを選んで、IDEスクエア用の解説記事として執筆することが決まっていました。そこで今回は、選挙後に与野党対立の焦点となっていた留保議席問題とその後成立した憲法改正を取り上げました。
解説記事は、「いつだれが何をしたか」「その結果どうなったのか」という事実関係を列挙するだけでは成立しません。「なぜその事象が起きたのか」「その事象がその社会でどのような意味を持つのか」といった分析や解釈が求められます。また、読者を引き込むために、記事の構成や問いの設定を工夫する必要があります。問いの設定という意味では学術論文と同じですが、その問いを「不思議だな」「なぜだろう」と一般読者の心をつかむような構成にすることがポイントです。執筆当初は何を説明したいのかを明確に意識できず冗長な文章しか書けませんでした。しかし、先輩研究者の指導や助言を受けて、記事の大きなストーリーを描き、それを念頭に置きながら最終的に一つの形にすることができました。
郡 昌宏(2024年入所 地域研究センター 動向分析研究グループ)
今後の研究へとつながる日々の作業
基本的には、午前中に専門地域である朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の現地新聞などの報道をチェックしてその日の出来事や重要記事の内容を記録する作業を行い、午後は研究書・論文を読んだり、執筆作業を進めたりしています。ただ、原稿の締め切りが近い時はそれにかける時間を増やすなど、状況に応じて日々の研究活動の内容を自分で調整しています。
この一年間の業務(研究活動)はどのようなスケジュールで進みましたか?
新入研究員向けの研修が業務進行のペースメーカーとなっていました。9月までは、各自の担当地域の1~2カ月ごとの動向について毎月発表し、研修担当の研究員からフィードバックを受けていました。これを通じて担当地域の動向をまとめる習慣や着眼点を身につけていきました。また、8~9月頃には北朝鮮の『アジア動向年報』(『動向』)バンドル版(1980年代)の「解説」を書く業務も行いました。
10月以降は、『IDEスクエア』での解説記事(「『地方発展20×10政策』とは何か――金正恩の戦略を読み解く」)の執筆にあたり、テーマ設定や構成、一般読者にとって読みやすい文章の作成法について個別にアドバイス・添削を受けました。
年が明けると、主要業務である『動向』の執筆が本格的に始まり、これまで蓄積してきた報道・重要事項の記録をもとに、1年間の担当地域の動向をまとめました。

北緯38度線付近を流れる臨津江(2013年撮影)
(インタビュー時点では)今はちょうど『動向』の執筆に取り組んでいるとのことですが、実際にその準備から執筆に至るまでの間で、予想以上に大変だったことには何がありますか?
『動向』業務に関しては、これまで日々記録をつけていたことがもちろん有益ではあったのですが、実際に執筆してみると、自分の記録の情報量やまとめ方に不十分な部分があることに気づき、報道を再確認するなどの手間が生じてしまいました。また、執筆ページ数があらかじめ決まっているので、それに収まるよう、内容を取捨選択しながら書くことも難しかったです。
総じて、1年目は毎日の報道の整理や解説記事の執筆など、慣れていないことの連続で、それらに予想以上に時間を使ってしまったように思います。そのため自身の研究を思うように進めることができず、もどかしい気持ちもありました。ただ、これらの業務を通じて研究テーマの材料が見つかることもあり、今後の研究につなげることを意識して日々のタスクに向き合っています。同様の業務を行ってきた先輩方には「1年目は大変だけれども、慣れれば普通にこなせるようになる」と励まされており、そうなるように努力を重ねたいと思っています。
高橋 尚子(2021年入所 地域研究センター 北東・東南アジア研究グループ)
入所後のサポートで心機一転、基礎から研究に取り組む
日本を対象とした研究から東南アジア研究の世界へ
地域研究センター 北東・東南アジア研究グループの高橋尚子です。2021年4月にアジ研に入所しました。現在はタイの動向事業を担当し,農村・農業分野に興味を持って研究に取り組んでいます。
私は,国内大学の農学研究科修士(農業経済)を修了してすぐにアジ研に就職しました。就職活動では,博士課程進学を金銭的な問題等で早々に諦め,大学院の分野と関わりをもてそうな自治体向けのコンサルやシンクタンク,メーカーを受けていたところ,アジ研の修士卒研究員募集をSNSで知りました。もともと農学を志したきっかけが飢餓問題に触れたことだったので,途上国の事業や研究にも興味があり,応募を決めました。
しかし,その後内定の連絡をいただいた時は,本当に地域研究の研究者になれるのだろうか,という不安がありました。というのは,まだまだ研究技術は未熟だと感じていましたし,自身の修士論文は日本を対象にしており,タイや東南アジアについて研究の土台となる知識はほとんどなかったためです。確かに学ぶことは多いですが,入所後は心機一転して基礎から研究に取り組めていると感じており,周囲の先輩方からたくさんサポートをいただいています。

入所後は個室もしくはブースが与えられ、研究に集中して取り組めます。
刺激が多く、学びの溢れる日々。タイ語の勉強も一から。
アジ研で過ごして1年たち,コロナ禍でなかなか現地に渡航できない現状が少し残念であるものの,少しずつ土台作りをしている最中です。研究分野が近い先輩にチューターとしてついてもらい,定期的に基礎理論や関連論文について勉強しているほか,所内外のタイ研究者の方との勉強会を開催していただき,学びが多い日々です。
アジ研は同じ国や地域に関わる研究者の先輩が多く所属しているので,自身の研究分野以外の話を聞き,議論できることがかなり刺激的だと思います。コロナ禍でなければ先輩の現地調査に同行する研修制度もあり,さらに研究員間では分野や地域も違う方とも,年次や役職に関係なく議論をし,アドバイスをもらえるフラットな関係性だと実感しているので,そのあたりは大学院と雰囲気が異なるかもしれません。これから新人の研究員の方が増えてきたら,分野や地域をまたいで,ぜひ一緒に基礎理論などの勉強会を開催したいです。
また,地域研究は現地語での調査や資料読解が必須なので,所内の研修制度を利用してタイ語の語学学校に通い始めました(現在はオンライン授業です)。アルファベットを使わない言語の習得は初めての経験で,一文字の読み書きに1分かかるような状態から始めましたが,近い将来,現地調査や海外派遣に行くことをモチベーションに楽しく学んでいます。

年次や役職に関係なく議論をし,アドバイスをもらえるフラットな関係性
研究は自分のペースで。タイ農村への現地調査を目標に。
今のところ,研究のペース感は修士学生のころとあまり変わっていない気がします。研究職員は裁量労働制が適応されるので,柔軟に出勤時間を調整でき,朝が弱い私のような人間にも優しい勤務体制になっています。
日々の業務では,毎年出版される『アジア動向年報』の執筆が大きな仕事になりますので,だいたい午前中に現地新聞やメディアで情報収集して日誌を付け,各種政策の整理をします。午後から本や論文を読んだり,勉強会の準備をしたり,提出する原稿がある場合は文献を探し,執筆を行っています。午前中の情報収集で引っかかることがあれば,午後にかけてその背景を調べていることもあります。
入所してはじめて執筆したのは『アジア動向年報』のバンドル版(一国の動向年報を10年分まとめる新企画)の概論で,先行文献や統計を参考にしながら,曲がりなりにも2010年代のタイ経済を見渡しました。一つの国について点でとらえる以上に,一連の線,そして面でとらえることの難しさを実感したと同時に,地域研究の奥深さを垣間見た仕事でした。今は,コロナ禍の制限緩和を待ちつつ,タイへの理解を深め,現地の農村に足を延ばせるよう研究計画を練ることが目標です。

研究所図書館には貴重な現地の新聞・書籍があり、研究には欠かせません。
水野 祐地(2021年入所 地域研究センター 北東・東南アジア研究グループ)
担当した仕事が自分の研究に直結
研究業務を行いながら博士号取得を目指す
はじめまして。地域研究センターにて研究員をしている水野と申します。2021年に入所し、インドネシアを担当国として政治について研究を行っています。もともと、修士の頃からインドネシアの政治について関心を持っており、そのまま博士課程に進学する予定だったのですが、アジ研が修士卒の募集を行っていると耳にして、応募してみたというのが入所のきっかけです。
アジ研の名前は私が学部生だった頃から聞いたことがあったのですが、当時は修士卒の募集が行われていなかったこともあり、入所するのが難しい研究機関であるとのイメージを持っていました。しかし、14年ぶりに修士卒の募集が行われるようになったうえ、入所してからも研究所の業務をこなしながら博士号の取得が可能であると聞いて、「この機会を逃す手はない」とダメ元で応募しました。

研究ブースにはすでにたくさんの資料が。
担当した業務の経験が、自分自身の研究の深化に
入所してからは、自分が想像していた以上に研究環境が整備されていて、与えられた業務をこなしながら、思う存分研究に打ち込むことができています。私の場合、現在の主業務はインドネシアの政治と経済の動向を追い、『アジア動向年報』と呼ばれる年報のインドネシアの章を執筆することです。そのため、毎日現地メディアを読み込み、時事の背後にある政治・社会問題や経済課題について、現地の人々の目線に立って理解するようにしています。
この業務をこなしていくだけでも、自分の研究内容と深い関わりがあり、それをさらに深化させてくれるものなのですが、それに加えて、自分が関心を持っている研究テーマについて資料や文献を読み込んだり、チューターの指導の下でディシプリンを勉強して基礎作りを行っています。
また、アジ研では業務の一環として科研費プロジェクトの実施が可能であることも大きな強みだと思います。2021年は新型コロナウイルスの影響で現地調査ができませんでしたが、その分の研究費で図書や資料を収集したり、PCなどの機器を整備したりすることができました。
アジ研の業務をこなすうえで根幹となるのが、担当国の言語の習得ですが、私の場合、学部の頃にインドネシアへ留学を行うなどして基礎を習得したことがあったため、入所後は研修費を使って個人講師とのプライベートレッスンを受けて、より高い語学力を身につけられるよう勉強を続けています。
さらに、アジ研内には非常に多様な国・地域の専門家が集まっているので、異なる国の専門家の方々との交流を通して、自分の担当国を観察するだけでは気づけなかった新しい視点を学ぶことができます。研究所の調査費で担当国以外の国々も訪問できるので、新型コロナウイルスの感染が落ち着いたら、是非ともこれまで訪問したことがなかった国々を訪れ、比較材料として異なる国・地域の事情を観察してみたいと考えています。
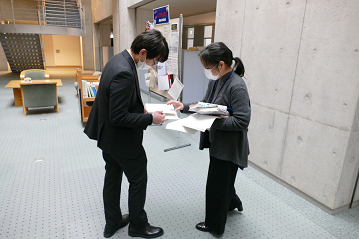
同じインドネシアを研究する濱田開発研究センター長と。気軽に相談できる雰囲気の組織です。
成果発信の機会を生かして
アジ研の研究員にとって最も大事なタスクのひとつが、研究成果や報告書の発信です。私の場合、『アジア動向年報』の執筆が主業務ですが、その前の段階として入所後最初に執筆したのが、『IDEスクエア』と呼ばれるアジ研のウェブ・マガジンに投稿した記事です。私が執筆した記事では、2021年のインドネシアを振り返った時に特に重要な政治問題として政府による市民社会に対する圧力があったため、これに関する現地の動向を整理し、問題となっている法律や現地の人々の声を取り上げました。
今後の私の課題は、博士号の取得に向けて研究課題を設定することです。 修士卒でアジ研に入所しても、博士課程にて調査を実施したり論文の執筆を行うスキルを習得したりする重要性は変わらないので、アジ研で働いている強みを生かしながら取り組めるテーマを探っていきたいと考えています。

研究所図書館は最大限活用しています。
三浦 航太(2022年入所 地域研究センター アフリカ・ラテンアメリカ研究グループ)
研究職として入所後、所内研究会と並行して博士論文を執筆
地域研究センター アフリカ・ラテンアメリカ研究グループの三浦航太です。2022年4月に入所しました。社会運動論(特に社会運動の政治的影響・帰結について)と、チリの社会・政治を専門としています。学部時代にチリに留学した際、大規模な学生運動を目の当たりにしました。そこで衝撃を受けたことが、私を研究の道へ、また社会運動論や地域研究の世界へといざないました。
私は入所前、博士課程を満期退学したのち、博士論文の執筆を進めながら、助教として大学に勤めていました。大学の公募にも何度か応募していましたが、その一方で、若手のうちに研究に没頭できる環境に身を置きたいとも考えていました。アジ研でラテンアメリカ研究に携わられてきた先輩方には、博士課程の時代からお世話になる場面が多かったこともあり、思い切ってアジ研の研究職採用に応募しました。
入所後は、所内研究会と並行して博論の執筆を進めました。アジ研の先輩方は、業務と博論執筆のバランスや、博論の進捗に常に気を配ってくださり、安心して業務と博論執筆を両立することができました。先輩方に進捗や目標を口に出して言うことで、自分自身に対して適度にプレッシャーをかけることもできたと思います。そのおかげで「チリにおける高等教育のパラダイム転換―学生組織、政治、社会の関係に着目した学生運動の政治的結果に関する分析」というタイトルで無事に博論を提出し、優秀学位論文賞をいただきました。

受賞式でのスピーチの様子。
アジ研に入って1年目の収穫は、何よりも、所内研究会を通じて自身の研究の世界が広がったことです。私の場合、入所した時点で博論が終盤に差しかかっており、ひたすらアウトプットを進めるという状況でした。一方で、所内研究会では、博論とはまた異なる様々なテーマについてインプットする機会となり、新しい問題意識や研究課題を見出すことができました。そうした新しい学びによって、博論を広い文脈の中に位置づけ直すこともできました。博論にとにかく集中する道もあったのかも知れませんが、多少きつくとも、並行して新しい研究テーマに向き合えたことは、今後のキャリアに必ず生きてくると思っています。
実は現在、現地調査でチリに滞在中!
さて、実はこの文章、現地調査で滞在中のチリの首都サンティアゴで書き進めています。今回の現地調査では、近年の社会運動や、社会運動から生まれた新しい政党について、関係者や研究者への聞き取りを行うほか、アーカイブや図書館での資料収集を行っています。また、空き時間には書店巡りもしています。私が研究する分野のチリの学術書の多くは、5年ほど前からだいぶKindleで読めるようになりましたが、知らなかった本に出会え、最新の出版動向が一目で把握できるのが、現地書店の変わらぬ魅力でもあります。

南米で最も高いビルGran Torre Santiagoから見たサンティアゴ市街地
研究職としてアジ研に入所し、博論を書き終えて、研究者のキャリアとしては第二段階に入るところです。ここから数年は、引き続き所内研究会への参加を通じて、自身の研究の世界を深め・広げたいと思っています。また、博論を書籍化すると同時に、第一段階では達成できなかった、論文を英語やスペイン語でも発表することにも励んでいきたいと考えています。




