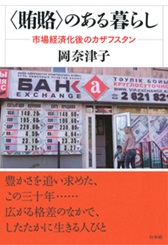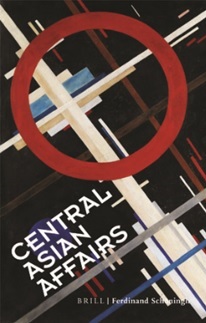IDEスクエア
論考
中国・新疆ウイグル自治区のカザフ人――不法入国とカザフスタン政府のジレンマ
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00051713
岡 奈津子
2020年4月
(16,818字)
はじめに
判決後、喜びに思わず両手で顔を覆うポニーテールの中年女性。狭い法廷に拍手と歓喜の声が響き渡る。ガラス張りの被告人席から出るように促された彼女は、集まった家族や支援者らと抱擁を交わした。さらに外に出て裁判所の前に立つと、ナザルバエフ大統領と同胞たちへの感謝の言葉を述べ、「カザフスタン万歳!」と叫びながら力強くこぶしを突き上げた1。
この女性の名はサイラグル・サウトバイ。中国・新疆ウイグル自治区出身のカザフ人で、2018年4月、偽造パスポートを使ってカザフスタンに不法入国した罪に問われていた。対中国境に近い南東部の町ジャルケントの裁判所は同年8月、彼女に執行猶予付き懲役6カ月の刑を言い渡した。焦点となった中国への強制送還については、入国目的が家族との再会であったこと、また夫と子ども二人がカザフスタン国籍を有することを考慮し、行わないとされた。
サウトバイの裁判は、カザフスタン国内のみならず国際的にも大きな関心を集めた。彼女が法廷で、新疆のカザフ人などを対象とした「再教育施設」の実態について詳細に証言したからだ。しかもサウトバイは単なる収容者ではなく、彼らを教育する職員として勤務していたため、少数民族を対象とした思想教育に関する機密文書にアクセスすることができたという。
近年、新疆のムスリム住民に対する人権侵害が国際的な批判を浴びている。中国政府は当初、「再教育施設」の存在そのものを否定していたが、のちに「職業技能教育訓練センター」(职业技能教育培训中心)であると説明した。テロ対策の一環ではあるが、センターへの「入学」はあくまで自由意思に基づいているというのが公式見解である。しかし国際人権団体や欧米諸国は、100万人以上の人びとが正当な理由もなく強制的に収容されているとして、拘束の中止と独立査察団の受け入れを求めた。2019年末、中国政府はこれらの施設にいた「生徒」はみな「卒業」したと発表したが、自宅軟禁、強制労働、刑務所への収監などの弾圧は続いている。
カザフスタンと国境を接する新疆には、140万人を超えるカザフ人が住んでいる。ムスリム住民としては、ウイグル人に次ぐ人口規模である。1990年代以降、新疆のカザフ人のなかには、カザフスタンの在外カザフ人呼び寄せ政策に呼応して移住する人びとがあらわれた。家族がカザフスタンと中国に分かれて住むことも珍しくなく、両国間の往来も活発であった。しかし最近では、中国政府による管理強化により、カザフスタンへの移動を事実上禁止される事例も生じている。
1991年の独立以降、カザフスタン政府は移住を希望する在外同胞を積極的に受け入れてきた。しかし、サウトバイのように、中国政府の弾圧を糾弾するカザフ人たちを手放しで歓迎しているわけではない。他方で、庇護を求める同胞を追い返すことも難しい。経済的な影響力を増す中国への警戒心が強まるなかで、「親中」と映る政策は国民の強い反発を引き起こすリスクがあるからだ。
本稿は、新疆からやってくるカザフ人の処遇をめぐり、カザフスタン政府が直面するジレンマに焦点を当てる。以下ではまず、不法入国者の裁判事例から、彼らがカザフスタンを目指した理由を明らかにし、先行研究や報道等に基づきつつ「再教育施設」の概要を示す。次に、カザフスタン政府の移民政策について、在外カザフ人の呼び寄せに至る歴史的背景と、民族構成の変化を受けた質的な転換に言及する。そのうえで、民族的同胞の庇護を要求する国内世論と、「反テロ闘争」への理解を求める中国とのはざまで、カザフスタン政府が新疆のカザフ人にどう対処しようとしているのかをみることとしたい。
注目された裁判
2018年以降、カザフスタンでは5人の中国籍カザフ人に対する裁判が行われている。彼らは「再教育施設」への収容を宣告されたり、その危険が迫っていたりしたことを越境の理由にあげ、パスポートを没収されたため合法的入国が不可能であったと主張した。また、配偶者や親きょうだいなど、カザフスタン国籍を持つ親族がいるという点も共通している。
この5人のうち、最初に被告人として法廷に立ったのが上述のサウトバイである2。保育園の園長を務め共産党員でもあった彼女は、家族と不自由のない暮らしを送っていた。しかし2016年以降、隣人や園児の親たちが夜間、相次いで連行され、身の危険を感じるようになった。カザフ語で学ぶことのできる学校が次々と閉鎖されたこともあり、将来に不安を抱いた夫妻は移住を決意したが、公務員であるサウトバイは出国を許されなかった。そのため、夫と子どもたちが一足先にカザフスタンに向かったのである。
新疆に残ったサウトバイは2017年11月、夜間に目隠しされたまま、見知らぬ場所に連行された。彼女自身の表現によれば、そこは「強制収容所」であった。2500人ほどの収容者の大多数はカザフ人だったが、ウイグル人やキルギス(クルグズ)人もおり、サウトバイは教師として働くことを命じられた。科目は中国語、中国の歴史と文化、共産党の政策、習近平の演説など多岐にわたり、発言内容も事細かに決められていた。生徒たちは名前ではなく番号で呼ばなければならず、彼らとの会話は禁じられていた。
2018年3月、サウトバイは来た時と同じように目隠しされ、自宅に戻された。この際、施設で見聞きしたことは決して口外してはならない、とくぎを刺されている。再び保育園で働き始めたのもつかの間、今度は教師としてではなく、彼女自身の思想を「純化」するため3年間収容すると告げられた。サウトバイが新疆を脱出する決意を固めたのは、この時である。
冒頭で触れたように、サウトバイは強制送還を免れたものの、難民申請は却下された。彼女に難民の地位を与えれば中国政府による弾圧を認めることになる。サウトバイのケースは中国側からとくに注視されていたため、カザフスタン政府としては反発を買うようなことは避けたかったのだろう。一家は2019年6月にカザフスタンを去り、現在はスウェーデンで暮らしている。
家族とともに安住の地を得て、メディアで積極的な発言を続けているサウトバイだが、カザフスタンへ入国した際の詳しい経緯に関しては口をつぐんでいる。公にされているのは、ホルゴス税関を通過したということである。ホルゴス国際国境協力センターはビザなし訪問が可能で、一定の金額・量以内なら商品が非関税で購入できる。多くの商人と買い物客が集まるため人目につきにくく、越境者にとって身を隠しやすいルートだ。
サウトバイが国境を越えた翌月の2018年5月には、やはりホルゴス経由でカイシャ・アカンとティレク・タバラクがカザフスタンへの入国を果たしている。
アカンの証言は、越境の経緯を具体的に語っている点で興味深い。彼女は「ある人物」から150万テンゲ(約50万円)の賄賂を要求されたが、所持金がそれより少なかったため値下げ交渉をし、中国元で支払うことで相手と合意した。その男はアカンを税関まで連れて行き、女性の商人たちに引き渡した。アカンは彼女たちの荷物の運搬を手伝うふりをして、税関を通過したという。それから1年以上が経過した2019年8月、アカンは内務省と国家保安委員会国境警備隊に不法入国を申告し、2019年12月、ジャルケントの裁判所で執行猶予付き懲役6カ月の判決を言い渡された3。
新疆出身者のなかには、カザフスタンで合法的に暮らしていたものの、中国に一時帰国した際に拘束され、戻れなくなったというケースも少なくない。タバラクの事例がまさにそれだ。彼は中国籍のままカザフスタンの居住許可を得ていたが、2017年末の訪中時、当局にパスポートを取り上げられてしまった。2020年1月半ば、ジャルケントの裁判所は懲役6カ月の判決を下したが、未決勾留日数の二倍の期間が刑に算入されたため(逮捕は2019年10月)、タバラクはまもなく釈放された4。
タバラクの裁判とほぼ同時期に、ジャルケントから北に数百キロ離れた東部の町ザイサンでも、不法入国者の裁判が行われていた。注目度という点ではこちらが勝っていたかもしれない。被告人の二人が逮捕前、SNSや公の場で窮状を訴えていたことに加え、国家保安委員会幹部が強制送還の可能性に言及していたからだ。
2019年10月初旬、カステル・ムサハンウルとムラゲル・アリムウルは新疆からカザフスタン北東部の国境を越えて入国し、その後、カザフスタン最大の都市アルマトゥに向かった。彼らは新疆で受けた弾圧に関する証言映像を公開するとともに、人権団体のオフィスで記者会見を開いた。二人は「再教育施設」の実態や警察の拷問について証言したが、なかでもムサハンウルは5年近く施設で拘束され、解放後も教育係として働かされたという。会見後、二人は逮捕され、拘置所に収容された5。
2019年末には、ダルハン・ディルマノフ国家保安委員会副議長が、ムサハンウルとアリムウルはカザフスタンと中国の合意に基づき送還されると発言し、物議をかもした6。しかし2020年1月下旬、裁判所は二人を中国に送還しない決定をし、それぞれに懲役1年を宣告した。この際、タバラクの場合と同様に、未決勾留日数の二倍の期間が刑に参入されため、2020年7月には釈放される予定だ7。
「再教育施設」の実態
不法入国者たちが収容されていた、あるいは収容を恐れた施設とは、いったいどのような場所なのだろうか。これについては研究者、報道機関、支援団体や国際人権団体によって、その実態の一部が明らかにされている。
Zenz(2019a, 2019b)は中国国内の行政文書や公式報道、建設資材・物資調達の入札情報、予算や求人に関する情報などをもとに、「再教育施設」の広まりと規模を推定した。それによると2017年春以降、こうした施設の拡張や新規建設が大規模に行われ、その数は1300~1400、収容者数は100万人に達したとみられる。また、オーストラリア戦略政策研究所は衛星写真を用いて28の施設の具体的な位置を特定し、各種の文献情報と照合したデータベースを作成した(Ryan, Cave and Ruser 2018)。これらの収容施設は2017~2018年に規模を急速に拡大したとされるが、その分析はZenz(2019a)とも一致する。
組織的弾圧を示す公文書も流出している。2019年11月、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)は、新疆ウイグル自治区の党中央政法委員会が作成した施設運営マニュアルを入手した。そこには収容者の洗脳方法、逃亡防止と違反行動に対する厳しい懲罰、生活の徹底的な監視など、施設を運営する上での指針が具体的に記されていた。また、ICIJがリークしたほかの文書には、AIを駆使した住民監視システムに関する情報や、海外在住者についての情報収集を命じる指令も含まれていた8。
同じく2019年11月には、ニューヨーク・タイムズが新疆における弾圧に関する別の公文書を入手している。なかでも注目されるのは、役人が休暇で帰省した学生たちの質問に対応するための詳細な想定問答集である。そこには、自宅に戻ってはじめて家族が施設に送られたことを知った学生から聞かれそうなこと、例えば、家族はどこへ行ったのか、職業訓練であるならなぜ帰宅できないのか、何らかの罪を犯したのか、などが列挙され、それぞれについて模範解答が示されていた9。
さらに2020年2月には、自治区南西部のホータン地区で拘束されたウイグル人311人に関する詳細な個人情報が流出した。この文書には施設に収容されることになった理由も記されているが、認められている人数以上の子を出産した、海外渡航経験がないにもかかわらずパスポートを所持していた、「要注意国」(後述)を訪問した、宗教的伝統に従ったなど、そのほとんどがテロ行為とは無関係なものばかりである10。
研究者や活動家による情報の収集・蓄積も進んでいる。ロシア系米国人研究者ジーン・ブーニンが作成した「新疆犠牲者データベース」(Xinjiang Victims Database)は、元・現収容者について、年齢、性別、民族、職業、出身地、収容時期、収容理由および健康状態などを収録しているが、その数は2020年4月現在、8400人分に達した11。このデータベースには当事者の詳細な証言も含まれている。なお、ブーニンは新疆出身のカザフ人の支援団体アタジュルト(後述)と交流があり、両者は互いの活動に深く関わっている。
かつて収容されていた人びとの証言により、施設内部の様子も明らかになりつつある(例えば、Human Rights Watch 2018)。拘束の主なターゲットは成人男性だが、施設には10代の未成年者から80歳を超える高齢者までの老若男女が収容されているという。数々の証言から浮かび上がってくるのは、セキュリティカメラ等を用いた周到な監視、イデオロギー教育と思想統制、肉体的・精神的・性的な虐待である。
収容者たちは中国語学習のほか、中国共産党を讃える歌を歌ったり、スローガンを繰り返し述べたりすることを強要される。殴打、水責め、睡眠はく奪、手錠や足かせなど、肉体的な拷問に関する告発も多い。鉄製の椅子に縛り付け長時間拘束する「タイガー・チェア」も使われているという。施設内でのレイプや強制的な堕胎も横行している模様だ。また多くの元収容者が、ムスリムにとって禁忌である豚肉食を強要されたと訴えている。
2019年12月、新疆ウイグル自治区のショフラト・ザキル主席は、施設にいた全員が「卒業」し、安定した職に就いたと発表した12。カザフスタン外務省も同年10月、施設に収容されているカザフ人は存在しないと述べている13。しかしカザフスタンでは、親族がまだ拘束されていると訴える人が後を絶たない。また、「再教育施設」が実際に閉鎖されつつあるとしても、ムスリム住民への弾圧がなくなったわけではない。収容者たちは解放後も、しばしば強制労働を科されているからだ。彼らはおもに繊維・衣料などの労働集約的な産業に従事し、わずかな賃金で長時間働くことを余儀なくされている(Zenz 2019c)。
施設の拡大が始まった2017年には、新疆における逮捕者と刑務所への収監者の数も激増している。ニューヨーク・タイムズによると、2017年だけで8万7000人が5年以上の刑期を宣告されたが、これは対前年比で10倍に増えているという。具体的な人数は不明だが、中国を脱出したウイグル人やカザフ人の証言によると、「再教育施設」から刑務所に移されたケースも存在する14。
さらに「塀の外」にいるムスリム住民も、自宅軟禁、居住地域外への移動禁止など、さまざまな制限を課されている。ヒューマン・ライツ・ウォッチは、新疆ではハイテク技術を駆使した監視システムにより隅々にまで管理が及んでおり、人びとの日常生活は収容施設内部のそれと多くの点で似通っていると指摘する(Human Rights Watch 2018)。
カザフスタンの在外同胞呼び寄せ政策
新疆のムスリム住民が尋問を受けたり逮捕・勾留されたりする理由のひとつに、外国とのつながりがある。新疆政府が作成した「要注意」とされる26カ国のリストには、カザフスタンなど中央アジア5カ国が含まれているが、これらの国に滞在した経験があったり、家族がいて連絡を取り合ったりすると、取り調べの対象になる。新疆のカザフ人のなかには、以前、自身がカザフスタンに滞在したり、親きょうだいや配偶者、子どもがカザフスタンに住んでいたりする人も少なくない。彼らはそれだけの理由で、潜在的な「スパイ」の扱いを受けているのである。
2010年中国国勢調査によれば、新疆ウイグル自治区の全人口は2182万人で、カザフ人はその6.5%(141.8万人)を占めている。同自治区の民族構成は、ウイグル人が全体の45.8%、漢族が40.5%で、カザフ人はそれに次ぐ第三の集団だ。中国全体のカザフ人人口は146万人なので、そのほとんどが新疆に住んでいることになる。自治区のなかでも、カザフ人は北部のイリ・カザフ自治州に集中している15。カザフスタンを除けば、最大のカザフ人人口を擁するのが新疆である。
遊牧生活を送っていたカザフ人が現在のカザフスタン領と中国領に分断されたのは、19世紀後半、ロシア帝国と清朝とのあいだで行われた国境画定による。その後、ロシア(のちにソ連)と中国それぞれの政治変動や深刻な食糧難を受け、西から東へ、あるいは東から西へと、双方向の移動が繰り返された。なかでも、帝政ロシア政府の徴用令をきっかけとする1916年反乱や、ソビエト政権下の1930年代に行われた遊牧民の強制的定住化・集団化は、数十万のカザフ人が中国領に逃れる事態を招いた。これとは逆に1962年には、6万人超のカザフ人が新疆からソ連側に越境する事件が発生した。1970年以降は、中ソ対立の深刻化により両国間の税関が暫時封鎖された。自由な往来が再び可能となったのは、ソ連末期のことである(野田 2015,Ablazhey 2016)。

1991年末に独立したカザフスタンは、その領域外に住むカザフ人に対し父祖の地への「帰国」を呼びかけてきた。カザフ人移民は、カザフ語で「帰還民」を意味する「オラルマン」と呼ばれる。この用語は法律上、定住を目的としてカザフスタンに来た外国籍ないしは無国籍のカザフ人を指す。したがって帰化した時点で「オラルマン」ではなくなるが、実際には国籍の有無にかかわらずカザフ人移民全体に対して使われることが多い。
在外カザフ人呼び寄せ政策には、カザフ民族の故地であるカザフスタンは、国家として在外同胞に道義的責任を負うという立場が反映されている。また、ロシア革命と内戦、強制的定住化・集団化、飢餓など、帝政ロシアおよびソ連時代の政治的混乱や戦火により諸外国に逃れざるを得なかった人びとおよびその子孫は、帰還の権利を認められるべきだとされた。ただし在外カザフ人がみな、そうした難民の子孫というわけではない。自らの移動によってではなく、国家間の線引きや変更のためにカザフスタンの領域外に住むことになったカザフ人も少なくないからだ。
在外カザフ人の「帰還」奨励には、憲法や移民法などの公的文書には明示的に書かれていない目的もあった。それはソビエト政権下で激減したカザフ人人口の増大と、言語・文化の復興である。カザフスタンはソ連時代に人口的・言語的ロシア化が最も進んだ共和国の一つであった。ロシア人が多い都市部や北部・東部を中心に、カザフ人自身のあいだでもカザフ語をあまり話さない、あるいはカザフ語よりもロシア語の読み書きのほうが得意な人びとが現れたのである。これに対し新疆やモンゴルではカザフ人が集住し、民族的特徴を保持しやすい環境にあった。ロシア化の波にさらされたカザフスタンのカザフ人に比べ、彼らは比較的よく民族の言語や伝統を保っていたのである。
カザフスタン共和国労働社会保障省によれば、1991年以降に移住し「オラルマン」のステイタスを得たカザフ人は、2020年初の時点で105.7万人にのぼっている。このうち、2019年の1年間では中国からの移民が7326人で最も多く、全体の41.5%を占めた16。ただしカザフ人移民の送り出し国は時期によって変化している。Alekseenko(2008)によれば、1990年代にはウズベキスタンからの移民が最大規模で、モンゴルがそれに続いていたが、その後モンゴル出身者は激減し、2003年以降はウズベキスタンと中国からの移民が増大した。現在も累計ではウズベキスタンが最大の送り出し国だが、中国からの移民が占める割合が増えつつある17。
人口的なカザフ化という目標に鑑みれば、在外カザフ人の「帰還」はそれなりの成功を収めたといえるだろう。ソ連最後の国勢調査(1989年)によれば、カザフスタンのカザフ人人口は全体の40.0%(649万人)に過ぎなかったが、2019年には68.0%(1251万人)に達している。ただし、このような変化をもたらした要因としては、1990年代のロシア系住民の大規模な国外流出も指摘しなければならない。ロシア系住民と比べた場合、出生率が相対的に高いことも、カザフ人の人口増につながっている。
民族構成の変化は、カザフスタンの移民政策を質的に転換させることになった。カザフ人が明らかな多数派となってからは、在外カザフ人の呼び寄せはもはや国家建設の重要な柱の一つではなくなったのである。2007年以降、移住費用の補償や住宅購入資金の提供を行う際には、移民の教育水準や技能・経験などに応じて優先順位がつけられるようになった。他方で政府は、民族を問わず、専門的技能を持つ旧住民にカザフスタンへの再移住を呼びかけている。移民政策においては民族的帰属よりも労働者としての「質」、すなわち移民がカザフスタン経済にどう貢献できるかが問われるようになっているのである(岡2013)。
さらに、上述のように近年の中国政府によるムスリム住民への弾圧強化は、在外カザフ人をめぐる問題に新たな展開をもたらしている。新疆からカザフスタンにやってきたカザフ人が、施設への収容をはじめとする人権侵害について証言し、抗議の声をあげるようになったからだ。そうした言動は新疆に残る親族を危険にさらすリスクをはらんでいるが、救済のためには自分たちが動くしかないと彼らは主張する。これまで「帰還民」は生活上の困難を抱えながらも、公の場で異議申し立てを行うことはほとんどなかった。しかし、新疆出身のカザフ人はいま、同胞の庇護を強く求めている。彼らはカザフスタン政府にとって、中国との関係に影響を及ぼしかねない存在になったのである。
カザフスタン政府のジレンマ
すでに触れたように、カザフスタン政府は新疆からの不法入国者を難民として認定していないが、少なくとも裁判になったケースについては中国への強制送還も行っていない。これは中国政府に配慮する一方で、国民感情を考慮した結果といえよう。
カザフスタンにおける中国のプレゼンスは年々増しており、とりわけ経済分野での存在感が際立つ。一帯一路構想を掲げる中国側にとっても、ユーラシアの中心に位置し豊富な資源を有するカザフスタンへの期待は大きい。カザフスタン政府としては、対中関係にひびが入りかねないようなことは極力回避したいのが本音だろう。
しかし、中国政府の求めに応じて不法入国者たちを引き渡せば、国内で強い反発を買うことは必至だ。それは単に同胞への同情からくるものではない。カザフスタンでは中国の影響力に対する警戒心が強まっており、それが「親中」的な政府への反発という形をとって表面化することもある。その代表例が、土地法の改正が契機となって発生した2016年春の抗議デモである。このとき人びとを行動に駆り立てたのは、国有地が外国人の手に渡ってしまうのではないかという懸念だったが、想定された外国人は中国人とほぼ同義であった(熊倉2018)。新疆のカザフ人に対する弾圧は、こうした反中感情をさらに強める要因ともなっている。
難しいかじ取りを迫られるなかで、2018年には水面下の交渉が功を奏したとみられる動きもあった。カザフスタンに移住して国籍を取得した後に中国を訪問し、中国籍の放棄手続きが終了していないとの理由で拘束された人びとについて、カザフスタン外務省はその解放を求め、中国側も一部、これに応じたのである18。カザフスタンのパスポートを没収された人に領事館が臨時パスポートを発行し、出国させたケースも報道されている19。2018年12月にはカザフスタン外務省が、2000人以上のカザフ人が中国籍の放棄とカザフスタンへの出国を許可されたと公表した20。
他方で、カザフスタン政府はこの時期、中国への配慮ともとれる対応を行っている。それがボランティア団体「アタジュルト(祖国)」のリーダー、セリクジャン・ビラシュの逮捕である。ビラシュは新疆出身のカザフ人で、2000年代初めにカザフスタンに移住して国籍を取得したのち、2017年、新疆で弾圧を受けたカザフ人のための支援団体をアルマトゥに立ち上げた。アタジュルトは当事者やその親族への援助に加え、彼らから証言を収集し発信する活動に取り組んできた。中国側から見れば「反中」的な団体といえるが、カザフスタン政府は団体登録こそ認めなかったものの、その存在を黙認していた。
ところが2019年以降、カザフスタン政府は取り締まりを強化する。同年2月、アタジュルトは未登録団体であるにもかかわらず活動を行ったとして罰金を課された。さらに3月、中国政府による弾圧を批判した発言が民族的反目扇動罪に当たるとして、リーダーであるビラシュが逮捕された。この条項は本来、異なる民族的・宗教的背景を持つ集団の平和的共存を維持するためのものだが、実際には反対派の政治活動を封じ込めるためにしばしば利用されてきた21。ビラシュの逮捕もその典型例といえよう。
2019年8月、ビラシュは今後アタジュルトの活動を行わないという誓約書にサインすることと引き換えに釈放された22。アタジュルトそのものも内部対立により分裂する。体制派に転じたメンバー二人が「アタジュルト」の名称で団体登録を申請すると、法務省はそれをすぐさま承認した。それまで一貫して却下していたのとは対照的である。他方、ビラシュの路線を継承する新代表とその支持者らは、さまざまな圧力や妨害により、以前のような活動ができなくなっているという23。
新疆から逃れてきたカザフ人の処遇をめぐっては、中国政府だけでなく米国政府も強い関心を示している。人権擁護の観点から強制送還をすべきではないというのが米国の立場だが、中央アジアで存在感を増す中国を牽制しようという意図も見え隠れする。
2020年2月初旬、カザフスタンを公式訪問したマイク・ポンペオ米国務長官は、ムフタル・トゥレウベルディ外務大臣との共同記者会見で「再教育施設」に言及し、協力して中国に弾圧を止めさせようと呼びかけた。また、ポンペオ長官は親族が施設に収容されていると訴えるカザフ人たちと面談し、ツイッターでその様子を紹介した。その際、カザフスタンが庇護を求めた人びとを強制送還しなかったことに感謝する、とコメントしている24。

さらに2020年3月、米国務省はサウトバイに「国際勇気ある女性賞(International Women of Courage Award)」 を授与した。同賞は「平和、正義、人権、ジェンダー平等、女性のエンパワーメントを擁護するにあたり並外れた勇気と指導力を発揮した世界中の女性を表彰する」もので、2020年には12人が選ばれている。ポンペオ長官は授賞式で、サウトバイは「ムスリム少数民族に対する中国共産党の弾圧について、最初に公言した犠牲者の一人」であり、彼女の勇気ある行動が他の元収容者や家族を鼓舞している、と褒め称えた。
当然のことながら中国政府はこれに猛反発した。張霄・在カザフスタン中国大使はフェイスブックで、カザフスタン訪問時のポンペオの言動を茶番だと切り捨てた。また、サウトバイへの賞の授与は中国の内政に干渉しようとする「恥知らずな挑発」であり、「まったく取るに足らない見世物」だと酷評した25。
新疆問題をめぐり米中の非難合戦が繰り広げられるなかで、カザフスタン政府は沈黙を貫いている。2019年3月、ヌルスルタン・ナザルバエフの突然の引退を受けて大統領に就任したカスムジョマルト・トカエフは、これまでも中国政府の「過激主義」との闘いに理解を示してきた。トカエフ大統領は2019年末、ドイツのテレビ局のインタビューで、国際人権団体の情報は現実を反映していないとし、新疆のカザフ人をめぐって「意図的に緊張状態が作り出されている」と苦言を呈した。そのうえで米中貿易戦争に触れつつ、カザフスタンは「グローバルな反中戦線」に加わってはならないと述べている26。
とはいえ、カザフ民族の歴史的祖国という国家理念を掲げるカザフスタンは、新疆出身のカザフ人たちの声を完全に無視することはできないだろう。また、国家建設の一環として実施してきた在外カザフ人呼び寄せ政策を放棄することも難しい。新疆のカザフ人をめぐる問題は、今後もカザフスタン政府に慎重な対応を迫ることになろう。
写真の出典
- 写真1 筆者撮影(2008年)
- 写真2 U.S. Department of State, Secretary of State Michael R. Pompeo, First Lady of the United States Melania Trump, and awardee Sayragul Sauytbay, an ethnic Kazakh from Xinjiang, pose for a photo, at the Department of State on March 4, 2020. [State Department photo by Freddie Everett/ Public Domain]
参考文献
- 岡奈津子2013.「『帰還民』へのまなざし――カザフスタンの在外カザフ人呼び寄せ政策と現地社会」山根聡・長縄宣博編『越境者たちのユーラシア』ミネルヴァ書房.
- 岡奈津子2010.「同胞の『帰還』――カザフスタンにおける在外カザフ人呼び寄せ政策」『アジア経済』51(6): 2-23.
- 熊倉潤2018.「中国の影響力拡大とそれに対する反発――中国カザフスタン関係から」IDEスクエア.
- 野田仁2015.「在外カザフ人①――中国のカザフ人」宇山智彦・藤本透子編『カザフスタンを知る60章』明石書店.
- Ablazhey, Natalia 2016. "Kazakh Diaspora in Xinjiang: History and Perspectives of Ethnic Migration in Kazakhstan." In Xinjiang – China’s Northwest Frontier, edited by K. Warikoo, Abington, Oxon: Routledge.
- Alekseenko, Aleksandr 2008. "Immigratsiia v Kazakhstane (1999-2005 gg.)." CAMMIC Working Papers No. 3. Center for Far Eastern Studies, University of Toyama.
- Human Rights Watch 2018. "‘Eradicating Ideological Viruses’: China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims."
- Ryan, Fergus, Danielle Cave and Nathan Ruser 2018. "Mapping Xinjiang’s ‘Re-education’ Camps." Australian Strategic Policy Institute.
- Zenz, Adrian 2020. "The Karakax List: Dissecting the Anatomy of Beijing’s Internment Drive in Xinjiang." The Journal of Political Risk 8 (2).
- Zenz, Adrian 2019a. "Thoroughly Reforming Them Towards a Healthy Heart Attitude – China’s Political Re-Education Campaign in Xinjiang." Central Asian Survey 38 (1): 102-128.
- Zenz, Adrian 2019b. "‘Wash Brains, Cleanse Hearts’: Evidence from Chinese Government Documents about the Nature and Extent of Xinjiang’s Extrajudicial Internment Campaign." The Journal of Political Risk 7 (11).
- Zenz, Adrian 2019c. "Beyond the Camps: Beijing’s Long-Term Scheme of Coercive Labor, Poverty Alleviation and Social Control in Xinjiang." The Journal of Political Risk 7 (12).
著者プロフィール
岡奈津子(おかなつこ) アジア経済研究所新領域研究センター・ガバナンス研究グループ長。PhD in Politics and International Studies. 近著に『<賄賂>のある暮らし――市場経済化後のカザフスタン』白水社(2019年)、"Changing Perceptions of Informal Payments under Privatization of Health Care: The Case of Kazakhstan," Central Asian Affairs 6(1): 1-20, 2019など。
注
- "Delo Sairagul’ Sauytbai: kazashke iz Kitaia aplodirovali u zdaniia suda," Sputnik, 2018/8/1; "Ethnic Kazakh Who Testified About ‘Reeducation Camps’ In China Will Not Be Deported," RFE/RL, 2018/8/1.
- Emily Rauhala, "New evidence emerges of China forcing Muslims into ‘reeducation’ camps," Washington Post, 2018/8/11; "Forced to teach in a ‘re-education’ camp," Outlook, BBC, 2020/1/14.
- Nurtai Lakhanuly, "‘Mne grozilo zatochenie v lager’’. Prigovor kazashke iz Sin’tsziana," RFE/RL, 2019/12/23. テンゲの円換算額の算出には2018年5月の為替レートを適用した。
- Nurtai Lakhanuly, "Kak vynosili prigovor ‘bezhavshemu iz Kitaia’ etnicheskomu kazakhu Tleku Tabaraku?," RFE/RL, 2020/1/16.
- Khadisha Akaeva, "Sud nad kazakhami iz Sin’tsziana: desiatki aktivistov, otvod sud’e i pogranichniki-svideteli," RFE/RL, 2020/1/6; Darkhan Umirbekov, "Chinese Kazakhs slip into Kazakhstan for asylum," Eurasianet, 2019/10/11.
- Chris Rickleton, "Kazakhstan: Asylum seeker trial begins, testing hawkish talk on Xinjiang," Eurasianet, 2020/1/7.
- Catherine Putz, "2 More Ethnic Kazakhs Who Fled Xinjiang Won’t Be Deported," Diplomat, 2020/1/22.
- Zenz (2019b); Bethany Allen-Ebrahimian, "Exposed: China’s Operating Manuals For Mass Internment And Arrest By Algorithm," International Consortium of Investigative Journalists, 2019/11/24.
- Austin Ramzy and Chris Buckley, "‘Absolutely No Mercy’: Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims," New York Times, 2019/11/16.
- Zenz (2020); Ivan Watson and Ben Westcott, "Watched, judged, detained: Leaked Chinese government records reveal detailed surveillance reports on Uyghur families and Beijing’s justification for mass detentions," CNN.
- Xinjiang Victims Database.
- Yanan Wang, "China claims everyone in Xinjiang camps has ‘graduated’," AP News, 2019/12/9.
- Asylkhan Mamashuly, "The Kazakhs Left Behind In Xinjiang," RFE/RL, 2020/1/21.
- Chris Buckley, "China’s Prisons Swell After Deluge of Arrests Engulfs Muslims," New York Times, 2019/8/31.
- Stanley Toops, "Spatial Results of the 2010 Census in Xinjiang," Asia Dialogue, 2016/3/7; "Chinese Ethnic Groups: Overview Statistics," University Libraries, University of North Carolina.
- "Bolee 17,6 tys. oralmanov pribyli v Kazakhstan v 2019 godu," Kazinform, 2020/1/22.
- 2008年10月1日時点でのオラルマンの出身国の人口構成(累計)は、ウズベキスタン59.7%、モンゴル13.7%、中国9.2%であった(岡2010)。これが2016年初にはウズベキスタン61.6%、中国14.2%、モンゴル9.2%となっている。"Pochti million oralmanov pribylo v Kazakhstan za 25 let," Kapital, 2016/2/9.
- Bruce Pannier, "Kazakhstan Confronts China Over Disappearances," RFE/RL, 2018/6/1.
- Reid Standish and Aigerim Toleukhanova, "Kazakhs Won’t Be Silenced on China’s Internment Camps," Foreign Policy, 2019/3/4.
- "Pokinut’ Kitai razreshili dvum tysiacham enicheskikh kazakhov," KazTAG, 2018/12/10; Dake Kang, "China allowing 2,000 ethnic Kazakhs to leave Xinjiang region," AP NEWS, 2019/1/9.
- 憲法第5条3項は「社会的、人種的、民族的、宗教的、階層的、あるいは氏族的反目を煽る(中略)目的を有する、あるいは活動を行う社会団体の結成および活動を禁じる」と定めている。
- Reid Standish, "‘Our Government Doesn’t Want to Spoil Relations with China’," Atlantic, 2019/9/3.
- Mehmet Volkan Kaşıkçı, "Documenting the Tragedy in Xinjiang: An Insider’s View of Atajurt," Diplomat, 2020/1/16.
- "Maik Pompeo v Kazakhstane: kritika Kitaia i nadezhda na sotrudnichestvo," RFE/RL, 2020/2/2.
- 張霄・在カザフスタン中国大使のフェイスブック、2020年2月4日、および3月6日。
- Zhanna Nemtsova, "Prezident Kazakhstana: My ne nazyvaem to, chto proizoshlo v Krymu, anneksiei," Deutsche Welle, 2019/12/4.
この著者の記事
- 2021.04.23 (金曜) [IDEスクエア] (続・世界珍食紀行)特別編 カザフスタン――感染症には馬乳が効く
- 2021.02.03 (水曜) [IDEスクエア] 論考:2020年キルギス共和国政変の背景と帰結――腐敗に蝕まれる「民主主義の島」
- 2020.04.24 (金曜) [IDEスクエア] 論考:中国・新疆ウイグル自治区のカザフ人――不法入国とカザフスタン政府のジレンマ
- 2018.08.03 (金曜) [IDEスクエア] (スポルティクス! スポーツから国際政治を見る)第2回 デニス・テン選手を悼んで――フィギュアスケーターの死がカザフスタン社会に問いかけたもの
- 2014.03.27 (木曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)ロシアによるクリミア併合のインパクト:カザフスタンの対応と「ロシア人問題」