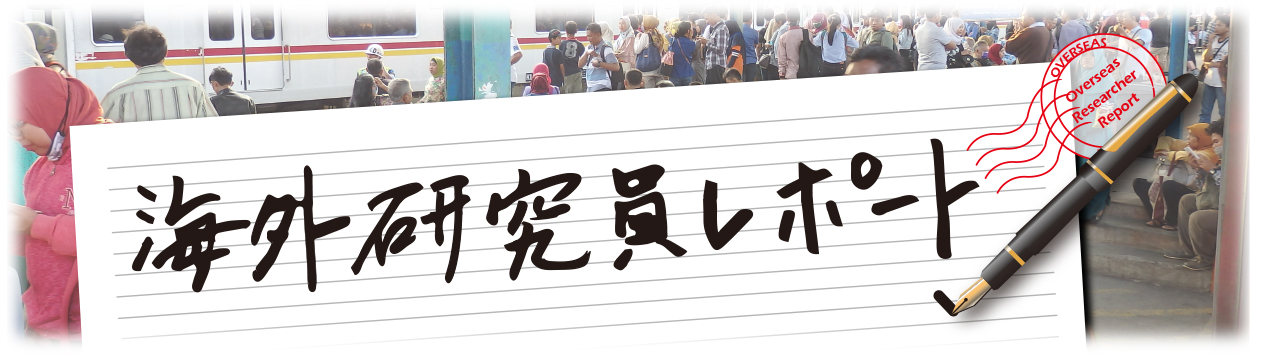IDEスクエア
「脱石炭」がもたらすもの――地域社会・気候変動・雇用(前編)
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00051824
2020年9月
(4,965字)
去る7月3日、梶山弘志経済産業大臣は日本国内の石炭火力発電所100基を2030年までに廃止すると発表した。昨今、脱炭素化社会の実現に向けて「脱石炭」に世界的な関心が集まっている。今回の発表を受け新聞紙上等では、発電所の閉鎖は気候変動対策としてどの程度の効果があるのか、またエネルギーの安定供給を継続するため、代替電源をいかにして確保するかといった観点の報道が目立った。だが実は、脱石炭には地域経済や雇用などへ少なからぬ悪影響をもたらすという問題がある。こうした側面を踏まえ、脱石炭はどのような形で進めていくべきだろうか。また持続可能な開発目標(SDGs)の視点からはどのような論点が見えてくるだろうか。本レポートは脱石炭に焦点を当て、地域社会や暮らしを守りながら脱炭素化社会を目指す「ジャスト・トランジション」の取組みを2回にわたって紹介する。
石炭火力発電所の廃止
日本はパリ協定1に基づき、2030年までに温室効果ガス(GHG)の年間排出量を26%(2013年度比)削減することを目標としている。また、昨年閣議決定されたパリ協定にもとづく長期戦略には、同協定の長期目標と整合的に石炭火力発電への依存度を引き下げ、CO2排出削減に取り組むと記載されている。石炭火力発電は、日本全体の発電量の32%を占めており、今回の発表はその半分にあたる非効率とされる石炭火力発電所を段階的に閉鎖するものである2(資源エネルギー庁2020)。ただし石炭は他の化石燃料に比べて地政学的リスクが低く、熱量当たりの単価が安いため、安定供給や災害リスクへの備えという観点から重要な燃料として認識されている。そのため政府は石炭火力発電を完全に廃止するのではなく、水力や他のエネルギーとともにエネルギーミックスを目指すとしている。資源エネルギー庁によると、今後、非効率な石炭火力発電所の閉鎖に向けて、(1)2030年フェードアウトに向けた規制的措置、(2)安定供給の確保・早期フェードアウト誘導、(3)基幹送電線の利用ルールの抜本見直しなどの検討を進めていく予定である(資源エネルギー庁2020)。
一方で、前述の記者会見では「地域性」の尊重についても触れられており、発電所閉鎖による地域経済への影響や沖縄など他の電源がない地域の存在を考慮して、画一的な進め方は行わないという。経済産業省の推計によると、全国の火力発電所の就業者数はおよそ1万人である(資源エネルギー庁2018)。今回の決定はかれらの雇用に影響を及ぼすのに加え、発電所が設置されている地域に経済的、社会的な打撃を与えると考えられる。実際、発電所を有する地方自治体では、地域の雇用の場の喪失、税収の減少などが懸念されている(日本経済新聞2020; 長崎新聞2020)。
温暖化対策と「暮らし」の両立
気候変動対策は私たちの社会や経済の仕組みを根本から変える可能性を持っている。炭鉱や石炭火力発電所がある地域のように、化石燃料に直接関連の深い産業に経済的に依存し、雇用や間接的な恩恵を受けてきたところでは、人びとの暮らしに大きな影響が出る。またこうした地域に限らず、工業製品の製造過程や農業、漁業を通じて、さまざまな場で化石燃料が利用されている。温暖化をストップするにはこれまでの化石燃料に依存した社会からの転換が必要だが、仕事がなくなれば生活が立ち行かなくなってしまう。温暖化対策を強引に進めれば、関連する雇用の喪失や貧困拡大、地域の衰退を招く危険性がある。環境、経済、社会的側面を多面的に考慮し、影響を受けるさまざまな人びとを包括的にとらえて取組みを進めていく必要がある。
ジャスト・トランジション(公正な移行)
こうしたジレンマを克服すべく近年注目を集めているのが「ジャスト・トランジション(公正な移行)」の概念である。ジャスト・トランジションとは、地球温暖化への対策を行うなかで、平等で公正な(=just)方法での脱炭素社会への移行を目指す概念である3(JTRC 2019)。気候変動対策は急務である一方、生活に直結するような負担の増加は激しい反発を招く。2018年にフランスで起こった炭素税導入をめぐるイエローベスト運動は記憶に新しい。ジャスト・トランジションはもともと1970年代に米国の労働組合運動に端を発するが、2015年にパリ協定で言及されて以降、気候変動対策によって生じる社会的、経済的影響を考慮し公正な転換を図る考え方として徐々に普及している。既存産業の縮小に伴う失業やコミュニティの衰退に対する支援など、「環境vs仕事」の対立構造を克服し、公正な形で社会転換を図るための取組みが始まっている。
SDGsの文脈においても、ジャスト・トランジションはSDGsの達成に寄与する重要な施策のひとつとされ、特にSDG7(エネルギー)、SDG8(雇用、経済成長)を中心にSDG13(気候変動)、SDG1(貧困)への間接的な貢献を目指している(Burrow 2017; ILO 2015)。
例えば、化石燃料に依拠する産業の縮小(石炭鉱山の閉山など)を行う際には、労働者の失業対策、影響を受ける地域への支援など、社会問題への対策が必要となる。国際労働機関(ILO)は、化石燃料に依存した現在のエネルギー利用から脱炭素型エネルギーの産出、利用への転換によって、将来的に600万人の雇用が失われる一方、アジア太平洋地域を中心に新たに2400万人の雇用が創出されると試算している(ILO 2018)。
現在2030年代の脱石炭を図るいくつかの国々が、国内の石炭採掘場や石炭火力発電所の閉鎖に伴う失業者対策、地域振興および再生可能エネルギー産業での雇用創出など対策を進めている。またトップダウンの施策のみならず、影響を受ける自治体やコミュニティにおいてもボトムアップで対策を講じているところもある(JTRC 2020)。
欧州では、欧州委員会が今年に入り「ジャスト・トランジション・メカニズム」を発足した。ジャスト・トランジション基金、中期投資戦略である「インベストEU」プログラム下のスキーム、公共部門融資の3本柱に1000億ユーロ規模の投資誘導を掲げる事業を開始した。その後始まったコロナ危機により、同基金への追加予算の計上、グリーンエコノミーによる雇用創出のため1500億ユーロの投資誘導目標を立てていた(安田2020)。未曾有の経済危機にあっても気候変動対策は急務であり、また経済対策としても失業者対策を再生可能エネルギーなどの新事業で賄うことを見込めるという期待があったかと思うが、残念ながら7月に入り方向転換され、ジャスト・トランジション関連予算の縮小が決定された4(Abnett 2020)。
こうした状況でも、2030年代の炭鉱閉鎖や石炭火力発電の停止を目指すドイツやカナダなどの国々では引き続きジャスト・トランジションの取組みが進む。ただし、脱石炭に向けたひとつの大きな流れとして順風満帆に進んでいるわけではない。ILOを中心とした国際機関や各国政府のほか、ビジネス団体やNGOなどさまざまな団体が「ジャスト・トランジション」の重要性を訴えているものの、その内容は多岐に渡る。またジャスト・トランジションは脱石炭に限った概念ではなく、すべての産業と交通や廃棄物処理などのインフラ政策など、脱炭素化社会に必要な転換を含んでいる。再生可能エネルギーなど新規事業の拡大によって脱炭素化社会への早急な移行を求める声がある一方、エネルギー転換によって影響を受ける労働者への補償を第一に訴える声、ポスト資本主義への転換、市場経済からの移行を求める声、あるいは社会的弱者を含め誰一人取り残さない公正さを求める声などもある(JTRC 2018; Ciplet and Harrison 2020)。脱炭素化社会の実現という共通の目的を掲げつつも、ジャスト・トランジションを通してさまざまな思惑がぶつかり合って存在しているのである。
後編では、そうした違いを念頭に置きつつ、炭鉱や石炭火力発電所の閉鎖など脱石炭に向けたジャスト・トランジションの取組みを進めるドイツ、南アフリカなどいくつかの事例を紹介する。
参考文献
- Abnett, K. (2020) "EU eyes cuts to green transition fund in late bid to strike recovery deal." Reuters. 7月20日.
- Burrow, S. (2017). Just Transition: A Report for the OECD. Just Transition Centre.
- Ciplet, D., & J. L. Harrison (2020). "Transition tensions: mapping conflicts in movements for a just and sustainable transition." Environmental Politics, 29(3), 435–456.
- ILO (2018). World Employment Social Outlook 2018: Greening with jobs. ILO.
- ----- (2015).Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all. ILO.
- JTRC (2019. Climate Justice from Below—Local Struggles for Just Transition(s).UNRISD.
- ----- (2018). Just Transition Research Collaborative (Phase I): Mapping Just Transition(s) to a Low-Carbon World. UNRISD.
- 資源エネルギー庁(2020)第1回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 合同 石炭火力検討ワーキンググループ 資料5 「非効率石炭火力のフェードアウトを巡る状況について」8月7日.
- -----(2018)「平成29年度電力市場環境調査」.
- 長崎新聞(2020)「『地元経済に影響大きい』 2030年度までに石炭火力休廃止へ 長崎県内から懸念の声」7月4日.
- 日本経済新聞(2020)「脱石炭火力、稼働年数で選別 地域ごと激変緩和も」7月13日.
- 安田啓(2020)「進む欧州グリーン・ディール投資計画の基盤整備」『ビジネス短信』JETRO,6月30日.
インデックス写真の出典
著者プロフィール
佐々木晶子(ささきあきこ) アジア経済研究所 海外派遣員(スイス・国連社会開発研究所)。2013年より研究マネジメント職として国際共同研究のコーディネートやアジ研の研究内容のアウトリーチなどに従事。2019年11月より国連社会開発研究所(UNRISD)にて客員研究員として、脱炭素社会に向けたトランジョン(Just Transition)における社会的企業、協同組合などの役割について研究を行っている。
注
- 2015年に採択された気候変動に関する国際的な枠組み。
- 石炭火力発電所の閉鎖は今年決定されたことではなく、すでに2018年に閣議決定されている第5次エネルギー計画にもとづいた決定である。
- ジャスト・トランジションには統一された定義がなく、国際労働機関(ILO)や国際労働組合総連合(ITUC)、Climate Justice Allianceなど異なる関心を持つさまざまな団体による多様な解釈が存在する。ここでは筆者が参加するJust Transition Research Collaborative (JTRC)による定義を使う。
- 例えばジャスト・トランジション基金は当初予算の375億ユーロ(約5兆円)から175億ユーロ(約2.2兆円)に削減された(Abnett 2020)。