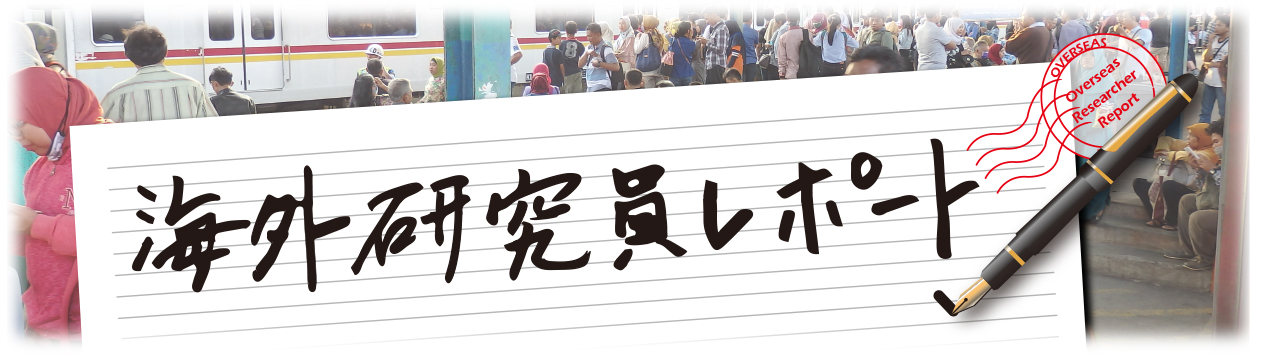IDEスクエア
シンガポールにおける華人アイデンティティと中国
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00051510
江藤 名保子
2019年11月
(6,377字)
シンガポール華人の立ち位置
マレー半島の先端に位置する都市国家シンガポール。ダボス会議の主催者として知られる世界経済フォーラムが発表した『2019世界競争力報告』では、世界1位にランクインした屈指の先進都市国家である。海上交通の要衝であるマラッカ海峡に面していることから、古くからゴムや錫などの交易地として栄えてきた。2019年はイギリス東インド会社のトーマス・スタンフォード・ラッフルズによるシンガポール上陸200周年であり、貿易中継地としてスタートした発展の歴史を振り返るイベントが多く開催されている。
シンガポールはまた、東京23区の1.2倍ほどの狭い国土でありながら多民族国家として知られる。2019年6月の発表によれば、総人口(国民、永住権者の総数)402万6209人のうち、中華系が299万3708人(74%)で最も多く、マレー系54万783人(13%)、インド系36万2637人(9%)と続く。公用語も英語、マンダリン(華語)、マレー語、タミル語の4つが認められている。また社会の高齢化を背景に海外の労働者を積極的に受け入れる政策を採っており、外国人労働者を含む総居住者数は570万3,600人と発表されている。
このうちシンガポール国籍をもつ中華系の人々は「華人」(Ethnic Chinese)と呼ばれ、中国国籍1を維持しながら在住している「華僑」(Overseas Chinese)と明確に区別されている。そして興味深いことに、この区別は近年、より強くなっているようである。8月に開催されたナショナル・デー(建国記念日)の記念式典でリー・シェンロン首相は、マンダリンで行ったスピーチ(英語、マンダリン、マレー語の3つのスピーチがある)で次のように述べた。
1950年代以来、中国は海外にいる華人を「海外華僑」と「華人」に区分してきました。 (中略)当時の中国総理である周恩来氏は、ひとたび所在国の国籍に加入すると、これらの華人はもはや中国国籍を所有せず、帰化国に忠実であるべきだと明確に表明しました。その時、私たちの先祖は、シンガポールに留まるか祖国に戻るかという、人生における大きな選択をしなければなりませんでした。結局、彼らのほとんどはシンガポールに留まることを選択し、他の人種の人々と共に多元的民族の社会と独立した国家を構築しました。
すなわち、中国政府側こそが華人を外国人としたのだ、という認識である。そして米中摩擦について言及し、「中国を支援する場合、米国および他の国は、シンガポールは華人がマジョリティーであるため、これを行っていると考えるかもしれません。一方、米国を支持する場合には、中国がそれを理解するとは限りません」との理解から、シンガポールの立場は「原則に従って行動しなければならず、感情に影響されない」ことだと説明した。
マンダリンでこのようなメッセージが発せられたのは、逆に華人社会では現在も中国に対するシンパシーが根強いことを示唆する。華僑・華人社会の内部では、家族の出身地域や姓ごとの宗郷会館、あるいは福建幇、潮州幇、広東幇、客家幇、海南幇(以上がシンガポールの五大幇)といった方言に基づく団体が、しばしば国境をまたいでネットワークを構成している。他方で国民統合の観点からすれば、華人ネットワークはしばしば閉鎖性が強く、かつては団体間の利権争いや抗争も頻発しており、これらをいかにシンガポール人として取り込んでいくかが政府にとって重要な政治課題だった。華人社会における地縁・血縁・業縁に基づく相互扶助団体の乱立や、建国期に学校教育を英語で受けた勢力である「英語派」と中国語で受けた「華語派」との政治闘争が繰り広げられたことも経験的教訓となっている。
ただし1965年の建国以降、中華系シンガポール国民(Chinese Singaporean)としてのアイデンティティは徐々に広がってきた。1986年には「シンガポール宗郷会館聯合総会」という華人社会を統括する組織も設立された。政策面での華人アイデンティティの推進を象徴的に表すのが、2017年の「シンガポール華族文化センター」(Singapore Chinese Cultural Center)設立だろう。もともとシンガポールには、中国政府による文化交流施設「シンガポール中国文化センター」(Singapore China Cultural Center、2015年開設)があり、中国文化の紹介等を担っている。これに対し「華族文化センター」の目的はシンガポールの華人文化の普及と次世代への引き継ぎにあり、国家による伝統文化保護の位置づけなのである。
しかしこのような華人と中国人の差別化は、米豪にみられる「シャープ・パワー」批判のような、中国の影響力拡大への反発を必ずしも意味しない。次に説明する重慶開発プロジェクトに現れるように、中国との関係構築は新しい展開を見せており、中国・シンガポール関係はむしろ発展している。
ラッフルズシティ重慶が示唆するもの
2019年9月、中国内陸部・重慶の朝天門広場にラッフルズシティ(来福士广场)がオープンし、その名前とマリーナベイサンズを彷彿とさせる外観が注目を集めた。この大型総合施設はキャピタランドとその傘下の不動産投資信託アセンダス・シンブリッジによる、シンガポール単一としては最大の都市開発プロジェクトである。
シンガポールは2015年に政府レベルで「中国シンガポール(重慶)戦略的相互接続実証イニシアティブ」(中新〈重庆〉战略性互联互通示范项目)に合意、金融サービス、航空、運輸、ロジスティクスおよび通信技術(ICT)など5分野での協力を推進してきた。イニシアティブの一環である「南方回廊」(Chongqing Connectivity Initiative - Southern Transport Corridor: CCI-STC)は、現在では重慶市をハブとして中国西部からASEAN諸国への物流を拡大する新輸送網として機能している。さらに2019年9月には、シンガポール情報通信メディア開発庁がシンガポール・重慶間のデジタル通信網を整備するプロジェクト「中国シンガポール(重慶)国際データチャネル」(China-Singapore 〈Chongqing〉 International Data Channel: IDC)を発表、情報通信においても最新技術を用いたコネクティビティ改善が図られることになる。
こうした大型開発プロジェクトが、シンガポールと重慶市の双方に経済的利益をもたらすのは言うまでもない2。ここでは、政治的なメリットも決して小さくないことを指摘したい。このプロジェクトはそもそも2015年11月、習近平国家主席が中国・シンガポール国交樹立25周年の記念行事に参加するためシンガポールを訪問した際に、既存の蘇州工業園区、天津エコシティに続く第3の政府間協力プロジェクトとして合意に至ったものである。3月に「シルクロード経済ベルトと21世紀海上シルクロードの共同建設推進のビジョンと行動」を発表して「一帯一路」構想を本格始動していた習政権にとって、同プロジェクトは格好の手土産となっただろう。
ただし、この時世界が注目したのは重慶コネクティビティ・イニシアティブよりもむしろ、台湾の馬英九総統(当時)もまた同国を訪れ、国家分断後初めての中台首脳会談が実現したことであった。ここでシンガポールが陰の立役者であったことも意味深い。
さらに重慶市は中国政府の直轄市であり、そのトップである党委員会書記のポストには政治的な重みがある。2012年に党委員会書記であった薄熙来が失脚した後には、当時、ポスト習近平の有力候補の一人と目された孫政才が書記に就任した。孫が中国の最高指導部である中央政治局常務委員に就任するためには、民衆に人気のあった薄熙来の影響力を上回る成果が必要であり、シンガポールからの都市開発プロジェクトは大きな支えとなったはずである。孫政才は2017年にあえなく失脚したが、その後任に習近平主席の側近である陳敏爾が就き、やはりポスト習近平候補として最高指導部入りを目指すうえで重慶市および周辺地域の経済発展の成果を基に政治的足場を固める必要がある。一方、シンガポール側としても次期リーダーとなる可能性があるトップに花を持たせることで中国との関係を維持するための布石となると考えられる。
このように政治的な観点から考える時、ラッフルズシティ重慶は重慶市の新しいランドマークであるだけでなく、中国政治のマイルストーンとしても、そしてシンガポールとの政治・経済協力の象徴としても意味を持つ。このような外交戦略には、人的ネットワーク作りに長けた華人社会の強(したた)かさを見る思いがする。
なぜ華人アイデンティティの強化が歴史問題を引き起こさないのか
建国以来、多民族国家でかつ新興独立国のシンガポールでは、国民の共同体意識を高めるために様々な統合策が採られてきた。例えばシンガポールの公団住宅であるHDBでは、民族的な閉鎖性を高めないための配慮から、1棟の住宅の中に定められた割合でエスニシティが配分されるよう部屋が割り当てられている。また国家としての歴史を紹介するシンガポール国立博物館のほかに、各民族の文化を伝える博物館としてチャイナタウン・ヘリテージセンター、マレー・ヘリテージセンター、インディアン・ヘリテージセンターがそれぞれあり、多様性と公平性が保たれている。
そして国民アイデンティティを涵養するにあたり多くの場合に重視されるのが、言語と歴史認識の共有である。まず言語についてシンガポールでは、4つの公用語のうち英語を第1言語とし、そのほか3つのうちの1言語でも教育を受けるバイリンガル教育制度が採られている。すなわち共通言語の普及と個別のアイデンティティに基づく言語の取得を両立させているのである。ただし華人に対しては1979年からスピーク・マンダリン・キャンペーンを開始し、地方ごとの方言ではなくマンダリンを教育することで「華人」としての一体性を政策的に高めてきた。
では歴史はどのように教育されてきたのか。シンガポールにおける華人アイデンティティの強化は、対日歴史問題の先鋭化をもたらさないのだろうか。
ここでは現地の子ども達も訪れる国立博物館の展示を手掛かりに、シンガポールの公的な歴史認識を考察しよう。同博物館では、シンガポールの歴史を①シンガプーラ期(移住してきたマレー系原住民の支配期)、②クラウン・コロニー期(英国の直轄植民地期)、③昭南島期(日本の占領期)、④シンガポール期(第2次世界大戦後)の4つの時期に区分している。
このうち、最も苦しかった時期として説明されるのが、日本の占領時代である。マレー半島からの日本軍の侵攻、熾烈な砲撃・爆撃を受けて連合軍が敗退した経緯、占領下の大変な食糧難とエネルギー難、「日本化」政策による生活の変化、そして占領直後の大規模な華人粛清。18歳から50歳の中華系の男性はすべて反日活動者であるか否かの審査対象となり、日本の憲兵隊が連行したうちの多くが戻らなかったという史実が淡々と、しかし明確に記されている。日本側の発表では5,000~6,000人、非公式推計では20,000~30,000人の犠牲者があるという。また当時の記憶をもつ市民に実施した複数のインタビュー記録(画像および音声)を公開しており、市民社会に及ぼした被害の深刻さを伝えている。

しかし日本軍の残虐さを殊更に強調する部分はなく、あくまで史資料の展示と解説が主である。そして後半では、苦しい時代を乗り越え、リー・クアンユーをはじめとする指導者たちのもとで独立と発展を果たしてきた、という歴史観が浮かび上がる。最終部では、1990年代以降に物質的に豊かになった生活、緑豊かな市街地などの説明によって明るい国家イメージを演出する。
以上に明らかなように、シンガポールが日本軍の侵攻および占領によって深刻な被害を受けたにもかかわらず反日感情が強くない背景には、当該時期の歴史に対する冷静な認識がある。そして現在のシンガポールでこうした歴史観が共有されている背景には、教育政策の設計段階で、どのような歴史教育を施すかという政治的選択がなされたはずである。すなわち建国後の、戦後の混乱を経て独立し国家建設をする過程において懸念すべきは日本ではないという情勢判断と、国民統合を図るうえで重視すべきは「歴史」ではなく経済発展であり国民生活の改善だという政策方針が寄与したと考えられる。
こうした現状からすれば、華人がマジョリティーである現在のシンガポールについて、「民族的に中国に接近しやすいに違いない」と見なすのは多分に短絡的である。確かにシンガポールは外交的に中国に接近しているように見える。しかし国内ではむしろ中国人と華人の境界線を濃く太くする方針が示されており、重慶プロジェクトにみる中国・シンガポール協力は戦略的かつ合理的判断に基づいたものである。ただしこうした諸々の選択を、中華社会に共通する現実主義の現れ、と評価してもあながち間違いではあるまい。
写真の出典
- 筆者撮影
参考文献
- シンガポール政府による2019年人口統計:Population, Annual, Department of Statistics, Singapore.
- シンガポール・中国政府の中国西部プロジェクトに関する報告(2015年):Press Release, Department of Trade and Industry, Singapore.
- シンガポール・重慶市の「南方回廊」に関する報告(2017年):Press Release, Department of Trade and Industry, Singapore.
- 情報通信メディア開発庁による国際データチャネルに関する報告(2019年): Launch of China-Singapore (Chongqing) International Data Channel.
- JETRO地域分析レポート「シンガポールから見た、重慶・ASEANを結ぶ陸海新輸送路(前編)」、「シンガポールから見た、重慶・ASEANを結ぶ陸海新輸送路(後編)」。
著者プロフィール
江藤名保子(えとうなおこ) アジア経済研究所在シンガポール海外研究員。博士(法学)。専門は中国政治外交、日中関係、東アジア国際政治。おもな著作に、『中国ナショナリズムのなかの日本――「愛国主義」の変容と歴史認識問題』勁草書房(2014年)、「中国の公定ナショナリズムにおける反『西洋』のダイナミズム」『アジア研究』第61巻第4号(2015年)、「日中関係の再考――競合を前提とした協調戦略の展開」『フィナンシャル・レビュー』138号(2019年)など。
注
- ここで中国という場合には、1949年に建国した中華人民共和国を指す。シンガポールは中華民国政府(現在の台湾)との関りも深く、中華アイデンティティとしては重複していた。例えば、東南アジアきっての有力な華僑であったタン・カーキー(陳嘉庚)はシンガポールに7つの華語学校を創設したが、シンガポール国立博物館にある当時の教科書には中華民国の国旗が示されている。タン・カーキーは厦門大学の創設者でもある。
- 経済的なメリットに関しては参考文献を参照されたい。
この著者の記事
- 2020.03.11 (水曜) [IDEスクエア] (海外研究員レポート)シンガポールの中台バランス外交
- 2019.11.27 (水曜) [IDEスクエア] (海外研究員レポート)シンガポールにおける華人アイデンティティと中国
- 2018.09.20 (木曜) [IDEスクエア] (世界を見る眼)(アジアに浸透する中国)特集にあたって――多元化する中国ファクター