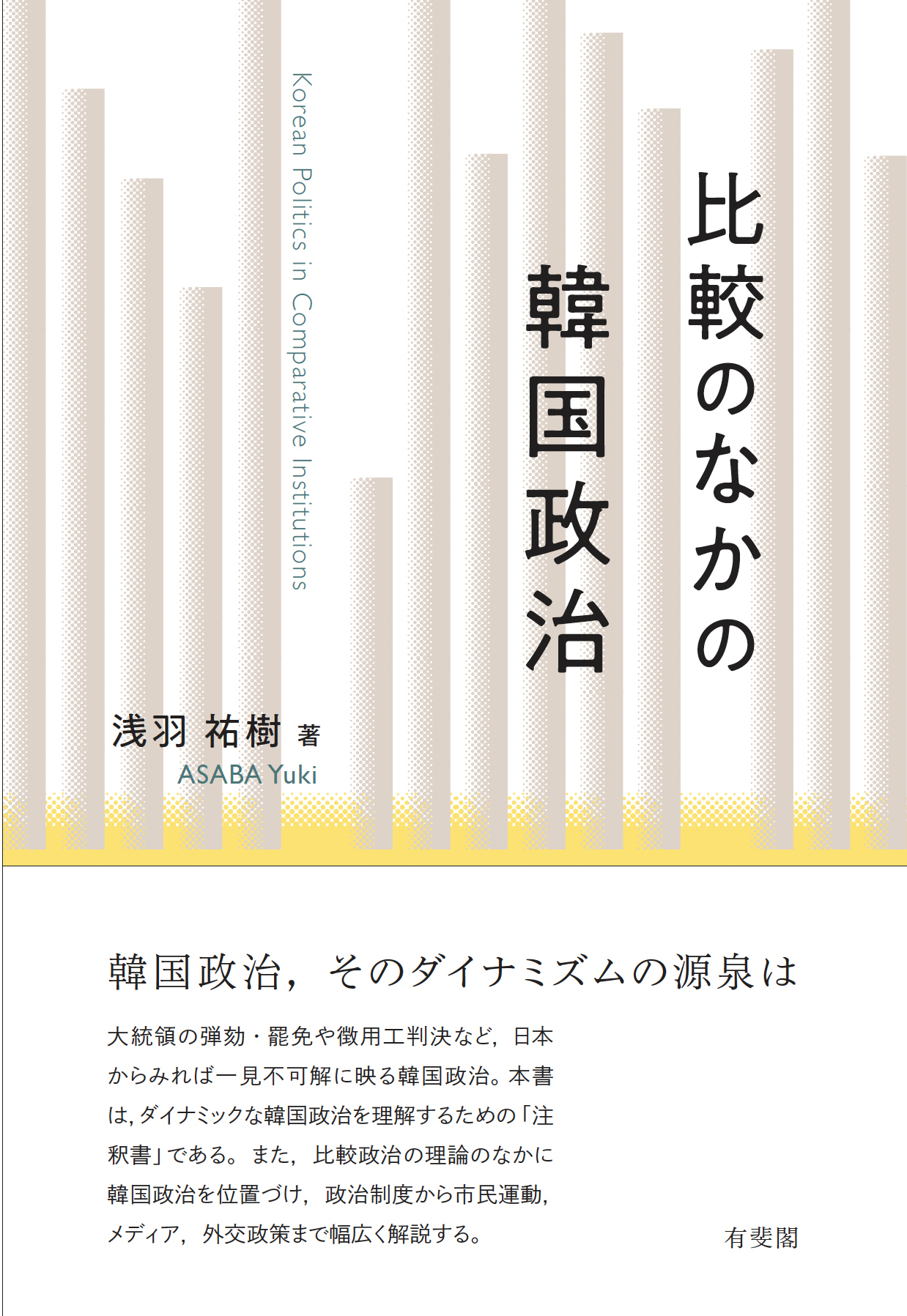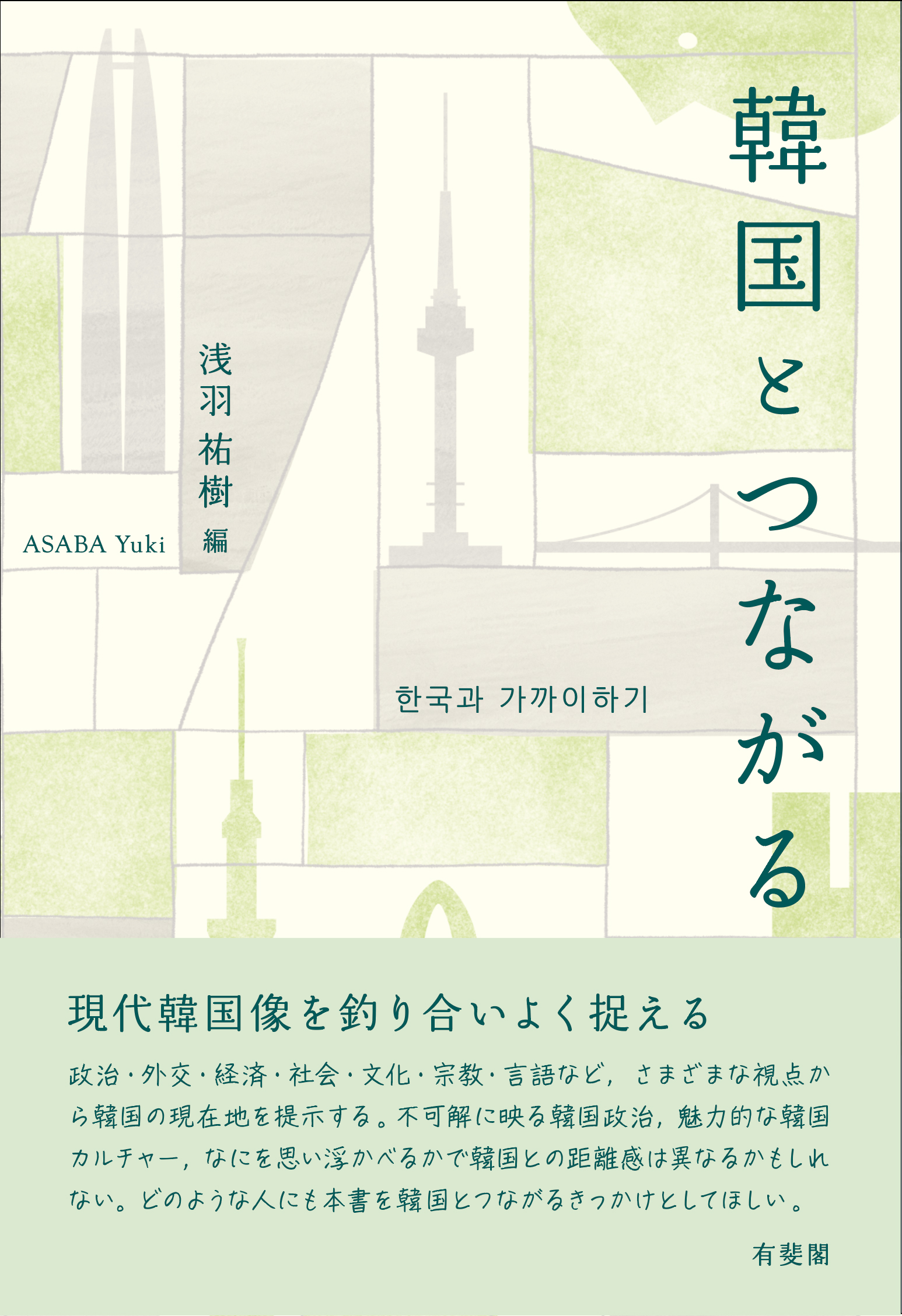IDEスクエア
「強い」李在明政権、「脆い」韓国民主主義
The Paradox of Power: A Robust Lee Jae Myung Presidency, A Vulnerable Korean Democracy
PDF版ダウンロードページ:https://hdl.handle.net/2344/0002001442
浅羽 祐樹
Yuki Asaba
2025年7月
(7,587字)
「民主韓国が戻ってきた」
李在明[イ・ジェミョン]氏が2025年6月4日に第21代韓国大統領に就任してから1カ月が経った。この間、韓国総合株価指数(KOSPI)は3000を突破し、「コリア・ディスカウント」から回復しつつあるようにみえる。李大統領はカナダで開催されたG7サミット(主要7カ国首脳会議)にもオブザーバー参加し、「民主韓国が戻ってきた(Democratic Korea is back)」ことを対外的に広く印象づけた。石破茂首相とも日韓首脳会談をおこない、「日韓両国は小さな意見の違いを乗り越えて、さまざまな面で互いに協力し助け合う関係として発展することを願う」と述べ、「政策の一貫性」や「国益重視の実用外交」への期待を日本側にもたせた(浅羽 2025b)。
李大統領は政権移行期間を経ることなく就任したため、当初、尹錫悦[ユン・ソンニョル]前大統領の長官(閣僚)たちとの同居を強いられた。しかし、与党「共に民主党」の金民錫[キム・ミンソク]議員が7月3日に国会の同意を経て国務総理(首相)に就任し、人事を加速化している。副総理兼企画財政部長官、外交部長官、法務部長官などが今後、国会の人事聴聞会を経て、順次、任命されるとようやく自前のスタッフが揃い、名実ともに李在明政権になる。一方、大統領室のほうはいち早く陣営を整え、「3室長(秘書室・政策室・国家安保室)、7首席(政務・広報疎通・傾聴統合・民情・経済成長・社会・AI未来企画)、1補佐官(財政企画)」体制となった。
職務遂行に対する国民からの評価は上々で、「よくやっている」という回答が65%に達し、「できていない」(23%)を大きく上回っている。大邱・慶北(56%対26%)や70代以上(56%対23%)といった、大統領選挙では李氏より「国民の力」の金文洙[キム・ムンス]候補を支持した層も、鳴りを潜めている(韓国ギャラップ 2025)。進歩層(90%対8%)や中道層(69%対18%)では肯定的な評価が圧倒しているし、保守層(41%対44%)でも賛否が拮抗している。それだけ、尹前大統領による非常戒厳の宣布(2024年12月3日)以来、6カ月間も続いた国政の混乱を収拾するリーダーシップへの期待が共有されているということである。
ただ、就任当初の高い評価はその後の成功を必ずしも意味しない。文在寅[ムン・ジェイン]大統領は同じ時期に歴代大統領のなかでもっとも高い評価(82%)を得たが、ソウル中央地検長や検事総長に抜擢した尹に政権を明け渡してしまった。前任者(朴槿恵[パク・クネ]大統領)の弾劾につながった「ろうそく集会」は左右を問わない緩やかな政治連合だったにもかかわらず、文大統領は進歩層だけの「ろうそく革命」として一方的に位置づけ、「積弊清算」の名のもと、検察を通じて保守派(朴や李明博[イ・ミョンバク]元大統領など)を断罪した。そのなかで、保守(右派)と進歩(左派)のあいだの分極化が進み、互いに敵対視するようになっていった。
はたして李在明大統領は就任演説で誓ったように、国民を大きく統合する頭領、「大統領」たりうるのか(李在明 2025)。

進歩に「傾いた運動場」
2025年6月3日に実施された第21代大統領選挙において、共に民主党の李在明は1987年の民主化以降、9回の大統領選挙のなかで最多得票数(1728万7513票)を記録し、得票率でも朴槿恵(51.6%)に次ぐ49.4%だった。投票率も79.8%であり、1997年以来の高さだった。
得票率で国民の力の金文洙(41.2%)との差は8.3ポイントである。金は尹錫悦政権で雇用労働部長官を務め、非常戒厳や弾劾・罷免に微温的な態度をとった。この間、「弾劾賛成」「政権交代」を求める世論が一貫して「弾劾反対」「政権継続」を20ポイント前後上回っていたなかで、圧勝とはいえない選挙結果である。
地域ごとの得票分布は「西高東低」であり、青(進歩)と赤(保守)が東西で真っ二つに割れているようにみえる。たしかに、李在明はソウル・仁川・京畿・大田・世宗・忠北・忠南・光州・全北・全南・済州など朝鮮半島西部の10カ所では最多得票した一方、釜山・大邱・蔚山・慶北・慶南・江原など東部の7カ所は金文洙が得票率1位だった。
しかし、広域自治体(17の市・道)ではなく、基礎自治体(226の市・郡・区)や総選挙の地域区(254)で集計し、李と金の得票率の様相を把握すると、別の姿が浮き彫りになる。地域区を基準にすると、「174対80」と差が開いている。特に、ソウル(40対8)・仁川(14対0)・京畿(57対3)の首都圏(111対11)は李の完勝といってよい(オーマイニュース 2025)。これは、共に民主党が国民の力に対して首都圏で圧勝した2020年総選挙(103対16)や24年総選挙(102対19)を凌駕する勢いである。
KBS・MBC・SBSのテレビ局3社が合同で実施した出口調査(KBS 2025)に基づいて、年齢・男女別に、李と金の得票率を検討する。李が大きく取りこぼしたのは70代以上(34.0%)と20代男性(24.0%)・30代男性(37.9%)だけである。60代は平均値と同じくらいの得票率(48.0%)であり、これは進歩的な86世代(1980年代に大学に通った1960年代生まれ)の一部が60代前半になったことが大きい。歳をとると保守化するという年齢効果よりも、民主化運動という青年期における共通経験による世代効果が生涯ずっと続いているということである。その下のX世代(40代・50代)は李の得票率が7割前後である。
特異なのは、MZ世代(20代・30代)だけ男女で政治志向や投票行動が異なることである。20代女性や30代女性は6割近くが李を支持する一方で、20代男性(36.9%+37.2%)や30代男性(34.5%+25.8%)は金文洙や改革新党の李俊錫[イ・ジュンソク](全有権者からの得票率は8.3%)を支持した。この層の李俊錫支持について単純に「右傾化」「アンチ・フェミニズム」としてだけで理解できないのは、20代女性(10.3%)や30代女性(9.3%)も李を平均値以上に支持していることからも明らかである。この背景には二大政党が3月に合意した年金改革による現役世代の負担増があるとみられ、反対の立場を鮮明にした李が批判の受け皿になった側面を見落としてはならない。
韓国では少子高齢化(2024年、出生率0.75、超高齢社会に突入)が類例なきスピードで進むなか、保守に追い風が吹くどころか、むしろ人口のボリュームゾーンを進歩が占めるようになってきている。2023年末現在、韓国国民の平均年齢は44.8歳、最頻値は52歳(1971年生まれ)である(行政安全部 2024)。
さらに、進歩は地域的にも、有権者や総選挙における地域区議席が集中している首都圏を確実に支持基盤に変えてきた。進歩に「傾いた運動場」は今後も続きそうである。
山積する政策課題
李在明大統領の与党である共に民主党は国会(定数300、欠員2)において167議席という圧倒的多数を占めている。ねじれが解消された国会、つまり統合政府(unified government)の場合、大統領はリーダーシップを発揮しやすい。
さらに、祖国革新党(12議席、以下同)、進歩党(4)、基本所得党(1)、社会民主党(1)、無所属(3)は事実上の与党連合であるため、野党は国民の力(107)と改革新党(3)だけである。
法律、人事、予算は「在籍議員過半数の出席と出席議員過半数の賛成」(憲法第49条)、つまり与党単独で議決できる。「在籍議員3分の2以上の賛成」(同第130条第1項)が必要な憲法改正すら、野党から10票の造反があれば、国民投票に付すことができる状況である。過去3年間、国会の過半数議席を有していても、尹錫悦前大統領の拒否権によって葬られてきた改革立法をようやく進めることができるようになったわけである。
李大統領は現在、共に民主党の党員のひとりにすぎないが、大統領選挙に立候補する直前まで代表を2期にわたって務め、与党を完全に掌握している。代表だけでなく、院内代表(院内総務)の選出にも党員(150万人!)の意向が反映されるようになり、共に民主党は国会議員が中心になる院内政党から、党員が主導する大衆政党へと完全に変貌を遂げた。党員と執行部はファンと推しの関係に近く、李は党員拡大のなかでスターダムを駆け上がった(浅羽 2024, 第8章)。
さらに、李大統領は、国務総理だけでなく、19の部(省)のうち8つ、統一部・法務部・国防部・行政安全部・文化体育観光部・環境部・女性家族部・海洋水産部の長官にも、与党の現職議員を起用した。韓国の「議院内閣制の要素が加味された」大統領制(憲法第43条、国会法第29条第1項)では、国会議員が国務総理や長官を兼職することができるが、与党議員の入閣は「政府・与党」の党派的な一体化を強める一方で、「国会対政府」という憲法機関同士の関係や牽制・均衡の機制を弱めるという懸念がある。
近年、どの国においても政策決定過程が首相官邸やホワイトハウスなどの執政中枢(core executive)に集中しているが、李大統領の場合、当選後直ちに就任し、いまなお自前の長官がひとりもいないなか、なおさら大統領室が司令塔にならざるをえない。特に、外交・安保の政策領域においては、国家安保室長の魏聖洛[ウィ・ソンラク]がG7サミットへの同行はもちろんのこと、オランダで開催されたNATO(北大西洋条約機構)首脳会議にも李大統領の代わりに出席し、ルッテ事務総長と面談するなど、フル稼働している。なにより、トランプ大統領が一方的に定めた相互関税の猶予期限が迫るなかで、魏室長を訪米させ、米韓首脳会談の開催、包括的な妥結につなげようとしている。
外交だけでなく、内政の課題も山積している。
輸出不振、物価上昇、不動産価格の高騰、消費低迷、自営業主の廃業の急増、成長鈍化など経済問題への対応を求める声が、どの世論調査の結果をみても、圧倒的に大きい。李大統領も、就任当日に非常経済点検タスクフォースを立ち上げ、31兆7914億ウォンの大型補正予算を2025年7月4日に成立させるなど、自ら陣頭指揮に当たっている。
同時に、大統領として最初に裁可した法律は、尹前大統領とその夫人に関連する疑惑を解明するために特別検察官を設置するものである。尹前大統領はすでに「内乱」(刑法第87条)を首謀したとして刑事裁判が進んでいるが、これまでの捜査では真相解明にほど遠いため、検察とは別の組織に再捜査させ、「外患の罪」(刑法第2編「各則」第2章)などでも新たに責任を追及するのが目的である。2024年10月に平壌でみつかったドローンは韓国軍が飛ばしたもので、局地戦を誘発し、戒厳の名分にしようとしたという疑惑がある。
要するに、軍を動員して憲政秩序を破壊しようとした内乱を完全に「克服」してこそ、国民統合が図られるというのである。
「国のかたち」を変える司法改革・検察改革
李在明大統領は就任前に5件の裁判で在宅起訴されている。そのうち公職選挙法違反の件は、大法院(最高裁)が2025年5月1日に2審の無罪判決を破棄し、ソウル高裁に差し戻した。「100万ウォン以上の罰金」より重い刑(1審判決は懲役1年、執行猶予2年)が確定することは必至で、そうなれば大統領候補の資格が取り消され、共に民主党は代わりの候補も立てられなくなるところだった。ソウル高裁が公判期日を同月15日に指定すると、李氏は「大統領の直接選出という民主化の成果、参政権という国民主権の根幹に反する司法クーデタである」と規定し、猛反発した。すると、ソウル高裁は初公判を大統領選挙後の6月18日に延期したが、尹錫悦大統領を罷免することで憲政秩序を護った憲法裁判所とは対照的に、大法院改革は一気に政治的な争点になった。
「大統領は内乱または外患の罪を犯した場合を除いては在職中刑事上の訴追を受けない」(憲法第84条)という規定ゆえに、尹大統領は罷免される前に内乱首謀の容疑で逮捕・勾留・起訴された。この「刑事上の訴追」に、すでに始まっている裁判の進行も含まれるのかは法解釈上の争いがあるが、李氏の大統領就任後、ソウル高裁は裁判を無期限延期した。他の件も相次いで無期限延期となったため、李大統領は少なくとも在任中、出廷しなくてもよくなった。
司法制度は議会制度や選挙制度と並ぶ国制の根幹である。韓国では、大法院と憲法裁判所という「2つの司法」(浅羽 2024, 第6章)を互いに牽制・均衡させることで人権を保障しようとしている。1987年に現行憲法へと改正した際に、「我ら大韓国民」(憲法前文)たる主権者は、紛争の法的解決や憲法判断をおこなう権限をそれぞれ別々の機関に委ねたのである。両者とも国民が直接選出していないが、それはあえて多数決原理や「民心(民意)」から独立させるためであるといえる。
その司法制度を変えようとする動きが与党内で盛んである。
第1に、大法官(最高裁判事)の増員、韓国版コート・パッキング(court-packing)である。現行の「14名」(裁判所組織法第4条第2項)から30名へと大幅に増やし、毎年4名ずつ4年間にわたって李大統領が任命するというものである。かつて米国のフランクリン・ルーズベルト大統領は大恐慌後のニューディール政策が連邦最高裁判所の違憲判断によって阻まれると、判事の数を9名から15名に一気に増やし、リベラル派の判事を送り込んで対抗しようとした。そうすると、連邦最高裁判所が翻意し、合憲判断に転じたため、結局、増員はされなかった(大林 2023)。
第2に、「裁判所の判決」(憲法裁判所法第68条第1項)も憲法裁判の対象にすることである。韓国では、裁判所が憲法裁判所に対して法律の違憲審査を求めるだけでなく、「公権力の行使または不行使によって憲法上保障された基本権を侵害された者」(同上)も救済を求める憲法訴願をおこなうことができる。これまで「裁判所に属する」司法権(憲法第101条第1項)、その最たる行使例である判決は憲法訴願の請求対象から除外されていた。それも含まれるようになると、2つの司法が相並ぶ体制から憲法裁判所を頂点とする4審制へと事実上移行することになる。
第3に、「刑事上の訴追」(憲法第84条)に裁判の進行も含まれると刑事訴訟法に明記し、公職選挙法を改正し、虚偽事実公表罪(第250条)の構成要件から「行為」の文言を削除することで、李大統領の「司法リスク」を完全に取り除くことである。
いずれも裁判所組織法、憲法裁判所法、刑事訴訟法、公職選挙法という法律の改正で実現できるし、与党単独で国会で議決できる。
さらに、検察改革も断行しようとしている。
法務部の外局である検察庁を廃止し、公訴庁へと再編して、起訴と公判維持だけを担当させる一方で、捜査は新設する重罪犯罪捜査庁や警察に専管させるというものである。同時に、尹前大統領を逮捕した高位公職者犯罪捜査庁の権限を強めるという。捜査権と起訴権を完全に分離することで、政府・与党には甘い一方で、野党を狙い撃ちにする「権力の犬」から、無差別性、衡平性、適法手続きを重視する「法の番人」へと改めるというのである。これも、法律の制定や改正だけで可能である。
憲法事項ではないにせよ、「国のかたち」を変えることになる司法改革や検察改革を十分な熟議の過程を経ることなく推し進めるのは、はたして憲法の趣旨に合致しているのか。

「自由民主的基本秩序」とは何か
「政治の問題」は、戒厳軍や司法など他の手段を通じて解決しようとしてはならない。そのためには、「寛容と自制」「対話と妥協」の姿勢が各自求められている。これは、憲法裁判所(2025)が尹錫悦大統領を罷免した際の説諭であるが、政権交代後の現在、李在明大統領と国会多数派の共に民主党にも当然、当てはまる。「民主共和国」(憲法1条1項)の本旨は、権力行使の恣意性の排除にあるというのである(浅羽 2025a)。
尹政権における31件(うち可決されたのは13件)に上る国会の弾劾訴追は戒厳の正当な事由にはなりえないが、憲法裁判所で罷免されたのは尹前大統領ただひとりであり、他はすべて棄却された。違法ではなくても、明らかに過剰な権限行使であり、「憲法的ハードボール」(Tushnet 2004)に当たる。法令上、過半数の賛成でおこなうことができるとしても、連発したり、単独で行使したりすると、ゲーム自体を脅かすことになりかねない。
共に民主党は2020年総選挙に際しても、自由韓国党(国民の力の前身)が反対するなかで、公職選挙法の改正を断行したことがある。憲法事項ではないにせよ、選挙制度は「国のかたち」の一部である。別のゲームを勝手に始めるプレーヤーは退場させるしかないが、主要なプレーヤーを抜きにルールの変更を繰り返すと、政治が成り立たなくなる。
韓国は民主化や新興民主主義の安定の典型例だったが、戒厳後、軒並み評価を下げた。V-Dem(2025)の指標では「自由民主主義」から「選挙民主主義」へ、EIU(2025)の指標でも「完全な民主主義」から「欠陥のある民主主義」へと後退した。戒厳が直ちに解除されていなければ、「専制体制」に転落していたかもしれない。その意味では、「K-Democracyの底力(レジリエンス)」が発揮されたといえる。
李大統領が回復しようとする憲政秩序も、尹前大統領がいまだ強調しているのも、少なくとも名目上は同じ「自由民主的基本秩序」(憲法前文)である。問題は、自由主義やリベラリズムの理解や内実化、民主主義との相剋や調和である。多数派/勝者とはいえ、絶対に侵してはいけない少数派や個人の領域を認め、それを制度的に保障することが核心である。
李大統領は「国民主権政権」を名乗っているが、司法改革や検察改革において争点になっている権力分立、法の支配、非選出機関への司法権の委任、選出機関(大統領や国会)やその時々の「民心(民意)」からの司法の独立は、「我ら大韓国民」(憲法前文)という主権者による憲法的決断である。尹の弾劾審判において憲法裁判所が当時の世論分布に従っていれば、5対3で棄却されていただろう。
主権者自ら「自制」しているということを、「大統領は国民の代理人にすぎない」と繰り返す李氏がどのように「自省」するかに、韓国民主主義のゆくえがかかっている。
写真の出典
- 写真1 Korea.net / Korean Culture and Information Service(CC BY-SA 2.0)
- 写真2 Seoul Institution(CC BY 4.0)
参考文献
〔日本語文献〕
- 浅羽祐樹(2024)『比較のなかの韓国政治』有斐閣。
- 浅羽祐樹(2025a)「韓国憲法裁判所と法の支配──尹錫悦大統領の弾劾審判」IDEスクエア、5月。
- 浅羽祐樹(2025b)「韓国・李在明大統領の『実用外交』と国交60年の日韓関係──変数は台湾めぐる立場の相違か」nippon.com、6月19日。
- 大林啓吾(2023)「裁判官の数をめぐる司法と政治──アメリカのプラクティス」慶應義塾大学法学研究会『法学研究』96巻2号、63-95ページ。
〔英語文献〕
- EUI (2025) “Democracy Index 2024.”
- Tushnet, Mark V. (2004) “Constitutional Hardball,” 37, J. Marshall L. Rev., pp. 523-553.
- V-Dem (2025) “Democracy Report 2025: 25 Years of Autocratization: Democracy Trumped?”
〔韓国語文献〕
- KBS (2025) “2025 대통령선거 출구조사 [2025年大統領選挙出口調査]” KBSウェブサイト、6月4日.
- 이재명[李在明] (2025) “대한민국 제21대 대통령 취임사 [大韓民国第21代 大統領 就任演説]” 대통령실[大統領室]ウェブサイト、6月4日.
- 오마이뉴스[オーマイニュース] (2025) “21대 대선 득표율, 총선 지역구 적용하면 어떻게 변할까[2025年大統領選挙の得票率を総選挙の地域区に当てはめるとどのようになるか]”6月9日.
- 한국갤럽[韓国ギャラップ] (2025) “한국갤럽 데일리 오피니언 제627호 2025년 7월 1주[韓国ギャラップ デイリーオピニオン 第627号(2025年7月第1週)]”7月4日.
- 헌법재판소[憲法裁判所] (2025)“2025. 4. 4. 2024헌나8 대통령(윤석열) 탄핵 [2025. 4. 4. 2024憲ナ8 大統領(尹錫悦)弾劾]” 헌법재판소[憲法裁判所]ウェブサイト.
- 행정안전부[行政安全部] (2024) “‘2024 행정안전통계연보’ 발간 [「2024行政安全 統計年報」刊行]” 행정안전부[行政安全部]ウェブサイト、8月27日.
著者プロフィール
浅羽祐樹(あさばゆうき) 同志社大学グローバル地域文化学部教授。Ph.D (Political Science).専門は比較政治学、韓国政治、司法政治論。著書に『比較のなかの韓国政治』(有斐閣、2024年)、『韓国とつながる』(有斐閣、2024年、編著)、『はじめて向きあう韓国』(法律文化社、2024年、編著)、『韓国語セカイを生きる 韓国語セカイで生きる』(朝日出版社、2024年、編著)など。