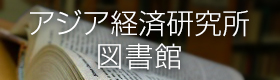時事解説: 南アフリカのゼノフォビアに対する反発——モザンビークにおける南アフリカ人国外退去要求——
アフリカレポート
No.53
PDF(419KB)
■ 時事解説: 南アフリカのゼノフォビアに対する反発——モザンビークにおける南アフリカ人国外退去要求——
■ 網中 昭世
■ 『アフリカレポート』2015年 No.53、pp.39-43
(画像をクリックするとPDFをダウンロードします)
2015年3月末に南アフリカのクワズールー・ナタール州のダーバンで外国籍と思われるアフリカ人を標的にした暴力的な排斥が発生し、やがて暴力はハウテン州ヨハネスブルグに飛び火した。4月20日時点で7人の死者を出し、暴力やこれに乗じた略奪行為を行った者だけでなく、同時期に摘発された入管法違反者も含めて310人が逮捕された。4月いっぱい続いたゼノフォビア(移民排斥)の末に、住居を追われて南アフリカ政府が設置した一時滞在キャンプや、国外等へ避難した人の数は、27日時点で8000人以上と見られ、その内訳は、推計モザンビーク人2000人、ジンバブウェ人700人であった[IOM 2015]。
南アフリカにおけるゼノフォビアはこれ以前にも頻発しており、過去最大のゼノフォビアは2008年に60人以上の死者と国内避難民推定2万人を出し、推定3万人が出身国へ帰国した。それに対して避難民の規模こそ小さいものの、今回のゼノフォビアに、標的とされた人々の出身国で抗議運動が起きた。なかでも、モザンビークでは外資系企業で働くモザンビーク人労働者たちが、同じ職場で働く南アフリカ人の国外退去を要求するという新たな現象が起きた。従来ならば、南アフリカのゼノフォビアに対するモザンビーク国内の反応は、避難民の保護と首都での市民による抗議デモ、そして予定調和的な外交対話に終始してきた。本稿では、モザンビーク社会変容の現れである新たな行為主体が立ち現れた背景を解説し、今後の展望を示す。
1. 解放闘争世代の対話と南アフリカ政府の姿勢
南アフリカでゼノフォビアが発生するたびに、南アフリカ国内外で元反アパルトヘイト運動家たちが解放闘争時代の連帯に言及しつつ、ゼノフォビアを諌めてきた。そして今回は、ゼノフォビアが4月16日にヨハネスブルグにまで拡大し、その翌17日に、国際的にも認知度の高いモザンビーク人作家ミア・コウト(Mia Couto)が、南アフリカ政府の具体的な対応を求めてジェイコブ・ズマ(Jacob Zuma)大統領に宛てた公開書簡を発信し、ズマ大統領もこれに応えたことには新奇性があった。こうした公開のやり取りが成立した背景には、コウトとズマの個人的な経験の共有がある。
コウトは、ズマが1980年代に政治亡命者としてモザンビークの首都マプトで同国政府系報道機関に雇用され、生計を立てていた時代の同僚であった。コウトは当時ズマがボディ・ガードを付けていなかったことに触れ、「(理想とする社会の実現のためには)国境は存在しないと考えていたから」こそ「我々モザンビーク人があなたのために盾になっていた」と解放闘争時代の両国民の関係を懐古したうえで、モザンビーク出身者に対する暴力的な排斥を直ちに終結させるよう具体的な行動をおこすことを要求した[Couto 2015]。
また、コウトの公開書簡と前後して、モザンビーク国内ではモザンビーク人労働者がストライキを組織し、南アフリカ人従業員の国外退去を要求していた。こうした状況に追い打ちをかけるかのように、ヨハネスブルグのアレクサンドラ地区でモザンビーク出身の露店商が4月18日に襲撃された瞬間を捉えた写真が翌19日に南アフリカの『サンデー・タイムズ』紙の一面に掲載され、南アフリカ国内外で批判が高まった[Times Live 2015]。悪化する事態に応じるため、ズマ大統領はバンドン会議60周年を記念して22日からインドネシアで開催されるアジア・アフリカ会議への参加を取りやめざるを得なかった。
24日付のズマ大統領からコウト宛の返書の内容は、犠牲者に対して哀悼の意を捧げ、両国の歴史認識を改めて共有している点で、従来型の外交対話の域を出てはいなかった[South African Government 2015a]。しかし、ズマ大統領は「南アフリカへ合法的に移民する我々のアフリカ人兄弟姉妹を受け入れている」と移民の合法性に言及することも忘れなかった。両者の公開書簡のやり取りはこの2通で終わったが、ズマ大統領は27日の南アフリカの祝日「自由の日」に行った演説でも、今回のゼノフォビアに触れ、モザンビーク人被害者が「非合法移民」であり、検挙を免れるために偽名を使用していたと強調した[South African Government 2015b]。
2. モザンビーク人労働者による抗議行動
モザンビーク人労働者による抗議は、解放闘争世代の対話と比べ議論の水準も当事者の社会的出自も異なるところから発生した。モザンビーク国内各地の労働者が同じ職場の南アフリカ人従業員の国外退去を求めた事例は3件確認された。
1件目の事例は4月16日、モザンビーク南部のイニャンバネ州パンデ・テマネ天然ガス田で操業する南アフリカの資源系企業サソール(Sasol)で発生した。同社のプラントへ向かう道路にモザンビーク人労働者がバリケードを築いてストライキを行い、同社で働く南アフリカ人の国外退去を要求した。ストライキは翌17日も続き、最終的にサソールは飛行機をチャーターし、退避を迫られた従業員とその家族およそ340人を帰国させた。南アフリカへと続くパイプラインに天然ガスを送る中核的な操業は支障なく続けられたものの、ガスの圧縮作業は停止した[Sapo Notícias 2015]。
2件目の事例は17日、モザンビーク南部の南アフリカとの国境地点レサノ・ガルシアの税関付近で発生した。南アフリカの建設会社WBHO(Wilson Bayly Holmes – Ovcon Limited)、天然ガスをもとにした電力発電所を操業するフィンランド企業ヴァルツィラ(Wärtsilä)社および南アフリカ企業ギガワット(Gigawatt)社のモザンビーク人従業員らが、職場から南アフリカ人従業員を退去させた後、国境付近で南アフリカのナンバー・プレートを付けた車両がモザンビークに入国するのを阻止しようと幹線道路を封鎖した。さらには騒動に便乗する群衆が、南アフリカのナンバー・プレートを付けた車両に対して投石をしたため、モザンビーク警察が通行車両を護衛し、道路封鎖は数時間後に解除された[AIM 2015a]。
3件目の事例は、ブラジル企業ヴァーレ(Vale)が開発を行う北部テテ州モアティーゼ炭鉱周辺で発生した。モザンビーク人労働者側の動きに関する詳細な報道はないものの、アイルランド企業ケンメアー(Kenmare)は28日に1391人の従業員のうち、南アフリカ人従業員62人を一時帰国させたと発表した[AIM 2015b]。また、南アフリカ企業ケンツ(Kentz)の対応の詳細は不明だが、両社合わせて、テテ国際空港からは400人以上の南アフリカ人がヨハネスブルグへ向けて出国したと報じられた[AIM 2015c]。
これらの事例では、南アフリカ人に負傷者などの被害は報告されていないが、いずれの企業もこれまでの度重なるゼノフォビアに対して、初めてモザンビーク人の労働者層が示した反応に慎重な対応を迫られた。
3. 経済成長と格差の中で生まれた新たな行為主体
1件目の事例と2件目の事例が、ほぼ同日に発生したことの連続性は明らかではないが、双方の労働現場は天然ガス田と変電所という関係にあり、物質的にパイプラインで繋がれている。さらに天然ガスは、南アフリカへの重要な電力供給源となっている。ソーシャルメディア上には、「ズマ大統領が謝罪しに来るまで、—南アフリカのエネルギー需要を賄う上で欠かせない—モザンビークからの電力と天然ガスの供給を停止するべきだ。」と、モザンビーク青年層からなる市民団体関係者による投稿が見られたという[BBC News 2015]。
抗議の主体となった人々が、石炭・天然ガスといったモザンビークの新興産業である採取・エネルギー産業に雇用の機会を得た労働者たちであったことは注目すべき点だ。近年のモザンビークは、7%台という高い経済成長率ゆえに脚光を浴び、採取・エネルギー産業を筆頭に多額の海外直接投資が行われ、2014年には88億ドルの海外直接投資に対して1万856件の新規雇用が創出された。しかし、そのうちマプトでの雇用は1612件のみであり、その他はマプト以外の地方で開発が本格化した採取・エネルギー部門の新興産業における雇用であった[Vines et al. 2015]。
これらの産業の労働現場でストライキを行った20代~30代の労働者は、1975年のモザンビーク独立後~90年代の紛争中に生まれた世代であり、モザンビークの人口の45%以上を占める15歳以上の労働人口のなかでも0.6%に過ぎない採取・エネルギー産業労働者の一部である。特にエネルギー産業に職を得ることができた人々は、中等以上の教育歴がある者の中でもわずか0.2%である[Instituto Nacional de Estatística 2015]。これは、ブルーワーカーの中のエリートと言えるだろう。
数少ないエリート労働者は都市部出身と推察され、その出自はソーシャルメディアに抗議の投稿を行った青年層と重複する一方で、彼らと一線を画するものがある。それは、ストライキ参加者の経験である。都市部の青年層は、既存の産業や公務員として都市部に職と生活の場を得ているが、ストライキを行った人々は、近年の海外直接投資によって農村部に忽然と現れた近代的なプラントを労働現場とする。彼らはそこで、これまでの都市生活では実感することのなかった自分の国の内部の格差を日々目の当たりにしながら、今回のゼノフォビアを引き起こした南アフリカ出身の従業員と同じ空間にいる。こうした経験が、彼らの職に対するリスクを負ってまでも抗議を行った動機となっていたと思われる。
おわりに
モザンビーク社会に関して明らかとなったのは、両国間を繋ぐ解放闘争世代の過去の理念はもはや今日の青年層には響かないという点だ。この世代のうち、今回の抗議ストライキを起こした主体は、親の世代が経験した独立直後の期待に満ちた時代を体感することもなく、紛争下で生まれ育った。そのため、モザンビークにおける南アフリカ企業の進出やエネルギー資源の需給といった両国間の関係や、なにより解放闘争世代が作ってきた紛争後のモザンビーク社会の拡大する格差をよりシビアに見据えている。今回の抗議行動は、彼らが解放闘争世代とは異なる視点で南アフリカとの関係を相対化し、さらには、モザンビーク社会における自らの位置づけを自問した末の選択であったと思われる。
《参考文献》
-
AIM(Agência de Informaҫão de Moҫambique)2015a. “Mozambique: Reaction against South Africa Attacks Spreads to Border.”
( http://allafrica.com/stories/201504180070.html , 2015年7月2日アクセス). -
AIM 2015b. “Mozambique: Kenmare Resources Repatriates South African Workers.”
( http://allafrica.com/stories/201504210032.html , 2015年7月2日アクセス). -
AIM 2015c. “Mozambican workers expel South Africans.”
( http://allafrica.com/stories/201504180057.html , 2015年7月2日アクセス). -
BBC News 2015.“South Africa xenophobia: Africa Reacts.”
( http://www.bbc.com/news/world-africa-32354993 , 2015年7月2日アクセス). -
Couto, Mia 2015. “Carta aberta de Mia Couto ao Presidente da África do Sul sobre o Genocídio de Moçambicanos naquele país.”
( http://www.miacouto.com.br/carta-aberta-de-mia-couto-ao-presidente-da-africa-do-sul/ , 2015年7月2日アクセス). - Instituto Nacional de Estatística 2015. Inquérito aos Orçamentos Familiares: IOF – 1º Trimestre. Boletim Trimestral . Maputo: Instituto Nacional de Estatística.
-
IOM(International Organization for Migration) “IOM Assists Victims of Migrant Attacks in South Africa.”
( https://www.iom.int/news/iom-assists-victims-migrant-attacks-south-africa , 2015年7月2日アクセス). -
Sapo Notícias 2015. “Sul-Africana Sasol repatria trabalhadores dos projectos em Moçambique por precaução.”
( http://noticias.sapo.ao/info/artigo/1437997.html , 2015年7月2日アクセス). -
South African Government 2015a. “President Jacob Zuma: Open letter to Mia Couto, Mozambican Writer and Poet.”
( http://www.gov.za/speeches/president-jacob-zuma-open-letter-mia-couto-mozambican-writer-and-poet-24-apr-2015-0000 , 2015年7月2日アクセス). -
South African Government 2015b. “President Jacob Zuma: Freedom Day Celebrations.”
( http://www.gov.za/speeches/president-jacob-zuma-freedom-day-celebrations-27-apr-2015-0000 , 2015年7月2日アクセス). -
Times Live 2015. “The brutal death of Emmanuel Sithole.”
( http://www.timeslive.co.za/local/2015/04/19/the-brutal-death-of-emmanuel-sithole1 , 2015年7月22日アクセス). - Vines, Alex, Henry Thompson, Soren Kirk Jensen, and Elisabete Azevedo-Harman 2015. Mozambique to 2018: Managers, Mediators and Magnates. Chatham House Report , London: Chatham House.
(あみなか・あきよ/アジア経済研究所)