温故知新 -アジア経済研究所の30年の歩み-
『アジ研と途上国研究』 -アジ研50周年記念特別企画-
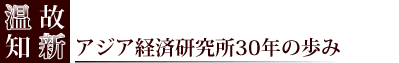
|
第一部
第二部
第三部 |
 『途上国の勉強』-小倉武一元アジ研会長 『途上国の勉強』-小倉武一元アジ研会長...アジ研での楽しみは調査研究部(現在の地域研究センターの前身)の毎週の研究(発表)会の傍聴であった。<中略>この研究会は、当局側の指図などに基づくものではなく、地域研究部の自主的な発起と運営によるものと理解している。アジ研会長を辞任してもう15年になるが、昔懐かしいというよりも、この自主的研究会に魅せられて、都合がつく限り、出席したく思っている。...  『座談会 アジ研の調査研究30年』から(抜粋) -川野重任東京大学名誉教授(元アジ研副所長)談- ...創立の頃の出版活動について言うと、早くから『アジア経済』やThe Developing Economiesという雑誌を矢継ぎ早に出したりしまして、職員にかなりのムリをお願いしたわけですが、今日、汗牛充棟ただならずといったようなたいへんな報告書が出てますね。恐らく世界中にこれほど多数の研究者を備え、またこれほど多数の図書資料、さらに図書資料についてのインフォメーション、地図、統計を抱えたところはない。アジ研は大変な宝庫ではないかという感じで、うれしく思っております。 ...やや口幅ったいことになりますけれども、論文というものは、わかったところだけ書くんですね。わからないことについて、こういうことはわからなかったということを自信を持って言うというところまでいけば、それを受けて、その次の人がリレーのバトンタッチみたいに、うまく走り出せるんですね。ところが前の人はどこを走ったのかよく分からないという場合には、重複してまた同じコースを走るということになってしまう。それでは積み重ねがないので、私はもったいないと思う。国際共同研究の場でも、そのような面でアジ研のポジティブな姿勢がいっそう出てくれば、成果がまた違ってくるのではないかな。 ...研究機関というのは何か万能選手であって、その研究成果からは万能の処方箋が出てきて、それを実施機関がただちに使える、というようなものでは本来ないと思うんですね。処方箋が書かれるためにはやはり診断があり、診断によってまず病状が明らかにされなければいけない。 -篠原三代平一橋大学名誉教授談(元アジ研会長)- ...30歳を超えたアジ研としては、もう一人前になったと国際的評価を受けるわけだから、単なる特定国のスペシャリストではなくて、一国を超えた視野で特定国の経済のパフォーマンスとか、あるいは政策運営自身に対しても柔軟構造でどんどんいろいろな判断を加えたり、コメントできるような、そういう研究者に成長していくことが大事ではないか。 
|
(「座談会‐アジ研の調査研究30年」(「アジア経済研究所30年の歩み」)より抜粋)



