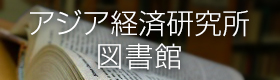東南アジア政治の比較研究
調査研究報告書
川村 晃一 編
2018年3月発行
表紙 / まえがき / 目次(278KB)
第1章
ナショナリズムを生み出す構造、制度、亡霊(313KB)/ 高木 佑輔
ナショナリズムは戦争や革命の記憶と結びつく。しかしながら、そうした激情がどこから来るのかを考えるのは簡単ではない。本稿では、ナショナリズム研究の古典『想像の共同体――ナショナリズムの起源と流行――』の枠組みを手掛かりにしつつ、フィリピン・ナショナリズムの起源とその展開について考えていく。『想像の共同体』において、ナショナリズムの起源は、出版語と植民地国家形成に見いだされる。19世紀、スペインの国力が落ちる中でフィリピン諸島は大英帝国中心の海洋秩序の中に組み込まれていった。その過程で、語学に対する需要が高まり、出版語としてのスペイン語を巧みに操る知識人が生まれ、そうした知識を享受する中間層も形成された。こうした知識人は、宗主国スペインと植民地フィリピンとの落差を否応もなく感じ、独立運動をけん引するようになった。このことを希代のナショナリスト、ホセ・リサールは比較の亡霊と名付けた。他方、植民地国家に出仕するフィリピン人が増加するのは米国植民地期であった。植民地国家で教育を受け、植民地国家の官僚となった人々は、このままでよいのかと自問するようになった。まるで亡霊のように取りついた疑問を抱えながら生きたナショナリストの肖像を描き出しながら、フィリピン・ナショナリズムの起源と展開について考察する。
第2章
第3章
現代東南アジアの首都圏における宗教と政治――ジャカルタの事例から――(308KB)/ 見市 建
第4章
東南アジアにおけるジェンダー問題の発生と展開(350KB)/ 田村 慶子
本稿は、ジェンダーという視点で、伝統社会から独立、国民国家建設を経て、民主化という過程にある東南アジアを、タイ、ベトナム、インドネシア、シンガポール、フィリピンを主な事例として考察するものである。
独立以前の東南アジアの伝統社会では、東アジアや南アジアに比べて、女性の経済的地位は高かったといわれている。これは、多くの東南アジアの家族が凝縮力の弱い双系的親族の結合であったことや、当時の人口が少なかったため、土地よりも労働力が重視されたことが要因で、「女性も外で働いていて当然」という社会通念が形成されたのである。ただ、このような相対的な経済的地位の高さは、政治的・社会的地位には決して反映しなかった。女子教育は、植民地期以前の伝統社会では無視されたためである。また、幼児婚や重婚、男性からの一方的な離婚が女性を苦しめていた。
欧米の植民地宗主国やキリスト教会は女子教育にも力を注ぎ、都市部エリート階級の女性の一部は一定の教育を受けて専門職にも従事するようになったものの、女性の地位が向上したとは決していえなかった。女性に貞節と父や夫への従属を奨励し、女子教育はそのような道徳規範の伝達にも力を入れるという、当時のヨーロッパの王朝やキリスト教会の男女の理想像や性的規範も東南アジアに持ち込まれたからである。さらに、20世紀になって東南アジア各地では民族意識が高揚したが、自治や独立の獲得がまず優先され、幼児婚や重婚、女子教育の遅れという問題は、社会全体の問題ではなく「女性の問題」として後回しにされた。東南アジアで唯一独立を維持したタイでも、19世紀末から西欧の教育や思想、システムを取り込んだため、男性優位の家父長制が衣を変え強化された。
独立後の多くの東南アジア諸国は、先進国からの資本・技術の導入と国内の安価な労働力の動員を集中的に行って工業化政策を進めた。若い女性は繊維、履物、衣服製造など労働集約型産業の単純・未熟練労働者として動員されて経済発展を支えた。親は女子よりも男子に教育をつけたがったため、初等教育のみで労働市場に出たのが女性であったためである。また「従順で使いやすい」というジェンダー的なステレオタイプゆえに、男性との賃金や昇進での差別は深刻だった。
一方で多くの政府は社会の基本的単位に家族を位置づけ、女性は労働者として経済発展に貢献すると同時に、家庭内の再生産労働(家事、育児、介護)も行うことを求めた。経済発展に邁進したい政府は社会福祉予算を最小限にしたいため、そのいわば「ツケ」を女性に負担させようとしたのである。そこにもステレオタイプ化されたジェンダー役割をみることができる。
このような状況が変化し、各国の国家政策にジェンダーの主流化という視点が入るようになったのは、1979年に国連女性差別撤廃条約(CEDAW)が採択されたこと、さらに国によって状況は異なるものの、女性NGOの活動を含む民主化運動の推進であった。しかし、性差別的なジェンダー概念は容易に変化させられるものではない。ステレオタイプ的なジェンダー規範は、様々な法律、慣習、そして国民のジェンダー意識や日常生活に大きな影響を与えている。さらに重要なのは、女性の社会進出および経済的自立が達成されても、家族・親族内での女性の立場、母・嫁・娘という役割に縛られ続ける限り、すなわちその意識を再生産する家父長的な規範から解放されなければジェンダーの主流化は困難であり、「女性の解放」は達成されないことであろう。
第5章
東南アジアでは、どの国においても民族問題が政治を動かす重要な要因のひとつだが、民族と政治の関係性は国ごとに異なる。そのためこの地域のエスニック・ポリティクスに関する研究は、いまでも一国研究が主流である。このような研究状況にあって、東南アジアにおける民族と政治の関係性を概観しようとするなら、どのような枠組みを用いればいいのか。本稿では、人口センサスを用いて各国の民族構成と宗教構成を整理したうえで、支配的民族集団が存在するか否か、支配的な宗教があるどうか、という2つの軸を設定することが、簡便だが有益な枠組みになりうることを示す。
第6章
ASEAN加盟国は地域機構としてのASEANに何を期待してきたか――当事者の主観とその歴史的変遷――(406KB)/ 湯川 拓
本稿はASEAN加盟国が地域機構としてのASEANにどのような機能を期待してきたか、という観点からASEANの50年の歴史を振り返るものである。ASEANは設立年の1967年から第一回首脳会議が開催された1976年までは加盟国間の信頼醸成が主たる機能であり、外交チャネルのための「場」として存在していた。1980年代にはカンボジア紛争に関して国際社会におけるロビー活動を行う「主体」としての機能を付与されるようになった。1990年代以降は経済協力の本格化と、自己を包摂するような広域的な枠組みを主導することの二点が軸となり、2000年代以降には、前者はASEAN経済共同体として、後者は「中心性」への志向性として、それぞれ深化あるいは顕在化してくことになった。しかし、近年においては加盟国間で期待するASEAN象が時に食い違う、加盟国にとってASEANという地域機構自体の重要性が相対化される、という変化もみられており、ASEAN協力へのある種の遠心力も存在する。
第7章
本稿では、人の移動をめぐるグローバルな課題の東南アジアにおける展開と取り組みを概観する予備作業として、植民地時代(16世紀-20世紀初頭)の東南アジアにおける人の移動の歴史的背景を整理した。東南アジアでは、近代以前に中国とインドを介する交易路が開拓され、中国出身の移動者が貿易から小売りまでを掌握し通商ネットワークを形成していた。19世紀に西洋による植民地化が進むと、宗主国との直接的関係と並んで植民地間の経済システムが形成され、それを回路とする人の移動が空前の規模で展開した。受入れ地では移民の管理が問題となり、管理のための新たな制度が模索される。こうして植民地期には人の移動とそのためのシステムの飛躍的発展と、移動する人を管理するための国家的制度(出入国管理、在留資格やその基本となる国境と領域主権)が構築された。
第8章
東南アジアにおける軍組織――欧米とどこが異なるのか――(398KB)/ 木場 紗綾
本稿は、東南アジアの軍の独自性を、第2次大戦以降の軍をめぐる欧米の理論との比較のなかで論じ、「東南アジアのどの部分が、従来の研究枠組みでは説明できないのか」を整理することを目的とする。独立後から冷戦期の東南アジアの軍隊は、国防ではなく国内治安維持(特に反共産主義作戦)に集中し、文民組織が担うべき農村開発のような事業も担当していた。そのため、この時期の軍の「実効性」を従来の枠組みで分析することが困難である。冷戦後、安全保障上の脅威の変容に伴って欧米の軍隊が組織の縮小と多様化をはかっていった時期に、東南アジアにおいてはその転換が起こらなかった。その理由は、軍が冷戦後も国内反乱分子への対応や民主化後のエリートとの役割分担、利益配分に多忙であったためである。欧米の軍隊が「外敵の消滅」と「新たな国際的な安全保障上の危機」への対応として組織再編に向かったのに対し、東南アジアの軍隊の規模の縮小・拡大は、文民エリートと軍との間の国内の調整、妥協によって決定された。東南アジアの軍隊は、地域紛争が共通の危機であるとの認識が希薄であり、平和維持活動を含む国際的な活動に貢献する動機づけが薄かったが、2004年のスマトラ沖地震・インド洋津波を機に地域間協力(軍による国際緊急援助隊の派遣を含む)を志向してきた。しかし、それは世界への貢献というよりは、域外大国に介入されないがためのASEANの枠組みを利用した地域間協力にとどまっている。文民統制が定着していないようにみえる東南アジアの新興民主主義国(特にフィリピン、インドネシア、タイ)においては、治安部門ガバナンスの進化のための国軍改革が議論されてきた。彼らは西欧の民主化財団の支援を受けつつも、市民社会の強化や議会の監視といった西欧的手法をそのまま受け入れることなく、土着エリート、軍人との対話や妥協を尊重し、「アジア的な」改革を模索している。そして各国の経験は共有されている。
第9章
立憲主義と東南アジアの憲法体制(373KB)/ 川村 晃一
本稿では、近代西欧で生まれた立憲主義という考え方や政治のあり方が、東南アジアでどのように受容され、どのように展開してきたかを明らかにするための準備作業として、憲政システムに関する学術的論点と論争の展開を概観した。そのうえで東南アジア諸国の憲政史を整理し、どのような経緯で、誰によって近代的な憲法が策定され、受容されたのか、その後その憲法はどのように変容していったのか、といった点を検討した。また、立憲主義や法の支配を確立するうえで重要な司法制度についての研究潮流を概観した後、東南アジアにおける司法制度の特徴と司法が政治において果たす役割の違いについて、先進東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン)を例にして考えた。東南アジア諸国において、「法の支配」がどのように導入され、展開してきたかを考えるうえでは、そもそもこれらの国々にとって「憲法とは何か」という問題をまず明らかにする必要がある。
第10章
分権・集権の軸からみた東南アジア諸国の中央地方関係(423KB)/ 岡本 正明
現在の東南アジアにおいては、非民主主義体制が主流である。そこで、本章では、主流である民主主義体制下にある東南アジア諸国の中央地方関係、地方行政・政治研究だけではなく、非民主主義体制下での中央地方関係、地方行政・政治にも視野を広げて分析した。第2次世界大戦後、東南アジア諸国が独立してから現在までの対象時期とし、分析の軸を集権/分権にして各国の中央地方関係を分析していった。もうひとつの軸を民主主義体制/非民主主義体制とすれば、4つの類型が存在する。最後に、それぞれの時期の各国の政治体制がどの類型に当てはまるかを検討した。