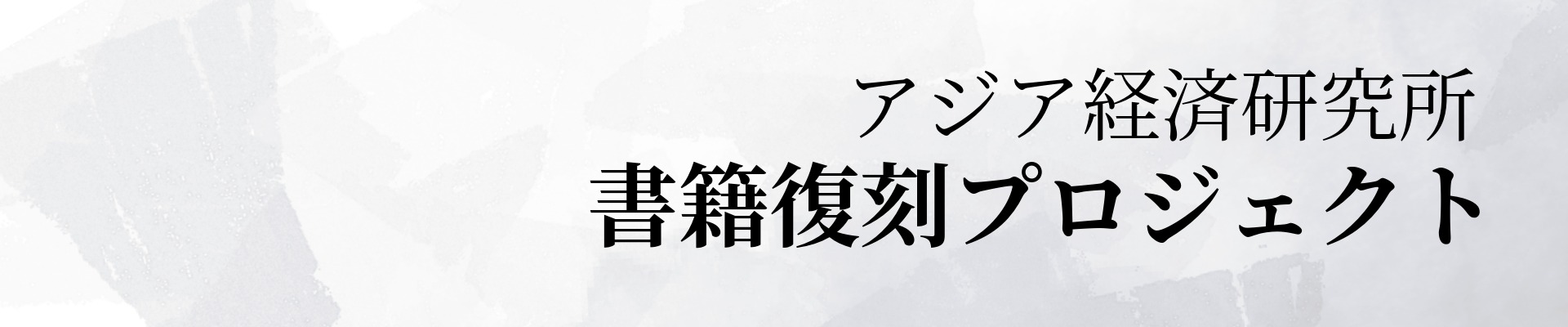出版物
アジア経済研究所 書籍復刻プロジェクト
(アジアを見る眼)「くらし」シリーズ
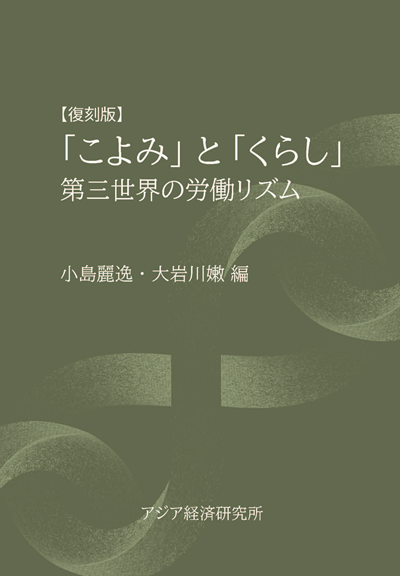
【復刻版】「こよみ」と「くらし」――第三世界の労働リズム――
- 著者/編者 小島麗逸・大岩川嫩
- ISBNコード 978-4-258-11001-8
- 底本出版年月 1987年4月
- 復刻出版年月 2025年9月
- 判型・ページ数 B6変形・268ページ
編者によるご紹介
33編の個別の論を掲げて途上国における「暦」のありかたをみているのが本書である。現在の世界では「国際的には世界共通暦としての地位を確立しているかのように考えられているグレゴリオ暦=いわゆる西暦も、第三世界では必ずしも日常生活の隅々までを律しているものではない」(補章)ことが、これらの各論の多彩な叙述で知られる。
具体的には、東アジア(中華文明圏、中国――山東農村、中国――山西省、韓国、香港)、東南アジア(マレーシア、タイ、ビルマ、フィリピン、ジャワ、インドネシア、ベトナム)、南アジア(インド、東インド、西インド、バングラデシュ、スリランカ、パキスタン)中東(アラブ、エジプト、イスラエル、イラン、シリアとレバノン)、アフリカ(アルジェリア、コートジボワール、ナイジェリア、ケニア)、ラテンアメリカ(ペルー、メキシコ、ブラジル)、オセアニア(ニューギニア)の各国・地域のそれぞれの興味深い固有の暦の歴史と現況が32人の社会科学研究者の観察・調査によって語られている。なかには、現在では公権力による布達からは外れているが、特定の地域に生きている人々の生活に密着した多くの自然暦の存在や、インカ暦、アステカ暦、マヤ暦などの土着の体系をもつ暦の詳細な解説もあり、興味は尽きない。さらに、暦の発生とかかわる人々の時間意識形成の問題について、ニューギニアのインボング族の事例などの報告もある。
「暦と季節感」と「ムスリムの刑事法」の2つの随想も掲載されている。
最後に、あらためて現行の太陽暦・太陰太陽暦・太陰暦の三大暦法を概観し、また国際標準時の現在やその問題点に触れ、また日本の暦の歴史をも解説する編者による補章が加えられている。
どのページを開いても、「こよみ」と「くらし」をめぐって読者の既成概念をゆさぶられる新鮮なおどろきがある。そのような知見に満ちているのが本書の魅力であろう。(大岩川嫩, 2025年4月)
復刻版(オンデマンド版)を購入する(有料)
目次
- はしがき(森崎久寿)
- Ⅰ 東アジア
- 中華文明圏――旧暦・新暦と公休日(小島麗逸)
- 中国――山東農村の年中行事(中生勝美)
- 中国――山西省農村のくらしの中の暦(加藤三由紀)
- 韓国の暦と民俗(桜井浩)
- 香港の暦と生活(内田知行)
- Ⅱ 東南アジア
- マレーシアの祝祭日と週休制(堀井健三)
- タイの暦法と干支(末廣昭)
- タイの暦と農民生活(野中耕一)
- ビルマの暦と生活(桐生稔)
- フィリピンの暦と生活(梅原弘光)
- ジャワ暦の体系とその変革(高橋宗生)
- インドネシア――バタック族の暦(篠塚英子)
- ベトナムの暦と生活(竹内郁雄)
- Ⅲ 南アジア
- インドの暦と休日(押川文子)
- 東インドの稲作農事暦(多田博一)
- 西インド――ある村の祭りと生活リズム(篠田隆)
- バングラデシュの農事諺――コナの格言(佐藤宏)
- スリランカ――シンハラ農村の星占いと時間意識(中村尚司)
- パキスタン――イスラーム暦と西暦のはざまで(深町宏樹)
- Ⅳ 中東
- アラブの暦と「時」(木村喜博)
- エジプトのコプト暦(長沢栄治)
- イスラエルの暦と生活――安息日をめぐって(池田明史)
- イランの暦法――イラン暦とイスラーム暦と西暦(岡﨑正孝)
- シリアとレバノンの祝祭日と公休日(木村喜博)
- Ⅴ アフリカ
- アルジェリアのワイン暦(宮治一雄)
- コートジボワールの独立記念日(原口武彦)
- ナイジェリア――ヨルバ社会の暦(島田周平)
- ケニアの暦と生活(児玉谷史朗)
- Ⅵ ラテンアメリカ
- ペルーの暦と生活(遅野井茂雄)
- メキシコ――ふたつの太陽暦(星野妙子)
- ブラジルの年中行事(小池洋一)
- Ⅶ オセアニア
- ニューギニアの生活暦(塩田光喜)
- Ⅷ 補章
- 暦の歴史をめぐって(大岩川嫩)
- 随想
- 暦と季節感(大野盛雄)
- ムスリムの計時法(林武)
- あとがき(小島麗逸/大岩川嫩)