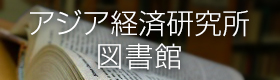アラブ諸国の政軍関係—分析の視角
政策提言研究
池内恵 (東京大学先端科学技術研究センター)
2011年11月
※以下に掲載する文章は、2011年度政策提言研究「 中東・南アジア地域の平和システム構築に向けて 」研究会における報告内容を要約したものです。
PDF (240KB)
体制変動のあり方を左右する軍
大規模デモによって政権の打倒を要求するという社会現象が政治の最大の課題として定着したアラブ諸国において、政権側の初期の対応や、政権の崩壊や存続を左右する要因として、軍の反応・動向が決定的であることが明らかになった。
チュニジアでは、大統領による弾圧の指令に軍が応じず中立を保ったことがベン・アリー前大統領の国外逃亡への決定的な要因となったと見られ、エジプトでは国軍がデモへの武力行使を控え、大統領とその一族に退陣を迫り、軍最高評議会を招集して国政の実権を掌握した。
リビアでは軍がデモの弾圧に加わると共に、軍内部から、東部キレナイカ地方で大規模に早期に離反が生じ、反政権の反乱武装勢力と合流して内戦となった。バーレーンでも軍は政権との一体性を強固に保ち、反政府大規模デモの鎮圧に加わり当面沈静化を果たしている。シリアでも軍が弾圧に動員され自国民への武力行使を行っていると見られるが、10月半ばの段階では、軍内部からの離反はそれほど大規模ではない。イエメンでは軍の特定の精強部隊が有力部族長によって統率されて反大統領派に転じ、大統領支持派の部隊も統率を保っており、小規模な衝突を繰り返して大規模な内戦に落ち込む寸前の淵にある。
このように、大規模デモという、共通の、新しいタイプの社会運動の広がりによって揺らぐアラブ諸国の体制の反応のあり方と持続性は、国による差が見えてきている。そして各国の政権の持続性は、少なくとも半年から一年といった短期的な時間軸の中では、軍の反応に大きく依存することが明らかになった。
これらの国々で異なる軍の反応は、いかなる要因によってもたらされたのだろうか。また、今後、各国でまた新たに大規模デモが生じた際に、それぞれの国で軍はどのような反応を示すと見込まれるのか。これを見ていくために、アラブ諸国の政軍関係を改めて検討し、各国の軍の特質を明らかにしておく必要がある。
「国民軍」と「政権軍」
大規模デモに直面して対応を迫られる過程で、各国の軍の性質の違いが明確になった。現象として見る限り、アラブ諸国の軍には、「国民軍」たりえている軍と、「政権軍」としての性質を濃くするものがあることが明らかになってきた。
軍が「国民軍」としての性質を明らかにしたのはチュニジアとエジプトである。両国では、軍の上層部が、大規模デモによって表出される民意に少なくとも心情的・象徴的な賛意を示して国民の軍としての立場を示し、それが国民の多くからも(少なくとも旧政権崩壊の前後においては)肯定的・積極的に受け止められた。政権による弾圧に際して中立を保ち、また、軍の中枢・最高指導層(大統領を除く)が一体性を保って対処したことが、内戦を予防し、社会治安の極端な悪化を食い止め、一定の連続性を持った移行期に移ることを可能にした。
他方で、リビアとシリアでは、軍の中枢部は政権と一体性を保ち、市民への武力行使を行った。リビアでは軍の中枢部と末端の兵卒の双方から離反者が出て、軍の一体性は損なわれた。シリアでは中枢部における目立った離反者はなく、末端の兵卒の離反が伝えられるものの、政権を武力的に揺るがすほどの規模とはなっていない。バーレーンも軍が政権との一体性を明確に露にしたが、リビアとシリアほどの規模の弾圧・衝突には至っていない。
イエメンではこの両者の類型の中間的な状況が存在しており、2011年10月末の段階で膠着状態にある。
政軍関係の分析視角
各国の軍の反応を分ける要因には、短期的なものと長期的なものが考えられる。短期的には、大統領やその側近と、軍中枢の有力指導者との間の、個人や組織間の関係や対立など、また個別のデモとそれに対する弾圧の経緯といった、偶然や属人的な要素も含んだ要因があるだろう。長期的には、各国で異なる政軍関係の歴史的・構造的な成り立ちが、個人間・組織間の偶発的なものを含む関係の前提として、作用していると考えられる。ここでは特に長期的な規定要因としての、政軍関係の歴史的・構造的な成り立ちを分析する視角をいくつか提示して今後の調査研究の叩き台としておきたい。
国民統合の程度と軍の組成
デモに際して軍が「国民軍」として振る舞った事例と、「政権軍」として対処した事例を対照して検討すると、アラブ諸国の各国で大きく異なる国民統合のあり方、進展度合いによって根底的に規定されている側面が指摘できる。チュニジアやエジプトはアラブ諸国の中で最も国民統合が進んでいる国である。軍においても、将校階層と徴兵による兵卒の階層の双方で、国民統合の進展を反映した、特定の部族や地域などに偏らない構成になっているものと見られる 1 。ここから、軍が、大規模デモによって示された国民の意思に同調する蓋然性が高くなる。
これに対して、リビア、シリア、イエメン、バーレーンでは、部族・地域・宗教・宗派による国民間の亀裂構造が存在し、国民統合が十分に進んでいない。これは軍の構成に、それぞれの国で異なる形で反映している。シリアやバーレーンでは少数宗派が軍を掌握し、その武力によって権力を維持するという構造になっている。シリアの場合人口の1割程度を占めるにすぎないアラウィー派が軍の将校層において7割から8割ほどを占めるといわれるほどに、バランスを失した人口構成が軍内部に生じている。バーレーンにおいても、人口的には少数のスンナ派が主体の軍が、多数を占めるシーア派の抗議行動に対峙している。これらの国では軍が国民全体を代表し、国民全体に帰属するのではなく、特定の宗派集団への代表・帰属意識を強めており、逆に国民の多数からも軍との一体性が認識されていない。リビアやイエメンも同様であるが、これらの軍においては各部隊や将校・兵卒がそれぞれの部族や地域への紐帯意識を強く維持していることから、大規模デモに直面した際に、軍の一体性が失われ、内戦に陥った(イエメンの場合は、陥りかけている)。
ただし、国民統合の度合いと軍の構成との間の因果関係・影響関係は逆方向である可能性がある。すなわち、国民統合の不全が軍の統合を疎外するというのではなく、その国の軍の特異な構成のされ方が、国民統合の進展に影響を与えたという可能性もある。近代国家において軍は、元来は国民統合を促進する有力な主体とされているものであり、その軍が人口構成を反映せず、部族・宗派間の特定の権力関係を反映して形成された場合、国民統合の阻害要因となっている可能性がある。
並行軍事組織の存在
アラブ諸国の多くでは、国軍に並行して、国家護衛隊、大統領親衛隊、治安部隊といった並行軍事組織(paramilitary)が、(場合によっては複数)存在している。また、軍の内部の精鋭部隊に大統領親族が司令官となり、実質上独自の指揮系統を確立している場合や、公式の並行軍事組織のさらに外側に、非合法・超法規的な民兵組織・暴力的集団が治安部隊の別働隊として組織されている場合がある。小規模の湾岸産油国やカダフィ政権のリビアなどでは、外国から傭兵が導入されているとみられる。
これらの組織は国土よりも政権を防衛し、特に国軍を監視しカウンターバランスとなってクーデタを阻止することに実質上の主たる使命がある。首都や戦略的に重要な地域に駐屯し、イスラーム主義過激派の掃討作戦でも主要な役割を果たす場合が多い。国軍と、場合によっては国軍以上の能力や規模を持つ複数の並行軍事組織の関係が、政軍関係の重要な要素となっている。
チュニジアとエジプトでは国軍がこれら並行軍事組織に対して物理的に優位に立ち、また国民の支持というモラル的な側面でも優位に立ったことが、事態の進展を早期に鎮静化する要因となった。チュニジアでは内務省傘下の国家護衛隊(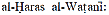 National Guard)は、軍と同様にベンアリー大統領から距離を置き、国家警護隊と大統領親衛隊を統括していたベンアリー側近のアリー・セリヤーティー(Ali Seriati)将軍は、ベンアリー国外逃亡の直後に小規模の銃撃戦を経て、国軍と警察によって逮捕されている。
National Guard)は、軍と同様にベンアリー大統領から距離を置き、国家警護隊と大統領親衛隊を統括していたベンアリー側近のアリー・セリヤーティー(Ali Seriati)将軍は、ベンアリー国外逃亡の直後に小規模の銃撃戦を経て、国軍と警察によって逮捕されている。
エジプトでは国防省傘下の共和国警護隊(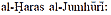 Republican Guard)、内務省傘下の中央治安部隊(
Republican Guard)、内務省傘下の中央治安部隊(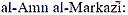 Central Security)、国家治安局(
Central Security)、国家治安局(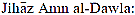 State Security Apparatus)があり、デモを弾圧しようとしたものの、逆にデモ隊により制圧される場面が生じ、威信を喪失した。それに対して、国軍は国民への共感を表明し、発砲を避け、部隊の統制を保って治安の安定をもたらしたことによって国民からの支持の確保を図った。ムバーラク大統領退陣後は、国家治安局長のハサン・アブドゥッラフマーン
State Security Apparatus)があり、デモを弾圧しようとしたものの、逆にデモ隊により制圧される場面が生じ、威信を喪失した。それに対して、国軍は国民への共感を表明し、発砲を避け、部隊の統制を保って治安の安定をもたらしたことによって国民からの支持の確保を図った。ムバーラク大統領退陣後は、国家治安局長のハサン・アブドゥッラフマーン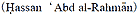 少将を拘束し(3月7日)、国家安全保安局そのものを解体する(3月15日発表)など、軍と並行する治安機構への優越性を保っている。
少将を拘束し(3月7日)、国家安全保安局そのものを解体する(3月15日発表)など、軍と並行する治安機構への優越性を保っている。
これに対して、リビアやシリアの弾圧の際には、並行軍事組織が装備や士気や政権への忠誠心でも概ね国軍に優越し、弾圧や内戦で先頭に立った。リビアでは三男サーアディーの率いる特殊部隊や、七男ハミースの指揮する陸軍第32旅団(32nd Reinforced Brigade)、カダフィ大佐の義理の弟のアブドッラー・サヌースィーが指揮した対内諜報機関(al-Amn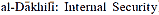 )、中国の文化大革命の際の赤衛兵にも似た革命委員会(
)、中国の文化大革命の際の赤衛兵にも似た革命委員会(
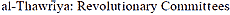 )傘下の民兵組織などが、最後までカダフィ政権に忠誠を誓い、弾圧や内戦を戦った。
)傘下の民兵組織などが、最後までカダフィ政権に忠誠を誓い、弾圧や内戦を戦った。
シリアの場合は、大統領親族が指揮を取っていた民兵特殊部隊の国防旅団を前身とする陸軍の第4機甲師団 2 や、バッシャール・アサド大統領も一時籍を置き、弟のマーヘル・アサド大佐が指揮を取る共和国護衛隊が、各地のデモ弾圧で中心的役割を担っている。また政権中枢部と水面下で繋がるとされるシャッビーハ(亡霊)と呼ばれる暴力組織がデモの弾圧を実行していると報じられている。他方、アサド政権は国軍については忠誠心の確かな部隊のみを弾圧の前線に立たせる工夫をしていると見られるが、逃亡・離反兵をシャッビーハが取り締まるなど、並行軍事組織の優位性が明らかである。10月半ばの段階では、国軍部隊の中から、大規模・組織的に離反して共和国護衛隊やシャッビーハ等に対峙する動きは確認されていない。
イエメンではアリー・アブドッラー・サーレハ大統領の息子のアハマド・サーレハ准将が率いる大統領直属の精鋭部隊である共和国警護隊(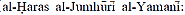 Yemen Republican Guard)が抗議行動に武力弾圧で対抗するのに対し、イエメン国軍内の精鋭部隊として知られる第1機甲師団を率いるアリー・ムフシン・アフマル少将が師団ごと反政府勢力に転じている。さらに共和国警護隊の一部も、複数の大隊(kutaiba)単位で反政府側に転じる動きが出ているなど状況は複雑であり、国軍と並行軍事組織の双方に一体性がなく、軍事的にも拮抗しているものと見られる。
Yemen Republican Guard)が抗議行動に武力弾圧で対抗するのに対し、イエメン国軍内の精鋭部隊として知られる第1機甲師団を率いるアリー・ムフシン・アフマル少将が師団ごと反政府勢力に転じている。さらに共和国警護隊の一部も、複数の大隊(kutaiba)単位で反政府側に転じる動きが出ているなど状況は複雑であり、国軍と並行軍事組織の双方に一体性がなく、軍事的にも拮抗しているものと見られる。
「制度化」の度合い
ここまで見てきたところから、チュニジアやエジプトでの比較的穏便で秩序だった軍の対応と、リビアやシリアやイエメンでの強硬かつ分裂的な軍の対応の相違の根底には、国全体と軍内部の双方での国民統合の度合いの差や、国軍と並行軍事組織の力関係が関わっていると見られるが、これらは、「制度化(institutionalization)」の程度の差によると一般化できる。通常、軍の近代化の進展を図る概念として「職業化(professionalization)」が多く用いられるが、職業化の主要な要件は軍の「非政治化」と「文民統制への従属」であり、それらが押し並べて進んでいないアラブ諸国の軍を見ていく際に、それほど有用ではない。これに対して「制度化」は、「家産的(patrimonial)」な軍と対比される概念である。
「家産的」な軍は、権威主義的な政治体制においてしばしば見られるものであり、大統領など最高権力者とその側近による恩顧主義的・恣意的な組織化がなされている軍である。それに対して「制度化」が進んだ軍は、規則によって統制され、予測可能性が高く、能力主義的に運営される。将校層や兵卒の募集や昇進が恣意的な基準ではなく平等に開かれ、昇進の基準が能力主義に基づき、軍が私的な武装集団ではなく公的な組織として確立され、軍規が守られている、といった要素が強まると「制度化」が進んだと見なすことができる 3 。
制度化が進んだ軍は、組織としての規律や自立性を持つようになり、政権中枢と必ずしも一致しない組織としての利益も考慮して行動する余地が出てくることから、「政権軍」としての要素を弱める可能性がある。また特定の人物や勢力への忠誠心ではなく国民全体への帰属意識や役割任務の意識を基本原則とする行動原理が確立されてくる。
チュニジアやエジプトでは、軍においてこれらの制度化が一定程度進んでいたことに起因して軍が大統領やその親族など政権中枢部からある程度自立した判断を行うことができたといえよう。エジプトではタンターウィー元帥・国防相の昇進に際して、ムバーラク一家への従属的姿勢が関係しているといった批判は聞かれるものの、その批判は原則としての能力主義が成立していることを前提としている。ムバーラク政権の末期の運営は、大統領一家とその側近による「家産的」様相を深めたとはいえ、それは軍には及んでいない。次男ガマールの大統領位世襲の動きも、支配政党の国民民主党(NDP)で枢要な地位に就かせるという形であって、軍籍を与えて急速に昇進させるといった手法は取らなかった。同様にチュニジアでも、大統領夫人のトラベルシ家を中心とした大統領親族の専横を批判されたベンアリー政権でも、軍には基本的に親族支配は及んでいない。
部族や宗派などによるリクルートや登用が行われ、大統領の息子や親族による軍・治安機構の統率が行われてきたリビアやシリアはこれと対照的であり、家産的様相を色濃くする。前出のように、リビアでは三男サーアディーや七男ハミースなどによる精鋭部隊の統率が行われ、シリアではバッシャールの大統領世襲の準備として急速な軍歴昇進が行われ、弟のマーヘルは実際に精鋭部隊の指揮を執っている。またシリアではバアス党による軍・治安機構の統制も強く、政党と軍の組織としての一体性が高い。このようにして制度化の度合いが低いリビアやシリアでは、軍がデモに対して独自の判断を下せないと見ることができる。イエメンはエジプト・チュニジア型かリビア・シリア型のどちらになるか、せめぎ合いの過程にあると見ることもできるし、そのどちらにも十分に進展しない膠着状態にあるとも考えられよう。
今後の各国の軍の反応
「国民統合」の進展度と、「並行軍事組織」との関係、そしてこの二つを中心とした「制度化」の程度によって、すでに大規模デモが政権を揺るがし軍が究極の選択を迫られた国について検討してきた。今後、さらに他のアラブ諸国でも政権が揺らぐほどの反政府抗議行動が生じた場合、各国の軍がどのような対応を取るか、これらの少ない切り口からの限定的なものではあるが、ある程度方向性や危険の所在を指摘することができる。
国民統合の不全に関係してもたらされる軍内部の統合の不全が、今後重要な意味をもって顕在化する可能性があるのは、ヨルダンだろう。ヨルダンの場合、土着の都市住民および部族勢力と、流入して人口の約半数を占めるに至ったパレスチナ系との潜在的な対立がある。ヨルダン国軍は国王に高い忠誠心を誓う、国民統合の象徴として威信を持ってきた。ヨルダン軍は1970年の「黒い9月」の武力衝突でパレスチナ難民の武装勢力を弾圧したように、パレスチナ諸勢力を潜在的な脅威の最重要ととらえている。ヨルダン国籍を持つパレスチナ人も、軍の戦闘部隊では少佐か最大限中佐までしか昇進せず、将官へ昇進できるのは兵站や軍医の分野のみと言われてきた 。 4 もちろん、ヨルダン王政は経済的にパレスチナ系の企業家と密接な関係を結んでおり、王妃をパレスチナ系から迎えるなどパレスチナ系の統合・取り込み策を進めている。しかしパレスチナ系の国家・王政への忠誠心を疑う見方や、「パレスチナ人に国を乗っ取られる」という脅威認識は、土着の部族系・都市住民から簡潔的に表明されており、それが王政批判につながりかねない。そのため軍においてはパレスチナ系の進出はまだタブーであると見られる。2009年には国王がパレスチナ系の将校を多く退役させ、土着系に入れ替えたという噂も流れている。筆者はこれに関する事実関係を確認できないが、そのような噂が流れること自体が、少なくとも潜在的・構造的には、なんらかの問題・摩擦が存在する可能性を示唆するものであり、注視する必要があると考える。デモによる政権への抗議や要求が王政そのものに矛先を向けるような事態に進展した場合、抗議行動を土着系とパレスチナ系との対立として政治問題化する動きが、政権側あるいは社会の中のいずれかから表面化すると、状況は流動化しかねない。その際にはヨルダンでも政軍関係の政治的重要性がさらに増し、(1) 軍内部でのヨルダン土着系とパレスチナ系の亀裂が表面化するか、(2) 軍と、国民の半数程度を占めるパレスチナ系との間の一体性が失われる形での紛争・衝突が生じるといったシナリオを懸念しなければならなくなる。
逆に、宗派による国民社会の中の亀裂が著しく、宗派集団による亀裂を重要な対立軸・結集軸として1975年から90年にかけて内戦が行われたレバノンの場合、内戦終結後に民兵組織の(ヒズブッラーを除く)解体がなされ、レバノン国軍への統合が進められている。その結果レバノン国軍は宗派ではなく国民軍としての性質を持ち始めているという報告もある 5 。ただしレバノン内政の安定・不安定には隣国シリアの介入やイスラエル・パレスチナ間の紛争、アラブ諸国やイランなど中東域内の対立・競合関係が複雑に影響しており、政軍関係のみを取り出して安定要因とみなすことはふさわしくないだろう。
一方、国軍と並行軍事組織の関係について注目を要するのは、潜在的にはサウジアラビアだろう。アブドッラー国王は、国王に就任する以前から国家警護隊(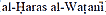 )を傘下に抱えてきており、国家警護隊は国軍と同等かそれ以上の規模の兵力を維持して、国軍へのカウンターバランスであり、サウジアラビア王制を護持してきた。首都リヤードや東部油田地帯などの重要地域ではほとんどの場合、国家警護隊が管轄している。国軍と国家警護隊の間の潜在的な対立を顕在化させずに抑えることが、近い将来に不可避となる王位の兄弟間・世代間の継承を安定的に進めるための不可欠の要素だろう。レバノンは内戦終結後多くの民兵集団は解体されレバノン国軍に編入されたが、ヒズブッラーのみは対イスラエル「抵抗」を戦うという名目やシリア・イランの支持によって武装解除を拒んでいる。パレスチナもハマースが独自の武装組織を維持しガザ地区を政治・軍事的に掌握している限りは実質的な国家設立の可能性は薄い。
)を傘下に抱えてきており、国家警護隊は国軍と同等かそれ以上の規模の兵力を維持して、国軍へのカウンターバランスであり、サウジアラビア王制を護持してきた。首都リヤードや東部油田地帯などの重要地域ではほとんどの場合、国家警護隊が管轄している。国軍と国家警護隊の間の潜在的な対立を顕在化させずに抑えることが、近い将来に不可避となる王位の兄弟間・世代間の継承を安定的に進めるための不可欠の要素だろう。レバノンは内戦終結後多くの民兵集団は解体されレバノン国軍に編入されたが、ヒズブッラーのみは対イスラエル「抵抗」を戦うという名目やシリア・イランの支持によって武装解除を拒んでいる。パレスチナもハマースが独自の武装組織を維持しガザ地区を政治・軍事的に掌握している限りは実質的な国家設立の可能性は薄い。
歴史の記憶
上記に挙げた三つの要素以外にも、政軍関係の多くの要因が複合的に関わって、軍のデモに対する反応を左右していると見られる。それらは、まず、(1) 経済利権:各国の軍が持つ経済利権の内実は歴史的経緯によって大きく異なる。軍がクーデタで権力を掌握した際に、土地を含む資産を前政権から継承したエジプトのような場合は、軍が固有の資産を持って政権から自立性を持つ潜在的能力がある。軍産複合体の発達具合も各国によって異なる。経済自由化・民営化・市場化の過程で生じるクローニー・キャピタリズムへの関与による軍への利益も、国によって程度が異なっているだろう。経済自由化によって出現する新興企業家層と軍との関係は、デモによる大統領など最高権力者やその取り巻きへの批判が高まった際の軍の反応を左右する重要な要素だろう。(2) 対外関係:米国など域外大国との関係は各国の政軍関係を根底で規定していると考えられる。エジプトやヨルダンは、対イスラエル和平を中心とした対米協調政策の見返りとして軍事・経済支援を受けてきた。それによって、米国の援助に依存する傾向や、米国が一定の抑制を聞かせるチャネルが存在していると考えられる。バーレーンやカタールなど、米国に基地を提供することによって米国の対中東安全保障政策に不可欠の便益を提供している場合、弾圧に対する米国の批判は鈍りがちであり、それによってデモに強硬な対処を取る可能性がある。また、2001年9月11日の同時多発テロ事件以後に米国の対外政策の新たな最重要項目となった国際テロ対策において、エジプト、チュニジア、ヨルダンに加え、サウジアラビア、イエメン、アルジェリアや、さらにはリビアまでもが、軍・治安機構が情報提供や共同作戦によって米国と関係を深めてきた。これらの政権が崩壊することは米国の対テロ作戦に抜本的な変化を迫る可能性がある。それを「人質」に取って、政権中枢の「家産的」な様相が濃い軍は、強硬な対処策を取ることを厭わないかもしれない。さらに、(3) 歴史的経緯:「国民が一丸となった対外戦争や独立戦争を経験したか」「国民を分裂させる内戦を近い過去に経験しているか」といった歴史的経緯は、政軍関係の基本的状況を規定しているだろう。アルジェリアの凄惨な独立戦争や、イラクがフセイン政権の下で対イラン戦争を闘ったことは国民の一体性の意識の醸成に影響しているだろうし、レバノンの内戦や、アルジェリアの対イスラーム主義武装勢力との内戦の経験は、反政府抗議行動と軍の関係を、他の国とは異なるものとするかもしれない。
【後記】
アラブ諸国の政軍関係という課題はこれで論じつくせるものでは到底なく、またその重要性から見て、稿を改めて論じる必要性を感じる。詳細な先行研究文献の紹介や、網羅的な各国の比較は、今後の機会に譲りたい。
大規模デモによって政権の打倒を要求するという社会現象が政治の最大の課題として定着したアラブ諸国において、政権側の初期の対応や、政権の崩壊や存続を左右する要因として、軍の反応・動向が決定的であることが明らかになった。
チュニジアでは、大統領による弾圧の指令に軍が応じず中立を保ったことがベン・アリー前大統領の国外逃亡への決定的な要因となったと見られ、エジプトでは国軍がデモへの武力行使を控え、大統領とその一族に退陣を迫り、軍最高評議会を招集して国政の実権を掌握した。
リビアでは軍がデモの弾圧に加わると共に、軍内部から、東部キレナイカ地方で大規模に早期に離反が生じ、反政権の反乱武装勢力と合流して内戦となった。バーレーンでも軍は政権との一体性を強固に保ち、反政府大規模デモの鎮圧に加わり当面沈静化を果たしている。シリアでも軍が弾圧に動員され自国民への武力行使を行っていると見られるが、10月半ばの段階では、軍内部からの離反はそれほど大規模ではない。イエメンでは軍の特定の精強部隊が有力部族長によって統率されて反大統領派に転じ、大統領支持派の部隊も統率を保っており、小規模な衝突を繰り返して大規模な内戦に落ち込む寸前の淵にある。
このように、大規模デモという、共通の、新しいタイプの社会運動の広がりによって揺らぐアラブ諸国の体制の反応のあり方と持続性は、国による差が見えてきている。そして各国の政権の持続性は、少なくとも半年から一年といった短期的な時間軸の中では、軍の反応に大きく依存することが明らかになった。
これらの国々で異なる軍の反応は、いかなる要因によってもたらされたのだろうか。また、今後、各国でまた新たに大規模デモが生じた際に、それぞれの国で軍はどのような反応を示すと見込まれるのか。これを見ていくために、アラブ諸国の政軍関係を改めて検討し、各国の軍の特質を明らかにしておく必要がある。
「国民軍」と「政権軍」
大規模デモに直面して対応を迫られる過程で、各国の軍の性質の違いが明確になった。現象として見る限り、アラブ諸国の軍には、「国民軍」たりえている軍と、「政権軍」としての性質を濃くするものがあることが明らかになってきた。
軍が「国民軍」としての性質を明らかにしたのはチュニジアとエジプトである。両国では、軍の上層部が、大規模デモによって表出される民意に少なくとも心情的・象徴的な賛意を示して国民の軍としての立場を示し、それが国民の多くからも(少なくとも旧政権崩壊の前後においては)肯定的・積極的に受け止められた。政権による弾圧に際して中立を保ち、また、軍の中枢・最高指導層(大統領を除く)が一体性を保って対処したことが、内戦を予防し、社会治安の極端な悪化を食い止め、一定の連続性を持った移行期に移ることを可能にした。
他方で、リビアとシリアでは、軍の中枢部は政権と一体性を保ち、市民への武力行使を行った。リビアでは軍の中枢部と末端の兵卒の双方から離反者が出て、軍の一体性は損なわれた。シリアでは中枢部における目立った離反者はなく、末端の兵卒の離反が伝えられるものの、政権を武力的に揺るがすほどの規模とはなっていない。バーレーンも軍が政権との一体性を明確に露にしたが、リビアとシリアほどの規模の弾圧・衝突には至っていない。
イエメンではこの両者の類型の中間的な状況が存在しており、2011年10月末の段階で膠着状態にある。
政軍関係の分析視角
各国の軍の反応を分ける要因には、短期的なものと長期的なものが考えられる。短期的には、大統領やその側近と、軍中枢の有力指導者との間の、個人や組織間の関係や対立など、また個別のデモとそれに対する弾圧の経緯といった、偶然や属人的な要素も含んだ要因があるだろう。長期的には、各国で異なる政軍関係の歴史的・構造的な成り立ちが、個人間・組織間の偶発的なものを含む関係の前提として、作用していると考えられる。ここでは特に長期的な規定要因としての、政軍関係の歴史的・構造的な成り立ちを分析する視角をいくつか提示して今後の調査研究の叩き台としておきたい。
国民統合の程度と軍の組成
デモに際して軍が「国民軍」として振る舞った事例と、「政権軍」として対処した事例を対照して検討すると、アラブ諸国の各国で大きく異なる国民統合のあり方、進展度合いによって根底的に規定されている側面が指摘できる。チュニジアやエジプトはアラブ諸国の中で最も国民統合が進んでいる国である。軍においても、将校階層と徴兵による兵卒の階層の双方で、国民統合の進展を反映した、特定の部族や地域などに偏らない構成になっているものと見られる 1 。ここから、軍が、大規模デモによって示された国民の意思に同調する蓋然性が高くなる。
これに対して、リビア、シリア、イエメン、バーレーンでは、部族・地域・宗教・宗派による国民間の亀裂構造が存在し、国民統合が十分に進んでいない。これは軍の構成に、それぞれの国で異なる形で反映している。シリアやバーレーンでは少数宗派が軍を掌握し、その武力によって権力を維持するという構造になっている。シリアの場合人口の1割程度を占めるにすぎないアラウィー派が軍の将校層において7割から8割ほどを占めるといわれるほどに、バランスを失した人口構成が軍内部に生じている。バーレーンにおいても、人口的には少数のスンナ派が主体の軍が、多数を占めるシーア派の抗議行動に対峙している。これらの国では軍が国民全体を代表し、国民全体に帰属するのではなく、特定の宗派集団への代表・帰属意識を強めており、逆に国民の多数からも軍との一体性が認識されていない。リビアやイエメンも同様であるが、これらの軍においては各部隊や将校・兵卒がそれぞれの部族や地域への紐帯意識を強く維持していることから、大規模デモに直面した際に、軍の一体性が失われ、内戦に陥った(イエメンの場合は、陥りかけている)。
ただし、国民統合の度合いと軍の構成との間の因果関係・影響関係は逆方向である可能性がある。すなわち、国民統合の不全が軍の統合を疎外するというのではなく、その国の軍の特異な構成のされ方が、国民統合の進展に影響を与えたという可能性もある。近代国家において軍は、元来は国民統合を促進する有力な主体とされているものであり、その軍が人口構成を反映せず、部族・宗派間の特定の権力関係を反映して形成された場合、国民統合の阻害要因となっている可能性がある。
並行軍事組織の存在
アラブ諸国の多くでは、国軍に並行して、国家護衛隊、大統領親衛隊、治安部隊といった並行軍事組織(paramilitary)が、(場合によっては複数)存在している。また、軍の内部の精鋭部隊に大統領親族が司令官となり、実質上独自の指揮系統を確立している場合や、公式の並行軍事組織のさらに外側に、非合法・超法規的な民兵組織・暴力的集団が治安部隊の別働隊として組織されている場合がある。小規模の湾岸産油国やカダフィ政権のリビアなどでは、外国から傭兵が導入されているとみられる。
これらの組織は国土よりも政権を防衛し、特に国軍を監視しカウンターバランスとなってクーデタを阻止することに実質上の主たる使命がある。首都や戦略的に重要な地域に駐屯し、イスラーム主義過激派の掃討作戦でも主要な役割を果たす場合が多い。国軍と、場合によっては国軍以上の能力や規模を持つ複数の並行軍事組織の関係が、政軍関係の重要な要素となっている。
チュニジアとエジプトでは国軍がこれら並行軍事組織に対して物理的に優位に立ち、また国民の支持というモラル的な側面でも優位に立ったことが、事態の進展を早期に鎮静化する要因となった。チュニジアでは内務省傘下の国家護衛隊(
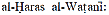 National Guard)は、軍と同様にベンアリー大統領から距離を置き、国家警護隊と大統領親衛隊を統括していたベンアリー側近のアリー・セリヤーティー(Ali Seriati)将軍は、ベンアリー国外逃亡の直後に小規模の銃撃戦を経て、国軍と警察によって逮捕されている。
National Guard)は、軍と同様にベンアリー大統領から距離を置き、国家警護隊と大統領親衛隊を統括していたベンアリー側近のアリー・セリヤーティー(Ali Seriati)将軍は、ベンアリー国外逃亡の直後に小規模の銃撃戦を経て、国軍と警察によって逮捕されている。エジプトでは国防省傘下の共和国警護隊(
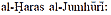 Republican Guard)、内務省傘下の中央治安部隊(
Republican Guard)、内務省傘下の中央治安部隊(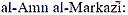 Central Security)、国家治安局(
Central Security)、国家治安局(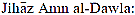 State Security Apparatus)があり、デモを弾圧しようとしたものの、逆にデモ隊により制圧される場面が生じ、威信を喪失した。それに対して、国軍は国民への共感を表明し、発砲を避け、部隊の統制を保って治安の安定をもたらしたことによって国民からの支持の確保を図った。ムバーラク大統領退陣後は、国家治安局長のハサン・アブドゥッラフマーン
State Security Apparatus)があり、デモを弾圧しようとしたものの、逆にデモ隊により制圧される場面が生じ、威信を喪失した。それに対して、国軍は国民への共感を表明し、発砲を避け、部隊の統制を保って治安の安定をもたらしたことによって国民からの支持の確保を図った。ムバーラク大統領退陣後は、国家治安局長のハサン・アブドゥッラフマーン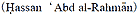 少将を拘束し(3月7日)、国家安全保安局そのものを解体する(3月15日発表)など、軍と並行する治安機構への優越性を保っている。
少将を拘束し(3月7日)、国家安全保安局そのものを解体する(3月15日発表)など、軍と並行する治安機構への優越性を保っている。これに対して、リビアやシリアの弾圧の際には、並行軍事組織が装備や士気や政権への忠誠心でも概ね国軍に優越し、弾圧や内戦で先頭に立った。リビアでは三男サーアディーの率いる特殊部隊や、七男ハミースの指揮する陸軍第32旅団(32nd Reinforced Brigade)、カダフィ大佐の義理の弟のアブドッラー・サヌースィーが指揮した対内諜報機関(al-Amn
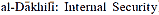 )、中国の文化大革命の際の赤衛兵にも似た革命委員会(
)、中国の文化大革命の際の赤衛兵にも似た革命委員会(
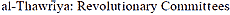 )傘下の民兵組織などが、最後までカダフィ政権に忠誠を誓い、弾圧や内戦を戦った。
)傘下の民兵組織などが、最後までカダフィ政権に忠誠を誓い、弾圧や内戦を戦った。シリアの場合は、大統領親族が指揮を取っていた民兵特殊部隊の国防旅団を前身とする陸軍の第4機甲師団 2 や、バッシャール・アサド大統領も一時籍を置き、弟のマーヘル・アサド大佐が指揮を取る共和国護衛隊が、各地のデモ弾圧で中心的役割を担っている。また政権中枢部と水面下で繋がるとされるシャッビーハ(亡霊)と呼ばれる暴力組織がデモの弾圧を実行していると報じられている。他方、アサド政権は国軍については忠誠心の確かな部隊のみを弾圧の前線に立たせる工夫をしていると見られるが、逃亡・離反兵をシャッビーハが取り締まるなど、並行軍事組織の優位性が明らかである。10月半ばの段階では、国軍部隊の中から、大規模・組織的に離反して共和国護衛隊やシャッビーハ等に対峙する動きは確認されていない。
イエメンではアリー・アブドッラー・サーレハ大統領の息子のアハマド・サーレハ准将が率いる大統領直属の精鋭部隊である共和国警護隊(
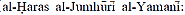 Yemen Republican Guard)が抗議行動に武力弾圧で対抗するのに対し、イエメン国軍内の精鋭部隊として知られる第1機甲師団を率いるアリー・ムフシン・アフマル少将が師団ごと反政府勢力に転じている。さらに共和国警護隊の一部も、複数の大隊(kutaiba)単位で反政府側に転じる動きが出ているなど状況は複雑であり、国軍と並行軍事組織の双方に一体性がなく、軍事的にも拮抗しているものと見られる。
Yemen Republican Guard)が抗議行動に武力弾圧で対抗するのに対し、イエメン国軍内の精鋭部隊として知られる第1機甲師団を率いるアリー・ムフシン・アフマル少将が師団ごと反政府勢力に転じている。さらに共和国警護隊の一部も、複数の大隊(kutaiba)単位で反政府側に転じる動きが出ているなど状況は複雑であり、国軍と並行軍事組織の双方に一体性がなく、軍事的にも拮抗しているものと見られる。「制度化」の度合い
ここまで見てきたところから、チュニジアやエジプトでの比較的穏便で秩序だった軍の対応と、リビアやシリアやイエメンでの強硬かつ分裂的な軍の対応の相違の根底には、国全体と軍内部の双方での国民統合の度合いの差や、国軍と並行軍事組織の力関係が関わっていると見られるが、これらは、「制度化(institutionalization)」の程度の差によると一般化できる。通常、軍の近代化の進展を図る概念として「職業化(professionalization)」が多く用いられるが、職業化の主要な要件は軍の「非政治化」と「文民統制への従属」であり、それらが押し並べて進んでいないアラブ諸国の軍を見ていく際に、それほど有用ではない。これに対して「制度化」は、「家産的(patrimonial)」な軍と対比される概念である。
「家産的」な軍は、権威主義的な政治体制においてしばしば見られるものであり、大統領など最高権力者とその側近による恩顧主義的・恣意的な組織化がなされている軍である。それに対して「制度化」が進んだ軍は、規則によって統制され、予測可能性が高く、能力主義的に運営される。将校層や兵卒の募集や昇進が恣意的な基準ではなく平等に開かれ、昇進の基準が能力主義に基づき、軍が私的な武装集団ではなく公的な組織として確立され、軍規が守られている、といった要素が強まると「制度化」が進んだと見なすことができる 3 。
制度化が進んだ軍は、組織としての規律や自立性を持つようになり、政権中枢と必ずしも一致しない組織としての利益も考慮して行動する余地が出てくることから、「政権軍」としての要素を弱める可能性がある。また特定の人物や勢力への忠誠心ではなく国民全体への帰属意識や役割任務の意識を基本原則とする行動原理が確立されてくる。
チュニジアやエジプトでは、軍においてこれらの制度化が一定程度進んでいたことに起因して軍が大統領やその親族など政権中枢部からある程度自立した判断を行うことができたといえよう。エジプトではタンターウィー元帥・国防相の昇進に際して、ムバーラク一家への従属的姿勢が関係しているといった批判は聞かれるものの、その批判は原則としての能力主義が成立していることを前提としている。ムバーラク政権の末期の運営は、大統領一家とその側近による「家産的」様相を深めたとはいえ、それは軍には及んでいない。次男ガマールの大統領位世襲の動きも、支配政党の国民民主党(NDP)で枢要な地位に就かせるという形であって、軍籍を与えて急速に昇進させるといった手法は取らなかった。同様にチュニジアでも、大統領夫人のトラベルシ家を中心とした大統領親族の専横を批判されたベンアリー政権でも、軍には基本的に親族支配は及んでいない。
部族や宗派などによるリクルートや登用が行われ、大統領の息子や親族による軍・治安機構の統率が行われてきたリビアやシリアはこれと対照的であり、家産的様相を色濃くする。前出のように、リビアでは三男サーアディーや七男ハミースなどによる精鋭部隊の統率が行われ、シリアではバッシャールの大統領世襲の準備として急速な軍歴昇進が行われ、弟のマーヘルは実際に精鋭部隊の指揮を執っている。またシリアではバアス党による軍・治安機構の統制も強く、政党と軍の組織としての一体性が高い。このようにして制度化の度合いが低いリビアやシリアでは、軍がデモに対して独自の判断を下せないと見ることができる。イエメンはエジプト・チュニジア型かリビア・シリア型のどちらになるか、せめぎ合いの過程にあると見ることもできるし、そのどちらにも十分に進展しない膠着状態にあるとも考えられよう。
今後の各国の軍の反応
「国民統合」の進展度と、「並行軍事組織」との関係、そしてこの二つを中心とした「制度化」の程度によって、すでに大規模デモが政権を揺るがし軍が究極の選択を迫られた国について検討してきた。今後、さらに他のアラブ諸国でも政権が揺らぐほどの反政府抗議行動が生じた場合、各国の軍がどのような対応を取るか、これらの少ない切り口からの限定的なものではあるが、ある程度方向性や危険の所在を指摘することができる。
国民統合の不全に関係してもたらされる軍内部の統合の不全が、今後重要な意味をもって顕在化する可能性があるのは、ヨルダンだろう。ヨルダンの場合、土着の都市住民および部族勢力と、流入して人口の約半数を占めるに至ったパレスチナ系との潜在的な対立がある。ヨルダン国軍は国王に高い忠誠心を誓う、国民統合の象徴として威信を持ってきた。ヨルダン軍は1970年の「黒い9月」の武力衝突でパレスチナ難民の武装勢力を弾圧したように、パレスチナ諸勢力を潜在的な脅威の最重要ととらえている。ヨルダン国籍を持つパレスチナ人も、軍の戦闘部隊では少佐か最大限中佐までしか昇進せず、将官へ昇進できるのは兵站や軍医の分野のみと言われてきた 。 4 もちろん、ヨルダン王政は経済的にパレスチナ系の企業家と密接な関係を結んでおり、王妃をパレスチナ系から迎えるなどパレスチナ系の統合・取り込み策を進めている。しかしパレスチナ系の国家・王政への忠誠心を疑う見方や、「パレスチナ人に国を乗っ取られる」という脅威認識は、土着の部族系・都市住民から簡潔的に表明されており、それが王政批判につながりかねない。そのため軍においてはパレスチナ系の進出はまだタブーであると見られる。2009年には国王がパレスチナ系の将校を多く退役させ、土着系に入れ替えたという噂も流れている。筆者はこれに関する事実関係を確認できないが、そのような噂が流れること自体が、少なくとも潜在的・構造的には、なんらかの問題・摩擦が存在する可能性を示唆するものであり、注視する必要があると考える。デモによる政権への抗議や要求が王政そのものに矛先を向けるような事態に進展した場合、抗議行動を土着系とパレスチナ系との対立として政治問題化する動きが、政権側あるいは社会の中のいずれかから表面化すると、状況は流動化しかねない。その際にはヨルダンでも政軍関係の政治的重要性がさらに増し、(1) 軍内部でのヨルダン土着系とパレスチナ系の亀裂が表面化するか、(2) 軍と、国民の半数程度を占めるパレスチナ系との間の一体性が失われる形での紛争・衝突が生じるといったシナリオを懸念しなければならなくなる。
逆に、宗派による国民社会の中の亀裂が著しく、宗派集団による亀裂を重要な対立軸・結集軸として1975年から90年にかけて内戦が行われたレバノンの場合、内戦終結後に民兵組織の(ヒズブッラーを除く)解体がなされ、レバノン国軍への統合が進められている。その結果レバノン国軍は宗派ではなく国民軍としての性質を持ち始めているという報告もある 5 。ただしレバノン内政の安定・不安定には隣国シリアの介入やイスラエル・パレスチナ間の紛争、アラブ諸国やイランなど中東域内の対立・競合関係が複雑に影響しており、政軍関係のみを取り出して安定要因とみなすことはふさわしくないだろう。
一方、国軍と並行軍事組織の関係について注目を要するのは、潜在的にはサウジアラビアだろう。アブドッラー国王は、国王に就任する以前から国家警護隊(
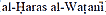 )を傘下に抱えてきており、国家警護隊は国軍と同等かそれ以上の規模の兵力を維持して、国軍へのカウンターバランスであり、サウジアラビア王制を護持してきた。首都リヤードや東部油田地帯などの重要地域ではほとんどの場合、国家警護隊が管轄している。国軍と国家警護隊の間の潜在的な対立を顕在化させずに抑えることが、近い将来に不可避となる王位の兄弟間・世代間の継承を安定的に進めるための不可欠の要素だろう。レバノンは内戦終結後多くの民兵集団は解体されレバノン国軍に編入されたが、ヒズブッラーのみは対イスラエル「抵抗」を戦うという名目やシリア・イランの支持によって武装解除を拒んでいる。パレスチナもハマースが独自の武装組織を維持しガザ地区を政治・軍事的に掌握している限りは実質的な国家設立の可能性は薄い。
)を傘下に抱えてきており、国家警護隊は国軍と同等かそれ以上の規模の兵力を維持して、国軍へのカウンターバランスであり、サウジアラビア王制を護持してきた。首都リヤードや東部油田地帯などの重要地域ではほとんどの場合、国家警護隊が管轄している。国軍と国家警護隊の間の潜在的な対立を顕在化させずに抑えることが、近い将来に不可避となる王位の兄弟間・世代間の継承を安定的に進めるための不可欠の要素だろう。レバノンは内戦終結後多くの民兵集団は解体されレバノン国軍に編入されたが、ヒズブッラーのみは対イスラエル「抵抗」を戦うという名目やシリア・イランの支持によって武装解除を拒んでいる。パレスチナもハマースが独自の武装組織を維持しガザ地区を政治・軍事的に掌握している限りは実質的な国家設立の可能性は薄い。歴史の記憶
上記に挙げた三つの要素以外にも、政軍関係の多くの要因が複合的に関わって、軍のデモに対する反応を左右していると見られる。それらは、まず、(1) 経済利権:各国の軍が持つ経済利権の内実は歴史的経緯によって大きく異なる。軍がクーデタで権力を掌握した際に、土地を含む資産を前政権から継承したエジプトのような場合は、軍が固有の資産を持って政権から自立性を持つ潜在的能力がある。軍産複合体の発達具合も各国によって異なる。経済自由化・民営化・市場化の過程で生じるクローニー・キャピタリズムへの関与による軍への利益も、国によって程度が異なっているだろう。経済自由化によって出現する新興企業家層と軍との関係は、デモによる大統領など最高権力者やその取り巻きへの批判が高まった際の軍の反応を左右する重要な要素だろう。(2) 対外関係:米国など域外大国との関係は各国の政軍関係を根底で規定していると考えられる。エジプトやヨルダンは、対イスラエル和平を中心とした対米協調政策の見返りとして軍事・経済支援を受けてきた。それによって、米国の援助に依存する傾向や、米国が一定の抑制を聞かせるチャネルが存在していると考えられる。バーレーンやカタールなど、米国に基地を提供することによって米国の対中東安全保障政策に不可欠の便益を提供している場合、弾圧に対する米国の批判は鈍りがちであり、それによってデモに強硬な対処を取る可能性がある。また、2001年9月11日の同時多発テロ事件以後に米国の対外政策の新たな最重要項目となった国際テロ対策において、エジプト、チュニジア、ヨルダンに加え、サウジアラビア、イエメン、アルジェリアや、さらにはリビアまでもが、軍・治安機構が情報提供や共同作戦によって米国と関係を深めてきた。これらの政権が崩壊することは米国の対テロ作戦に抜本的な変化を迫る可能性がある。それを「人質」に取って、政権中枢の「家産的」な様相が濃い軍は、強硬な対処策を取ることを厭わないかもしれない。さらに、(3) 歴史的経緯:「国民が一丸となった対外戦争や独立戦争を経験したか」「国民を分裂させる内戦を近い過去に経験しているか」といった歴史的経緯は、政軍関係の基本的状況を規定しているだろう。アルジェリアの凄惨な独立戦争や、イラクがフセイン政権の下で対イラン戦争を闘ったことは国民の一体性の意識の醸成に影響しているだろうし、レバノンの内戦や、アルジェリアの対イスラーム主義武装勢力との内戦の経験は、反政府抗議行動と軍の関係を、他の国とは異なるものとするかもしれない。
【後記】
アラブ諸国の政軍関係という課題はこれで論じつくせるものでは到底なく、またその重要性から見て、稿を改めて論じる必要性を感じる。詳細な先行研究文献の紹介や、網羅的な各国の比較は、今後の機会に譲りたい。
2011年10月31日
参 考
- ただしエジプトの場合は人口の一割程度を占めるキリスト教徒(コプト教徒)が軍の戦闘部隊の司令官としてイスラーム教徒に命令を出せるか、という議論の分かれる問題が存在する。
- 前身はバッシャール大統領の叔父(ハーフィズ・アサド前大統領の弟)リフアト・アサドが指揮していた国防旅団。リフアト・アサドが政権から離反した後に陸軍傘下に吸収されたが、独立した政権防衛組織としての性質を保っているとされる。
- 「制度化」の概念はEva Bellin, "Coercive Institutions and Coercive Leaders," in Marsha Pripstein Posusney and Michele Penner Angrist (eds.), Authoritarianism in the Middle East: Regimes and Resistance , Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2005, p. 28に依拠した。
- Alexander Bligh, "The Jordanian Army: Between Domestic and External Challenges," Middle East Review of International Affairs , Vol. 5, No.2 (Summer 2001). http://meria.idc.ac.il/journal/2001/issue2/bligh.pdf
- Oren Barak, The Lebanese Army: A National Institution in a Divided Society , Albany, State University of New York Press, 2009.