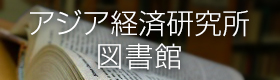インド民主主義体制のゆくえ:多党化と経済成長の時代における安定性と限界
調査研究報告書
近藤 則夫 編
2008年3月発行
はじめに (345KB)
第1章
インド政治論のメタモーフォシス - 1980年代から90年代以降へ - (512KB) / 佐藤 宏
1980年代のインド政治研究の分野では、インド政治論の革新ともいえるような興味深い複数の分析視角が提示された。これらの革新は、インディラ・ガンディーによる非常事態後のインド政治の新たな展開と、新自由主義的な市場主義の潮流が加速した同時代の国際環境とによって触発されたものである。この時期の代表的なインド政治論として、プラナブ・バルダンおよびロイド・ルドルフとスーザン・ルドルフによる政治経済学的研究さらにはラジュニ・コターリーとジェームズ・マナーによる政党政治研究をとりあげ、それぞれの内容とその後の方法的、理論的な展開を追う。これら1980年代における一連の研究を検討することは、90年代に顕著になった経済自由化、多党政治化、ヒンドゥー至上主義の台頭といったインド政治の新たな様相の解明にも不可欠な作業である。
第2章
インドにおける政治システムの安定性に関する考察 (401KB) / 三輪博樹
インドでは、有権者の政治参加の手段としては、選挙での投票がもっとも重要であり、また、選挙に対する信頼度も高い。他方で、有権者の団体加入の割合が低いことなどもあって、国家と社会との間をつなぐ政党の役割が重要なものとなっている。また、現在のインドの中央政局における政党システムは、インド国民会議派とインド人民党(BJP)を中心とした2極的な構造となっており、現在のところ、比較的安定した状態を維持している。しかしその一方で、民主主義の「実質的」な面における問題や、カーストや宗教などの違いによる対立など、安定した民主主義体制を維持していく上で不利と思われる要素も多い。
このような状況に対しては、肯定的な評価と否定的な評価の両方が可能であるが、本論ではより肯定的な立場をとる。すなわち、社会的・政治的に不利な条件のもとでも、一定の要素がそろえば、少なくとも政治システムのレベルでは安定を維持することができると考えられ、それを肯定的に評価すべきであるという立場である。インドにおけるそのような要素としては、第1に、選挙政治に関する特徴が考えられる。第2に、インド国内の地域的多様性が考えられる。最後に、インドの政党政治の特徴と、インドが採用している
連邦制という政治制度が持つ機能が考えられる。今後は、これらの要素の特徴やその働きについて、より詳細かつ実証的に検証していくとともに、政治システムにおける安定性を民主主義そのものの安定性につなげられる可能性や、その手段についても検討していきたい。
このような状況に対しては、肯定的な評価と否定的な評価の両方が可能であるが、本論ではより肯定的な立場をとる。すなわち、社会的・政治的に不利な条件のもとでも、一定の要素がそろえば、少なくとも政治システムのレベルでは安定を維持することができると考えられ、それを肯定的に評価すべきであるという立場である。インドにおけるそのような要素としては、第1に、選挙政治に関する特徴が考えられる。第2に、インド国内の地域的多様性が考えられる。最後に、インドの政党政治の特徴と、インドが採用している
連邦制という政治制度が持つ機能が考えられる。今後は、これらの要素の特徴やその働きについて、より詳細かつ実証的に検証していくとともに、政治システムにおける安定性を民主主義そのものの安定性につなげられる可能性や、その手段についても検討していきたい。
第3章
インド憲法改正およびその関連法令とこれに関わる最高裁判例 - 第93 次改正を例に - (309KB) / 浅野宜之
インド憲法について検討するにあたり、その手がかりとなるのが憲法改正である。そして、過去94回にもおよぶ憲法改正について検討する中で、インド憲法に関して重要な論点である「憲法の基本構造」の問題に当たる。この「憲法の基本構造」は、たとえ議会であっても改正のなしえない部分ということで、憲法改正のみならず、インドの統治機構あるいはインド司法について考察する際にも、重要な論点となるものである。
本稿では、インド憲法とその改正について考えるにあたり、2005年になされた憲法第93次改正を取り上げ、憲法改正法とこれに対応して制定された法令、なかでも2006年連邦教育機関(入学における留保)法を検討の対象とし、憲法改正に関していかなる議論がなされ、これに対応していかなる立法がなされたのかを概観した。そして、これらの立法に対して批判的な立場から提起された訴訟について検討し、その中でいかなる論点が提示されているのか、概観する。論点毎に今後精査は必要であるが、そうした検討を通じて、インド司法のあり方や憲法の全体像の把握につながるものと考える。
本稿では、インド憲法とその改正について考えるにあたり、2005年になされた憲法第93次改正を取り上げ、憲法改正法とこれに対応して制定された法令、なかでも2006年連邦教育機関(入学における留保)法を検討の対象とし、憲法改正に関していかなる議論がなされ、これに対応していかなる立法がなされたのかを概観した。そして、これらの立法に対して批判的な立場から提起された訴訟について検討し、その中でいかなる論点が提示されているのか、概観する。論点毎に今後精査は必要であるが、そうした検討を通じて、インド司法のあり方や憲法の全体像の把握につながるものと考える。
第4章
インド労働組合の政治経済論と非組織部門労働者の組織化 - 文献サーベイ - (463KB) / 太田仁志
小稿では、インド民主主義のコンテキストにおける労働組合のありようについて、労働組合を政治経済論の議論の中で位置づけること、そして非組織部門労働者の組織化に関する労働組合の取り組みを明らかにすること、という2つの観点から文献整理を行った。政治政党系列下の労働組合ナショナルセンターは必ずしも労働者の立場に立った労働運動を展開できていない。また、労働組合は非組織部門労働者の組織化の重要性は認識しているものの、組織化に成功しているとはいえない。労働組合は社会組織の取り組みから学ぶべ
きことがあるが、労働に関する取り組みについては、社会組織は労働組合に代替するものではないと考えられる。
きことがあるが、労働に関する取り組みについては、社会組織は労働組合に代替するものではないと考えられる。
第5章
インドにおける分権化の進展とパンチャーヤト政治への住民参加 (411KB) / 森 日出樹
インドでは1993年の第73次憲法改正を受けて、地方制度(パンチャーヤト制度)改革への新たな取り組みが始まる。パンチャーヤトに地方自治体としての地位が与えられ、権限の委譲が進められると共に、パンチャーヤト(地方議会)における指定カースト/指定部族(SC/ST)や女性への留保議席制度の導入、有権者全員が参加できる村民会議の設置など、幅広い住民(特にこれまで政治の意思決定過程から排除されてきた人々)の参加による地方政治の民主化が図られてきた。本稿では先行研究のレビューを行いながら、制度改革により分権化の進展さらにはパンチャーヤト政治への住民参加(パンチャーヤト政治の民主化)がどの程度促進されてきたのかを考察する。
パンチャーヤトへの権限委譲・分権化の進展に関しては、州政府の裁量によるところが大きいため、州によりその取り組みに温度差が見られ、必ずしも州間で足並みがそろわないのが現状である。また、地方自治に欠かせない自主財源の乏しさも指摘されている。住民参加に関しては、留保議席の導入は社会的に不利な立場に置かれてきた人々にパンチャーヤト政治への参加の機会を与えることになった。パンチャーヤト議員の属性においても、脱エリートの傾向がうかがえる。しかし、その一方で、議員としての役割を果たしていない議員の存在が目立ち、エリートによるパンチャーヤト政治の支配も指摘されている。村民会議においても、機械的に開催される傾向があり、住民の議論の場となっていないことが様々な事例研究から伺える。開発(行政)の効果や効率性の向上が必ずしも分権化の推進や住民参加を必要とするものではないことも示唆されているが、分権化と住民参加に力を入れてきたケーララ州や西ベンガル州においては全般的に見て比較的公正な貧困削減政策が実現されていることも事実である。しかし、そうした州においても支持政党に基づく住民の過度の分断や対立がより幅広い住民の参加や対話を困難にさせているとも考えられる。
パンチャーヤトへの権限委譲・分権化の進展に関しては、州政府の裁量によるところが大きいため、州によりその取り組みに温度差が見られ、必ずしも州間で足並みがそろわないのが現状である。また、地方自治に欠かせない自主財源の乏しさも指摘されている。住民参加に関しては、留保議席の導入は社会的に不利な立場に置かれてきた人々にパンチャーヤト政治への参加の機会を与えることになった。パンチャーヤト議員の属性においても、脱エリートの傾向がうかがえる。しかし、その一方で、議員としての役割を果たしていない議員の存在が目立ち、エリートによるパンチャーヤト政治の支配も指摘されている。村民会議においても、機械的に開催される傾向があり、住民の議論の場となっていないことが様々な事例研究から伺える。開発(行政)の効果や効率性の向上が必ずしも分権化の推進や住民参加を必要とするものではないことも示唆されているが、分権化と住民参加に力を入れてきたケーララ州や西ベンガル州においては全般的に見て比較的公正な貧困削減政策が実現されていることも事実である。しかし、そうした州においても支持政党に基づく住民の過度の分断や対立がより幅広い住民の参加や対話を困難にさせているとも考えられる。
第6章
インドにおける現代のヒンドゥー・ナショナリズムと民主主義 - 研究レビュー - (430KB) / 近藤則夫
インドでは1980年代以降、コミュナル暴動の頻発化、ヒンドゥー・ナショナリズムの昂揚がみられ、民族奉仕団やインド人民党といった、いわゆるサング・パリヴァールの活動が目立ってきた。本稿では近年のヒンドゥー・ナショナリズム研究の主なものを筆者の視点から整理し、ヒンドゥー・ナショナリズムの現状を把握し、研究、特にインドの民主主義におけるヒンドゥー・ナショナリズムの位置づけに関する研究において何が問題となっているのか把握しようとするものである。研究状況の検討の結果、歴史、政治史、現代政党政治などにおいては、ヒンドゥー・ナショナリズムの研究は実績を上げており、例えば1980 年代以降の会議派システムの衰退による政治的隙間の拡大がヒンドゥー・コミュナリズムやヒンドゥー・ナショナリズムの昂揚の大きな要因であったことなどを明らかにしている、と言えるであろう。しかし、その社会との関わり、例えば、社会各階層のヒンドゥー・ナショナリズムへの反応などに関してはまだまだ不十分であるし、社会の他の運動、例えば「その他後進階級」の運動などとの関連も分析は不十分である。ただ社会との関わり合いでヒンドゥー・コミュナリズムやヒンドゥー・ナショナリズムが最も先鋭に現出するコミュナル暴動に関しては、その重要性の故に、重要な研究が多く存在する。最後にこれまでの研究をふまえてヒンドゥー・ナショナリズムの今後の展開には、それが「全てを包括」しようとする運動であるかぎり、言説レベルでの限界、そして、コミュナル暴動の限界という2 つの大きな限界が存在し、少なくとも「全てを包括」することは不可能との暫定的結論を提示した。
第7章
インドにおけるナクサライト研究 (326KB) / 中溝和弥
社会経済的解放を実現するために暴力革命を掲げる政治勢力が、議会制民主主義に参加する条件は何だろうか。途上国の中で例外的に民主制をほぼ一貫して維持してきたインドにおいて、40 年間に及ぶナクサライト運動の存続は、自由と平等を必ずしも十分に実現してこなかったインド民主主義の問題点を浮き彫りにしている。これまでのナクサライト研究は、インド民主主義とナクサライト運動を二項対立的に対置して、インド民主主義の偏向を暴くことに関心を集中してきた。
しかし、ナクサライト運動の展開を振り返れば、インド民主主義とナクサライト運動は常に対立関係に立つのではなく、逆に議会制への参加が常に課題となっていたことに気付く。議会制と運動を対立関係として捉えることに縛られていた既存研究は、必ずしも議会制と運動の相互作用を十分に検討してこなかったが、政府と毛派の暴力的対立が激化する現在においてこそ、相互作用を検討し、暴力革命を掲げる政治勢力が議会制民主主義に参加する条件を探ることが求められている。
しかし、ナクサライト運動の展開を振り返れば、インド民主主義とナクサライト運動は常に対立関係に立つのではなく、逆に議会制への参加が常に課題となっていたことに気付く。議会制と運動を対立関係として捉えることに縛られていた既存研究は、必ずしも議会制と運動の相互作用を十分に検討してこなかったが、政府と毛派の暴力的対立が激化する現在においてこそ、相互作用を検討し、暴力革命を掲げる政治勢力が議会制民主主義に参加する条件を探ることが求められている。
第8章
インド北東地方の民族運動: ナガ民族について (569KB) / 井上恭子
インド北東地方は、イギリス植民地時代を経て独立後の政治的展開の過程で、「特殊、個別」的扱いを受けてきた。そのことにより植民地時代にはインド本体との一体感が希薄であった。また、多民族、多言語、しかも多数の少数民族を擁する住民構成は、それぞれの民族がそれぞれの特性の保持あるいは居住地域の確保、権限の拡大を求める動きを生んできた。これらの動きは、「インドからの独立」の主張を生み、その主張が満たされないことで極端な場合、反政府武装運動に向かった。
本章ではナガ民族をとりあげて検討する。イギリス植民地時代に隔離的な扱いをされてきたナガにとって、1947年のインド独立に際してインドとの併合が唯一絶対の選択肢ではなかった。ナガは、まず自治の確保を求めたが政府は弾圧的方法で対応した。ナガは、政府への不満を募らせ、反政府武装闘争・独立闘争を展開した。ナガの運動は、1950年代半ばから1970年代にかけての激しい武装闘争を経て、1997年以降は政府と武装組織の話し合いがもたれ、停戦で合意が成立、現在、和平会談が進んでいる。現在の「ナガの和平」は、中央政府にとってはナガ武装グループを北東地方の他の武装グループから切り離す積極的な意味がある。またナガの武装グループにとっては、「独立」を掲げて対立の姿勢を保持しながら、中央政府と話し合い停戦を継続することに利益を見出していると考える。紛争・対立状態の継続つまり「停戦と話し合いの状態」の継続が政府にとって利益で、武装勢力にとっては既得権益の保持に有利という奇妙な状況が生まれている。
本章ではナガ民族をとりあげて検討する。イギリス植民地時代に隔離的な扱いをされてきたナガにとって、1947年のインド独立に際してインドとの併合が唯一絶対の選択肢ではなかった。ナガは、まず自治の確保を求めたが政府は弾圧的方法で対応した。ナガは、政府への不満を募らせ、反政府武装闘争・独立闘争を展開した。ナガの運動は、1950年代半ばから1970年代にかけての激しい武装闘争を経て、1997年以降は政府と武装組織の話し合いがもたれ、停戦で合意が成立、現在、和平会談が進んでいる。現在の「ナガの和平」は、中央政府にとってはナガ武装グループを北東地方の他の武装グループから切り離す積極的な意味がある。またナガの武装グループにとっては、「独立」を掲げて対立の姿勢を保持しながら、中央政府と話し合い停戦を継続することに利益を見出していると考える。紛争・対立状態の継続つまり「停戦と話し合いの状態」の継続が政府にとって利益で、武装勢力にとっては既得権益の保持に有利という奇妙な状況が生まれている。