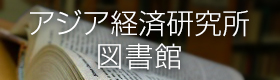出版物
ピックアップ
【著者インタビュー】「アウェーな環境が私を鍛えてくれた」2021年度水資源・環境学会賞受賞 大塚健司研究員に聞く
『中国水環境問題の協働解決論――ガバナンスのダイナミズムへの視座――』
大塚 健司 著
2019年8月発行
ISBN:978-4-771-03225-5
大塚健司研究員の著書『中国水環境問題の協働解決論――ガバナンスのダイナミズムへの視座――』(晃洋書房、2019年)が「2021年度水資源・環境学会賞」を受賞しました。20年以上にわたる中国の水環境問題研究を1冊にまとめるまでの歩みを本人に聞きました。

―― おめでとうございます。思いがけない受賞だったとか?
そうなんです。まったく予想していませんでした。というのも、直前の2020年度はコロナ禍の影響もあって表彰自体がなかったんですね。この本は2019年に出したものですから、直後の2020年度にお声が掛からなかった以上はもう対象にならないだろうと思っていたんです。ところが次の2021年度での受賞と聞いて、とても驚きました。でも率直にうれしく思いました。
―― 水資源・環境学会はどんな学会ですか?
この学会は、国内外の水資源・環境問題に関心を持つ幅広い分野の研究者の集まりです。日本の水資源・環境問題の研究といえば琵琶湖・淀川流域をフィールドにした学際的な研究の蓄積がたくさんありますが、この学会でもそうした具体的なフィールドに基づく研究報告のほか、最近の例ではSDGsや水害との関係など実践的な課題についても活発に議論がなされています。私はこの学会とは、2015年に刊行された学会誌の特集「水資源・環境学をどう学ぶか?――若手研究者へのメッセージ」に寄稿を依頼されて以来のご縁となります。
―― どの点が評価されたと感じていますか?
学会長の仲上健一先生(立命館大学)にもおっしゃっていただきましたが、今回の本が20年以上にわたる中国の水環境問題研究の集大成であるというところだと思います。途上国ではよくあることかもしれませんが、とりわけ中国では、水汚染のようなマイナスの側面を外国人が調査することは難しい。また急に調査に入れなくなってしまったかと思えば、しばらくすると何事もなく受け入れてくれたりする。そうした不確実な状況のなかであっても、タイミングや場所、テーマをずらしながら、この研究を続けてきたということが評価されたのだと思います。
もう1つ、私の知る限り中国の水環境問題に関する社会科学分野の類書はあまり多くありません。中国の水問題という形でタイトルに掲げている本はいくつかありますが、本書のような体系的なフィールドワークを踏まえた単著はこれまでなかったのではないでしょうか。そこも評価をしていただいたのかなという気はしています。

―― 現地になかなか行けないというのは歯がゆいですね
私が中国の水問題に関心を持ったのは、アジ研に入所したばかりの1990年代半ば頃、たまたま見かけた日本の新聞記事がきっかけです。そこで中国の淮河(わいが)流域で深刻な水汚染が発生し、沿岸住民の飲み水が確保できなくなるという報道を目にして興味を持ったのですが、水汚染の現場にはなかなか入ることができないでいました。本格的に現地に入ることができたのは、「癌の村」で活動する現地NGOと出会った2004年、その新聞報道から約10年後のことです。さらに、その後は現地の情勢が悪化したこともあって、翌年2回訪れた後にしばらく行くことができなくなりました。2012年の再訪問まで7年間の空白が生じることになります。
それでも、私にはその間に並行して進めていた太湖(たいこ)のプロジェクトがありました。太湖は周辺地域の工業化などに伴って1980年代から水質悪化が進行し、2007年にはアオコが大量発生して水道水の供給が麻痺したところなんですが、私たち研究グループはアメリカのウィルソンセンターや中国の南京大学との共同プロジェクトを通じ、2008〜2011年度の4年にわたって集中的に現地調査を行うことができました。結果として、場所もタイミングも異なるこの2つの事例が、本書のタイトルとなった水環境問題の「協働解決論」につながっていきました。
―― この本は書き下ろしですか?
本書は2018年に筑波大学大学院に提出した博士論文がベースになっています。これまでのフィールドワークで訪れた2つの流域(太湖・淮河)の事例から、中国の水汚染問題を「対話と協働」というコンセプトで解決に導くことができるのではないか、という視点から分析・考察を行いました。それまでにアジ研で発行したレポートや単行書の内容も盛り込んでいます。
太湖の事例では、水汚染問題に関して住民・企業・政府間で話し合う「コミュニティ円卓会議」という社会実験を通じて、対話と協働の可能性を探りました。もう1つの淮河の事例では、地元の環境NGOによる活動が、政府主導の政策と相互作用をみせながら水汚染対策を促進させていく過程を明らかにしています。

―― 博士論文から単行本にする過程で変わったことはありますか
タイトルを少し変えました。博士論文のときは「中国の水環境問題の協働解決に向けたガバナンス」というタイトルだったんですが、単行本にするにあたってメインタイトルから「ガバナンス」という言葉を外して、「協働解決論」という言葉を前面に打ち出しました。
実は以前、別の出版社の新書担当の方とお話をしたときに、私が「ガバナンス」というものに興味がありますと言ったら、ビジネスマンが読むには難しすぎると言われたことがあるんです。それがずっと頭に残っていて、今回の本も私としてはNGOや政策担当者といった現場で実践を行っている人にも読んでいただきたかったので、ガバナンスではなくて別の言葉の方がいいだろうと思っていたんですね。代わりになる言葉がなかなか見つからないまま煮詰まってきたときに、いっそのこと「協働解決論」とするほうがストレートでよいと思うようになりました。
――「連環性」というキーワードも出てきます
「流域」の問題を解決しようとするとき、そこには多様なアクターが存在します。理工系の専門家からすると流域というのはある決められた空間というイメージがあるのですが、社会科学的な視点からすれば一様ではありません。物や人の経済的な活動は分水嶺を軽々と越えていくわけですし、生活文化や歴史的な観点でとらえれば峠のあちらとこちらがつながっていたかもしれない。それぞれのアクターによって流域のとらえ方は異なるのです。
ところが、たとえば行政が考えている流域と、住民やNGOなどがとらえている流域の概念が一致していないことがよくあります。そこにガバナンスの失敗の根源的な問題があると私は考えています。政府、企業、住民、NGOなどの多様な主体が、水文学的、生態学的、経済的、政策的、文化的という5つの次元で、どのようにつながりをもち、どのようなマトリクスを描いているのか、それを流域ごとに明らかにすることが、「流域ガバナンス」の第一歩だと考えています。

――ところで、環境問題は社会科学で解決できるのですか?
それは本当によく議論になることで、同じ年に英語で出版した編著のブックトークでも工学系の専門家から「社会学的なことをやっても解決できないよ」というようなことを言われました。確かに社会科学的なアプローチだけでは解決できないかもしれませんが、一方で、技術があっても解決できていない現場があるという現実を知っていただきたいのです。
例えば太湖流域の農村では、当面の対策として小規模分散型の排水処理施設をあちこちに整備していましたが、設置する場所が明らかにおかしかったり、うまく動いていない施設があったりしました。技術としては正しいんだけれども、適切に使われていない。これをどうやって説明しますか、ということなんです。
それはもちろん、技術の使い方を知らない、知識がないということなんですが、もっと根底にあるのは環境対策に対するインセンティブがないということなんですね。政府はキャンペーン的に号令をかけるんだけれども、資金的な手当てがなく、少なくとも当時は人事評価に目立って反映されるわけでもない。となれば、現場では環境や水処理のことはないがしろになってしまうでしょう。こうした問題に多角的にアプローチできるのが、ガバナンスの研究だと思います。
――社会科学者と理工学者が協働することは可能でしょうか
いろいろと難しいところはありますが、現場ではコラボレーションが進んでいます。例えばあるNPOの活動では、浄化装置を作っているエンジニアと環境ジャーナリストや私のような研究者が一緒に参画しています。最近、お互いの垣根を越えて1冊の本をつくりました。バックグラウンドの違う人たちが、同じ問題解決に対して一緒にコミュニケーションをとっていくことは可能だと思いますし、むしろ環境問題解決への糸口の1つになるはずです。
私が学んできた環境学はまさに、専門の垣根を超え、お互いの橋渡しをしていくという重要な役割を担っています。問題解決を一緒にやろうという人たちと共通の言語と概念をつむいでいくことが私たちの目指すところなんだろう思います。
―― 異分野の人たちとのコミュニケーションは難しいでしょう
これまでずっとアウェーな環境に身を置いてきたので、鍛えられた部分はありますね。私はもともと工学部に入った理系の人間ですが、修士で環境政策を学び、卒業して民間コンサルタントで1年間働いたのちにアジ研に入所しました。最初のころはずいぶん肩身のせまい思いをしたものです。環境問題は理系の研究分野じゃないの?と言われたこともありました。ところが20年以上経って博士号取得のために大学院に戻ってみたら、理工系の先生からかなり叩かれて、そこでまたアウェー感を感じてしまう(笑)。毎日が、どうやって異分野の人に自分の考えをわかってもらうか、その試行錯誤と鍛練の積み重ねでした。でも、結果的に私はそこで鍛えられたんです。今ではそのアウェーな環境こそが私のフィールドで、学際的な学問である環境学の主戦場なのだと思っています。
(取材日:2021年9月9日)
(聞き手:池上健慈、写真撮影:長峯ゆりか)