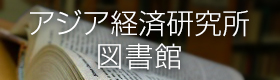出版物・報告書
報告書・レポート
トピックリポート
No.33
[緊急レポート]「スハルト体制の終焉とインドネシアの新時代」
第1章 多難なインドネシアの新時代
32年に及ぶインドネシアのスハルト政権が崩壊した。「開発の父」と讃えられたスハルト前大統領のインドネシア経済の開発は評価されるが、その長期政権そのものに腐敗、癒着及び縁者びいきに基づく制度疲労が生じ、その統治能力の再生は不可能になった。折しも、97年7月に発生したアジア通貨危機はインドネシアを最大の餌食とし、スハルト体制の開発の成果を台無しにしてしまった。ルピアの価値は1年間で6分の1に減価し、経済・金融システムは崩壊し、国民の2人に1人が経済的窮乏に陥った。強権体質で進めてきた開発体制はその内部から否定されたと言える。改革の主役はウィラント国軍司令官主導の国軍であり、その支持を背景にハビビ新政権が動き出した。新政権をいかに評価し、その方向を探ることが今後のインドネシアを理解する上で重要である。
1. スハルト退陣の意義
1-1. スハルト体制の崩壊とウィラント国軍司令官の役割
98年5月21日、スハルト前大統領は、ハビビ前副大統領に大統領職を委譲した。32年の安定政権はもろくも崩れ去り、スハルト氏は側近政治家及び親族もろとも政治、社会及び経済活動から一斉に退かねばならない状況に追いつめられた。スハルト失脚とともにハビビ副大統領も当然その職を解かれるとの下馬評であったが、大統領の交代を「1945年憲法」に則って行うという国軍の意向によって、ハビビ氏がかろうじてその政治生命を維持することができた。その背景としては、憲法上の規定ではハビビ氏以外に後継大統領の有資格者がいないということもあったが、実際には現在のインドネシア政治情勢を完全に把握できる人物が未だに登場していないということである。今回の政変の立役者ともいえるウィラント国軍司令官兼国防治安大臣は、スハルト後継者のダークホース的存在として早くから各界の期待がかけられてはいたが、同司令官が一挙に大統領に昇格するには時期尚早であった。その理由は、5月初旬の北スマトラの州都メダンにおける暴動、12—17日におけるジャカルタでの約1200人の犠牲者を伴った大暴動、その他全国各地での反政府デモなどが、ウィラント国軍司令官とスハルト氏の娘婿であるプラボウォ戦略予備軍(KOSTRAD)司令官を両雄とする国軍内部の対立があったことである。この対立は一応ウィラントグループに軍配が上がった。しかし、謀略によって暴動を誘発させた疑いがあり、21日に解任されたプラボウォKOSTRAD司令官に対する処遇は甘いもので、彼は陸軍中将の階級では名誉あるバンドンにある国軍士官学校校長に任命された。もちろん、このポストは直接の指揮権を発動できる実戦部隊を持たないため、プラボウォ本人にとっては不満であったと伝えられる。プラボウォ司令官が力の源泉とした特殊部隊(KOPASSUS)はKOSTRAD直轄からはずされ、組織編成上は陸軍参謀長の下に置かれ、その指揮権は国軍司令官が有することになった。しかし、プラボウォ中将と政治的に近いと言われていたファイサル・タンジュン現政治担当調整大臣はハビビ新内閣にとどまり、スバギオ陸軍参謀長、シャフリ・ジャヤ師団(ジャカルタ)司令官などの更迭が未だないことにも留意するべきである。
1-2. ハビビ新政権の不安定要因
スハルト辞任と、プラボウォ中将の更迭及び12日にトゥリサクティ大学学生デモ隊に発砲してジャカルタ暴動のきっかけを作った17名の軍人を裁判にかけるだけに留まった事後処理は、ハビビ大統領就任という政治的妥協の一特徴を示す。98年1月にハビビ副大統領有力説がでただけで、ルピアの対米ドルレートが1日で40%も暴落したほどの不人気ぶりに示されるとおり、ハビビ新大統領の政治的基盤は脆弱である。すでに、新大統領就任の合法的手続きを確認するための国民協議会特別会議開催や総選挙実施のための準備日程、およびその手続きを巡り各界からのハビビ批判が多出している。ハビビ大統領としてはこれらの日程をできる限り先延ばしして、その政治生命の維持を望んでいる。
新政権の基盤が固まりにくい原因はどこにあるのだろうか。第1に、最大の理由は権力の最大の担い手である国軍内の勢力バランスが流動的であることだ。ウィラント国軍司令官が、今後プラボウォグループの一掃に成功し、国軍の全権を掌握できるかどうかがキーポイントになろう。しかし、一層やっかいなことは、スハルト退陣と引き替えに、ハビビ擁立を条件としてウィラント国軍司令官に協力した軍人グループが存在する可能性があることだ。6月上旬の段階では国軍内主要ポストの人事異動が進んでおらず、ウィラント司令官の今後の人事権発動を注視する必要がある。この論拠は、ハルモコ国会議長のスハルト退陣勧告に対し、ウィラント司令官がそれを「個人的意見」と退け、スハルト追い落としを一時留保したのは、ハビビ擁立派の態度が明確でなかったことと、5月19日の時点でプラボウォ麾下のKOSTRADを掌握し切れていなかったと推測されることにある。この段階でことを急げば武力衝突の危険性もあったと思われる。しかし、ウィラント派は、20日のオランダに対する蜂起を記念する「民族覚醒の日」に予定された100万人規模の反政府集会を取りやめさせたことを通じプラボウォ派の力を完全に制圧すると、その夜の内にスハルトを退陣に追い込む条件を整備することができた。その過程で、ハビビ擁立派はプラボウォを見捨て、ウィラントへの協力に傾いたものと思われる。これを急がせた要因は、米国のオルブライト国務長官のスハルト辞任勧告を意味する「スハルト大統領は歴史に残る名誉を得る機会を得ている」という発言であった。勝ち馬に乗ることでスハルト一族とともに沈没船に残ることを避けるインドネシア特有の政治パフォーマンスがあったといえよう。これは国軍内の潜在的対立を残すことになった。
第2に、民主化勢力が分裂状態にあることである。スハルト辞任の背景には3月以降に高まったスハルト前大統領、その親族及び取り巻きグループに対する、知識人・学生などの直接名指しの批判と退陣要求があった。それ以前のデモや暴動では対政府直接批判はあったが、スハルト個人に対する攻撃は初めてであった。スハルト氏にとってもこれは内心穏やかであったはずはない。しかし、この批判運動も連携的で、全国同時多発的ではあったが、必ずしも一定の戦略下で組織化されたものではない。指導的立場にあった、都市部の改革派であるムハマディア議長のアミン・ライス氏、農村部で影響力のあるナフダトゥール・ウラマ(NU)総裁のアブドル・ラフマン・ワヒド(通称グス・ドゥル)及びインドネシア民主党のメガワティ前総裁らの表向きの連携は見られたが、それは反スハルトで一致しただけのことで、スハルト後のそれぞれの政治的思惑は異なる。グス・ドゥルは比較的ハビビ新政府に対して肯定的な姿勢を示し、メガワティもアミン・ライスの急進的な民主化要請とは一線を画して、スハルトに対する性急な中傷を心痛いこととして退けている。ウィラント司令官もメガワティと同様の発言をしている。メガワティとしては過激な民主化運動がせっかくのスハルト退陣の成果を台無しにすることを懸念しているのであろう。グス・ドゥルは、これまで継続してきたNUの非政治団体路線を守り、NU内部の政党化運動を抑えたいところである。こうした不統一はハビビ新体制の背後にある国軍が、内からの改革路線を推進するにあたって、調整に時間を要するという結果をもたらすことになろう。また、急進改革グループの活動が再び暴発し、政治的に利用される最悪の可能性も想定しておかなければならない。
2. ハビビ新政権の課題
2-1. 急がなければならない信頼の回復
ハビビ新政権にとって、国家経済の再建を急ぐためには、とにかく政治の安定が第一条件である。しかし、96年のメガワティ・インドネシア民主党総裁の引き下ろしの責任を問い、シャルワン・ハミド内務大臣の辞任を求める学生など急進グループによる政府批判は、政権内部の勢力バランスにも影響するであろう。同内相はハビビ大統領に近い人物とされている。また、政変以降にもメダンやスラバヤなどの地方都市では労働組合のデモなどが発生しており、治安当局と衝突し、死傷者が出ている。こうした状況から、IMFはコンディショナリティーの見直しを理由に援助資金の引き出しを遅らせている。早くとも7月にならないと援助の実施ができないとの情報が飛んでいる。バクリー・インドネシア商工会議所会頭も大統領に対して、国際的信頼を回復するために大使級のミッションを各国に派遣するように6月9日に勧告した。これについてはハビビ大統領も了承したが、問題はミッション派遣によるインドネシアの苦しい現状の説明だけでは国際的信頼の回復はできないことだ。
経済再建に関してハビビ政府がやるべきことは、明確かつ実効性のある緊急再建プログラムを作成することである。すでにそのための下敷きとしてIMFのコンディショナリティーがあるが、これがインドネシア経済の実状にそぐわない部分が多かったために実行可能性という点で難点があった。インドネシア政府は財政補助金の削減を急ぐために、石油製品の大幅値上げをしたが、これが経済困窮下にある庶民の生活を脅かし、5月の暴動のきっかけになったことは明らかである。プログラム作成に際しては、IMF、世界銀行、アジア開銀等の国際金融機関の協力も必要であるが、インドネシアが主体性を持つことが重要である。経済再建の最初の難関である約800億ドルの民間債務問題も、6月上旬の国際銀行団との交渉で4年から8年の返済猶予となり、再建プログラム作成の条件整備が進んでいる。スハルト退陣により、KKN(腐敗、癒着及び縁者びいき)など従来のしがらみを断ち切り、斬新かつ合理的な政策立案の条件は整ったのである。残念ながら、新たに組閣された開発改革内閣はブディオノ国家開発企画庁(Bapennas)長官等の少数を除いて、閣僚の顔ぶれに新味が少ないことが気がかりである。若手の新人テクノクラートの登用が必要であるが、積極的にハビビ政権に参画しようとする人材は多くないようだ。
2-2. 経済再建実行に必要な政治的浄化
政変によりスハルト一族への報復的行動は急である。原油の独占輸入権など石油公社(プルタミナ)関連の一族への特権はすべて剥奪された。一説には一族全体で240億ドルといわれる蓄財疑惑の解明を迫る声も高まっており、また、一族は官民の要職を辞任せざるを得なくなっている。また、スハルト最大の癒着パートナーとして一世を風靡したサリム・グループの凋落が急である。国有銀行を含めてインドネシア最大の資産を有したバンク・セントラル・アシア(BCA)も、暴動最中には略奪の対象になり、その後は全国規模での取り付け騒動に襲われ、破産状況に陥った。サリムグループは多額の資産を海外に逃避させたと言われるが、インドネシアへの復帰は望めないであろう。インドネシアの政治文化・風土からすると、スハルト一族に対する報復行動は厳しくならざるを得ないが、実権を握るウィラント国軍司令官は法に基づく措置を執るとして一族擁護の柔軟姿勢を見せている。一族に対する糾弾は厳しいが、政変前にはミニ・スハルトとして不評だったハビビ新大統領に対する批判はあまり高まっていない。いまスハルト一族以外の蓄財問題を取り上げることは、政治基盤の弱い現政権にとってタブーなのかもしれない。しかし、国内外の信頼を得るためには近い将来にこの問題を白日に晒す必要があろう。
2-3. 民主化の限界
いわゆるKKNの問題は32年に及ぶ長期政権下での強権的政治の副産物であり、民主化を望む国民の批判の的になったことは当然である。学生や知識人グループが民主化運動の中心であり、特に、3月以降のスハルト本人を直接批判する示威行動は政権交代の圧力になった。ただし、かかる民主化運動が統一的に組織化されていたかは疑問である。学生組織間のインターネットでの情報交換が活発であったことや大学教官の支援も目立ったが、彼らがスハルト退陣とKKN糾弾以外に具体的に何を主張したかについては明確ではない。事態をより複雑に見せる要因はアミン・ライス・ムハマディア議長をはじめとするイスラム指導者の影響が強く、民主化運動と宗教的正義感からくる改革運動が混在していたことである。こうした要因は民主化運動を表面的には高めたようだが、暴動の発生によって民主化運動は一次埋没した。この背景には、本来民主化運動を支えるべきインドネシアの中産階級の未成熟がある。一般的にはインドネシアの中産階級は人口の7%程度といわれ、そのうちの半数が政治的に無力化されている華人系インドネシア人である。ハビビ新政権になり、反政府活動家、東ティモール独立運動指導者などが次々に釈放され、政党結成の自由化、労働組合運動の自由化等、民主化政策が打ち出されている。これらは民主化運動の要請に応える措置であるが、国軍の政治路線の転換に促された結果でもある。ハビビ新政権がウィラント国軍司令官主導の国軍のバックアップによって成立したという現実は、体制内からの民主化があったことを意味する。それはハビビ大統領が言うように民主化ではなく「改革」であり、新内閣も3月に発足した第7次開発内閣を継承する「開発改革内閣」と定義づけられている。今後は国軍も開かれた政治路線を踏襲すると思われるが、国軍が権力の主要な担い手であり続けるのならば、民主化の方向には限界があろう。国軍が内からの自己改革をどこまでできるのかが、インドネシアの民主化を決定づける。
2-4. 制度改革と総選挙の実施
スハルトからハビビへの大統領職の委譲は1945年憲法に基づくもので一応合法的であるが、法的には、任期途中での大統領の辞任という「非常事態」に対する緊急措置として位置づけられる。ハビビ大統領が本格政権を築こうとするならば、改めて国民協議会でハビビ大統領の就任が承認されなくてはならない。そのためには総選挙の実施が不可欠である。ハビビ政府は現在、1999年5月に予定される総選挙後、年末に国民協議会を開催する意向のようである。批判グループの一部が要求する選挙前の国民協議会開催の場合、現国民協議会議員のステータスをどうするのかという問題が生じる。ウィラント司令官はその家族の議員辞任を発表しているし、次々と辞職議員が出ている。ハビビ大統領も99年12月の国民協議会では縁者びいきに基づく議員の選出はしないと言明している。しかし、議員定数1000人中200人以上がスハルトの縁故議員であり、長女のトゥトゥット(通称)ら近親をはじめ多くの議員が辞職を明らかにしていない。この問題だけでも容易に解決できそうにもない。また、民主化グループからは総選挙早期実施の要望が高まっている。実際のところ、法規に基づき総選挙を実施するためには、選挙法、政党法など関連政治諸法の改正が事前に必要であり、さらに、選挙実施の具体的準備のために時間が必要であるから、政府としては早期実施には踏み切れない。しかし、ハビビ大統領に対する批判は根強い。批判グループの言い分は、総選挙を先延ばしすることでハビビ政権の延命が図られるのではないかということである。大統領の職権は重大であり、諸制度改革と総選挙実施の過程で、ハビビ大統領がその権力を強化する可能性は大きい。もちろん、そのためには、大統領自身が身辺浄化をし、国民の信頼を得なければならない。
3. 新しいインドネシアの課題
3-1. 1945年憲法とパンチャシラの政治道具化
スハルト前大統領が支配体制を強化する道具として利用してきたイデオロギーは1945年憲法の前文にある建国五原則「パンチャシラ」である。すなわち、全知全能の神への信仰、公正にして善良な人道主義、インドネシアの統一、代表者間の協議による全会一致の叡知によって指導される民主主義、及び全インドネシア国民に対する社会正義である。スハルト政府は1978年にパンチャシラの理解と実践の指標を採択し、これに背くことは反逆として、強権支配のための政治的道具として利用してきた。国家転覆罪、大統領侮辱罪などはその法的表現であり、民主化の動きをことごとく封じてきた。現在、改革あるいは民主化の声が高まる中で、政治関連諸法の改正、政治犯の釈放や名誉回復、報道の自由化、結社の自由化などの要求が出ているのは、スハルト支配体制に対する批判と反動である。いずれはスハルトによる憲法とパンチャシラのねじ曲げがあったとして憲法解釈の是正があろう。しかし、憲法の改正などによる国体の変更はないであろう。その理由は、国軍が政治経済に関与することを正当化する「二重機能」を温存する必要性が高いからである。
3-2. SARA問題と国軍内部抗争
SARAとはインドネシアが国家の社会政治的タブーとしてきた問題である。これは、種族問題、宗教問題、人種問題、社会政治勢力間の問題(あるいは国軍内部の問題)の4つのインドネシア語の頭文字をとった略語である。SARAは暴動の際にもっとも目に見える発現をする。華人街の襲撃略奪は人種問題であり、華人襲撃はモスレムとクリスチャンあるいは仏教徒との宗教間抗争となり、暴動の背後には必ず国軍内部の権力闘争がある。また、東ティモールの独立運動はジャワ人の東ティモール支配への反発とモスレムとカトリック教徒の抗争として現れる。スハルト前政権はSARAを触発する行動は厳しく弾劾してきたが、ハビビ政府も間違いなく同様の姿勢をとる。ウィラント司令官も改革に名を借りた破壊行為に厳しい対処をすると明言している。しかし、「国軍内部の問題」とかっこ付きで示される問題は批判グループの見解であり、国軍は決して容認しない表現である。国軍の建前は内部問題がないことになっているからだ。しかし、過去、10年に1度の頻度で発生した反日暴動(74年)、ジャカルタイスラム暴動(83年)、メダンの反華僑暴動(94年)等の背後には常に国軍内部の権力闘争があり、これがSARA問題発現の最大の要因となっている。今回のスハルト失脚が国軍内の亀裂とジャカルタ暴動をきっかけにしたと言う観点からすると、SARAは明らかにスハルト体制のタブーであったといえる。ハビビ体制もスハルト体制同様にSARAからフリーではない。改革がどこまで進められるかは別として、スハルトが30余年の間に強化してきた体制とそれをバックアップしてきた国軍の体質は容易に変えられるものではない。現在国軍は一応の統制はとれているとはいえ、ウィラント司令官が完全に国軍を掌握し、その改革路線を実施するためには時間が必要である。更迭されたプラボウォ前KOSTRAD司令官も6月10日のハビビ大統領と国軍首脳との会議に出席しており、依然として一定の地位を有しているようだ。99年5月と同年末にそれぞれ予定されている総選挙実施と国民協議会開催をめぐって内部抗争が再燃する可能性がある。ハビビ大統領が続投できるのか、あるいはウィラント司令官が取って代わるのか、予断はできない。いずれの場合でもその決着は国軍の統一と支持にかかっている。ハビビ大統領は次の国民協議会に「みずから」立候補しないと明言したが、同大統領としては、現在与えられた大統領職権をフルに活用し、ハビビ政権の強化と国軍その他の支持を取り付け、続投体勢を準備したいところであろう。そのためには、ハビビ大統領としては総選挙と国民協議会をできるだけ遅らせて、時間稼ぎが必要である。
3-3. 国軍の二重機能
国軍内部の権力闘争が生じた場合、二重機能論争が表面化することは経験的に明らかになっている。二重機能とは国軍の民政への関わり方についての政治路線を意味する。この路線は国軍が常に政治の中心的役割を果たすという基本を維持し、決して近代西欧諸国型の文民支配体制を意味していない。その根拠は、国軍がオランダ植民地からのインドネシア解放のために国民とともに闘った人民解放軍的存在と自認しているところにある。論争の焦点は国軍がどのような方法で二重機能を果たすべきかに当てられている。近年の論争は、ジャワ語で「トゥトゥ・ウリ・ハンダヤニ」のスローガン、すなわち国軍は後方より社会及び政治活動を支援するという低姿勢の中身をめぐるものであった。実際にはこのスローガンが実態と乖離し、ファイサル・タンジュン前国軍司令官の時代には国軍がすべての社会・政治グループを従える形で力の政治をしてきたことに反発が強まった。その典型的な例が、民主的方法で選出された元スカルノ大統領の長女メガワティ・インドネシア民主党総裁が国軍の介入で解任され、その後にジャカルタでの「民主党暴動」が発生したことである。こうした高圧的姿勢がスハルト政権の末期的症状を示していたことは明らかである。権力の主要な担い手である国軍の内からの改革の動きがあって当然であり、これが今回の政変につながった。
ウィラント司令官に代表される現在の国軍の二重機能に関する理解は、民主化の必要性を認める改革路線である。もちろんこれには「秩序ある改革」を維持し、国家を不安定にする無責任な活動を許さないとする限定付きのものである。たとえば、東ティモール独立運動の集会などには厳しい弾圧がされている。二重機能論争の中身については、従来あまり明確に開示されてこなかったが、今回は国軍も国内外の理解と信頼を得るために明確化する必要が生じたようだ。スハルト辞任後間もない5月25日、スシロ・バンバン・ユドヨノ政治社会担当参謀長は記者会見で国民の改革期待に沿う二重機能の見直しを明らかにした。同参謀長はウィラント司令官の懐刀であり、現在の国軍のトップイデオローグといわれる。新しい二重機能とは、(1)国軍が従来のように常に政治の先陣にある必要がないこと、(2)国軍は、歴史的経緯から重要な地位を占めてきたが、今後は、よりよい目的に向けて影響力を有する地位に立つように変革する、(3)国軍は直接的な方法で社会政治勢力に影響力を行使してきたが、今後は間接的な影響力を維持する、(4)国軍は国軍以外の勢力との友好関係を基礎に政治的役割分担を行う、の4点である。ユドヨノ参謀長の発言は今後の国軍の政治関与の方向を示すが、これが国軍内で合意されたかどうかは未だ明らかでない。しかし、改革はすでに国際的にも約束されており、これを実施できない限りインドネシアに対する信頼の回復はなく、不安定状態が長引くことになる。
3-4. 国際協調の維持が不可欠
政治的安定を達成し、早急な経済再建を成功させるためには国際的支援を取り付けることが肝要である。97年10月以降、430億ドルのIMFパッケージ支援の実施をめぐりIMFとの関係がぎくしゃくし、結果的に経済混乱を深化させてしまった。この背景にはIMFの政策介入の硬直性があったと言えるが、最悪の要因はスハルト政府の改革の意志がきわめて希薄だったことである。IMFが提示した丁子流通独占、合板カルテルなど独占的商慣行の撤廃を含む援助条件は、スハルト一族およびクローニーに対し特権の放棄を求めるものであり、スハルト政権には絶対にのめない条件であった。だがIMFにとっては、財政の透明性確保などとともに、スハルト一族らへの特権付与による歪みの是正が、インドネシア政府を信頼するための最低条件であった。政変の結果、スハルト一族の特権が一気に剥奪されたため、インドネシア及び国際社会の間の相互理解の第一条件はすでに整った。6月はじめには懸案であった約800億ドルの民間債務問題も3年据え置きで、4年から8年の返済期間延長が合意され、IMF融資の実施交渉も進められるようになった。昨年の1人あたり1300ドル強の国内総生産額が単純計算では200ドル台に落ちてしまった現段階での経済状況では楽観できないが、国際援助実施の再開期待から、経済再建にもようやく明るい方向が見えはじめている。
経済再建にとって具体的に取るべき課題は山積している。崩壊してしまった金融システムの再建、一説には過去からの累計で2600億ドルを超えるとされる海外に逃避した華人系企業と個人資産の呼び戻し、資金や原材料不足によって極度に落ち込んでいる生産活動の再開等のほかに、新規外国資本投資の呼び込みなどである。また、50年来の大干魃により、98年中に米供給だけでも400万トン不足という大凶作からの回復、1300万人に上る失業者対策など、きりがない。こうした諸問題の処理が遅れれば遅れるほど、社会不安が増長することは間違いない。これらの問題への対応を誤れば、暴動再発の可能性なども否定できなくなる。そうした最悪の事態を避けるためにも国際社会はインドネシアの状況を十分理解して援助する必要がある。インドネシアは伝統的にナショナリズムが根強い国である。早急な経済再建策とその実施に対する支援体制が形成されないとなれば、インドネシアは対外排斥の道を選ぶおそれがある。そうなれば、この30年来培ってきたASEAN協力、APEC協力などに見られる積極的姿勢が後退せざるを得ない。そのときには国内の華人社会に対する排斥も強まり、一層の経済混乱の深化を招く。そうさせないためには、インドネシアを国際社会から孤立させてはならない。インドネシアに最大の援助を供与している日本は、物質的にも知的にも積極的な支援を行い、国際社会の対インドネシア支援強化にイニシアティブを発揮することが求められている。
(尾村敬二)