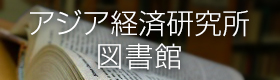グローバル化とマネーの太平洋
調査研究報告書
塩田 光喜 編
2012年3月発行
まえがき (11KB)
目次/執筆者紹介 (19KB)
序章
グローバル化とマネーの太平洋 (69KB) / 塩田 光喜
はじめに
第1節 グローバル化-驚異の20年
第2節 ITと金融 -グローバル化の原動力
第3節 -証券化- 金融テクノロジーの錬金術
第4節 世界分業体制の大変動
第5節 グローバル化のオセアニア
第6節 グローバル化のオセアニア -その歴史的位相
第7節 マネー・メイクス・ユー・クレイジー
第8節 グローバライザー、グローバライズト
イギリスのマルクス主義史家、エリック・ホブズボームは、資本主義は市場開放の時代(「資本の時代」)と市場閉鎖の時代(「帝国の時代」)の交替をくり返すと喝破した。
1989年のベルリンの壁崩壊から始まった地球大の市場開放の20年は、世界のGDPを3倍に、貿易額を5倍に、金融資産を30倍(!)に膨張させた。これを称して、グローバリゼーションという。
このグローバリゼーションをもたらしたのは、それまで軍事・研究用に限定されていたインターネットの商業利用の開始と証券化と呼ばれる金融工学を用いた金融資本主義の発展であった。
中でもデリバティブと呼ばれる金融商品の取引額は、年間5京円(5兆円の1万倍)を超え、世界のGDPの10倍を超える。こうして、世界経済は「尾っぽ(金融)」が、「体(実体経済)」を振り回していく金融資本主義へと突入していく。
グローバリゼーションの20年間は、マネーがマネーを生むマネタライゼーションの20年間でもあった。
マネーは世界の隅々にまで浸透し、太平洋の島々も例外ではなかった。
熱帯林伐採、カツオ・マグロなどの高級回遊魚漁獲権、鉱山開発権などを求めて、白人や華僑が入りこみ、マネーをばらまいた。マネーが人間と人間の絆を断ち切り、共同体と伝統文化を解体していった。
太平洋諸島民はマネーを欲し、マネーなしで生きられなくなっている。
それがグローバリゼーションの20年が、太平洋にもたらした現実である。
第1章
森林資源の開発とグローバル化現象 ソロモン諸島の植林事業にみるブリコラージュ戦術 (86KB) / 石森 大知
はじめに
第1節 グローバル化のなかの地域社会
第2節 北ニュージョージアの伐採史
第3節 植林事業の立ち上げ-モデル村と管理主体の動向
第4節 モデル村から近隣村落へ-P村における植林の取組み
第5節 グローカル化概念の再検討
おわりに
大規模な森林伐採は、環境破壊を含むさまざまな弊害を地域社会にもたらす。ソロモン諸島の森林伐採をめぐっては、地域社会、研究者、環境保護団体、援助供与国などから警告が発せられてきた。にもかかわらず政府は、森林伐採を規制して環境保全へと導く実効的な政策を欠いてきた。そのような状況下、地域社会の人びとの間で「植林事業」が望まれている。ニュージョージア島の北部では、外国資本による皆伐がおこなわれてきたが、現在では伐採跡地を対象に地域社会の人びと主導で植林事業が進行している。ただし、植林の取り組みには、技術や物資の移転の度合いによって、地域社会内でも相違がみられる。P村では、豪州からの援助は欠乏しており、人びとは村落で手に入るものを寄せ集め、試行錯誤のうえ使用した。このようなブリコラージュ戦術を、人びとはローコロというピジン語の概念で表現する。これはグローカル化の動きにも思えるが、じつはそうとは言い切れない。なぜなら、ローコロ概念は、グローバル化の影響で入ってきた「正しいやり方」があるにもかかわらず、(自分たちは)それを実行できないことを意味するからである。ローコロという決して称揚的ではない控えめな自己表現は、グローカル化というよりも、むしろ、グローバル化が周辺世界にまで浸透していることを示すのである。
第2章
トンガ王国における新政治制度確立の意味 民主化運動の帰結とその問題点 (148KB) / 大谷 裕文
第1節 はじめに
第2節 民主化運動の揺籃
第3節 民主化運動の発展
第4節 熱狂の時代
第5節 再折衝の模索
第6節 新政治制度の探求
2010年11月25日、トンガの長い民主化運動の帰結として、現国王トゥポウ5世が「我々の王国にとって最も重大で最も歴史的な日」と形容した総選挙(国の命運を決する大きな出来事)が実施され、その結果、ロード・トゥイヴァカノを首相とする、新憲法に基づいた初めての内閣が2011年1月中旬にスタートした。本論文は、過去25年に亘る民主化運動展開の歴史過程に見られるプラクティス、プラクシス、及び出来事への方法論的焦点付けを通して、トンガ社会における「変化」と「持続」の相反的関係を明らかにし、この新しい政治制度確立が民衆にとってどのような意味を持っているのかを読み解くことをその目的としている。そのために本論文では、これまでのトンガにおける民主化運動の展開を、総選挙というおおきな「出来事」に留意しながら5つの局面、すなわち(1) 民主化運動の揺籃(1980年代初めから1990年総選挙に至るまで)、(2) 民主化運動の発展(1990年総選挙後から1999年総選挙に至るまで)、(3) 熱狂の時代(1999年総選挙後から2005年総選挙を経て2006年11月16日ヌクアロファ事件に至るまで)、(4) 再折衝の模索(ヌクアロファ事件から2008年4月24日総選挙に至るまで)、(5) 新政治制度の探求(2008年4月24日総選挙から2011年1月新内閣発足まで)に分け、各局面におけるプラクティス・プラクシス・出来事の絡み合いを、2節から6節までの対応する各節において叙述・分析を行っている。以上のような各節の叙述・分析を踏まえて、論文の末尾で、新政治制度確立が民衆にとって何を意味しているのかという問いに対する答えを提示している。この結論部分で筆者が強調したことは、およそ次の通りである。
トンガのジャーナリストの中には、今回の選挙制度改革をかなり大きな改革としてきわめて肯定的に捉えている人もいる。確かに現実の具象的な組織レベルでは、民衆派はこれまで実現することが出来なかった17民衆議席や首相の閣僚任命権等を勝ち取っている。民主化運動のリーダーの中にも、「大きな勝利」を強調する人は珍しくはない。しかしながら、より抽象度の高い制度レベルで捉えるならば、今回の選挙制度改革を「大きな改革」と呼ぶことはできない。トンガ王国の場合、それは、1870年代、ジョージ1世の時代に確立した制度、すなわち政治権力と宗教的聖性を兼ね備え、「不変の統治権」を有する国王が王国政治の中心に存在し、この国王を貴族が取り巻き、その下に貴族議員の選出に全く参加することができない民衆が位置づけられるという基本原則に相当する。この基本原則は、今回の選挙制度改革によっても全く変化していないので、政治制度それ自体の改革を掲げてきた民主化運動は、当初の大目的(原則の改革)を達成することはできず、一連の出来事の絡み合いは全体として制度レベルのファーイン・チューニングの枠内に収まってしまったと判断せざるを得ない。特に、1990年代以来、トンガの民主化運動が最も重要な目標としてその撤廃を求めてきた、33名の貴族のみによって互選される貴族議席(9議席)がそのまま残ってしまったことは、政治制度改革の大きな挫折点であった。ところでなぜ、あれほどの高揚を見せた民主化運動が、最も重要な政治制度改革の目標を実現できずに、穏やかな制度レベルの再調整に収束することになったのであろうか。ペシ・フォヌアは、その理由を、アキリシ・ポヒヴァを始めとする民主派議員が、「戦術で負け、裏をかかれ、数で負けた」結果であると述べ、議会における民衆派議員の議会運営における見通しの甘さ、戦術の拙さ、地道な努力を厭う消極性を批判している。
トンガの民主化運動は、民主化運動揺籃の時代から約25年の歳月をかけて、まがりなりにも新政治制度への移行を達成し、「最大限の譲歩」を獲得した。しかし、「新政治制度」という名称にもかかわらず、この譲歩は組織レベルの変化であり、政治制度は変わることなく持続しているのである。視点を当面の組織レベルの現実的な改革遂行に転じた場合においても、「中国人問題」、「WTO問題」、「超教派キリスト教運動のインパクト」、「民主派エートス問題」など、民主化運動の関係者に残された現実的課題はあまりにも多い。しかも、これらの課題の全てが、トンガ王国全体がその中に置かれている状況、すなわちグローバル化の進展という状況と密接に結びついているだけに、対処が極めて困難な問題である。とりわけ重要な問題は、現状の妥協(ファーイン・チューニング)の枠を越えて原則の民主化を更に進める気構えがあるのか否かという、「民主派議員のエートス問題」である。現在の民主派議員の間に見られる「自己満足的な雰囲気」から見て、このエートス問題こそが、グローバル化の進展に伴う社会・政治・経済状況の深刻化の中で、元YWAMの宣教師であったカラフィ・モアラの言動に代表されるような超教派キリスト教運動(24)の影響による民衆レベルのプラクティス・プラクシスの変容を民衆議員が受け止めることができるのか否かという問題が、民衆にとっての重要な政治問題として浮上していると言えるであろう。
第3章
グローバル化と政治的不安定性——フィジー諸島共和国二〇〇六年クーデタ後の臨時政権の正当性をめぐる闘争を事例として (118KB) / 丹羽 典生
第1節 はじめに
第2節 フィジーのクーデタ史からみる2006年の特徴
第3節 ガバナンス・クーデタの進展——臨時政権の理念と正当性をめぐる闘争
第4節 臨時政権の孤立化とフィジー人の諦念としての受容
第5節 終わりに
本稿では、グローバル化と紛争などの政治的不安定性との関連という視点から、フィジー諸島共和国でもっとも近年に起きた2006年のクーデタとその後の政治的展開と課題を事例として考察する。フィジーは、1987年にオセアニア史上最初のクーデタが発生してから政治的混乱の絶えない国である。これまでのクーデタが先住民民族主義と親和性の高い政治的主張を掲げていたのに対して、2006年のそれでは、ガバナンスという市民主義的要求を旗印にしたクーデタという意味で、独特な位置づけにある。本稿では、クーデタ発生から現在まで、目的として当初掲げていたガバナンスの理念を、臨時政権側がいかなる政策を通じて実現しようとしているのか、反対勢力との折衝、先住系フィジー人の今回のクーデタに対する意見にも触れつつ分析をする。そして、軍によって決行された2006年のクーデタとその後の臨時政権による正当化の確執に焦点を当てることを通じて、言説の上では広義のグローバル化(近代化路線)と親和性が高いようにみえる2006年のクーデタも、実践の水準では違った姿がみえてくることを指摘する。
第4章
保護される人権、切り裂かれる社会—パプアニューギニアにおける反DV政策の功罪— (133KB) / 馬場 淳
はじめに
第1節 DVの日常性?!
第2節 反DVの国際人権レジーム
第3節 DVに対するパプアニューギニアの取り組み
第4節 保護命令規則の概要
第5節 事例
第6節 グローバル化の暴力——保護命令の「誤解」から
おわりに
本稿の目的は、パプアニューギニアで昨今施行された保護命令制度を対象に、グローバル化の功罪を明らかにすることである。具体的には、(1)「女性に対する暴力」撤廃のグローバルな動きを受けて、パプアニューギニアが保護命令制度を制定・施行するまでのプロセスを明らかにするとともに、(2)その保護命令制度の運用実態を具体的に記述し、(3)それが地域社会にどのような混乱やジレンマを生み出すのかを考察する。結論としては、保護命令がDV対策として一定の意義をもつことを認めつつ、それを社会文化的コンテクストの中に位置づけることで、DV問題には還元しえぬ別の問題を浮き彫りにし、暴力に抗する法が別の「暴力」になってしまう逆説を示す。その際、筆者は、保護命令がもたらす状況を当事者や周囲の人々がどう解釈しているのかという地域社会側の反応に注目する。事例を通してわかるのは、当事者や関係者が保護命令を「離別の法」と理解していることである。これがDV問題とは別のレベルで、当事者や関係者に混乱や葛藤を引き起こす要因になっている。もちろん、それは「誤解」であるが、人々の根深い知覚評価図式によって支えられているがゆえに、すぐれてリアルなものでもある。たしかに、DVに苦しむ女性たちを暴力から保護するこの制度の重要性は強調してもしすぎることはない。しかし社会文化的現実や人々の知覚評価図式への配慮なき政策・制度は、地域社会側に違和感やジレンマ、そして新たな問題を引き起こすということも事実なのである。
第5章
日本の遠洋漁業の窮状と出稼ぎキリバス人漁船員—グローバル化のもたらす経済的相互依存と文化的閉鎖性— (151KB) / 風間 計博
はじめに
第1節 キリバスの経済的脆弱性と外国船出稼ぎ
第2節 カツオマグロ漁業の窮状と外国人船員の雇用
第3節 日本漁船の出稼ぎ生活
第4節 キリバス人漁船員の金銭消費
第5節 キリバス人漁船員の減少
第6節 経済的依存と文化的閉鎖性
おわりに
本論では、日本の遠洋漁船に乗り込むキリバス人出稼ぎ者に焦点をあてる。1990年代、漁船員不足を解消し人件費を削減するために、遠洋漁船ではキリバス人等の外国人雇用を促進してきた。一方、キリバス政府にとって、外国船への自国民の派遣は外貨獲得の重要な政策である。キリバス住民にとっても、現金や工業製品を獲得するうえで、外国船出稼ぎは貴重な機会である。しかし、2000年代中葉以降、トラブルを起こすキリバス人漁船員は頻繁に解雇され、インドネシア人に置換される傾向が強まった。解雇は、キリバス人と雇用者側との相互理解の不足が一因である。しかし、グローバル化の進展により、経済的効率性の論理が卓越するなか、漁業の国際競争は激化している。外国人に依存する遠洋漁業においても、文化的他者の理解にかけるコストは削られ、不適合な出稼ぎ者は容易に切り捨てられるしかないのである。
第6章
太平洋島嶼国に対するドナー国の外交戦略 「太平洋・島サミット」に見る日本の太平洋島嶼国外交を中心に (135KB) / 黒崎 岳大
はじめに:第5回太平洋・島サミットと「太平洋環境共同体」構想
第1節 大洋州島嶼国における地域連合と豪州・ニュージーランドの動向
第2節 域外ドナー国による大洋州島嶼国外交の展開: ODA支援と地域枠組みの可能性
第3節 日本の太平洋島嶼国外交
第4節 考察:太平洋環境共同体にみる日本の対島嶼国外交とPIF内部の現状
本稿では、日本政府が第5回太平洋・島サミットで「太平洋環境共同体」という地域協力の枠組を提示したことに着目し、日本が太平洋島嶼国に対してどのような外交方針を目指しているのかについて、他の域外国の対島嶼国外交と比較し、また戦後の対島嶼国外交の流れを踏まえながら、地域協力機構という枠組を形成していく可能性について検討した。
太平洋島嶼国・地域が加盟している地域協力機構である太平洋諸島ファーラム(PIF)は、戦後宗主国の政治的な発言力・影響力から解放されることを目的に設立された。当初は、域外各国が地域に対して共通の利益を求めるために歩調を同じくした緩やかな地域協力グループであったものの、2000年以降豪州・ニュージーランドによる支配的立場が高まる中で、次第に同地域の中核的な地域協力機構として組織化を強めていき、地域統合のための核としての影響力を高めていくようになっていった。その結果、域内の島嶼国からは、次第に批判的な意見も出されるようになってきた。
地域統合という色彩を急激に強めているPIFに対して、カウンターパートとして強く認識し、多国間外交を推進しているのがEUである。一方で、豪州・ニュージーランドに対する批判的な意見を利用しながら、二国間外交をベースに影響力を拡大させているのが中国・台湾であり、また自国の政治的・経済的利益をもとに独自のグループ外交を展開しているのが米国である。
こうした近年のドナー国によるPIFへのアプローチに対して、同地域へのトップ・ドナー国の一つである日本は、1997年以来5度にわたり「太平洋・島サミット」を開催し、戦後同地域との関係強化を進めてきた。特に直近の第5回太平洋・島サミットで提唱された「太平洋環境共同体(Pacific Environmental Community)」構想を発表し、島嶼国との間の新しい関係構築の枠組みを構築する意図を示している。その一方で、この動きは、潤沢なODAを背景に、二国間外交を進めてきた日本の対太平洋島嶼国外交が、他のドナー国との援助協調や限られた援助スキームを選択と集中させることへとシフト転換せざるを得ない状況にあり、その結果、多国間外交を進めるうえでの地域協力機構との関係強化を求められていることを示唆している。