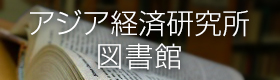湾岸、アラビア諸国における社会変容と国家・政治 -イラン、GCC諸国、イエメン-
調査研究報告書
福田 安志 編
2007年3月発行
はしがき・目次・執筆者一覧 (182KB)
第1章
湾岸、アラビア諸国における国家、経済発展、社会変容 (472KB) / 福田安志
湾岸地域における国家体制は、王政、首長制、イスラーム共和国など特異な政体をとることが多い。それらの国家やその政治・経済が特異な存在であることは、イラン、イラク、イエメンなどの国々がWTO(世界貿易機構)の未加盟国になっていることにも示されている。サウジアラビアも2005年まで未加盟であった。湾岸地域で特異な国家体制が存在してきた背景には、社会・文化的な要素、歴史的な要素、厳しい国際環境と域外大国の介入などの要因があると考えられる。しかし、そうした特異な国家体制を形成してきた要因は固定的なものではなく、変化していくものであり、その変化は国家体制にも大きな影響を与えることになる。変化をもたらす要因としては石油が重要である。湾岸、アラビア地域ではすべての国家が原油を生産しており、石油は、経済を発展させ社会変容をもたらす原動力として重要な役割を果たしている。経済が石油を中心に動いていることは、サウジアラビアの例からも見て取れる。1970年代後半の第1 次オイルブームの時期には、石油収入が急増し、財政支出が大幅に増え、経済に強いインパクトを与えた。経済の急激な発展が起こり、それは、農村の崩壊や都市化を進めるなど、社会にも強い影響を与え社会変容を進め、政治にも大きな影響を与えた。もっとも、石油が経済に与えるインパクトについては、産油量と経済規模の相違により、国ごとに異なっている点に注意が必要である。イエメンは一人当たり産油量が少なく、石油のインパクトが最も少ないと考えられるが、にもかかわらず、イエメンでは他の国よりも一歩先をいく変化が起きている。
第2章
イラン・イスラーム共和体制における統治権力と国民 —バスィージの実態理解へ向けて— / 佐藤秀信
第3章
イランにおける地方議会制度と地方自治の発展 —ハータミー期における展開とその前提条件についての予備的考察 / 鈴木均
第4章
サウジアラビアにおける統治体制 (475KB) / 福田安志
本章では、制度的側面からサウジアラビアの統治体制について述べる。サウジアラビアの統治体制は君主制であり、しかも、国王が実権を持っている。また、イスラームが強い影響力を持っていることもその特徴となっている。君主制やイスラームの強い影響力は、18世紀半ばにサウード家とワッハーブ派が協力して第1 次サウード朝を建国したときにはじまるものである。サウード家とワッハーブ派との関係は、以後、第2 次、第3 次サウード朝へと受け継がれ、1932年のサウジアラビア王国の成立を経て、現在へとつながっている。現在でも、サウジアラビアの統治体制はサウード家出身の国王と王族有力者を中心にして作られており、国家はワッハーブ派と強いつながりを持っている。ワッハーブ派はサウード家による王政を正統化する役割を果たしており、王政の安定を考える時、ワッハーブ派の存在は重要である。国王を頂点とした統治体制は、行政機構、諮問評議会、司法、軍事機構などの国家機構によって支えられている。行政機構の要所には王族が配置され、サウード家の統治を支える役割を果たしている。こうした、国王を頂点とした統治体制の下で、国民に政治参加の機会を与える目的で1993年に発足したのが諮問評議会である。しかし、諮問評議会の議員は勅選で、また立法権もなく、国民の間からは「民主化」を求める声が上がっている。
第5章
クウェートとカタル:「レンティア国家」の変遷 (835KB) / 水島多喜男
本稿は、従来、対米外交上の必要から語られることが多かった湾岸アラブ産油国の「民主化」を、国内における統治の正当性の維持に必要な経済問題への対処と捉え、この仮説をクウェートとカタルにおいて検討している。湾岸産油国の政治社会を概念化した「レンティア国家」は、「レント」の配分によってはその「社会の危機」を克服できないため、国内の新たな富の生産と分配を担う中間層の増加と非軍事的なテクノクラート集団の統治能力の発展を必要とする。その結果、国内では石油生産からもたらされる「レント」の分配のもつ硬直性を避けることができ、国内の統治を安定化させることができるが、同時に、富と統治能力を手に入れた中間層と非軍事的なテクノクラート集団の要求を新たに満たす必要が生じる。そしてその結果、政治の領域における「民主化」が不可避となる。クウェートの「民主化」の背景には、80年代から90年代にかけてのクウェート国民の間の経済格差の拡大があり、カタルの「民主化」の背景には、カタルをグローバル化の進む世界市場に適応させ、高等教育修了者にホワイト・カラーとしての雇用を保障する必要があった。
第6章
イエメンの政治変化と経済変化 (751KB) / 松本弘
1990年南北イエメン統一によるイエメン共和国の成立以後、イエメンはそれまでの政治経済状況とは一線を画す、新しい国家へと移行した。統一自体は冷戦崩壊に前後する世界的な変化に即するものであったが、統一直後の湾岸危機・戦争および1994年内戦により、その政治経済状況は危機に瀕する。しかし、内戦後に構造調整を受け入れて以降、経済は好転し、経済の再建は政治や社会の安定化にもつながった。
そのような統一以後の政治変化と経済変化の関係を考察すれば、イエメンにおける変化とは、いわば「旧思考的価値観」から「新思考的価値観」へと社会が移行するプロセスと捉えられる。前者は、冷戦期の集団指導や大政翼賛といった古い行動パターンに基づく政治判断であり、それは結果的に政治的対立と経済的疲弊をもたらした。これに対し、後者は冷戦後の現実主義的な傾向であり、それは競争・競合を自明のものとして経済的利益を求め、結果的には政治的安定にもつながるものであった。無論、後者の場合はマクロ経済の安定を図りながら、補助金や公務員の削減、為替・金融の自由化、税制改革などによって国民生活に「痛み」を強いるものであり、その意味でプラス・マイナスの両面を有する。しかし、イエメンの場合は、補助金の削減による生活基礎物資の値上げのたびにデモ・暴動が生じるものの、度重なる選挙ではその「痛み」を伴う構造調整を選択した現政権への支持が拡大し続けている。
このことから、「新思考的価値観」は積極的であれ消極的であれ、民主化という政権と社会のダイアローグのなかで評価され、定着しているといえよう。「旧思考的価値観」から「新思考的価値観」への移行は、とりもなおさずイエメンが統一以前の「特異な国」から、「普通の国」へと変貌する過程に他ならない。それは、イエメン以外の多くの国々にも共通する傾向であり、その共通性がイエメンの変化に関わる基層または中核となっている。しかし、イエメンの事例にはそのような共通性のみならず、変化の内容や展開にイエメン独自の特殊性も存在する。この共通性と特殊性との関係や境目に関わる考察が、イエメンのより大きな社会変容への評価につながろう。