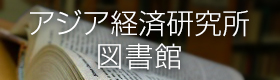イラク・クルディスタン独立住民投票の誤算
アジ研ポリシー・ブリーフ
No.102
吉岡 明子
PDF (654KB)
- クルディスタン地域の独立を問う住民投票は、圧倒的な賛成多数という結果を得たものの、イラク国内外からの猛反発に遭って、独立への道筋をつけるという当初の目的は失敗に終わった。その背景には、住民投票を進めたKDPによる計算違いがあった。
イラクの自治区クルディスタン地域では、2017年9月25日に自治政府がイラクからの独立を問う住民投票を実施した。北部4県を中心とする自治区内に加えて、2014年から自治政府が実効支配し、将来的な併合を視野に入れているキルクークなどの係争地も投票の対象とされた。投票日が近付くにつれてイラク内外で投票の延期や中止を求める声が高まったものの、自治政府は予定通り強行することを選んだ。そうした地域内と係争地の有権者のうち72.16%が投票所へ足を運び、実に92.73%が独立への賛成票を投じた。投票日当日は、自治区の主都エルビルはお祭り騒ぎの様相であった。
自治政府が描いていた青写真は、圧倒的多数の市民がイラクからの独立を望んでいるという住民投票の結果を交渉材料として、イラク政府と将来の独立に向けた本格協議を開始するというものだった。しかし、いざ住民投票が行われると、イラク政府は隣国のイランやトルコと共に空港の国際便停止や国境封鎖を含む経済制裁に乗りだし、イラク軍が北上して、クルド兵ペシュメルガが一方的に支配していた係争地のほとんどを軍事的に奪還するに至った。その結果、クルドは、今では自治区の存続を最優先事項にせざるを得ない状況となり、独立の夢は遥か遠のいた。
自治政府の指導部は、無論、イランやトルコなど国内にクルド人人口を抱える隣国がイラク・クルドの独立問題に反発するであろうことは予想していた。しかしながら、イラク政府がこれほど強硬な態度で住民投票を拒否することや、ましてや軍事的手段に訴えるということまでは想定していなかった。そうした軍事行動を可能にした背景には、クルド政党間の足並みの乱れや、国際社会からの支援の不在といった、独立問題をめぐるクルドの計算違いが存在した。
イラク国内の反発
今回の住民投票を積極的に主導したのは自治政府の中でも与党第一党であるKDP(クルディスタン民主党)だった。彼らにとって最大の誤算は、イラクの多数派であるアラブ人が、クルドの独立要求に一定の理解を示すと想定していたことだったと言っていい。
まず、そもそもクルディスタン地域内には、今後もイラク国家に留まり続けることを支持する声はほとんどない。これは住民投票で独立にNoという回答が極めて少なかったことが示すとおりだ。人々の間にはフセイン政権時代の圧政の記憶が生々しく語り継がれている上、すでに自治区ができて四半世紀が経っており、物理的にも心理的にもイラク国家との距離は開いている。
他方で、クルディスタン地域以外のイラクにおいては、イラク人は民族や宗派の違いによって分断されるべきではなく、平和裏に共存すべきだというイラク・ナショナリズムが依然として強く存在する。そうした感情は、イラク国土からジハード主義組織ISを放逐し、勝利を収めようとしているというタイミングでさらに強化されていた。こうした理想的なイラク・ナショナリズムを強調する立場からは、しばしば、クルドの独立願望は見過ごされ、矮小化される傾向にある。
アラブ人政治家にとっては、普段からクルド人政治家と付き合いがあり、彼らの独立願望をよく知っていたとしても、クルドの独立という不人気な政策をあえてアラブ人有権者に売り込むメリットは何一つとしてない。アラブ社会においては、2003年のイラク戦争以来、政治面でも治安面でもイラク国家が極めて不安定化する一方、その脆弱性を突く形で、外交や国防、天然資源など国家主権に関わる領域にも影響力を行使し、あたかも独立国家のように振る舞うクルディスタンに対する苛立ちが高まっていた。2014年のISによるモスル陥落に伴う混乱に乗じて係争地や油田をクルドが実効支配したことは、そうした苛立ちや不満をさらに高める結果になったことは想像に難くない。
住民投票後に実施された、キルクークに対する前例のないイラク軍の軍事行動は、そうしたアラブ社会の怒りによって後押しされた側面がある。イラクの世論や民衆感情は、クルディスタンの中と外で大きく異なることが多い。独立の実現可能性を推し量る上で、KDP指導部がアラブ社会の空気を読み誤ったことは大きな敗因の一つだった。
クルド政党間の不和
ただし、クルド政党間の不和がなければ、イラク政府にキルクークを奪還されることもなかっただろう。KDPが住民投票を強く推進する一方で、自治政府のパートナーであるPUK(クルディスタン愛国同盟)の対応は党内で割れており、野党のゴランやイスラーム政党は、独立よりもクルディスタン内政の改革が先だとして住民投票の実施に反対していた。
しばしば、KDPが住民投票を強力に推進したのは、クルディスタン地域内の政治・経済危機、統治の失敗から市民の目を逸らすことが目的だったのではと指摘される。そうした理由が無関係だった訳ではないだろうが、むしろ、かつてイラク政権に対するゲリラ闘争を行い、ここまで自治を率いてきたマスウード・バルザーニ自治政府大統領らの世代にとっては、独立の大義が何にも優先することは論を俟たない。さらに言えば、ゲリラ闘争と自治を率いてきた自分たちこそがクルディスタンを代表しているのであって、自分たちが独立への道筋を主導することは当然のことだと認識する傾向にあった。そうした考え方ゆえに、彼らは、独立は望むが「バルザーニ王朝」は望まない、というクルド社会に存在したジレンマを過小評価していたのかもしれない。PUKやゴランが地盤とするスレイマニヤでは、住民投票の投票率が50%程度で、賛成票も80%程度に留まったと言われている。
そもそも住民投票に否定的だったPUKの一派は、イランやイラクからの強い圧力に晒された結果、投票から半月後には、イラク軍の進行を前にしてキルクークの前線から一方的に兵士を撤収させることを決めた。KDPが域内における合意形成を軽視したことが、かつてバルザーニが「クルディスタンの心」と呼んだキルクークを失わせる結果となった。
国際社会の反応
最後のKDPの誤算は、国際社会の態度である。既存の国境線を尊重するという国際規範が存在する以上、原則として分離独立は国際社会には支持されない。だが同時に、民族自決の権利もまた否定しがたい規範である以上、独立への反対はしばしば多くの国の政府関係者の口からは、「今は独立への良い時期ではない」という曖昧な文言によって発せられていた。
欧米諸国政府はこれまで、決して公にクルドの独立を支持することはなかったが、他方で、自治区の主都エルビルの領事館を自治政府の外交カウンターパートとし、イラク政府の反対にもかかわらず石油メジャー企業のクルディスタンへの投資を黙認するなど、クルディスタンを事実上の国のように扱ってきた。対IS戦が始まると、欧米諸国からの軍事支援はイラク政府のみならずペシュメルガにも拡大された。こうした状況は、いずれ欧米はクルドの独立を受け入れるという認識をKDPが抱く要因となったと言えよう。
しかしそれは、独立問題をめぐってイラク政府と自治政府の間で紛争となった場合、クルディスタンを主権国家と同等に扱うということを意味していたわけではなかった。かくして、軍事作戦が実行に移された時、国際社会はイラク軍のキルクークへの進行を静観した。住民投票の数日前に、国連安保理が住民投票への「懸念」を表明した時にはすでに、クルディスタンは国際社会における味方を失っていたのだろう。
(よしおか あきこ/日本エネルギー経済研究所中東研究センター)
本報告の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。