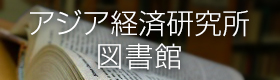イラン・イスラーム共和国のクルド政策
アジ研ポリシー・ブリーフ
No.82
貫井 万里
2017年3月31日発行
PDF (762KB)
- 1979年の革命後に成立したイラン・イスラーム共和国体制下では、主要民族・宗派であるペルシア民族・シーア派ムスリム優位の多民族・宗教共存政策が実施されてきた。
- 体制エリートのクルド政策は、少数民族・宗派問題自体を否定する立場から、治安対策アプローチ、懐柔策、包括的アプローチまで、イデオロギーや時代背景によって、多岐にわたる。
- 少数民族・宗派問題は、歴史的に欧米列強が中東諸国への介入の口実としてきたために、非常にデリケートな問題である。イラン政府が、海外からの「人権」を理由とした同問題への関与に敏感であるという点を理解する必要がある。
イランにおけるクルド系住民の人口は、549~784万人とされ、主にイラン北西部のイラク国境に近いクルディスタン州、イーラーム州、ケルマーンシャー州、西アゼルバイジャン州などに多く居住する。その約6割がスンナ派ムスリムで、約2~3割をシーア派ムスリムが占め、少数のキリスト教徒クルド人及びスーフィー教団の信奉者に加え、古代からの自然崇拝を継承するクルド系部族も存在する。
1979年の革命後に成立したイラン・イスラーム共和国体制下で、イラン国内に居住するクルド系住民がどのように位置づけられてきたのであろうか。

社会学者のナーイェレ・トウヒーディーは、少数民族・宗派政策を、(1)同化政策、(2)交渉型多民族・宗教共存政策、(3)主要民族・宗派優位型多民族・宗教共存政策に類型化している1。革命後のイラン・イスラーム共和国は、憲法第15条及び19条において、下記のように規定し、ペルシア語及びシーア派ムスリムの優位を基礎としつつも、一定程度の少数民族・宗派の権利を許容してきた。
第15条:イラン国民の公用及び共用の言語並びに文字はペルシア語である。公式の記録、通信及びテキスト並びに教科書はこの言語及び文字によらなければならない。しかし、地方における出版、マスメディア及び学校での地域文学の授業における地方語及び部族語の使用はペルシア語と併用すれば自由である。第19条:イラン国民は出身氏族、部族の如何を問わず、平等な権利を享有する。色、人種、言語、その他このようなものにより、何ら特権を与えられることはない。
従って、イランの少数民族・宗派政策は、類型(3)に分類可能である。
1979年のイラン革命後、クルド人活動家たちは、自治権、クルド語教育、クルド人主体の治安維持機関の創設、クルド居住地域の行政機構の役人の任免権などを要求してきた。その際、国外に逃亡したクルド武装組織とは異なり、国内に留まり、イラン・イスラーム体制の枠内での権利拡張運動を目指す方向を選んだクルド人活動家たちは、他のマイノリティと同様に、憲法で規定された権利が実際に運用されていないことを非難し、憲法で保障された権利の実現を訴えるという形で活動をしてきた。こうしたマイノリティの権利要求に対する体制エリートのアプローチは、イデオロギーや時代背景によっていくつかの立場に分けることができる。
第1に、イラン革命の指導者で初代最高指導者に就任したルーホッラー・ホメイニー師は「クルド人も全てムスリム」と主張し、少数民族固有の権利や民族問題の存在自体を否定した。この「少数民族・宗派問題を否定する立場」の場合、イスラーム体制を支持する者は、ホディー(体制派khodī)として、宗派・民族に関係なく許容され、体制批判派は、ゲイレホディー(反体制派gheire-khodī)の烙印が押され、徹底弾圧された。
第2に、クルド系住民全体を、「国民の一体性を脅かし、いつ反体制派や外国政府に寝返るかわからない危険分子」とみなす「治安対策アプローチ(securitization approach, ”negāh-e amnīyatī”)」があげられる。革命直後に、イラン・クルド民主党(Kurdish Democratic Party of Iran: KDPI)の武装蜂起をイラクのサッダーム・フセイン政権が支援したことや、現在でも外国政府が「イラン国内で弾圧されている少数民族の人権保護」を主張し、一部の反体制クルド武装組織に資金援助をしている事実がある。そのため、イスラーム革命防衛隊(Islamic Revolutionary Guards Corps: IRGC)によるクルド人活動家や組織の取締りは、全く根拠のないものではない。他方で、こうしたアプローチは、少数民族・宗派への取締りの行き過ぎを生み出したり、マイノリティに融和的な国内の改革派を「外国の煽動」に影響されているとして攻撃する格好の口実として、時に利用されたりしている面も否定できない。
第3のアプローチは、少数民族・宗派が外国の煽動に影響されやすいのは、弾圧策の反動や中央と地方の社会・経済的格差を原因とするとして、少数民族・宗派が多く住む国境地帯の経済開発を主張する立場である。こうした懐柔策は、マイノリティの一定の要求を満たせたとしても限界がある。それは、憲法に規定されたマイノリティに対する不平等の根本的解決を目指していないことを原因とする。
最後に、マイノリティの文化的・政治的権利を保障・拡大することは、イランのイスラーム体制全体の民主化プロセスの一要素と捉える「包括的アプローチ」である。国内の保守派は、この考えをイスラーム体制の崩壊につながりかねないとして警戒しているため、「包括的アプローチ」の実現は、本稿執筆段階の2017年時点では難しい局面にある。
イラン革命後の混乱やイラン・イラク戦争、アメリカによるイラク侵攻など、イラン国内外が転換期にある時、クルド民族の権利拡張要求が高揚し、それを利用しようとする外国政府との接触の疑いから、中央政府のクルドへの不信感が募るという不幸が繰り返されてきた。また、他方でイスラーム体制内でも、少数民族・宗派に対するアプローチが異なり、政争によって国内の不平等の是正や全国民への基本的な権利の付与が遅れてきた側面がある。しかし、いずれの政治派閥も、クルド人もイラン国民を構成する一要素と認め、多民族・宗派の共存と一定の権利保障を原則とする共通認識がある点がイランの特徴である。そして、革命から30年を経て、クルド系住民が多く住む地域でも次第に教育が普及し、生活が豊かになるにつれて、独立よりも現体制の枠内でより良く生きることを現実視するクルド人が増えたとしても不思議ではない。
少数民族・宗派問題は、歴史的に欧米列強が中東諸国への介入の口実としてきたために、非常にデリケートな問題である。そのため、イラン政府を含めて、クルド系住民を多数擁する国々が、クルドを含めたマイノリティの問題に対して、特に海外からの「人権」を理由とした同問題への関与に非常に敏感であるという点を理解する必要がある。
(ぬきい まり/公益財団法人 日本国際問題研究所)
脚注
- Tohidi, Nayereh, "Ethnicity and Religious Minority Politics in Iran," in Contemporary Iran: Economy, Society, Politics: Economy, Society, Politics, edited by Ali Gheissari, Oxford University Press, 2009.
本報告の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。