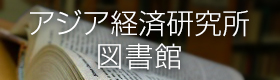中東政治の変容とイスラーム主義の限界
アジ研ポリシー・ブリーフ
No.38
鈴木 均
2014年5月7日
PDF (460KB)
- 「アラブの春」以降、中東アラブ地域における主要な政治的イデオロギーだった「イスラーム主義」の限界が露呈。
- アラブ各国やアフガニスタン、シリア、カフカース地域、そしてマリ国境地帯などでは、政治的な民主化と社会の近代化を求める「リベラルな」政治勢力と、社会的・宗教的な規範に忠実であろうとする従来の「イスラーム主義」的な政治勢力の間で対立・衝突が深刻化。
- アラブ各国やシリアは、不安定な政治的変革の道を進むのか、あるいは軍部などの「中立な」既成権力に政治的安定を委ねるのか、といった不毛な選択に直面。
- イランにおける2009年の大統領選挙とその後の民主化要求運動は、権力側との政治的な妥協と国民的な和解プロセスを先導する可能性があり、「イスラーム主義」後を考察するうえで非常に興味深い事例。
アラブ各国における体制転換後の苦闘
中東アラブ世界のかつての盟主であったエジプトでは、2013年7月初旬に国軍主導による体制転換が発生し、その政治的混乱は現在まで継続している。この出来事は2011年初頭から始まったこの地域の長期的な政治的変動の性格をある程度暗示するものとして位置付けられる。すなわち、従来この地域の主要な政治的イデオロギーであった「イスラーム主義」の限界が露呈したと見なすことができるのである。
1950年代に高揚したアラブ・ナショナリズムが1970年代以降に政治的な求心力を失うなかで、それに代わって1980年代以来、中東各国に浸透していた「イスラーム主義」的な政治潮流は、ムスリム大衆の社会的な支持を拡大しながら、社会主義とは異なる「第三の道」を提示するものとして「アラブの春」の直前まで期待されていた。
チュニジア、エジプト、リビア、イエメンなどアラブ各国においてそれぞれの形で旧来の権威主義体制が崩壊した後、「イスラーム主義」諸勢力が政治的に前面に出てきたのは、そうした事情によるものである。彼らは、少なくともムスリム大衆に訴えるだけの具体的なモデル持っていた。彼らは、ムスリム同胞団やサラフィー主義者など、歴史的な経緯によって幾つかの政治集団を形成しており、それぞれにイスラームの教義に従った地道な奉仕活動などを通じて、社会的な組織力と動員力を養ってきた。
イスラーム主義 VS. 民主化勢力?
だが、実際には、2011年以降のアラブ各国における既成の権威主義体制に対する国民的な抵抗は、彼ら「イスラーム主義」の内部からではなく、むしろその外側で情報化とグローバル化の波に晒される都市部中間層の若年世代を中核にして起こっていた。彼らは、組織化という意味では政治的に未成熟であったが、それは決して現在までの政治過程において、彼らが退場していったことを意味していない。
「アラブの春」による体制転換後、現在も再建途上にあるアラブ各国では、事態が最も好転しつつあるとされるチュニジアも含めて、政治的な民主化と社会の近代化を求める「リベラルな」政治勢力と、従来からの自らの社会的・宗教的な規範に忠実であろうとする「イスラーム主義」的な政治勢力の間での意識の断絶、そしてそれに基づく対立・衝突が日々深刻化している。そしてこれは、体制転換を遂げたアラブ各国に限ったことではない。戦争状態の続くアフガニスタンやシリア、対ロシアのテロの恐怖に怯えるカフカース地域、アルジェリア南部のマリ国境地帯などでも、同様に深刻な社会的・政治的な亀裂の構造が看取できる。
これは、広い意味では、中東地域における近代化過程の歴史的矛盾であろうが、そう言っただけでは何の意味もない。従来、「イスラーム主義」の政治的な主張がこの地域の市民・大衆を引きつけてきたのは、強弱の差はあれ一様に欧米による19世紀以来の帝国主義的な「侵略」と「収奪」に対する異議申し立てをモチーフとして内包してきたことによるものである。また、その極端な現れがアルカイダに代表される「国際テロ組織」の反欧米的な主張であろう。
だが、こうした主張に心底から共感することもできず、さりとて現在の(ないし「アラブの春」以前の)腐敗した権威主義体制にも飽き足らない新たな社会層は、上述のアラブ各国における体制転換後の「イスラーム主義」勢力による新体制の建設を、エジプトの場合においては、まず憲法制定プロセスにおいて破壊したということになる。
中東アラブ世界のかつての盟主であったエジプトでは、2013年7月初旬に国軍主導による体制転換が発生し、その政治的混乱は現在まで継続している。この出来事は2011年初頭から始まったこの地域の長期的な政治的変動の性格をある程度暗示するものとして位置付けられる。すなわち、従来この地域の主要な政治的イデオロギーであった「イスラーム主義」の限界が露呈したと見なすことができるのである。
1950年代に高揚したアラブ・ナショナリズムが1970年代以降に政治的な求心力を失うなかで、それに代わって1980年代以来、中東各国に浸透していた「イスラーム主義」的な政治潮流は、ムスリム大衆の社会的な支持を拡大しながら、社会主義とは異なる「第三の道」を提示するものとして「アラブの春」の直前まで期待されていた。
チュニジア、エジプト、リビア、イエメンなどアラブ各国においてそれぞれの形で旧来の権威主義体制が崩壊した後、「イスラーム主義」諸勢力が政治的に前面に出てきたのは、そうした事情によるものである。彼らは、少なくともムスリム大衆に訴えるだけの具体的なモデル持っていた。彼らは、ムスリム同胞団やサラフィー主義者など、歴史的な経緯によって幾つかの政治集団を形成しており、それぞれにイスラームの教義に従った地道な奉仕活動などを通じて、社会的な組織力と動員力を養ってきた。
イスラーム主義 VS. 民主化勢力?
だが、実際には、2011年以降のアラブ各国における既成の権威主義体制に対する国民的な抵抗は、彼ら「イスラーム主義」の内部からではなく、むしろその外側で情報化とグローバル化の波に晒される都市部中間層の若年世代を中核にして起こっていた。彼らは、組織化という意味では政治的に未成熟であったが、それは決して現在までの政治過程において、彼らが退場していったことを意味していない。
「アラブの春」による体制転換後、現在も再建途上にあるアラブ各国では、事態が最も好転しつつあるとされるチュニジアも含めて、政治的な民主化と社会の近代化を求める「リベラルな」政治勢力と、従来からの自らの社会的・宗教的な規範に忠実であろうとする「イスラーム主義」的な政治勢力の間での意識の断絶、そしてそれに基づく対立・衝突が日々深刻化している。そしてこれは、体制転換を遂げたアラブ各国に限ったことではない。戦争状態の続くアフガニスタンやシリア、対ロシアのテロの恐怖に怯えるカフカース地域、アルジェリア南部のマリ国境地帯などでも、同様に深刻な社会的・政治的な亀裂の構造が看取できる。
これは、広い意味では、中東地域における近代化過程の歴史的矛盾であろうが、そう言っただけでは何の意味もない。従来、「イスラーム主義」の政治的な主張がこの地域の市民・大衆を引きつけてきたのは、強弱の差はあれ一様に欧米による19世紀以来の帝国主義的な「侵略」と「収奪」に対する異議申し立てをモチーフとして内包してきたことによるものである。また、その極端な現れがアルカイダに代表される「国際テロ組織」の反欧米的な主張であろう。
だが、こうした主張に心底から共感することもできず、さりとて現在の(ないし「アラブの春」以前の)腐敗した権威主義体制にも飽き足らない新たな社会層は、上述のアラブ各国における体制転換後の「イスラーム主義」勢力による新体制の建設を、エジプトの場合においては、まず憲法制定プロセスにおいて破壊したということになる。
イランの政治変化に見る新たな可能性
こうして、エジプトの場合は軍部の介入によってムスリム同胞団が権力の座から引きずり降ろされるなど、イスラーム主義が現実問題への解決能力という点で深刻な限界を露呈することとなった。そのようななか、アラブ各国は、不安定な政治的変革の道を進むのか、あるいは軍部などの「中立な」既成権力に政治的安定を委ねるのか、といった不毛な選択に直面している。当初は、「アラブの春」に呼応して政治的な民主化を希求したシリアの場合もまた、基本的な構図としてはこのような極めて狭い選択の幅をめぐって不毛な堂々めぐりを繰り返しており、その意味で、他のアラブ国と同様のジレンマに陥っていると言える。
こうした政治的なアポリアを超えて、中東社会が本来もっている若いポテンシャルを地域的な発展に結びつける新たな芽はどこにあるのだろうか。このことを考える際に、イランにおける現在の政治的なプロセスはある示唆を含んでいるように思われる。2013年8月のロウハーニー政権の登場とその後の核交渉の進展は、「アラブの春」のような政治体制の急激な変動を伴うものではなかったが、この間の変化を背後で支えていたのが、「イスラーム主義」以降の政治意識を共有する若い世代の登場であった。
イラン革命以来35年を経て、現在のオバマ政権が米・イラン関係の改善に大きな意欲を見せているのは、それが単に二国間関係に留まらず、シリア問題やアフガニスタン撤兵、イラク問題と深く連動していくという期待が大きいゆえだろう。だが、イラン側から見た場合、それ以上に大きな意味をもっているのは、2009年の大統領選挙とその後の民主化要求運動が、史上初めてとも言えるほど、権力側との政治的な妥協と国民的な和解へのプロセスを歩み始めているように見えることである。
これは、イランの地域的な覇権の伸長と湾岸アラブ国との対立といった問題とは別に、中東地域全体の「近代化」と「民主化」に関わる問題として、真剣に考察すべき興味深い事例である。これが、「イスラーム主義」を超えようとする動きとなるのか、注意深くその動向を見守るべきである。
こうして、エジプトの場合は軍部の介入によってムスリム同胞団が権力の座から引きずり降ろされるなど、イスラーム主義が現実問題への解決能力という点で深刻な限界を露呈することとなった。そのようななか、アラブ各国は、不安定な政治的変革の道を進むのか、あるいは軍部などの「中立な」既成権力に政治的安定を委ねるのか、といった不毛な選択に直面している。当初は、「アラブの春」に呼応して政治的な民主化を希求したシリアの場合もまた、基本的な構図としてはこのような極めて狭い選択の幅をめぐって不毛な堂々めぐりを繰り返しており、その意味で、他のアラブ国と同様のジレンマに陥っていると言える。
こうした政治的なアポリアを超えて、中東社会が本来もっている若いポテンシャルを地域的な発展に結びつける新たな芽はどこにあるのだろうか。このことを考える際に、イランにおける現在の政治的なプロセスはある示唆を含んでいるように思われる。2013年8月のロウハーニー政権の登場とその後の核交渉の進展は、「アラブの春」のような政治体制の急激な変動を伴うものではなかったが、この間の変化を背後で支えていたのが、「イスラーム主義」以降の政治意識を共有する若い世代の登場であった。
イラン革命以来35年を経て、現在のオバマ政権が米・イラン関係の改善に大きな意欲を見せているのは、それが単に二国間関係に留まらず、シリア問題やアフガニスタン撤兵、イラク問題と深く連動していくという期待が大きいゆえだろう。だが、イラン側から見た場合、それ以上に大きな意味をもっているのは、2009年の大統領選挙とその後の民主化要求運動が、史上初めてとも言えるほど、権力側との政治的な妥協と国民的な和解へのプロセスを歩み始めているように見えることである。
これは、イランの地域的な覇権の伸長と湾岸アラブ国との対立といった問題とは別に、中東地域全体の「近代化」と「民主化」に関わる問題として、真剣に考察すべき興味深い事例である。これが、「イスラーム主義」を超えようとする動きとなるのか、注意深くその動向を見守るべきである。
(すずき ひとし/地域研究センター上席主任調査研究員)
本報告の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。