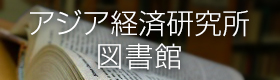ODAをラディカルに考え直す
アジ研ポリシー・ブリーフ
No.37
平野 克己
2014年4月30日
PDF (387KB)
政府開発援助(ODA)は、ここ半世紀ほどの短い期間で生成された、とてもestablishedとはいえない、ほかの政策に比べれば完成度の低い政策概念である。とはいえ、それが背負っている理念の崇高さを鑑みれば、いたずらに批判的であるよりも建設的に考えていくことが重要だ。しかし、既存の論議を不問の前提とするのは賢明ではない。ODAの定義を含め、根底部分から考え直していくラディカルな思考が必要であり、建設的でもある。
援助政策は省をもつべきか
ODAは政策概念として未完であるため普遍性に乏しい。そのため、ドナー各国によって実施機関のステイタスが大きく異なる。外交政策を担う外務省や、通貨政策を担う中央銀行の位置づけがどこでもおおよそ似通っているのとは対照的である。
ドイツは当初から、イギリスは1997年から再び、援助政策のための省を設置している。これは、考えてみると不思議だ。
日本の援助は通商産業省の管轄で始まり、やがて四省庁体制になった。政策手段が貿易投資に関するものなら経済産業省が所轄するし、金融ならば財務省の所轄だろう。中国の援助が商務部の所轄なのは、基本的には政策手段に基づいた差配だといえる。
だが、そもそも援助政策が開発途上国との関係を構築維持するための一手段である以上、それは当然外交の一環であるから、外務省が要とならなければならないはずだ。アメリカでは、国内農政の一部として対外援助法とは別の法的裏づけをもって生まれた食糧援助(PL480)が農務省管轄である以外は(軍事援助を除いて)国務省が主に所管している。
援助が外務省から独立した省をもてば二重外交に陥る恐れが発生する。閣内調整があったにしても、外交当局と援助当局が一つの国に対して異なる方針を立てて接触する可能性を排除できない。省庁構成としてこの可能性を許すには、両者にそれぞれ異なる使命を配分していなければならない。外交とは別個のラインをつくって遂行したほうが効率的になる援助政策とは、いったいどのようなものか。
イギリス国際開発省(DFID)に与えられている任務は国益ではない「国際益」であり、開発途上国における開発促進とミレニアム開発目標(MDGs)達成への貢献だけである。となれば外務省とは別の仕事だ。だが、開発途上国との良好な関係構築維持という国益に言及することなく国民の税金を外国人のために使う政策は、理解が難しい。
国際益即国益として理解できる唯一の例は覇権国だ。アメリカならば、世界秩序を構築して維持するために公金を投入するだろう。覇権国だけは、みずからを主体とした世界政策をもつ。では、イギリスの“世界政策”とはなんだろうか。前覇権国としての自恃と遺産だろうか。対米協力だろうか。いずれにしろイギリスは、植民地支配の過去をもちながら、アフリカで嫌われてはいないのである。
国際益や国際公共財という理念が、人類の進歩を象徴する大切なものであることは論を俟たない。しかしながら、さまざまな国家に分散した10億人を超える絶対的貧困層を救済するというのは、世界総生産の0.2%にすぎないODAが掲げてよい、現実的で妥当な政策目標だろうか。
わが国では援助政策を説明するに際して、当初は市場の開拓や資源確保が謳われ、1980年代以降は国際的な相互依存関係の維持強化が強調されてきた。だが、国によって日本との関係の濃淡は大いに異なる。親日的であるか反日的であるかを含めわが国との関係ぶりを考慮することなく、開発途上国の福利厚生一般を政策目標にすることを、はたして日本の納税者は許すだろうか。
ODAの定義は改変されるべきか
ODAの定義、すなわち「政府および公的機関が開発途上国の開発促進や福利向上のために支出する、グラントエレメント25%以上の資金」は、1972年にOECD開発援助委員会(DAC)が決めたものである。それからすでに40年が経過した。中国をはじめDACに加盟していない新興援助国が多数登場している現在、はたしてこれはいまでも、国際指標として妥当だろうか。
たとえば、日本のODAのグラント比率は54.7%でDAC加盟国中最低水準にあるが、それは、日本だけが大規模な開発金融(円借款)を提供しているからである。ODAの実績はネット額で計上されることになっているので、年によっては返済額が供与額を上回る円借款は、ほとんどカウントされていない。日本の貢献としてカウントされているのは無償援助ばかりなのにグラント比率は低く算定されるというのは、おかしくはないだろうか。
新興ドナー国の援助は借款が中心だ。金融であるからこそ多くの資金が動員できている。歴史的に開発原資の主体でありつづけてきた開発金融よりも無償援助のほうを高く評価する現在のODA定義は、経済史的観点からみておかしい。新興ドナーの貢献を正当に計れるものでもない。開発金融がどんなに巨額でも、それに見合う返済額があれば、その国は援助をしていないということになってしまう。順調な返済実績は、むしろ評価されるべきことのはずである。少なくとも国内ではそうだ。
社会政策的な無償供与と経済政策に属する開発金融は、国内政策においてはそもそも別個の政策分野に属す。私は、無償援助と開発金融は別建てで集計すべきであり、さらには、開発金融については収支表を公表するのが望ましいと考えている。開発金融をネットとグロスで集計するという現在のやり方は、実態をみるうえでも会計上も意味がない。
またODAを国際益に資するべきものとして措定し、できるだけ国益性を排して顕彰するというのであれば、マルチ援助、つまり国際開発機関への拠出を主体とすべきである。バイの援助は供与先が各国の裁量で決まる以上、それと、国益に基づいて遂行される外交とを峻別することはできない。マルチとバイを合算するのは、論理的におかしい。
ODA大綱は改定されるべきか
現行の「新ODA大綱」は2003年に策定されたものだが、日本の援助政策が現在の姿になったのは、官民連携が挿入された2008年の第4回アフリカ開発会議からといってよい。したがって現在のODA大綱は、すでに時代遅れである。
さらにいえば、現行の大綱は実質に乏しい文書であると思う。援助政策の目的を「国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じてわが国の安全と繁栄の確保に資する」ことだとする文言は、なにも援助政策に限ったものではなかろう。外交政策一般の目的、あるいは理念というべきだ。
史上稀に見る財政赤字を抱えている日本政府が、それでも援助に公金を投入するのであれば、それはいったいなんのためなのかを明確に示さなくてはならない。つまり、日本にとって望ましい対開発途上国関係を展望し、その構築をめざすという政策論でなければならない。援助論は、理念を語るものから政策科学に進化しなければならないと思うのである。
ODAは政策概念として未完であるため普遍性に乏しい。そのため、ドナー各国によって実施機関のステイタスが大きく異なる。外交政策を担う外務省や、通貨政策を担う中央銀行の位置づけがどこでもおおよそ似通っているのとは対照的である。
ドイツは当初から、イギリスは1997年から再び、援助政策のための省を設置している。これは、考えてみると不思議だ。
日本の援助は通商産業省の管轄で始まり、やがて四省庁体制になった。政策手段が貿易投資に関するものなら経済産業省が所轄するし、金融ならば財務省の所轄だろう。中国の援助が商務部の所轄なのは、基本的には政策手段に基づいた差配だといえる。
だが、そもそも援助政策が開発途上国との関係を構築維持するための一手段である以上、それは当然外交の一環であるから、外務省が要とならなければならないはずだ。アメリカでは、国内農政の一部として対外援助法とは別の法的裏づけをもって生まれた食糧援助(PL480)が農務省管轄である以外は(軍事援助を除いて)国務省が主に所管している。
援助が外務省から独立した省をもてば二重外交に陥る恐れが発生する。閣内調整があったにしても、外交当局と援助当局が一つの国に対して異なる方針を立てて接触する可能性を排除できない。省庁構成としてこの可能性を許すには、両者にそれぞれ異なる使命を配分していなければならない。外交とは別個のラインをつくって遂行したほうが効率的になる援助政策とは、いったいどのようなものか。
イギリス国際開発省(DFID)に与えられている任務は国益ではない「国際益」であり、開発途上国における開発促進とミレニアム開発目標(MDGs)達成への貢献だけである。となれば外務省とは別の仕事だ。だが、開発途上国との良好な関係構築維持という国益に言及することなく国民の税金を外国人のために使う政策は、理解が難しい。
国際益即国益として理解できる唯一の例は覇権国だ。アメリカならば、世界秩序を構築して維持するために公金を投入するだろう。覇権国だけは、みずからを主体とした世界政策をもつ。では、イギリスの“世界政策”とはなんだろうか。前覇権国としての自恃と遺産だろうか。対米協力だろうか。いずれにしろイギリスは、植民地支配の過去をもちながら、アフリカで嫌われてはいないのである。
国際益や国際公共財という理念が、人類の進歩を象徴する大切なものであることは論を俟たない。しかしながら、さまざまな国家に分散した10億人を超える絶対的貧困層を救済するというのは、世界総生産の0.2%にすぎないODAが掲げてよい、現実的で妥当な政策目標だろうか。
わが国では援助政策を説明するに際して、当初は市場の開拓や資源確保が謳われ、1980年代以降は国際的な相互依存関係の維持強化が強調されてきた。だが、国によって日本との関係の濃淡は大いに異なる。親日的であるか反日的であるかを含めわが国との関係ぶりを考慮することなく、開発途上国の福利厚生一般を政策目標にすることを、はたして日本の納税者は許すだろうか。
ODAの定義は改変されるべきか
ODAの定義、すなわち「政府および公的機関が開発途上国の開発促進や福利向上のために支出する、グラントエレメント25%以上の資金」は、1972年にOECD開発援助委員会(DAC)が決めたものである。それからすでに40年が経過した。中国をはじめDACに加盟していない新興援助国が多数登場している現在、はたしてこれはいまでも、国際指標として妥当だろうか。
たとえば、日本のODAのグラント比率は54.7%でDAC加盟国中最低水準にあるが、それは、日本だけが大規模な開発金融(円借款)を提供しているからである。ODAの実績はネット額で計上されることになっているので、年によっては返済額が供与額を上回る円借款は、ほとんどカウントされていない。日本の貢献としてカウントされているのは無償援助ばかりなのにグラント比率は低く算定されるというのは、おかしくはないだろうか。
新興ドナー国の援助は借款が中心だ。金融であるからこそ多くの資金が動員できている。歴史的に開発原資の主体でありつづけてきた開発金融よりも無償援助のほうを高く評価する現在のODA定義は、経済史的観点からみておかしい。新興ドナーの貢献を正当に計れるものでもない。開発金融がどんなに巨額でも、それに見合う返済額があれば、その国は援助をしていないということになってしまう。順調な返済実績は、むしろ評価されるべきことのはずである。少なくとも国内ではそうだ。
社会政策的な無償供与と経済政策に属する開発金融は、国内政策においてはそもそも別個の政策分野に属す。私は、無償援助と開発金融は別建てで集計すべきであり、さらには、開発金融については収支表を公表するのが望ましいと考えている。開発金融をネットとグロスで集計するという現在のやり方は、実態をみるうえでも会計上も意味がない。
またODAを国際益に資するべきものとして措定し、できるだけ国益性を排して顕彰するというのであれば、マルチ援助、つまり国際開発機関への拠出を主体とすべきである。バイの援助は供与先が各国の裁量で決まる以上、それと、国益に基づいて遂行される外交とを峻別することはできない。マルチとバイを合算するのは、論理的におかしい。
ODA大綱は改定されるべきか
現行の「新ODA大綱」は2003年に策定されたものだが、日本の援助政策が現在の姿になったのは、官民連携が挿入された2008年の第4回アフリカ開発会議からといってよい。したがって現在のODA大綱は、すでに時代遅れである。
さらにいえば、現行の大綱は実質に乏しい文書であると思う。援助政策の目的を「国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じてわが国の安全と繁栄の確保に資する」ことだとする文言は、なにも援助政策に限ったものではなかろう。外交政策一般の目的、あるいは理念というべきだ。
史上稀に見る財政赤字を抱えている日本政府が、それでも援助に公金を投入するのであれば、それはいったいなんのためなのかを明確に示さなくてはならない。つまり、日本にとって望ましい対開発途上国関係を展望し、その構築をめざすという政策論でなければならない。援助論は、理念を語るものから政策科学に進化しなければならないと思うのである。
(ひらの かつみ/地域研究センター上席主任調査研究員)
本報告の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。