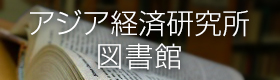援助政策を考え直す 経済学から国際政治学へ
アジ研ポリシー・ブリーフ
No.36
平野 克己
2014年4月30日
PDF (393KB)
2013年4月から「援助政策研究会」を立ち上げた。従来の援助論とはまったく異なる視点から援助政策を検討するためである。
これまでの援助論はおよそ、どのような支援が開発途上国の開発をもっともよく促進するかという観点から語られるのが常であった。しかし正確にいえば、これは援助政策そのものを見ているのではなく、開発というテーマを側面から、間接的に検討しているのである。これは開発研究の一種であるから、主に開発経済学の手法が使われてきた。また、提言相手は援助国の政府ではなく開発途上国の政府や人々ということになる。
つまりこれでは日本政府に対する提言にならない。援助の大宗である開発援助に開発効果が求められるのは当然だが、開発効果は一義的には援助受取国に帰属するのであって、それがいったい援助の出し手にどのような利益をもたらすのかが問われなければならない。それが援助を供与する目的だからである。たとえば、もし日本の援助によってある国の経済力が高まり、その結果その国が問題行動に出て日本との関係が緊張するような事態を招くなら、そのような援助に日本の納税者は賛成するだろうか。
これまでの援助論はおよそ、どのような支援が開発途上国の開発をもっともよく促進するかという観点から語られるのが常であった。しかし正確にいえば、これは援助政策そのものを見ているのではなく、開発というテーマを側面から、間接的に検討しているのである。これは開発研究の一種であるから、主に開発経済学の手法が使われてきた。また、提言相手は援助国の政府ではなく開発途上国の政府や人々ということになる。
つまりこれでは日本政府に対する提言にならない。援助の大宗である開発援助に開発効果が求められるのは当然だが、開発効果は一義的には援助受取国に帰属するのであって、それがいったい援助の出し手にどのような利益をもたらすのかが問われなければならない。それが援助を供与する目的だからである。たとえば、もし日本の援助によってある国の経済力が高まり、その結果その国が問題行動に出て日本との関係が緊張するような事態を招くなら、そのような援助に日本の納税者は賛成するだろうか。
私たちがめざすのは、援助を提供することで日本にどのような影響がもたらされるか、日本にとって望ましい援助政策とはなにかを探索することである。そもそも日本への貢献が期待できないのであれば、公金を投入して政府が援助を行う意義を主張できず、納税者に対して説明がつかなくなる。援助に限らず政策とはすべからくそういうものであり、主権者への説明責任を負っている。援助が政府の行う政策である以上、援助を受け取る側における効果と同時に、日本にとっていかなる意味と効用があるのかを、漠然とした曖昧な言辞ではなく、はっきりと示さなくてはならない。
日本への貢献には資源安全保障や食糧安全保障、輸出市場の開拓と確保など、経済的利益が含まれる。だがそれだけではない。国際社会のなかに日本の安全と繁栄のための基盤をビルトインしていくためにはさまざまな方途が必要で、経済分野はその一部にすぎない。たとえ経済的利益が得られなくても、払わなくてはならない負担はある。良好な経済環境は、それを可能にする国際関係なくしては獲得できないのである。そして、そのような国際関係を実現するには、そのための外交戦略が要る。
国際社会に作用するすべてのモメンタムを考察対象にして、その作用の連関を明らかにし、国際戦略の作成を専門とする学問が国際政治学である。したがって、本研究会は開発経済学ではなく国際政治学を方法論とする。私自身は経済学の出身だが、かねてより国際政治学者が援助政策を本格的にとりあげ、彼らのディシプリンを総動員して四つ相撲を組んでもらえないかと望んできた。
じつは、経済学は援助の存在意義を十全には説明できない。経済成長や開発効果を実現するのに不足している資源が補塡されるのなら、それは、だれが提供してもどこから注入されてもかまわない。言葉をかえれば援助の提供者は無差別なのであり、提供者の違いが効果や結果に影響を与えることは経済学の体系上ない。だから、経済学に援助政策は解けないのである。
開発経済学に限らず開発論はすべて、援助政策論なくしては援助国政府にとって意味をもたない。国際社会が人類の貧困問題に一体となって取り組むという「国際開発」理念を支えとするには、国際政治の現実はあまりに国家中心的で、かつ対立的である。また、援助の現場はときに非常に競争的だ。
こういう議論に対して開発業界の人々は嫌悪感を示すことが多い。だが欧米諸国は当初から、開発と援助をめぐる国際政治を認識したうえで外交を展開してきた。
そもそもイギリスとフランスが援助政策を始めたきっかけは、植民地が独立して別国家になったあと、それら諸国との関係を再構築しなければならないという差し迫った要請であった。第二次世界大戦後も植民地を放棄しようとしなかった英仏はインドシナ戦争やスエズ戦争に打って出るが、世界大戦で疲弊した本国財政に植民地維持のための負担は耐えがたいものだった。援助政策は、その財政負担を減らし、ながく親しんだ植民地省予算に代わる新しい予算費目を創出して定着させるためのものだった。
旧植民地の開発を、旧宗主国だけの責任ではなく国際問題として措定したのは、当時ロイド銀行会長であったフランクスが1956年にアメリカで行った「南北問題」講演である。また、欧州経済共同体(EEC)設立のためのローマ条約は海外領土との連合規定を含んでいたが、これは仏領アフリカに対する支出をEEC全体に拡散するものだったし、EECが開発途上国と結んだヤウンデ協定やロメ協定は、帝国崩壊後にフランスが築いた地域大の新しいシステムであった。このようにして英仏は、植民地政策を援助政策に改装することで開発援助を国際化し、多大な植民地維持費から解放されて、戦後の財政再建に成功したのである。
1960年にアフリカ諸国が大挙して独立し、途上国陣営が国際社会の多数派を構成するようになると、国連や世界銀行は開発問題に対処する体制を整えた。アメリカは、ケネディ政権の下で開発援助のためのシステムを完成させた。現在のODAの登場である。
大英帝国から世界政策を継承した当初のアメリカは、旧植民地の開発促進に関していささか楽観的な趣があったが、ベトナム戦争での敗北、第4次中東戦争での石油危機は、アメリカの世界戦略に深刻な反省を強いた。援助法案を通すための議会対策としてニクソン政権が打ち出したのがベーシックヒューマンニーズ(BHN)路線だが、この、きわめて人道主義的な援助論によってアメリカが集中的に援助を投入したのは、エジプトとイスラエルである。アメリカの援助はその後20年にわたって、主として中東戦略の政策手段として機能した。
援助政策の本質を知るひとつの手立ては、それがどの国に集中しているかを見ることである。人類普遍の貧困対策として開発援助があるなら、どの援助国も援助配分は似通ったものになるはずだし、二国間援助より多国間援助が多くなるのが自然だろう。だが現実には援助総額の7割以上は常にバイの援助であり、またドナーによって援助配分はまったく異なっている。
すなわち援助政策は間違いなく外交の一部である。外交当局から独立した“二重外交”として援助があるわけではない。ただそこにはパワーポリティクスとしての外交を超えるコスモポリタンな価値が期待され、人類的視点にたった“正義”を包摂しうる可能性を負託される。それが、援助政策を理念的に支えるという構図になるのである。
とはいえ援助に関する正確な理解は、こういった理念によって現実の政策を糾弾することではけっして得られない。国際開発理念が先にあって、それが援助政策を創製したわけではない。理念から現実を論じるのはマルクス主義が犯した過ちだ。その過ちをくりかえすことなく、歴史学者が歴史を見るように、援助政策における国際政治を観察し直さなくてはならないのである。
日本への貢献には資源安全保障や食糧安全保障、輸出市場の開拓と確保など、経済的利益が含まれる。だがそれだけではない。国際社会のなかに日本の安全と繁栄のための基盤をビルトインしていくためにはさまざまな方途が必要で、経済分野はその一部にすぎない。たとえ経済的利益が得られなくても、払わなくてはならない負担はある。良好な経済環境は、それを可能にする国際関係なくしては獲得できないのである。そして、そのような国際関係を実現するには、そのための外交戦略が要る。
国際社会に作用するすべてのモメンタムを考察対象にして、その作用の連関を明らかにし、国際戦略の作成を専門とする学問が国際政治学である。したがって、本研究会は開発経済学ではなく国際政治学を方法論とする。私自身は経済学の出身だが、かねてより国際政治学者が援助政策を本格的にとりあげ、彼らのディシプリンを総動員して四つ相撲を組んでもらえないかと望んできた。
じつは、経済学は援助の存在意義を十全には説明できない。経済成長や開発効果を実現するのに不足している資源が補塡されるのなら、それは、だれが提供してもどこから注入されてもかまわない。言葉をかえれば援助の提供者は無差別なのであり、提供者の違いが効果や結果に影響を与えることは経済学の体系上ない。だから、経済学に援助政策は解けないのである。
開発経済学に限らず開発論はすべて、援助政策論なくしては援助国政府にとって意味をもたない。国際社会が人類の貧困問題に一体となって取り組むという「国際開発」理念を支えとするには、国際政治の現実はあまりに国家中心的で、かつ対立的である。また、援助の現場はときに非常に競争的だ。
こういう議論に対して開発業界の人々は嫌悪感を示すことが多い。だが欧米諸国は当初から、開発と援助をめぐる国際政治を認識したうえで外交を展開してきた。
そもそもイギリスとフランスが援助政策を始めたきっかけは、植民地が独立して別国家になったあと、それら諸国との関係を再構築しなければならないという差し迫った要請であった。第二次世界大戦後も植民地を放棄しようとしなかった英仏はインドシナ戦争やスエズ戦争に打って出るが、世界大戦で疲弊した本国財政に植民地維持のための負担は耐えがたいものだった。援助政策は、その財政負担を減らし、ながく親しんだ植民地省予算に代わる新しい予算費目を創出して定着させるためのものだった。
旧植民地の開発を、旧宗主国だけの責任ではなく国際問題として措定したのは、当時ロイド銀行会長であったフランクスが1956年にアメリカで行った「南北問題」講演である。また、欧州経済共同体(EEC)設立のためのローマ条約は海外領土との連合規定を含んでいたが、これは仏領アフリカに対する支出をEEC全体に拡散するものだったし、EECが開発途上国と結んだヤウンデ協定やロメ協定は、帝国崩壊後にフランスが築いた地域大の新しいシステムであった。このようにして英仏は、植民地政策を援助政策に改装することで開発援助を国際化し、多大な植民地維持費から解放されて、戦後の財政再建に成功したのである。
1960年にアフリカ諸国が大挙して独立し、途上国陣営が国際社会の多数派を構成するようになると、国連や世界銀行は開発問題に対処する体制を整えた。アメリカは、ケネディ政権の下で開発援助のためのシステムを完成させた。現在のODAの登場である。
大英帝国から世界政策を継承した当初のアメリカは、旧植民地の開発促進に関していささか楽観的な趣があったが、ベトナム戦争での敗北、第4次中東戦争での石油危機は、アメリカの世界戦略に深刻な反省を強いた。援助法案を通すための議会対策としてニクソン政権が打ち出したのがベーシックヒューマンニーズ(BHN)路線だが、この、きわめて人道主義的な援助論によってアメリカが集中的に援助を投入したのは、エジプトとイスラエルである。アメリカの援助はその後20年にわたって、主として中東戦略の政策手段として機能した。
援助政策の本質を知るひとつの手立ては、それがどの国に集中しているかを見ることである。人類普遍の貧困対策として開発援助があるなら、どの援助国も援助配分は似通ったものになるはずだし、二国間援助より多国間援助が多くなるのが自然だろう。だが現実には援助総額の7割以上は常にバイの援助であり、またドナーによって援助配分はまったく異なっている。
すなわち援助政策は間違いなく外交の一部である。外交当局から独立した“二重外交”として援助があるわけではない。ただそこにはパワーポリティクスとしての外交を超えるコスモポリタンな価値が期待され、人類的視点にたった“正義”を包摂しうる可能性を負託される。それが、援助政策を理念的に支えるという構図になるのである。
とはいえ援助に関する正確な理解は、こういった理念によって現実の政策を糾弾することではけっして得られない。国際開発理念が先にあって、それが援助政策を創製したわけではない。理念から現実を論じるのはマルクス主義が犯した過ちだ。その過ちをくりかえすことなく、歴史学者が歴史を見るように、援助政策における国際政治を観察し直さなくてはならないのである。
(ひらの かつみ/地域研究センター上席主任調査研究員)
本報告の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。