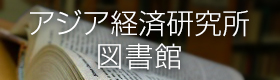論考:中央アフリカにおける国家の崩壊
アフリカレポート
No.52
PDF(697KB)
中央アフリカでは、2013年3月、当時のボジゼ政権がムスリムを主体とする武装勢力セレカの攻撃によって瓦解して以降、宗教の差異を基軸とする対立が激化し、暴力に歯止めがかからない状況が続いている。こうした「宗教対立」の根本には、政治秩序の崩壊がある。現在の混乱は、植民地化以前の奴隷狩りをも含む長期の歴史過程において中央アフリカ国家に埋め込まれた矛盾の噴出と解釈できる。フランスをはじめとする国際社会の関与は、人道危機を緩和する効果があった一方で、結果として国土の分断を促した。事態は依然として流動的だが、中央アフリカが政治秩序の確立に失敗すれば、国際安全保障上の著しい脅威となることは避けられない。
はじめに
中央アフリカ共和国の深刻な人道危機が世界の耳目を集めている。アフリカ大陸中央部に位置するこの国では独立以降クーデタが頻発してきたが、2013年3月にボジゼ(François Bozizé)大統領が反政府武装勢力セレカ(Séléka)によって放逐された後、国土を実効支配する能力を持った政権が存在せず、暴力や略奪に歯止めがかからない状況が続いている。とりわけ深刻なのは、宗教が社会的亀裂となって噴出する暴力の応酬である。ムスリムから成るセレカは、非ムスリムを標的として略奪、暴行、殺戮を繰り返した。一方、キリスト教徒の民兵組織アンチバラカ(Anti-balaka)がムスリムと目された人々を暴行、虐殺し、首都バンギからムスリムが大量に脱出する事態となった。双方の陣営とも、性暴力や子ども兵の徴用に手を染めている。2014年2月の段階で全人口約450万人のうち250万人が人道支援を必要とし、国内避難民の数は70万人に達し、28万8000人が難民として周辺国に逃れ、6万5000人の外国人が国外に脱出したとされる[UN 2014b, para16]。
こうした「法と秩序の完全な崩壊」[UN 2014b, para26]に対して、国際社会も手をこまねいてきたわけではない。中央アフリカに対しては、中部アフリカの地域機構である「中部アフリカ諸国経済共同体」(Economic Community of Central African States: ECCAS)が平和維持部隊「中央アフリカ平和確立ミッション」(Mission de consolidation de la paix en Centrafrique: MICOPAX)を長年派遣してきたが、事態が深刻化した2013年12月には、フランスが1600人規模の部隊を派兵(「サンガリス作戦」)し、アフリカ連合(African Union: AU)もMICOPAXを拡充して5500人規模の「アフリカ連合中央アフリカ支援国際ミッション」(Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine: MISCA)を展開させた。2014年に入ると、ヨーロッパ連合が平和維持部隊の派遣に踏み切り 1 、MISCAを母体とする1万人規模の国連PKO「国連中央アフリカ安定化統合多局面ミッション」(Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine: MINUSCA)の派遣が決定された 2 。しかしながら、国際社会の関与は、現状では十分な効果を挙げていない。軍事介入によって犠牲者数が抑制されたことは間違いないが、セレカとアンチバラカの勢力圏で国土が分断され、中央アフリカは統一国家と呼べない状況にある。
独立以来政治的不安定が続いてきたとはいえ、中央アフリカで宗教を基軸として広範かつ深刻な対立が起こったのは史上初である。なぜこうした事態に至ったのだろうか。国際社会はどのように対応すべきなのだろうか。中央アフリカに関する先行研究は少なく、現時点では事態を正確に理解することが先ずもって重要である。本稿では、公開情報に基づいて、事態の展開を再構成する(第1節)。そのうえで、なぜ宗教を基軸とする対立が起こったのか検討する(第2節)とともに、国際社会の軍事的な関与をどのように評価すべきかを考えたい(第3節)。
1.事態の展開
(1)セレカによる政権獲得
独立後の中央アフリカは、安定した政治権力を常に欠いてきた。有力な指導者ボガンダ(Barthélemy Boganda)を独立直前に飛行機事故で失った後、ダッコ(David Dacko)を後継者として1960年に独立したものの、わずか5年後に軍司令官のボカサ(Jean-Bédel Bokassa)がクーデタで権力を握った。ボカサは自らを皇帝と称するなど独裁体制を築いたが、その人権抑圧と腐敗が国際的な批判を招き、フランスの軍事介入によって1979年に失脚した。その後、ダッコが政権に復帰したが、人々の支持は低調で、1981年には参謀総長のコリンバ(André Kolingba)が再びクーデタを引き起こした。冷戦終結後にアフリカ諸国を席捲した民主化潮流のなかで、中央アフリカでも1993年に大統領選挙が実施され、現職のコリンバを破ってパタセ(Ange-Félix Patassé)が選出された。しかし、パタセ政権は経済危機と汚職によって人々の支持を失い、1990年代後半には軍の反乱が頻発した。結局、2003年、元軍参謀長のボジゼが武力で政権を奪った。
政治的不安定が常態化するなか、中央アフリカの政治指導者はしばしば権力闘争において外国の軍事力を利用してきた。1979年に首都バンギで反政府デモが勃発した際、ボカサはその鎮圧のために、隣国ザイール(現コンゴ民主共和国)に介入を求めた[小田 1986, 202]。ダッコはフランスの軍事介入を利用して政権に復帰し、パタセは兵士が蜂起した際にフランス軍やアフリカ諸国の平和維持部隊「バンギ協定監視アフリカ諸国ミッション」(Mission Interafricaine de Surveillance des Accords de Bangui: MISAB) 3 の手を借りて対応した。さらに、2002年10月に反乱軍の攻撃を受けると、パタセは鎮圧のために、カダフィ政権のリビアとコンゴ民主共和国の反政府武装組織「コンゴ解放運動」(Mouvement de Libération du Congo: MLC)の支援を得た。ボジゼの政権奪取に際しては、チャドのデビィ(Idriss Déby Itno)大統領が大きな役割を果たした。ボジゼが率いた反乱軍兵士の5分の4はチャド人だったと言われている[ICG 2007, 16]。
ボジゼは2004年に新憲法を制定し、翌年には大統領選挙に勝利した。制度的な側面で政権基盤が固まったものの、実効的統治は首都バンギとその周辺だけで、地方の国家機構は事実上機能しなかった。これは、中央アフリカの歴代政権と同じである[Bierschenk and Olivier de Sardan 1997]。2000年代半ば以降になると、チャドやスーダンとの国境付近で複数の武装勢力が跋扈するに至った。このなかには、旧パタセ派と関係が深い「民主主義再興人民軍」(Armée Populaire pour la Restauration de la Démocratie: APRD)のように北西部で活動していた組織もあるが、多くは「正義平和愛国会議」(Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix: CPJP)や「結集民主勢力同盟」(Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement: UFDR)のように北東部に基盤を置いていた。そのいずれにも、近隣のチャド人やスーダン人が参加していた。
こうした武装勢力の跋扈には、中央アフリカの統治能力の弱さに加えて、隣接地域の政治情勢が大きく影響している。中央アフリカに隣接するスーダンのダルフールで武力紛争が激化するのは2003年以降だが、これによってスーダンとチャドの間で難民と武装勢力が大挙して往来を繰り返した。チャドでも2000年代には地方で反乱が頻発している[武内2008]。紛争長期化によって、北東部のこの地域には、戦闘員としての経験を豊富に持つ人々が大量に生み出された。国籍にかかわらず、彼らは特定の政治勢力に対する忠誠心が低く、戦争に従事して生活する傭兵のような存在であり、時に強盗や追い剥ぎも行って国境付近の恒常的な治安悪化要因となった[Debos 2008]。2000年代半ば以降、ボジゼ政権は国際社会の協力も得て、これら武装勢力と和平協定やDDR(武装解除・動員解除・再統合)をめぐる交渉を進めたが、十分な成果は得られなかった。
中央アフリカの公用語の1つであるサンゴ(Sango)語で「連合」を意味するセレカは、これら北東部で活動する反政府武装勢力の連合体で、2012年9月頃までに結成された[Bradshaw and Fandos-Rius 2013, 257]。チャド、スーダンとの国境に近い北東部は人口希薄な地域で、住民の多くはムスリムである。中央アフリカ国民の8割以上はキリスト教やアニミズムを信仰する非ムスリムであり、人口の多くは西部や南部に居住する。北東部は植民地期以降最も開発が遅れた地域であり、独立後ボジゼまでの大統領はすべて南部のキリスト教徒だった。セレカには北東部のグラ(Goula)人やルンガ(Rounga)人が多く参加していたが、一貫した政治プログラムを持った組織とは言えず、当初はDDRの手当増額など経済的な要求を掲げていた[JA 2013a, 21-22]。
セレカが首都に向けた進軍を開始するのは2012年12月のことだが、この時にはスーダン人やチャド人などの外国人傭兵が加わり、また進軍中に国内のプール(Peulh)人などのムスリムをリクルートして、その規模は急速に膨れ上がった 4 。2003年にはチャドの支援を受けて政権を奪取したボジゼだが、数年前からデビィ大統領との関係は悪化しており、チャドはむしろセレカと通じていた[Marchal 2013a, 2-3]。セレカの進軍に恐れを成したボジゼはフランスに軍事介入を求めたが、オランド仏大統領はこれを拒否した。マリへの介入(2013年1月)直前のこの時期、中央アフリカの優先度は低いと判断されたのである[JA 2013b]。結局、チャドのデビィやコンゴ共和国のサス・ンゲソ(Denis Sassou-Ngesso)など周辺国指導者のイニシアティヴによって和平協定(2013年1月11日、リーブルヴィル協定)が結ばれ、権力分有が合意された。しかし、3月になってセレカはこの合意を反故にして再び進軍を開始し、3月24日に首都バンギを制圧した。ボジゼはカメルーンに亡命し、UFDRの指導者ジョトディア(Michel Djotodia)が国家元首に就任した 5 。これによって、中央アフリカ史上初めてムスリム勢力が政権を握った。ただし、ジョトディアは自らを移行期政権として位置づけ、リーブルヴィル協定で首相に任命されていた人権派弁護士のテイアンガイエ(Nicolas Tiangaye)を留任させ、旧中央アフリカ軍(Forces armées Centrafricaines: FACA)で尊敬を集めていたドレ・ワヤ(Jean-Pierre Dollé-Waya)を国軍参謀長に任命するなど、国民融和を模索する姿勢も示していた。
(2)仏軍介入とその影響
セレカは武力によって政権を獲得したが、治安の確立を優先課題とはしなかった。貧困地域の出身者や外国人傭兵、犯罪者から構成された急ごしらえの反乱軍は、首都への進軍の途中、そしてボジゼを放逐して政権を握った後も、住民への略奪や暴行を繰り返した。役所、病院、学校、教会、一般家屋などが、破壊、放火、略奪された。自動車、オートバイ、電化製品など、様々な略奪品がチャドやスーダン方面へ持ち去られ、国境の町の市場に並んだ[JA 2013d]。セレカはムスリムから構成されており、略奪や暴行の被害を受けたのは主としてキリスト教徒(非ムスリム)であった[HRW 2013a] 6 。セレカ兵の暴力と略奪が問題視されると、2013年9月、ジョトディアはセレカの解散を宣言したが、これは特段の効果をもたらさず、セレカ兵を首都から地方に移動させて略奪を拡散させただけであった[JA 2013d]。
セレカの略奪や暴力に対して、キリスト教徒側の民兵組織アンチバラカが結成され、2013年の後半以降、その反攻が活発化する。アンチバラカもまた、反政府武装勢力のAPRD、旧国軍FACA、その他自衛組織や犯罪者などの寄り合い所帯であり、統一的な意思決定機能を持った組織ではない。セレカ側の略奪や暴行に対抗するために組織されたアンチバラカであったが、ムスリムの一般人を襲い、モスクを破壊して、自分たちの領域からムスリムを追放していった。セレカとアンチバラカは、相互に戦闘を交えると言うよりも、それぞれが民間人を襲撃、略奪することによって、大衆レベルの暴力の応酬を激化させていった[HRW 2013b]。
セレカが権力を握った後、ECCASの首脳が調停に乗り出し、移行期を18ヶ月とするとともに、地域機構の平和維持部隊MICOPAXを700人から2000人に増強した[UN 2013, para10]。しかし、これも暴力の抑制には無力で、2013年後半になると、セレカ支配下の実態を告発するNGOの報告が国際社会を震撼させることとなった 7 。オランド仏大統領は8月下旬にNGOから中央アフリカの状況を聞いて衝撃を受けたと言われ[JA 2013d, 41]、その後フランスは介入への準備と国際社会への働きかけを強めていった。結局、アンチバラカが首都バンギに本格的な攻勢をかけるとの情報を得て、オランドは12月5日軍事介入に踏み切った。予定より3日前倒しし、当初計画の1200人を1600人に増員しての単独介入であった[AC 2013]。
仏軍介入後の政治過程の展開は急速だった。統治能力を問題視されたジョトディアは、後ろ盾とも言えるデビィに見放され、2014年1月10日、チャドの首都ンジャメナで開催されたECCAS首脳会議の場で辞任表明を余儀なくされた 8 。セレカ兵は首都バンギの兵営に隔離され、後に地方へと撤退した。1月20日には元バンギ市長のサンバ・パンザ(Catherine Samba-Panza)が暫定大統領に選出された 9 。セレカ主導の政権が倒れ、その軍事的脅威がバンギで消失すると、ムスリムに対する暴行や略奪が激化した。人々の反感はセレカを支援していると見られたチャドへ向かい、チャド人の商店は略奪され、平和維持活動に参加しているチャド部隊は人々の敵意の的となった。チャド政府は1月に2万人もの自国民を脱出させ[JA 2014a]、4月にはMISCAから部隊を撤収した[LM 2014d]。フランス軍やMISCAはアンチバラカの活動抑止に努めているが、人員不足から十分な対応ができず[UN 2014b, para55]、バンギ以外での活動は限定されたものでしかない。
中央アフリカが直面する危機は重層的である。アンチバラカが主導するムスリムへの暴力は収まってはいないし、地方ではセレカ兵による襲撃も続いている。こうした直接的な暴力の結果、人々の生活基盤は甚大な損傷を受けた。国内避難民や難民の数の多さは、それを雄弁に示すものである。また商業活動に従事し、流通ネットワークを担っていたムスリムが避難したために、バンギの物資流通は麻痺状態にある。略奪と暴行を受けた商人たちは、たとえ治安が回復してもすぐには戻らないだろう。経済の混乱が長期化することは避けられない。さらに、一連の事件は、中央アフリカの国民統合にきわめて深刻な打撃を与えた。バンギからセレカが撤収し、ムスリムが避難した結果、現在の中央アフリカは、アンチバラカが強い影響力を持つ西部とセレカが支配する東部に事実上分断されている[LM 2014c]。この分断を克服し、中央アフリカ国民の和解と再統合を進めるためには、長い歳月と真摯な努力が必要となろう。
2.「宗教対立」の実相
セレカがキリスト教徒に、アンチバラカがムスリムに暴行と略奪を加えたことは疑いのない事実である。一方、中央アフリカでは、建国以来政治的不安定こそ継続してきたものの、こうした宗教的な対立が顕在化したことはなかった。なぜ今回、宗教の違いが深刻な社会的亀裂として浮上したのだろうか。この点を考えるために、中央アフリカのイスラームについて国家形成との関連で概観しておきたい。
中央アフリカは、旧フランス領赤道アフリカの構成単位であるウバンギ・シャリ(Ubangui-Chari)の独立によって建国された。ウバンギ・シャリは、コンゴ川の支流であるウバンギ川を南部の、チャド湖に注ぐシャリ川を北部の境界とする植民地行政単位である。主要なエスニック集団であるバンダ(Banda)、バヤ(Gbaya / Baya)、サラ(Sara)、ンブム(Mboum)はいずれもイスラーム化されておらず、キリスト教やアニミズムを信仰する 10 。ムスリムは、この国の総人口の1割程度に過ぎない。キリスト教がこの地域に入るのは植民地化とほぼ時を同じくするから、植民地化以前は国土の大部分でイスラームが浸透していなかったことになる。
中央アフリカにおけるムスリムの主要な構成集団として、次の3つを挙げることができる。第1に、北東部の住民である。中央アフリカ北部は、フランスの支配が確立される以前、より北方のサヘル地域に位置するボルヌ(Bornu)、バギルミ(Baguirmi)、ワダイ(Wadai)、ダルフール(Darfur)などのイスラーム化された諸国との関係が深かった 11 。特に、南北スーダンやチャドに隣接する北東部のヴァカガ(Vakaga)県、バミンギ・バンゴラン(Bamingui-Bangoran)県、オート・コット(Haute-Kotto)県などの領域は、19世紀後半、バギルミやワダイと関係が深いダル・アル・クティ(Dar-al-Kuti)国の領域およびその影響圏であり、サハラ以北に輸出するために激しい奴隷狩りが行われた[Kalck 1992, 48-49]。これにより、中央アフリカ北東部の人口は激減したが、グラ人やルンガ人などその地域の住民はイスラームを受容した。
第2に、プール人である。プール人はフルベ(Fulbe)とも呼ばれ 12 、西アフリカからスーダンにかけてのサヘル地域に広く居住する。もともと牧畜を生業とし、イスラームを受容している。18~19世紀にはサヘル地域から現在のカメルーンにかけての広い地域で聖戦を遂行し、多数のイスラーム国家を樹立した歴史を持つ[嶋田 1995]。現カメルーンのアダマワ高原に成立したプール人諸国家にとって、バヤ人など中央アフリカ西部に居住する非ムスリムの人々は奴隷狩りの対象だった。バヤ人は19世紀末、プール人に対する大規模な反乱を起こしている[Kalck 1992, 66]。今日、中央アフリカ国内に居住するプール人の多くは、商業や牧畜で生計を立てている。彼らは長くこの地域で暮らしてきたものの、コミュニティのなかではマイノリティである。
第3に、チャド人を中心とする外国人である。先述したように、チャド人やスーダン人は近年中央アフリカ北部で紛争や犯罪に深く関与してきた。APRD、CPJP、UFDRなど、2000年代半ばから活発に活動する反政府武装勢力の指導者にもこうした人々が多く見られる。彼らの多くはムスリムである。加えて、ボジゼ政権期には、中央アフリカに対するチャドの影響力が著しく高まった。チャドに依存して政権を獲得したボジゼは、年下のデビィを「兄貴」(grand frère)と呼び [Marchal 2013a, 2]、ボディガードにもチャド人を配置していた。ボジゼを「デビィに任命された中央アフリカの知事」と呼ぶ者さえいたほどである。結果として、多くのチャド人が経済機会を求めて首都バンギにも移入してきた。バンギの住民の多くにとって、ムスリムとはチャド人であり、したがって外国人なのであった[AC 2011]。
こうした歴史的経緯と社会構造を踏まえた時、セレカによる政権奪取を次のように解釈することができよう。セレカの軍事的勝利によって、中央アフリカ史上初めてムスリムが政治権力を握った。一方、バンギの住民をはじめとする多くの人々にとって、セレカは最も後進的な地域の出身者と外国人から成る組織であり、彼らは暴行や略奪など「野蛮」な行為を繰り返した。それはまさに、身内には決して行わない、よそ者の蛮行であった。セレカが暴行や略奪を行う際、プール人などムスリムを手引きとして利用し、また彼らに有利な計らいをしたことはしばしば指摘されており[HRW 2013a, 10]、MICOPAXの構成部隊であったチャド軍がセレカに親和的だったとの指摘もある[Marchal 2013b, 2]。2013年12月末には、MISCAのチャド部隊が、セレカを武装解除しようとしたブルンジ部隊を攻撃するという前代未聞の事件が起こっている 13 。こうしたなか、政治指導者の煽動と相まって 14 、セレカによる暴力の犠牲となった人々の間には、ムスリムやチャド人に対する報復感情が充満したのである。
もともと中央アフリカに根深い「宗教対立」の歴史があったわけではない。政治秩序が崩壊するなかで、略奪や暴行、そして報復の相手を探すために、「ムスリム」、「クリスチャン」という社会的なレッテルが利用されただけである。しかし、いったんこうした社会的亀裂に沿って甚大な人的、物的被害が出てしまうと、その修復は容易ではない。
3.軍事介入の効果と課題
2013年12月、オランド仏大統領が軍事介入を決断した主たる理由は、人道危機が看過できない状況であったためである。旧宗主国のフランスに、中央アフリカに対する様々な利権があることは疑いない。また、特に英米系のメディアが強調するように[AC 2013]、混乱の結果としてアルカイダ系グループが流入することを恐れたという理由もあろう。しかし、マリでの軍事的関与を抱え、ボジゼからの介入要請を一度は拒否したフランスがこの時期介入を決意した要因として、人道的配慮がきわめて大きかったことは強調すべきである。政治秩序が崩壊し、多数の一般人が紛争に動員される状況下、アンチバラカが本格的な反攻に乗り出せば、膨大な犠牲者が出ることは避けられない。特に首都バンギなど西部においてムスリムは社会的マイノリティであるから、大量虐殺の危険性が現実味を帯びる。人口的少数派のトゥチが全土で虐殺の対象となった1994年のルワンダ・ジェノサイドと同じ構図である。ルワンダ内戦の際、ジェノサイドに責任を負うハビャリマナ政権への支援を続け、国際的な批判を浴びたフランスがこの点を意識していなかったとは考えにくい 15 。切迫した状況のなか、大量殺戮防止のための軍事行動を取る能力と意思を持つのは自分たちしかいないという意識は、オランド政権指導部に共有されていたと思われる。
介入の当初から、フランスは中央アフリカ問題を自分たちだけで抱え込まず、「国際化」することを目指していた。フランスが派遣した部隊の規模は当初1600人であり、アフガニスタンに数万人の兵士を送ったアメリカとは比較にならない。フランスはまた、自国軍の役割をAUの平和維持部隊MISCAの支援活動と位置づけ、同時にヨーロッパ連合(EU)や国連による平和維持活動を求めるなど、国際社会における正統性がより高い形で中央アフリカに関与しようとしてきた。フランスとアフリカ旧植民地との癒着した関係が「フランサフリック」という言葉で語られることがあるが、オランド政権としてはこうした疑念や批判を招かないよう、心を砕いてきたと言えよう。規模は小さいながらもEUが派兵に踏み切り、国連もまた平和維持部隊派遣に合意したことで、事態はフランスが望む「国際化」の方向へと進みつつある。
軍事介入は事態を急速に、かつ大きく展開させた。ただし、その評価は簡単ではない。フランスの介入が大量殺戮を防止したことは評価すべきだろう。バンギでのムスリムに対するリンチや、地方都市におけるセレカの襲撃が報じられているが、フランスの介入がなければ犠牲者数はもっと多かったはずである。大量殺戮を一定程度抑止した点で介入は有効であった。それはまた、政治過程をスピードアップさせる効果を持った。治安の確立に取り組む意欲を疑われたジョトディアは退陣を余儀なくされ、サンバ・パンザ政権の下で移行プロセスが明確化した。それを支える国際的な枠組みも、徐々に整えられつつある。
一方で、フランスの軍事介入は、結果として国土の分断をもたらした。介入とともにセレカは兵舎に戻り、その後自らの地盤である北部や東部へと移動したために、バンギを含む西部ではアンチバラカが圧倒的に優勢となった。保護者を失ったムスリムは、この地域からの脱出を強いられた。セレカはバンギから去ったが、戦闘に敗れて撤退したわけではない。その勢力は大きな損害を受けておらず、国土の東半分を実質的な支配下に置いたままである。フランス軍にせよ、MISCAにせよ、地方への展開は十分できていない。情報は極めて乏しいものの、東部などでセレカの暴力や略奪が継続している可能性は高い。セレカとアンチバラカの暴力を統御できない限り、それぞれの勢力圏で社会的マイノリティに対する排斥が続き、中央アフリカは1つの主権国家としての実態を失っていくだろう。
まとめと展望
中央アフリカの危機は「宗教対立」と表現されることが多いが、その本質はむしろ「国家の崩壊」にある。宗教の差異という亀裂がこの国で顕在化したのは、セレカが政権を奪取して以降、わずかここ1年あまりのことに過ぎない。「宗教対立」は中央アフリカという国家の形成過程に埋め込まれた様々な矛盾が、政治秩序が崩壊するなかで噴出した結果である。そこには、植民地化以前の奴隷狩り、フランスによる恣意的な国境画定、北東部の開発の遅れ、建国以来の政治的不安定と国家機構の機能不全、フランスやチャドとの特殊な関係といった要因が幾重にも影響を与えている。
事態はなお予断を許さない。人道危機は依然としてきわめて深刻だし、国土の分断を克服するための施策は未だなされていない。人道支援に迅速に取り組む必要があることは言うまでもないが、分断された国家をどのように再建するのか、中央アフリカの政治指導者は、国際社会とともに真剣に考えねばならない。そこで優先されるべき課題として次の3点を指摘しておきたい。
第1に、セレカとアンチバラカを解体し、国民が信頼できる治安機構を確立することである。治安部門改革はボジゼ政権期から取り組まれてきたが、目立った成果を挙げられなかった。しかし、全土を巻き込む内戦が起こってしまった以上、これを最優先の課題としなければならない。第2に、東部地域の開発である。中央アフリカは世界の最貧国の1つだが、東部、特に北東部地域は歴史的に中央政権から放置され、貧困や治安悪化を招いてきた。ムスリムが多数を占めるこの地域を中央政府に再統合することが、紛争後の国家建設の前提条件を成す。第3に、地域的な取り組みである。セレカに多数のチャド人、スーダン人が参加した事実が示すように、中央アフリカの紛争は近隣諸国と深く連関している。ダルフールや南スーダンで紛争状態が継続している今日、中央アフリカ一国単位で平和構築の施策を考えても意味がない。ECCASやAUなど地域機構の主体的な関与の下、実効的な対策を検討する必要がある。
これらはいずれも容易な事業ではない。しかし、もし中央アフリカが秩序確立に失敗し、アフリカ中央部に無法地帯が出現すれば、その国際安全保障上のコストは計りしれないものとなろう。
2014年5月29日脱稿。
付記:本稿執筆のための調査には、アジア経済研究所運営費交付金のほか、次の科研費補助金を得た。課題番号23221012、23243019、25101004。
参考文献
〈日本語文献〉
小田英郎 1986『アフリカ現代史III中部アフリカ』山川出版社.
嶋田義仁 1995『牧畜イスラーム国家の人類学——サヴァンナの富と権力と救済』世界思想社.
武内進一 1995「誰がルワンダに武器を与えたのか?——NGOによる調査資料から」『アフリカレポート』20: 10-15.
武内進一 2008「チャドの不安定化とダルフール紛争」『アフリカレポート』47: 9-14.
〈外国語文献〉
AC (Africa Conflidential) 2011. “Mastering the Militias.” 52(19), 23 September: 10-11.
AC (Africa Conflidential) 2013. “Central African Republic: On the Brink.” 54(25), 13 December: 4.
Bierschenk, Thomas and Jean-Pierre Olivier de Sardan 1997. “Local Powers and a Distant State in Rural Central African Republic.” The Journal of Modern African Studies 35(3): 441-468.
Bradshaw, Richard A. and Juan Fandos-Rius 2013. “Recent history, The Central African Republic.” In Africa South of Sahara 2014 (43rd Edition). London: Routledge, 253-259.
Debos, Marielle 2008. “Fluid Loyalties in a Regional Crisis: Chadian ‘Ex-Liberators’ in the Central African Republic.” African Affairs 107(427): 225-241.
FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’homme) 2013. République centrafricaine: Un pays aux mains des criminels de guerre de la Séléka. Paris.
HRW (Human Rights Watch) 2013a. «Je peux encore sentir l’odeur de mort»: La crise oubliée des droits humains en République centrafricaine. New York.
HRW (Human Rights Watch) 2013b. «Ils sont venus pour tuer»: Escalade des atrocités en République centrafricaine. New York.
ICG (International Crisis Group) 2007. “République centrafricaine: anatomie d’un état fantôme”, Rapport Afrique de Crisis Group No.136.
JA (Jeune Afrique) 2013a. “Centrafrique: Peut-on sauver le soldat Bozizé?” 2713, du 6 au 12 janvier: 20-26.
JA (Jeune Afrique) 2013b. “France: L’arme au pied?” 2713, du 6 au 12 janvier: 26.
JA (Jeune Afrique) 2013c. “Djotodia, du maquis aux lambris.” 2725, du 31 mars au 6 avril: 14-15.
JA (Jeune Afrique) 2013d. “Centrafrique: A qui la faute?” 2751, du 29 septembre au 5 octobre: 38-42.
JA (Jeune Afrique) 2013e. “Sans foi ni loi.” 2751, du 29 septembre au 5 octobre: 42.
JA (Jeune Afrique) 2014a. “Centrafrique-Tchad: La déchirure.” 2765, du 5 au 11 janvier: 10-12.
JA (Jeune Afrique) 2014b. “Centrafrique: Catherine et les soudards.” 2768 du 26 janvier au 1er février: 10-12.
Kalck, Pierre 1974. Histoire de la république centrafricaine. Paris: Editions Berger-Levrault.
Kalck, Pierre 1992. Historical Dictionary of the Central African Republic. Metuchen and London: The Scarecrow Press.
LM (Le Monde) 2014a. “Centrafrique: Comment la France a précipité la fin de Djotodia.” 10 janvier.
LM (Le Monde) 2014b. “Centrafrique: l’EU enverra des soldats « aussi vite que possible ».” 20 janvier.
LM (Le Monde) 2014c. “Centrafrique: Victoire de la ‘purification ethnique’ contre les musulmans.” 5 mars.
LM (Le Monde) 2014d. “Le Tchad se retire de la force africaine en République centrafricaine.” 3 avril.
Marchal, Roland 2013a. “Un bégaiement de l’histoire? La crise en RCA en 2012-2013.” Paper presented at the Séminaire Douala, held on February 17, 2013.
Marchal, Roland 2013b. “CAR: The Return to War.” Paper written for the World Bank.
Prunier, Gérard 1995. The Rwanda Crisis: History of a Genocide: 1959-1994. London: Hurst and Company.
UN (United Nations) 2013. “Report of the Secretary-General on the Situation in the Central African Republic.” (S/2013/261, 3 May 2013)
UN (United Nations) 2014a. “Letter dated 25 February 2014 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council.” (S/2014/45)
UN (United Nations) 2014b. “Report of the Secretary-General on the Central African Republic Submitted Pursuant to Paragraph 48 of Security Council Resolution 2127 (2013).” (S/2014/142, 3 March 2014)
- 2014年1月20日、欧州連合理事会(Council of the European Union)は、中央アフリカにおいてMISCAとフランス軍によって遂行されてきた文民保護活動を支援するために、軍事活動に従事する決定を下した[UN 2014a]。その規模は500人程度と想定されており[LM 2014b]、4月から現地で活動を開始した。
- 2014年4月10日付安保理決議第2149号。本格的な展開は9月以降にずれ込む見通しである。
- 1996年12月のフランス・アフリカ首脳会議の場でパタセが提案し、ブルキナファソ、チャド、ガボン、マリなどのアフリカ諸国が総勢約800人の部隊を提供した。MISABは、1998年に国連PKOの「中央アフリカ国連ミッション」(Mission des Nations Unies en République centrafricaine: MINURCA)に引き継がれ、2000年に撤退した。
- セレカを構成する主要武装勢力は合わせて5000人程度と推計されるが、セレカに参集した兵士は全部で2万5000人と言われる。それだけ外国人傭兵や機会主義者が数多く参加したのである[JA 2013e]。
- 北東部ヴァカガ県生まれの彼は、エスニック集団としてはグラ人である。2003~2006年にダルフールのニャラ(Nyala)に領事として滞在し、チャドの反政府勢力やスーダンのグラ人との間にネットワークを築いた[JA 2013c]。
- この時期、セレカの兵士が略奪や暴行を主導したことは疑いないが、ムスリムが加害者でキリスト教徒が被害者という構図は相対化して考える必要がある。セレカの行動に乗じて、FACAの元兵士や一般市民が略奪に参加したし、カネがあればセレカ兵を雇って略奪を逃れることもできた。ムスリムであれ、キリスト教徒であれ、混乱のなかで貧困層が被害を受けたのである[Marchal 2013b, 9-10]。
- 特に、HRW[2013a]とFIDH[2013]の2つの報告書の影響が大きい。
- この背景には、フランスの周到な根回しがある。年明け早々、ルドリアン仏国防相はチャドとコンゴ共和国を訪問し、ジョトディア排除に向けた入念な打ち合わせを周辺国首脳との間で行った[LM 2014a]。
- サンバ・パンザはカメルーン人の父と中央アフリカ人の母を持ち、フランスで法学を学び、ビジネスで成功した経験を持つ。ンジャメナ生まれでアラビア語を話すが、有力な野党政治家のジゲレ(Martin Ziguélé)に近いとされ、セレカと結びつきが強いわけではない[JA 2014b]。
- バンダは主として国土の中部に、バヤは西部に居住する。サラの主要居住地はチャド南部、ンブムのそれはカメルーン東部にあり、中央アフリカ国内ではそれぞれとの国境付近が居住地域となっている。
- 植民地期以前から独立までの中央アフリカ史については、Kalck[1974]が詳しい。
- 牧畜に従事するプール人は、ンボロロ(Mbororo)、ンバララ(Mbarara)、フラタ(Fulata)などと呼ばれる[HRW 2013a, 35]。
- Radio France International, “Centrafrique: coups de feu entre Burundais et Tchadiens de la Misca” 24 décembre 2013 ( http://www.rfi.fr/afrique/20131224-rca-burundais-tchadiens-misca-tirent-dessus/ ).
- ボジゼは亡命した後、全てはチャドのせいだというメッセージを発し続けた。単純化された陰謀論が浸透し、チャド人への敵意を煽った[Marchal 2013b, 17]。また、マスメディアでムスリムを標的とするヘイトスピーチが流されたことも指摘されている[UN 2014b, para8]。
- ルワンダのジェノサイドとフランスの責任については、武内[1995]、Prunier[1995]を参照。