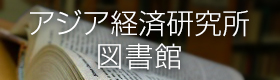『中国の台頭』と『反動の季節』: 香港とシンガポールに見る、摩擦と反作用のかたち
政策提言研究
2013年2月
PDF (432KB)
※以下に掲載する論稿は、平成24年度政策提言研究「 中国・インドの台頭と東アジアの変容 」研究会の久末亮一委員が、研究会活動を通じて得た知見を自らの責任において取りまとめたものです。
はじめに
「中国の台頭にともなう周辺諸国・地域との摩擦」と聞いて先ず思い起こすことは領土・領海紛争や貿易摩擦といった問題であろう。しかし本稿は、そうした枠組みで発生している摩擦を取り扱うものではない。むしろ本稿では、21世紀に入ってからの中国の膨張によって、有形無形のインパクトが外に向かうことを契機に、その進出先となった周辺諸国・地域で社会問題が生じ、国民・市民レベルでの反発が噴出していることに着目する。その上で、摩擦と反作用の生じる構造や背景について考えてみたい。
こうした問題は特に、中国からのインパクトが大量かつ直接的になるほど、その受け皿となっている「場」で顕著となっている。その前線こそが、香港とシンガポールという2つの都市である。これらの都市は、それぞれ「一国両制」と「独立国家」というステータスの違いはあるが、地域内の集散地であるがゆえに、この10年ほどの間で中国からのインパクトを直接・間接的に受けることで、次第に大きな摩擦が起こってきた。これに対して現在は、まさに「反動の季節」とも言うべき、さまざまな反作用が生じている。
これらの事象は、現在あるいは将来において、他地域でも同様に起こりうる摩擦や反作用を想定する上での、貴重な先行事例でもある。そこで本稿は、中国との接触において前線となっている、香港とシンガポールという2つの都市に着目しながら、かつて筆者が歩き、接触し、感じてきた、人々の言葉、街の様子、起こっている事象などを織り込みながら、上記問題の構造や背景に迫りたいと考える。
1.香港の「反国民教育」運動に見えるもの
2012年後半の香港では、一つのテーマが社会を大きく揺るがした。それが香港の公教育における、いわゆる「国民教育」をめぐる一連の騒動である。これは愛国主義的な教育を学校で実施する導入計画に対し、香港市民から幅広い反対運動が巻き起こり、香港政府が事実上の政策撤回に追い込まれた、というものである。
プログラムの内容は、「中国人としてのアイデンティティ」を育成するため、2012年9月の新学期から公立小学校で「道徳・国民教育」科目が導入され、2013年からは中学・高校でも順次導入される予定となっていた。しかし、その内容は21世紀の現代社会においては、恐ろしく常軌を逸した内容であった。「中国モデル」というタイトルの教材冊子は、中国共産党については、進歩的かつ無私無欲で団結が固いと解説し、また複数政党制はアメリカなどの国々に見られるように国家に最悪の事態をもたらす、などと記している。また1989年の天安門事件など、現代中国および共産党の失政や問題ともいえる部分については、言及がなされていない。
この天地が逆転したような荒唐無稽なプロパガンダを押し付けようとしたことに、香港市民は敏感に反応した。「反国民教育」の世論は日増しに高まり、8月末には9万人近い人々が参加する反対デモが発生し、国民教育に反対する意思を表明した。この世論による強烈な批判を受けて、9月8日、梁振英行政長官は、導入は各校の判断に任せ、全面導入についても期限を設定しないと表明し、事実上の政策撤回を表明した。
この一件は、国家安全保障・反逆罪・分裂行為などについて規定した基本法23条の立法化問題について、2003年に発生した香港市民による広範囲な反対運動と同じ構造である。それは中国共産党の教条、すなわち20世紀の「負の遺産」とも言うべき全体主義的な社会・思想統制という押し付けに対して、21世紀の現代を生きる市民社会の声が、正面から衝突しているのである。香港社会は、単純に実利主義・利益主義の権化のように見られがちである。しかし実際には、後述のように、長年にわたって築かれてきた健全な市民社会の良識が根付いていることを、「反国民教育」運動は示している。それは専制者の圧制に対して、屈することのない自由な市民の意思である。
しかし中国は、この市民社会というコンセプト自体を、まったくといってよいほど理解していない。香港市民の反応を、「健全」な民衆の声と捉えることはなく、ただの反国家・反体制・反党的な動きとしか看做さない。これは中国における為政者の思考の本質が、全体主義・専制主義に基づく「支配」にあることを考えれば、まったく不思議なことではない。現在、中国国内のみならず、香港にも、あるいは世界にも、中国の異常な「経済発展」に幻惑され、事物の本質を見失い、あるいはそれに擦り寄る意見が溢れている。しかし彼の体制の本質とは、中国伝統の専制主義と、20世紀の生み出した恐るべき全体主義という、二つの「支配」の思考を正統に受け継いだものであることを、決して忘れてはならない。
このように考えれば香港では、いまや恐ろしいほど対極的な政治概念が、先鋭なかたちで衝突しているのではなかろうか。それはまた、膨張する中国という存在と向き合わざるを得ない、21世紀という時代のあり方を象徴している。
2.「一国両制」のリアル・ポリティククス
1997年の香港返還は、香港の人々の手の届かないところで取り決められた。英国と中国の取り決めでは、返還後50年間は香港の地位や体制を保証し、「一国両制」(一国二制度)の下で「港人治港」(香港人が香港を統治する)を守る、という建前が合意されていたはずであった。
しかし返還後、香港が直面した現実は、これとは裏腹なものであった。政治面では、特別行政区の行政長官選挙、立法会の議会選挙などに対して、中央は明白な資金的・組織的な介入をおこない、広義の民主派の台頭を押さえ込んできた。また、実質的な治安維持法となる基本法23条の立法化についても、現在まで実現はしていないものの、制定に向けて露骨なまでの介入をおこなってきた。あるいは保障されていたはずの司法の独立性についても、最終的な司法解釈などについては中央の批准・承認に従う必要があり、この面でも香港にはガラス天井がはめ込まれている。
たしかに香港の特別行政区政府は、行政長官を含めて「香港人」で占められ、運営されてはいる。しかし現実には、中央が常に介入し続け、その意図の下にあり続けることが、「一国両制」という現実、特に中華人民共和国という専制的な非民主国家の主権下に入った香港の現実であった。こうした事態を、皆が予見しえなかった訳ではない。しかし多くの香港人にとっては、これが避けがたい現実であった。「雨が降って濡れたところで、天を恨んでも仕方がない」のである。
これは植民地時代からも同様であった。ハイレベルでの政治など、香港人にはどうしようもない「天の上」の話であり、香港人が自らの運命を自らで決めることなどは、常識では想像もつなかいことだったのである。こうしたなかで、香港人の特性のひとつである、機会主義・実利主義の精神が培われていった。機を見るに敏であり、自己の損得を追求するために生きることが、かつての香港人のあり方であった。それゆえに、香港社会の経済利益優先の風潮を批判している「リベラル」な者でさえ、自己の株式投資や不動産投資が生み出す利益には、あっけらかんとした態度であからさまに喜びをあらわにする。
こうした土壌のなかで、返還直後から数年まで、香港の友人たちからは、事あるごとに中国との一体化は決して悪くない、経済的な恩恵や繁栄を保障してくれる、香港人も中国人であり、日々強くなる祖国中国に誇りを感じる、などと迎合的な意見が多く聞かれた。これは「天に逆らえない以上は、現世で実利を得る」思考そのものであった。
しかし、いまや香港人の感情は、かつて迎合的な態度をとっていた者すら、口をつぐむか、あるいは反中国的な態度に変化するほど、中国への不満を強めている。かつての迎合的態度は、中国という枠組みのなかで利益を得ようとする人間の、表面的な口からしか聞くことはできない。しかし、こうした人々ですら本音は異なる。大陸が関与するエリート青年組織に名を連ねる野心家の若手弁護士は、「自分の利益が第一。中国は祖国でも、政府や共産党には興味がない。だがビジネスや社会的成功には役立つ」と述べ、ある政府高官ですら、「結局、中央は香港人を信用していない。私が考えるのは、中国のなかで香港の利益を最大化することだ」と述べていた。
3.踏み躙られた「市民社会」のルール
それでは、この十数年で生じた変化とは何であったのか。何が香港の人々を、中国への苛立ちへと駆り立てているのであろうか。そこには強大化する中国のインパクト、さらには中国から流入するヒトやカネの所作が、香港における「市民社会」のルールを踏み躙り続けてきたという事実がある。
それは何も高尚なものを意味するわけではない。私たちにとっては至極あたりまえの、統治者が築き上げる上からの秩序ではなく、市民が社会のなかで築き上げてゆく文明社会のルールは、香港社会でも培われてきた。特に40代以下の香港人は、香港社会における意識の成熟とともに成長してきた。彼らは安定して豊かになった時代に生まれ、そのなかで権利意識や公民意識を育み、またインターネットなどのITツールの利用によって、それ以前の世代が物理的・言語的な情報アクセスの限界を抱えていたのとは異なり、境界を越えた自由な範囲を行き来し、幾万もの情報や思想に接することができる。
これらの世代は、それまでの「受動性のなかの能動」とも言える、かつての機会主義・功利主義を第一とした香港人意識とは異なる意識を持っている。彼らは程度の差こそあれ香港の自主性、言い換えれば香港が育んできた、そして彼ら自身を育んできた、香港の市民社会という存在・価値観を重んじる意識が強い。同時に、もはや彼らにとって政治とは「天の上」の話ではない。こうした意識をベースとした香港人にとって、専制的な権力によって異なる価値観を押し付けようとする大陸の強圧的な態度は、市民社会の常識から逸脱したものとして映る。「祖国」と「共産党」がなすことには、異を唱えず黙って従えなどというロジックは、当然ながらまったく通用しないのである。
こうした背景の一方で、この10年で中国との接触がより直接的なものとなってきた現実が、香港人のなかの中国に対する複雑な意識を増幅させてきた。2003年のSARS危機以降、中国は香港との間にCEPAを締結し、また香港における人民元オフショアセンターとしての役割を段階的かつ確実に付与・強化してきた。加えて、中国から香港を訪問する旅行客のビザ制限の大幅緩和は、中国人の香港への大量流入をもたらした。しかしこれらは、単にヒト・モノ・カネの往来が自由化され、香港に経済的恩恵をもたらしたことを意味しなかった。
たとえば大陸から来た観光客は、単なるカネを落とすだけの存在ではなく、恐るべき厄介者であった。道端で子供に大小便をさせる、地下鉄の乗車ルールを守らない、行列への割り込みを平気でおこなうなど、傍若無人かつ野蛮な振る舞いがクローズアップされた。しかし、この程度であれば香港市民からの失笑と顰蹙を買うだけで済んでいた。
ところが実際に深刻であったのは、中国からの巨大な勢いで流入するヒトやカネが、大挙して不動産物件を買い漁り、あるいは投資移民資格を得ていったことである。不動産価格は投機資金の流入から急上昇し、一般市民が自らの自宅を購入することが遠い夢となりつつある。あるいは、中国の妊婦が香港に押し寄せ、香港市民が使うべき公立病院のベッドで出産し、その子供が市民権を獲得することで、香港での居住権や教育権を得ていった。あるいは粉ミルクなど、安全な生活必需品が中国で不足していることを受けて、密輸業者が香港で市民の生活必需品を買い占めては中国に送る活動も大規模におこなわれた。国境近くの駅前では、密輸業者たちが物資を卸したり詰め替えたりする作業が、公然とおこわれるようになっていった。
「有銭大晒」(ヤウチン・ダイサイ)という広東語がある。直訳すれば「銭を持っていれば、とにかく偉い」というところか。しかしこの言葉は、通常は否定的な意味を込めて使われる。カネが万能のように思われがちな香港社会ではあるが、人の世の常で、実際にはカネの力で傍若無人に振る舞い続けることは、やはり羨望と反感の入り混じった顰蹙を買うのである。まさに香港が返還後に経験してきたことは、21世紀に入って膨張し台頭する中国、その権勢や資金によって、香港の築き上げてきた市民社会としての主体性や秩序を踏み躙られるというものであった。これを香港市民が日常のレベルでも実感するほど、中国との直接的な接触が増加してきたのが、この10年ほどの時間であった。
4.蘇る「龍獅旗」
「龍獅旗」という旗がある。かつて、英国の直轄植民地(クラウン・コロニー)であった時代に、香港の象徴として定められたものである。
他の英国植民地あるいは英連邦国と同様、左上に四分の一にはユニオン・ジャックがあしらわれ、右半分には香港独自の図柄が記されている。それは香港島(Hong Kong Island)を象徴する緑の島の上で紋章を挟みながら、中国を象徴する東側の龍と、英国を象徴する西側のライオンが対峙しつつ、英国王の代理人を象徴する紋章上の小さなライオンが、香港という「東洋の真珠」を持って、西側のライオンに献じるという図柄である。
19世紀半ば、ウェスタン・インパクト(西欧の衝撃)というグローバリゼーションのうねりが世界規模での延伸を開始し、この潮流のなかで台頭した新たな枠組みの一つである大英帝国も、アジアの各所を包摂していった。それは単純な、面としての領土的併呑ではない。現在のグローバリゼーションと同様に、地球上のさまざまな政体・社会・人々・事象が包摂されるのと同じ構図である。香港とは、こうした大きな歴史的文脈のなかで誕生した「場」であった。
香港という都市は、「帝国の時代」の枠組みのなか、地域内の膨大な「つながり」と「流れ」を集散・調整・結節する機能をはたしながら、地域全体に組み込まれつつ、あらゆる方面に対して開かれた「場」となった。その役割をはたしつづけていることが、香港が19世紀半ばから21世紀初頭の現在に至るまで、アジア太平洋の経済的要衝として存立している理由である。
その意味では香港という存在を、英国自らが国民国家的な領土併呑の思考を構図化するカタチで「龍獅旗」に描いたことは、大英帝国の持つ二面性、言い換えれば矛盾を象徴している。そこに描かれている香港とは、19世紀型の帝国が持つ、世界を包摂するフレームワークや、このなかをつなぐ「場」としての側面ではなく、大英帝国が併呑した植民地という、国民国家の側面を強調するものだからである。
しかし、この見方に従えば香港という「場」の捉えかたは、「英領香港」という主権的・領土的な次元でのみ規定されてしまうことになる。それが今日には香港を、「中華人民共和国香港特別行政区」という側面だけで捉えてしまう陥穽にもつながっている。それに、こうした観点では香港という「場」の本質的な存在理由だけでなく、今日の香港が直面している社会現象の根源も理解することはできない。
いずれにしても、「帝国の時代」の香港を象徴する「龍獅旗」は、1997年における香港の中国への主権返還という区切りをもって、植民地時代の追憶を想起させる以外、その役割を終えるはずであった。
ところが21世紀の今日、香港では新たな「龍獅旗」が復活しつつある。それが、中国による香港への介入・影響拡大に反発しはじめた香港人たちによる、「香港アイデンティティ」の象徴としての役割である。もっとも、それは統一的な図柄がなく、一部では植民地時代のユニオン・ジャックの図柄が混じったものが使用され、あるいは一部ではロイヤル・ブルーの地に、かつての旗の右半分の図柄を中心として、そのなかに「香港」という漢字二文字を織り込んだものもある。
いずれにしても、この「龍獅旗」の復活は、現在の香港が置かれた立場、香港市民が感じている現状への不満、そして香港人にとっての「香港」の位置を模索する姿と重なる。それは決して、英国による植民地統治を懐かしむものなどではない。一部の人々は、植民地時代のどこに自由や平等があったのか、民主主義があったのかと言う。しかし、新しい「龍獅旗」が意味するものとは、先述のように香港が育み、そして開花させてきた市民社会、その主体性や価値観を象徴しているのである。そして、ここで対立概念となるのが、まさに自由・人権・法治といった市民社会の成立前提を無視し、いまだに専制と覇権に固執し、そのレジームをもって香港に影響力を及ぼそうとする「中華人民共和国」なのである。
現代の香港は、異様に膨張・台頭する中国という存在に、あらゆる側面で正面から接し、向き合わざるを得ない最前線となっている。そこで発生する各種の摩擦は、おそらくは今後の世界が、中国と向かい合うときにも避けては通れないであろう途でもある。同時に香港での事象を、単純に中国という国民国家の枠組みにおける「一国両制」という観点から観察するだけでは、種々の問題における本質は見えなくなる。
香港という都市は、現在でも中国と世界の間におけるさまざまな価値観が摩擦を伴いながら交錯する、最も熱い「場」なのである。
5.シンガポールの憂鬱
近年、膨張する中国のインパクトと接することで、矛盾や摩擦が深刻化するもう一つの場所が、東南アジアの要、シンガポールである。しかし、この矛盾や摩擦とは、南シナ海や東シナ海の問題のように、政治レベルでの統治機構同士の対立ではない。それは香港と同様に、膨張する中国からの流入と接触が、国民感情レベルで各種反発を引き起こしているのである。
歴史的に見ればシンガポールは、建国以前からのマラヤ共産党や労働組合との対立関係から反共主義を採る一方で、全方位外交の下、中国とのバランスを取ることには早くから注力してきた国でもある。現在に至るまで、外交・経済を含めた地域安全保障の側面では、米国を主軸とした既存の秩序枠組みを重視する一方、経済面では長年にわたって中国との協力関係を確立してきた。
このため中国は、シンガポールにとって第3位の貿易相手国(2012年上半期506億米ドル)であり、また累積では563億米ドルの投資をおこなっている。リー・シェンロン首相は2012年9月の中国訪問で、「発展する中国はシンガポールと経済面でお互いに協力できる」と改めて表明しており、今後も両国の経済関係を積極拡大する姿勢を強調している。この結果として、たしかに経済的にはシンガポールと中国のリンケージは確実に深まり、上述の規模にまで拡大した。
一方では、この10年ほどの中国との直接的接触、特にヒトの大量流入によって、シンガポール国民の間には悪感情が渦巻きはじめている。シンガポールでは1990年代から、外国人労働者の受け入れ、特に中国からのそれが急速に拡大した。これは、それまで使っていた華人系マレーシア人などの賃金コストが上昇したことを代替するための措置であった。さらに21世紀に入ると、政府は国内人口の膨張政策を採りはじめ、非公式にはそれまでの人種別人口構成比率を維持しつつ、中国人への永住権や国籍の付与を拡大しはじめた。特に、法律・金融・会計などといった高度専門職だけでなく、中級技能者、さらには「フィナンシャル・インベスターズ・スキーム」(金融管理局管轄)や「グローバル投資プログラム」(経済開発庁管轄)などの各種投資支援プログラムに沿って移住を希望する投資家に対しても、国籍や永住権の付与を拡大していったとされる。
ところが、いまや外国人労働者だけでも国内人口の約18%以上を占めるようになった現状が、「シンガポール国民」との摩擦を生み出すことになる。たとえば専門職や高度技能者の拡大は、国民との間で雇用市場における競合関係を生み出した。中国人投資家による投資資金の流入は、住居用不動産をはじめとした不動産価格高騰の原動力の一つにもなった。また労働者や移民たちが英語を解することなく、普通話に基づくコミュニティを形成しはじめ、従来からの地域社会のなかに溶け込もうとしない、あるいは社会慣習など各種の感覚のズレから、さまざまな問題を惹起していった。これらは従来からの国民にとって、大きな不満となっていった。
6.反動の季節
今やシンガポールは、過去十数年で膨張した中国のインパクトと直に接することで、矛盾や摩擦が深刻化し、その反作用としての「反動の季節」を迎えつつある。2011年から2012年には、これを象徴する出来事が相次いで発生した。
一つは、2011年にシンガポールでおこなわれた総選挙の結果である。これは、それまで絶対的な支配力を保ってきた政権与党「人民行動党」(PAP)が、定数87議席のうち、改選前85議席から81議席に後退するという、従来のシンガポールの常識からすればPAPの実質的敗北にあたる一大事であった。これは同時に、政府が近年とってきた政策への不信任を意味するものであり、その大きな要因の一つは、明らかに外国人労働力や移民の問題であった。
この選挙で示された民意を受けて、政府は2011年から2012年にかけて外国人労働力の流入に対する引き締め策を強化し、また投資移民向けのプログラムについても、廃止や基準引き上げなどによる対応を迫られた。一方で、労働力不足や人件費上昇が見込まれており、経済界からは懸念や不満が噴出している。また、社会の開放性や活力の維持という観点から、外国人労働力や移民の受け入れは必要不可欠であるという点も、政府・与党内ではコンセンサスとなっている。そこでシンガポール政府は、労働力全体における外国人比率が長期的に3分の1を超えないという大枠のなかで、微調整の柔軟性をもたせるという方針を示している。
こうして政策的には、調整や均衡への模索がはじまっているが、副次的に派生してきた外国人労働力や移民への反感拡大といった社会問題は、依然として根強い点には注意を要する。特に2012年に発生した2つの事件は、中国からの移民や労働者との不協和音を、さらに増幅させることになった。
一つは、2012年5月に発生した、ある交通事故である。これは31歳の中国人投資移民が、イタリア製高級車を飲酒運転で暴走させた挙句、交差点で赤信号を無視してタクシーに激突し、タクシーの運転手と乗客であった日本人女性が死亡するという事故であった。この内容の悲惨さもさることながら、運転していたのが中国人の若い投資移民であったことから、国民からは異常なほどの怨嗟や反感が生まれ、シンガポール社会では大きな議論を巻き起こした。
もう一つは、2012年11月末の公共交通会社SMRTでのストライキである。これはSMRTの中国本土系バス運転手が、シンガポール籍やマレーシア籍の運転手と比較して昇給幅が小さく、待遇が劣悪であることを理由に、11月26日から171人が座り込みの抗議活動をおこない、27日にも88人が職場復帰しなかった事件である。これは管理国家のシンガポールでは26年ぶりのストライキであり、外国人労働者が起こしたという点で、社会に大きな衝撃を与えた。政府は他の外国人労働者への波及を恐れ、迅速にこれを「不法ストライキ」と認定、首謀者5人を逮捕(うち4人を起訴)、29人を強制送還とした。これについて世論調査では、回答者の78%がストライキ参加者の処罰を求めるなど、多くの国民の反応は冷淡であり、中国人を中心とした外国人労働者に対する厳しい見方を実感せざるを得ない。
7.歴史の再演?
もっとも、新しい移民の大量流入にともなう、それまでの定住者との摩擦という問題は、19世紀のシンガポールにも存在した。
シンガポールは、19世紀のグローバリゼーションに添うかたちで、大英帝国という枠組みが地域を包摂するなか、アジアとヨーロッパという東西を結ぶ拠点として、また東南アジアの地域内を結ぶ「場」として成立した。この中継地としてのシンガポールが発展する大きな原動力の一つとなったのが、19世紀半ば以降、中国南部からの移民労働力が東南アジアに拡散する際の、東南アジア側の集散地となったことである。
こうしてシンガポールに到着した中国南部からの移民は、閩南語表現で新参外来者を指す「新客」(シンケー)と呼ばれた。これに対して、マレー半島にはすでに数代にわたって定住し、マレー系との混血やマレー文化との融合によって独自の文化・価値観を形成していた華人系住民、いわゆるプラナカンと呼ばれた集団が存在していた。彼らは、すでに現地の土侯や英国の植民者などによる多重支配が混在するマレー半島で独自の位置を形成し、その一部は社会や経済などの各方面における仲介者としての地位を確立していた。
すでに数代にわたって地場を築いてきたプラナカンと、19世紀のグローバリゼーションによって、新たに爆発的な勢いをもって大量流入した新客は、英国人などの部外者からみれば「Chinese」(華人)というエスニシティによって一括りにすることが可能であった。それは現代においても、シンガポール国民のマジョリティーを占めるのが華人系であることから、中国、あるいは中国からの労働者や移民との間での、現実にはありえない親和性を述べる人が多いことにも通じる。
しかし人間とは、近いようで遠いほど、むしろ苛立ちを強め、奇妙な対立や憎悪が生じやすいものである。これはプラナカンと新客の間も同様であり、そのアイデンティティ、社会経済的な地位、文化的な素養などには、明らかな差異があった。
もっとも、19世紀において、こうした摩擦は次第に収斂していくことになる。その最大の理由は、植民地体制という基本的にはオープンな「場」のなかで、大量の新客の流入によって生じた社会経済的な構造変化を、すでに現地での社会的位置を固めていたプラナカンの集団が機会として捉え、これを利権化することで受容していったことにある。たとえば移民労働力の差配、各種必要物資の供給など、移民労働力自体を利用し、時には搾取する構造が成立した。こうした社会構造の形成のなかで、プラナカンと新客の再融合も進んだことから、新しい海峡華人(ストレート・チャイニーズ)が誕生してゆく。
8.シンガポーリアンの創生と皮肉
それでは現代において、大量に流入する中国からの新しい移民や労働力と、「シンガポーリアン」の間では、新たな融合が進むのであろうか。ここでおそらく壁となるのが、19世紀と現代の決定的な環境差異である。すなわち、海峡植民地や英領マラヤという、開放性を前提としたオープンな「場」は存在せず、あくまでもシンガポールという、小さいながらも独立した主権国家が存在しているという点である。
1965年の建国以来、シンガポールは国民国家となることを余儀なくされた。そして、この「国民の創生」は、「建国の父」であるリー・クアンユーという海峡華人の申し子、すなわち客家の血を引くプラナカンの英語教育エリート、が規定して生み出したシンガポーリアンという人工的概念に基づきおこなわれてきた。初期においては、華人社会の郷党別セグメントを方言追放によって破壊し、また政治的対立を巻き込むかたちで、華人社会での既存権力者が拠り所としていた「華人」というエスニシティの強調自体も否定しながら、シンガポーリアンという意識を人々に扶植しようと試みてきた。
しかし1980年代に入ると、リー・クアンユーはそれまでの英語・華語(=普通話)の二重言語教育政策の失敗にもかかわらず、スピーク・マンダリン・キャンペーン(Speak Mandarin Campaign)を強化した。また1990年代には、中国への理解を深めるための中国関係の研究や展示会にも頻繁に予算が振り向けられ、華人系シンガポール人たちのアイデンティティに、自らのルーツが中国であることを認識させようとするキャンペーンが開始されるようになった。これは飛躍を開始しつつあった中国とのリンケージを強化し、これによる経済的機会を追求するためのものであった。
その精神的態度は、あくまでも独立国家シンガポールとしての国民アイデンティティをベースにしたものであると同時に、成長機会としての「台頭する中国」との間に、中国系であることの同源性を功利的に強調することで、より緊密な関係性を構築しようと試みたものでもあった。また一方で、そこには長年にわたって自らのアイデンティティを問わざるをえなかった、東南アジアにおける華人の「心性の彷徨」が、一抹にせよあったことも否定はできない。
もっとも、こうした政府にとってのご都合主義的なアイデンティティの押し付けが、国民によって共有されたのかは、大いに疑問である。むしろ、現在では皮肉なことに、政策が意図せざる方向性を向きながら、シンガポールの人々は、いまやその国民としてのアイデンティティに目覚めはじめている。それは教育や徴兵による刷り込みなどではなく、新たに急増した移民という外からの衝撃による反作用としての、シンガポーリアン意識の覚醒である。皮肉なことに、人工的概念として創生され、為政者の都合によって培養・扶植されてきたはずのシンガポーリアンというアイデンティティは、いまやシンガポールの人々が、「中国の台頭」にともなう大量の外来者と直接的に接触することによって、逆に彼らの「国民」としての意識を覚醒させてしまったのである。
もっとも注意すべきは、外国人労働力や移民の問題に対する批判の底流には、従来の管理社会としてのシンガポール、言い換えれば政府のあり方自体を批判する意図があり、外国人労働力や移民の問題自体はそのための契機なり象徴となっているにすぎないという点である。こうした意識や活動は、自らの権利意識に目覚め、また既存の社会秩序に対して不満を持つ、特に40代以下の若いシンガポール人たちに顕著である。彼らはウェブやSNSといったネットツールを利用しながら、政府に対する批判的意見を活発に発信している。そしてまさに、彼らの世代を中心として、この数年のシンガポールでは、それまでの政府にとって都合の良い意図とは裏腹なかたちで、「シンガポール人」としてのアイデンティティが再確認されるという事態が起きているのである。
おわりに
一言で「中国の台頭」と呼ばれるものは、実際には多面的な影響を地域全体に与えている。その影響は、必ずしも政治・外交・軍事の側面だけではなく、あるいはマクロでの経済の側面だけではない。たとえば、中国における圧倒的な人口や、不均衡な経済体系から生み出される莫大な富などが、外への機会を求めて急速に流出する現象も、大きな影響をともなうものである。これは21世紀におけるグローバリゼーションのなかで、ヒト・モノ・カネの往来が、新しいテクノロジーやインフラの進歩によって、過去に類を見ないほど激しくなっていることと、軌を一にしている。
こうした流出は、19世紀のグローバリゼーションと同様に、いくつかのポイントに集積されてから移動している。そのポイントの役割をはたしているのは、やはり19世紀と同じく、香港とシンガポールという2つの地点である。ところが、中国の巨大なインパクトを受けた両地では、この10年ほどの間、中国に対する不満や反感が、さまざまなかたちで噴出するようになってきた。それは冒頭でも記したように、為政者や政体の間での政治的対立ではない。それは、よりミクロな部分での、しかし大量の中国からのインパクトによって生じた社会問題、これに対する反作用としての市民や国民のレベルでの反発である。
この摩擦と反発の高まりが、21世紀に入って中国が異常な膨張を開始したことと期を一にしている点は、きわめて象徴的である。すなわち、それ以前における中国との日常における直接的な接触が少ない時代には、「香港も中国である」、「華人系シンガポール人の祖先の地は中国である」と言われていたように、「華人」や「中国」というアイデンティティを軸としたリンケージは可能であるかのように言われていた。しかし、実際の中国という現実、すなわち膨張した圧倒的数量による影響、中国人たちとの落差を目の当たりにしたとき、かつての期待は裏切られ、反比例するように人々の反発も強まっていった。
ただし香港とシンガポールで似て非なる部分は、前者では中国本土やその代弁者と化した香港政府に対する市民社会からの批判となる一方で、後者では中国自体に対する批判ではなく、シンガポールの管理社会に不満を持つ国民が、政府やその政策を批判している点である。これは両者の政治体制が「一国両制」であるか、あるいは「独立国家」であるかの違いもさることながら、批判の主体となっている人々の意識形成が、それぞれに異なる歴史的経緯を歩んできたことにもよる。言い換えれば、中国からの大量の流出が、その流入先で問題を引き起こすという構造は同じであっても、それらは摩擦の端緒に過ぎず、その反作用の発生する根源やメカニズムについては、背景・環境・事情の差から、異なったものとなりうることもわかる。
いずれにしても、この10年ほどに香港とシンガポールが経験し、今日迎えている事態とは、中国という存在が膨張するだけでなく、それとの接触がより直接的となるほど、現在あるいは将来において、他地域でも同様に起こりうるものと考えられる。言い換えれば、「中国の台頭」に対する「反動の季節」とは、世界史的な展開として見れば、実は今まさにはじまったばかりなのかもしれない。
「中国の台頭にともなう周辺諸国・地域との摩擦」と聞いて先ず思い起こすことは領土・領海紛争や貿易摩擦といった問題であろう。しかし本稿は、そうした枠組みで発生している摩擦を取り扱うものではない。むしろ本稿では、21世紀に入ってからの中国の膨張によって、有形無形のインパクトが外に向かうことを契機に、その進出先となった周辺諸国・地域で社会問題が生じ、国民・市民レベルでの反発が噴出していることに着目する。その上で、摩擦と反作用の生じる構造や背景について考えてみたい。
こうした問題は特に、中国からのインパクトが大量かつ直接的になるほど、その受け皿となっている「場」で顕著となっている。その前線こそが、香港とシンガポールという2つの都市である。これらの都市は、それぞれ「一国両制」と「独立国家」というステータスの違いはあるが、地域内の集散地であるがゆえに、この10年ほどの間で中国からのインパクトを直接・間接的に受けることで、次第に大きな摩擦が起こってきた。これに対して現在は、まさに「反動の季節」とも言うべき、さまざまな反作用が生じている。
これらの事象は、現在あるいは将来において、他地域でも同様に起こりうる摩擦や反作用を想定する上での、貴重な先行事例でもある。そこで本稿は、中国との接触において前線となっている、香港とシンガポールという2つの都市に着目しながら、かつて筆者が歩き、接触し、感じてきた、人々の言葉、街の様子、起こっている事象などを織り込みながら、上記問題の構造や背景に迫りたいと考える。
1.香港の「反国民教育」運動に見えるもの
2012年後半の香港では、一つのテーマが社会を大きく揺るがした。それが香港の公教育における、いわゆる「国民教育」をめぐる一連の騒動である。これは愛国主義的な教育を学校で実施する導入計画に対し、香港市民から幅広い反対運動が巻き起こり、香港政府が事実上の政策撤回に追い込まれた、というものである。
プログラムの内容は、「中国人としてのアイデンティティ」を育成するため、2012年9月の新学期から公立小学校で「道徳・国民教育」科目が導入され、2013年からは中学・高校でも順次導入される予定となっていた。しかし、その内容は21世紀の現代社会においては、恐ろしく常軌を逸した内容であった。「中国モデル」というタイトルの教材冊子は、中国共産党については、進歩的かつ無私無欲で団結が固いと解説し、また複数政党制はアメリカなどの国々に見られるように国家に最悪の事態をもたらす、などと記している。また1989年の天安門事件など、現代中国および共産党の失政や問題ともいえる部分については、言及がなされていない。
この天地が逆転したような荒唐無稽なプロパガンダを押し付けようとしたことに、香港市民は敏感に反応した。「反国民教育」の世論は日増しに高まり、8月末には9万人近い人々が参加する反対デモが発生し、国民教育に反対する意思を表明した。この世論による強烈な批判を受けて、9月8日、梁振英行政長官は、導入は各校の判断に任せ、全面導入についても期限を設定しないと表明し、事実上の政策撤回を表明した。
この一件は、国家安全保障・反逆罪・分裂行為などについて規定した基本法23条の立法化問題について、2003年に発生した香港市民による広範囲な反対運動と同じ構造である。それは中国共産党の教条、すなわち20世紀の「負の遺産」とも言うべき全体主義的な社会・思想統制という押し付けに対して、21世紀の現代を生きる市民社会の声が、正面から衝突しているのである。香港社会は、単純に実利主義・利益主義の権化のように見られがちである。しかし実際には、後述のように、長年にわたって築かれてきた健全な市民社会の良識が根付いていることを、「反国民教育」運動は示している。それは専制者の圧制に対して、屈することのない自由な市民の意思である。
しかし中国は、この市民社会というコンセプト自体を、まったくといってよいほど理解していない。香港市民の反応を、「健全」な民衆の声と捉えることはなく、ただの反国家・反体制・反党的な動きとしか看做さない。これは中国における為政者の思考の本質が、全体主義・専制主義に基づく「支配」にあることを考えれば、まったく不思議なことではない。現在、中国国内のみならず、香港にも、あるいは世界にも、中国の異常な「経済発展」に幻惑され、事物の本質を見失い、あるいはそれに擦り寄る意見が溢れている。しかし彼の体制の本質とは、中国伝統の専制主義と、20世紀の生み出した恐るべき全体主義という、二つの「支配」の思考を正統に受け継いだものであることを、決して忘れてはならない。
このように考えれば香港では、いまや恐ろしいほど対極的な政治概念が、先鋭なかたちで衝突しているのではなかろうか。それはまた、膨張する中国という存在と向き合わざるを得ない、21世紀という時代のあり方を象徴している。
2.「一国両制」のリアル・ポリティククス
1997年の香港返還は、香港の人々の手の届かないところで取り決められた。英国と中国の取り決めでは、返還後50年間は香港の地位や体制を保証し、「一国両制」(一国二制度)の下で「港人治港」(香港人が香港を統治する)を守る、という建前が合意されていたはずであった。
しかし返還後、香港が直面した現実は、これとは裏腹なものであった。政治面では、特別行政区の行政長官選挙、立法会の議会選挙などに対して、中央は明白な資金的・組織的な介入をおこない、広義の民主派の台頭を押さえ込んできた。また、実質的な治安維持法となる基本法23条の立法化についても、現在まで実現はしていないものの、制定に向けて露骨なまでの介入をおこなってきた。あるいは保障されていたはずの司法の独立性についても、最終的な司法解釈などについては中央の批准・承認に従う必要があり、この面でも香港にはガラス天井がはめ込まれている。
たしかに香港の特別行政区政府は、行政長官を含めて「香港人」で占められ、運営されてはいる。しかし現実には、中央が常に介入し続け、その意図の下にあり続けることが、「一国両制」という現実、特に中華人民共和国という専制的な非民主国家の主権下に入った香港の現実であった。こうした事態を、皆が予見しえなかった訳ではない。しかし多くの香港人にとっては、これが避けがたい現実であった。「雨が降って濡れたところで、天を恨んでも仕方がない」のである。
これは植民地時代からも同様であった。ハイレベルでの政治など、香港人にはどうしようもない「天の上」の話であり、香港人が自らの運命を自らで決めることなどは、常識では想像もつなかいことだったのである。こうしたなかで、香港人の特性のひとつである、機会主義・実利主義の精神が培われていった。機を見るに敏であり、自己の損得を追求するために生きることが、かつての香港人のあり方であった。それゆえに、香港社会の経済利益優先の風潮を批判している「リベラル」な者でさえ、自己の株式投資や不動産投資が生み出す利益には、あっけらかんとした態度であからさまに喜びをあらわにする。
こうした土壌のなかで、返還直後から数年まで、香港の友人たちからは、事あるごとに中国との一体化は決して悪くない、経済的な恩恵や繁栄を保障してくれる、香港人も中国人であり、日々強くなる祖国中国に誇りを感じる、などと迎合的な意見が多く聞かれた。これは「天に逆らえない以上は、現世で実利を得る」思考そのものであった。
しかし、いまや香港人の感情は、かつて迎合的な態度をとっていた者すら、口をつぐむか、あるいは反中国的な態度に変化するほど、中国への不満を強めている。かつての迎合的態度は、中国という枠組みのなかで利益を得ようとする人間の、表面的な口からしか聞くことはできない。しかし、こうした人々ですら本音は異なる。大陸が関与するエリート青年組織に名を連ねる野心家の若手弁護士は、「自分の利益が第一。中国は祖国でも、政府や共産党には興味がない。だがビジネスや社会的成功には役立つ」と述べ、ある政府高官ですら、「結局、中央は香港人を信用していない。私が考えるのは、中国のなかで香港の利益を最大化することだ」と述べていた。
3.踏み躙られた「市民社会」のルール
それでは、この十数年で生じた変化とは何であったのか。何が香港の人々を、中国への苛立ちへと駆り立てているのであろうか。そこには強大化する中国のインパクト、さらには中国から流入するヒトやカネの所作が、香港における「市民社会」のルールを踏み躙り続けてきたという事実がある。
それは何も高尚なものを意味するわけではない。私たちにとっては至極あたりまえの、統治者が築き上げる上からの秩序ではなく、市民が社会のなかで築き上げてゆく文明社会のルールは、香港社会でも培われてきた。特に40代以下の香港人は、香港社会における意識の成熟とともに成長してきた。彼らは安定して豊かになった時代に生まれ、そのなかで権利意識や公民意識を育み、またインターネットなどのITツールの利用によって、それ以前の世代が物理的・言語的な情報アクセスの限界を抱えていたのとは異なり、境界を越えた自由な範囲を行き来し、幾万もの情報や思想に接することができる。
これらの世代は、それまでの「受動性のなかの能動」とも言える、かつての機会主義・功利主義を第一とした香港人意識とは異なる意識を持っている。彼らは程度の差こそあれ香港の自主性、言い換えれば香港が育んできた、そして彼ら自身を育んできた、香港の市民社会という存在・価値観を重んじる意識が強い。同時に、もはや彼らにとって政治とは「天の上」の話ではない。こうした意識をベースとした香港人にとって、専制的な権力によって異なる価値観を押し付けようとする大陸の強圧的な態度は、市民社会の常識から逸脱したものとして映る。「祖国」と「共産党」がなすことには、異を唱えず黙って従えなどというロジックは、当然ながらまったく通用しないのである。
こうした背景の一方で、この10年で中国との接触がより直接的なものとなってきた現実が、香港人のなかの中国に対する複雑な意識を増幅させてきた。2003年のSARS危機以降、中国は香港との間にCEPAを締結し、また香港における人民元オフショアセンターとしての役割を段階的かつ確実に付与・強化してきた。加えて、中国から香港を訪問する旅行客のビザ制限の大幅緩和は、中国人の香港への大量流入をもたらした。しかしこれらは、単にヒト・モノ・カネの往来が自由化され、香港に経済的恩恵をもたらしたことを意味しなかった。
たとえば大陸から来た観光客は、単なるカネを落とすだけの存在ではなく、恐るべき厄介者であった。道端で子供に大小便をさせる、地下鉄の乗車ルールを守らない、行列への割り込みを平気でおこなうなど、傍若無人かつ野蛮な振る舞いがクローズアップされた。しかし、この程度であれば香港市民からの失笑と顰蹙を買うだけで済んでいた。
ところが実際に深刻であったのは、中国からの巨大な勢いで流入するヒトやカネが、大挙して不動産物件を買い漁り、あるいは投資移民資格を得ていったことである。不動産価格は投機資金の流入から急上昇し、一般市民が自らの自宅を購入することが遠い夢となりつつある。あるいは、中国の妊婦が香港に押し寄せ、香港市民が使うべき公立病院のベッドで出産し、その子供が市民権を獲得することで、香港での居住権や教育権を得ていった。あるいは粉ミルクなど、安全な生活必需品が中国で不足していることを受けて、密輸業者が香港で市民の生活必需品を買い占めては中国に送る活動も大規模におこなわれた。国境近くの駅前では、密輸業者たちが物資を卸したり詰め替えたりする作業が、公然とおこわれるようになっていった。
「有銭大晒」(ヤウチン・ダイサイ)という広東語がある。直訳すれば「銭を持っていれば、とにかく偉い」というところか。しかしこの言葉は、通常は否定的な意味を込めて使われる。カネが万能のように思われがちな香港社会ではあるが、人の世の常で、実際にはカネの力で傍若無人に振る舞い続けることは、やはり羨望と反感の入り混じった顰蹙を買うのである。まさに香港が返還後に経験してきたことは、21世紀に入って膨張し台頭する中国、その権勢や資金によって、香港の築き上げてきた市民社会としての主体性や秩序を踏み躙られるというものであった。これを香港市民が日常のレベルでも実感するほど、中国との直接的な接触が増加してきたのが、この10年ほどの時間であった。
4.蘇る「龍獅旗」
「龍獅旗」という旗がある。かつて、英国の直轄植民地(クラウン・コロニー)であった時代に、香港の象徴として定められたものである。
他の英国植民地あるいは英連邦国と同様、左上に四分の一にはユニオン・ジャックがあしらわれ、右半分には香港独自の図柄が記されている。それは香港島(Hong Kong Island)を象徴する緑の島の上で紋章を挟みながら、中国を象徴する東側の龍と、英国を象徴する西側のライオンが対峙しつつ、英国王の代理人を象徴する紋章上の小さなライオンが、香港という「東洋の真珠」を持って、西側のライオンに献じるという図柄である。
19世紀半ば、ウェスタン・インパクト(西欧の衝撃)というグローバリゼーションのうねりが世界規模での延伸を開始し、この潮流のなかで台頭した新たな枠組みの一つである大英帝国も、アジアの各所を包摂していった。それは単純な、面としての領土的併呑ではない。現在のグローバリゼーションと同様に、地球上のさまざまな政体・社会・人々・事象が包摂されるのと同じ構図である。香港とは、こうした大きな歴史的文脈のなかで誕生した「場」であった。
香港という都市は、「帝国の時代」の枠組みのなか、地域内の膨大な「つながり」と「流れ」を集散・調整・結節する機能をはたしながら、地域全体に組み込まれつつ、あらゆる方面に対して開かれた「場」となった。その役割をはたしつづけていることが、香港が19世紀半ばから21世紀初頭の現在に至るまで、アジア太平洋の経済的要衝として存立している理由である。
その意味では香港という存在を、英国自らが国民国家的な領土併呑の思考を構図化するカタチで「龍獅旗」に描いたことは、大英帝国の持つ二面性、言い換えれば矛盾を象徴している。そこに描かれている香港とは、19世紀型の帝国が持つ、世界を包摂するフレームワークや、このなかをつなぐ「場」としての側面ではなく、大英帝国が併呑した植民地という、国民国家の側面を強調するものだからである。
しかし、この見方に従えば香港という「場」の捉えかたは、「英領香港」という主権的・領土的な次元でのみ規定されてしまうことになる。それが今日には香港を、「中華人民共和国香港特別行政区」という側面だけで捉えてしまう陥穽にもつながっている。それに、こうした観点では香港という「場」の本質的な存在理由だけでなく、今日の香港が直面している社会現象の根源も理解することはできない。
いずれにしても、「帝国の時代」の香港を象徴する「龍獅旗」は、1997年における香港の中国への主権返還という区切りをもって、植民地時代の追憶を想起させる以外、その役割を終えるはずであった。
ところが21世紀の今日、香港では新たな「龍獅旗」が復活しつつある。それが、中国による香港への介入・影響拡大に反発しはじめた香港人たちによる、「香港アイデンティティ」の象徴としての役割である。もっとも、それは統一的な図柄がなく、一部では植民地時代のユニオン・ジャックの図柄が混じったものが使用され、あるいは一部ではロイヤル・ブルーの地に、かつての旗の右半分の図柄を中心として、そのなかに「香港」という漢字二文字を織り込んだものもある。
いずれにしても、この「龍獅旗」の復活は、現在の香港が置かれた立場、香港市民が感じている現状への不満、そして香港人にとっての「香港」の位置を模索する姿と重なる。それは決して、英国による植民地統治を懐かしむものなどではない。一部の人々は、植民地時代のどこに自由や平等があったのか、民主主義があったのかと言う。しかし、新しい「龍獅旗」が意味するものとは、先述のように香港が育み、そして開花させてきた市民社会、その主体性や価値観を象徴しているのである。そして、ここで対立概念となるのが、まさに自由・人権・法治といった市民社会の成立前提を無視し、いまだに専制と覇権に固執し、そのレジームをもって香港に影響力を及ぼそうとする「中華人民共和国」なのである。
現代の香港は、異様に膨張・台頭する中国という存在に、あらゆる側面で正面から接し、向き合わざるを得ない最前線となっている。そこで発生する各種の摩擦は、おそらくは今後の世界が、中国と向かい合うときにも避けては通れないであろう途でもある。同時に香港での事象を、単純に中国という国民国家の枠組みにおける「一国両制」という観点から観察するだけでは、種々の問題における本質は見えなくなる。
香港という都市は、現在でも中国と世界の間におけるさまざまな価値観が摩擦を伴いながら交錯する、最も熱い「場」なのである。
5.シンガポールの憂鬱
近年、膨張する中国のインパクトと接することで、矛盾や摩擦が深刻化するもう一つの場所が、東南アジアの要、シンガポールである。しかし、この矛盾や摩擦とは、南シナ海や東シナ海の問題のように、政治レベルでの統治機構同士の対立ではない。それは香港と同様に、膨張する中国からの流入と接触が、国民感情レベルで各種反発を引き起こしているのである。
歴史的に見ればシンガポールは、建国以前からのマラヤ共産党や労働組合との対立関係から反共主義を採る一方で、全方位外交の下、中国とのバランスを取ることには早くから注力してきた国でもある。現在に至るまで、外交・経済を含めた地域安全保障の側面では、米国を主軸とした既存の秩序枠組みを重視する一方、経済面では長年にわたって中国との協力関係を確立してきた。
このため中国は、シンガポールにとって第3位の貿易相手国(2012年上半期506億米ドル)であり、また累積では563億米ドルの投資をおこなっている。リー・シェンロン首相は2012年9月の中国訪問で、「発展する中国はシンガポールと経済面でお互いに協力できる」と改めて表明しており、今後も両国の経済関係を積極拡大する姿勢を強調している。この結果として、たしかに経済的にはシンガポールと中国のリンケージは確実に深まり、上述の規模にまで拡大した。
一方では、この10年ほどの中国との直接的接触、特にヒトの大量流入によって、シンガポール国民の間には悪感情が渦巻きはじめている。シンガポールでは1990年代から、外国人労働者の受け入れ、特に中国からのそれが急速に拡大した。これは、それまで使っていた華人系マレーシア人などの賃金コストが上昇したことを代替するための措置であった。さらに21世紀に入ると、政府は国内人口の膨張政策を採りはじめ、非公式にはそれまでの人種別人口構成比率を維持しつつ、中国人への永住権や国籍の付与を拡大しはじめた。特に、法律・金融・会計などといった高度専門職だけでなく、中級技能者、さらには「フィナンシャル・インベスターズ・スキーム」(金融管理局管轄)や「グローバル投資プログラム」(経済開発庁管轄)などの各種投資支援プログラムに沿って移住を希望する投資家に対しても、国籍や永住権の付与を拡大していったとされる。
ところが、いまや外国人労働者だけでも国内人口の約18%以上を占めるようになった現状が、「シンガポール国民」との摩擦を生み出すことになる。たとえば専門職や高度技能者の拡大は、国民との間で雇用市場における競合関係を生み出した。中国人投資家による投資資金の流入は、住居用不動産をはじめとした不動産価格高騰の原動力の一つにもなった。また労働者や移民たちが英語を解することなく、普通話に基づくコミュニティを形成しはじめ、従来からの地域社会のなかに溶け込もうとしない、あるいは社会慣習など各種の感覚のズレから、さまざまな問題を惹起していった。これらは従来からの国民にとって、大きな不満となっていった。
6.反動の季節
今やシンガポールは、過去十数年で膨張した中国のインパクトと直に接することで、矛盾や摩擦が深刻化し、その反作用としての「反動の季節」を迎えつつある。2011年から2012年には、これを象徴する出来事が相次いで発生した。
一つは、2011年にシンガポールでおこなわれた総選挙の結果である。これは、それまで絶対的な支配力を保ってきた政権与党「人民行動党」(PAP)が、定数87議席のうち、改選前85議席から81議席に後退するという、従来のシンガポールの常識からすればPAPの実質的敗北にあたる一大事であった。これは同時に、政府が近年とってきた政策への不信任を意味するものであり、その大きな要因の一つは、明らかに外国人労働力や移民の問題であった。
この選挙で示された民意を受けて、政府は2011年から2012年にかけて外国人労働力の流入に対する引き締め策を強化し、また投資移民向けのプログラムについても、廃止や基準引き上げなどによる対応を迫られた。一方で、労働力不足や人件費上昇が見込まれており、経済界からは懸念や不満が噴出している。また、社会の開放性や活力の維持という観点から、外国人労働力や移民の受け入れは必要不可欠であるという点も、政府・与党内ではコンセンサスとなっている。そこでシンガポール政府は、労働力全体における外国人比率が長期的に3分の1を超えないという大枠のなかで、微調整の柔軟性をもたせるという方針を示している。
こうして政策的には、調整や均衡への模索がはじまっているが、副次的に派生してきた外国人労働力や移民への反感拡大といった社会問題は、依然として根強い点には注意を要する。特に2012年に発生した2つの事件は、中国からの移民や労働者との不協和音を、さらに増幅させることになった。
一つは、2012年5月に発生した、ある交通事故である。これは31歳の中国人投資移民が、イタリア製高級車を飲酒運転で暴走させた挙句、交差点で赤信号を無視してタクシーに激突し、タクシーの運転手と乗客であった日本人女性が死亡するという事故であった。この内容の悲惨さもさることながら、運転していたのが中国人の若い投資移民であったことから、国民からは異常なほどの怨嗟や反感が生まれ、シンガポール社会では大きな議論を巻き起こした。
もう一つは、2012年11月末の公共交通会社SMRTでのストライキである。これはSMRTの中国本土系バス運転手が、シンガポール籍やマレーシア籍の運転手と比較して昇給幅が小さく、待遇が劣悪であることを理由に、11月26日から171人が座り込みの抗議活動をおこない、27日にも88人が職場復帰しなかった事件である。これは管理国家のシンガポールでは26年ぶりのストライキであり、外国人労働者が起こしたという点で、社会に大きな衝撃を与えた。政府は他の外国人労働者への波及を恐れ、迅速にこれを「不法ストライキ」と認定、首謀者5人を逮捕(うち4人を起訴)、29人を強制送還とした。これについて世論調査では、回答者の78%がストライキ参加者の処罰を求めるなど、多くの国民の反応は冷淡であり、中国人を中心とした外国人労働者に対する厳しい見方を実感せざるを得ない。
7.歴史の再演?
もっとも、新しい移民の大量流入にともなう、それまでの定住者との摩擦という問題は、19世紀のシンガポールにも存在した。
シンガポールは、19世紀のグローバリゼーションに添うかたちで、大英帝国という枠組みが地域を包摂するなか、アジアとヨーロッパという東西を結ぶ拠点として、また東南アジアの地域内を結ぶ「場」として成立した。この中継地としてのシンガポールが発展する大きな原動力の一つとなったのが、19世紀半ば以降、中国南部からの移民労働力が東南アジアに拡散する際の、東南アジア側の集散地となったことである。
こうしてシンガポールに到着した中国南部からの移民は、閩南語表現で新参外来者を指す「新客」(シンケー)と呼ばれた。これに対して、マレー半島にはすでに数代にわたって定住し、マレー系との混血やマレー文化との融合によって独自の文化・価値観を形成していた華人系住民、いわゆるプラナカンと呼ばれた集団が存在していた。彼らは、すでに現地の土侯や英国の植民者などによる多重支配が混在するマレー半島で独自の位置を形成し、その一部は社会や経済などの各方面における仲介者としての地位を確立していた。
すでに数代にわたって地場を築いてきたプラナカンと、19世紀のグローバリゼーションによって、新たに爆発的な勢いをもって大量流入した新客は、英国人などの部外者からみれば「Chinese」(華人)というエスニシティによって一括りにすることが可能であった。それは現代においても、シンガポール国民のマジョリティーを占めるのが華人系であることから、中国、あるいは中国からの労働者や移民との間での、現実にはありえない親和性を述べる人が多いことにも通じる。
しかし人間とは、近いようで遠いほど、むしろ苛立ちを強め、奇妙な対立や憎悪が生じやすいものである。これはプラナカンと新客の間も同様であり、そのアイデンティティ、社会経済的な地位、文化的な素養などには、明らかな差異があった。
もっとも、19世紀において、こうした摩擦は次第に収斂していくことになる。その最大の理由は、植民地体制という基本的にはオープンな「場」のなかで、大量の新客の流入によって生じた社会経済的な構造変化を、すでに現地での社会的位置を固めていたプラナカンの集団が機会として捉え、これを利権化することで受容していったことにある。たとえば移民労働力の差配、各種必要物資の供給など、移民労働力自体を利用し、時には搾取する構造が成立した。こうした社会構造の形成のなかで、プラナカンと新客の再融合も進んだことから、新しい海峡華人(ストレート・チャイニーズ)が誕生してゆく。
8.シンガポーリアンの創生と皮肉
それでは現代において、大量に流入する中国からの新しい移民や労働力と、「シンガポーリアン」の間では、新たな融合が進むのであろうか。ここでおそらく壁となるのが、19世紀と現代の決定的な環境差異である。すなわち、海峡植民地や英領マラヤという、開放性を前提としたオープンな「場」は存在せず、あくまでもシンガポールという、小さいながらも独立した主権国家が存在しているという点である。
1965年の建国以来、シンガポールは国民国家となることを余儀なくされた。そして、この「国民の創生」は、「建国の父」であるリー・クアンユーという海峡華人の申し子、すなわち客家の血を引くプラナカンの英語教育エリート、が規定して生み出したシンガポーリアンという人工的概念に基づきおこなわれてきた。初期においては、華人社会の郷党別セグメントを方言追放によって破壊し、また政治的対立を巻き込むかたちで、華人社会での既存権力者が拠り所としていた「華人」というエスニシティの強調自体も否定しながら、シンガポーリアンという意識を人々に扶植しようと試みてきた。
しかし1980年代に入ると、リー・クアンユーはそれまでの英語・華語(=普通話)の二重言語教育政策の失敗にもかかわらず、スピーク・マンダリン・キャンペーン(Speak Mandarin Campaign)を強化した。また1990年代には、中国への理解を深めるための中国関係の研究や展示会にも頻繁に予算が振り向けられ、華人系シンガポール人たちのアイデンティティに、自らのルーツが中国であることを認識させようとするキャンペーンが開始されるようになった。これは飛躍を開始しつつあった中国とのリンケージを強化し、これによる経済的機会を追求するためのものであった。
その精神的態度は、あくまでも独立国家シンガポールとしての国民アイデンティティをベースにしたものであると同時に、成長機会としての「台頭する中国」との間に、中国系であることの同源性を功利的に強調することで、より緊密な関係性を構築しようと試みたものでもあった。また一方で、そこには長年にわたって自らのアイデンティティを問わざるをえなかった、東南アジアにおける華人の「心性の彷徨」が、一抹にせよあったことも否定はできない。
もっとも、こうした政府にとってのご都合主義的なアイデンティティの押し付けが、国民によって共有されたのかは、大いに疑問である。むしろ、現在では皮肉なことに、政策が意図せざる方向性を向きながら、シンガポールの人々は、いまやその国民としてのアイデンティティに目覚めはじめている。それは教育や徴兵による刷り込みなどではなく、新たに急増した移民という外からの衝撃による反作用としての、シンガポーリアン意識の覚醒である。皮肉なことに、人工的概念として創生され、為政者の都合によって培養・扶植されてきたはずのシンガポーリアンというアイデンティティは、いまやシンガポールの人々が、「中国の台頭」にともなう大量の外来者と直接的に接触することによって、逆に彼らの「国民」としての意識を覚醒させてしまったのである。
もっとも注意すべきは、外国人労働力や移民の問題に対する批判の底流には、従来の管理社会としてのシンガポール、言い換えれば政府のあり方自体を批判する意図があり、外国人労働力や移民の問題自体はそのための契機なり象徴となっているにすぎないという点である。こうした意識や活動は、自らの権利意識に目覚め、また既存の社会秩序に対して不満を持つ、特に40代以下の若いシンガポール人たちに顕著である。彼らはウェブやSNSといったネットツールを利用しながら、政府に対する批判的意見を活発に発信している。そしてまさに、彼らの世代を中心として、この数年のシンガポールでは、それまでの政府にとって都合の良い意図とは裏腹なかたちで、「シンガポール人」としてのアイデンティティが再確認されるという事態が起きているのである。
おわりに
一言で「中国の台頭」と呼ばれるものは、実際には多面的な影響を地域全体に与えている。その影響は、必ずしも政治・外交・軍事の側面だけではなく、あるいはマクロでの経済の側面だけではない。たとえば、中国における圧倒的な人口や、不均衡な経済体系から生み出される莫大な富などが、外への機会を求めて急速に流出する現象も、大きな影響をともなうものである。これは21世紀におけるグローバリゼーションのなかで、ヒト・モノ・カネの往来が、新しいテクノロジーやインフラの進歩によって、過去に類を見ないほど激しくなっていることと、軌を一にしている。
こうした流出は、19世紀のグローバリゼーションと同様に、いくつかのポイントに集積されてから移動している。そのポイントの役割をはたしているのは、やはり19世紀と同じく、香港とシンガポールという2つの地点である。ところが、中国の巨大なインパクトを受けた両地では、この10年ほどの間、中国に対する不満や反感が、さまざまなかたちで噴出するようになってきた。それは冒頭でも記したように、為政者や政体の間での政治的対立ではない。それは、よりミクロな部分での、しかし大量の中国からのインパクトによって生じた社会問題、これに対する反作用としての市民や国民のレベルでの反発である。
この摩擦と反発の高まりが、21世紀に入って中国が異常な膨張を開始したことと期を一にしている点は、きわめて象徴的である。すなわち、それ以前における中国との日常における直接的な接触が少ない時代には、「香港も中国である」、「華人系シンガポール人の祖先の地は中国である」と言われていたように、「華人」や「中国」というアイデンティティを軸としたリンケージは可能であるかのように言われていた。しかし、実際の中国という現実、すなわち膨張した圧倒的数量による影響、中国人たちとの落差を目の当たりにしたとき、かつての期待は裏切られ、反比例するように人々の反発も強まっていった。
ただし香港とシンガポールで似て非なる部分は、前者では中国本土やその代弁者と化した香港政府に対する市民社会からの批判となる一方で、後者では中国自体に対する批判ではなく、シンガポールの管理社会に不満を持つ国民が、政府やその政策を批判している点である。これは両者の政治体制が「一国両制」であるか、あるいは「独立国家」であるかの違いもさることながら、批判の主体となっている人々の意識形成が、それぞれに異なる歴史的経緯を歩んできたことにもよる。言い換えれば、中国からの大量の流出が、その流入先で問題を引き起こすという構造は同じであっても、それらは摩擦の端緒に過ぎず、その反作用の発生する根源やメカニズムについては、背景・環境・事情の差から、異なったものとなりうることもわかる。
いずれにしても、この10年ほどに香港とシンガポールが経験し、今日迎えている事態とは、中国という存在が膨張するだけでなく、それとの接触がより直接的となるほど、現在あるいは将来において、他地域でも同様に起こりうるものと考えられる。言い換えれば、「中国の台頭」に対する「反動の季節」とは、世界史的な展開として見れば、実は今まさにはじまったばかりなのかもしれない。