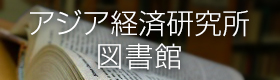中国軍事戦略の趨勢と海軍
政策提言研究
阿部純一 (霞山会主席研究員)
2011年7月
※以下に掲載する文章は、平成23年度政策提言研究「 中国・インドの台頭と東アジアの変容 」第2回研究会(2011年7月7日開催)における報告内容を要約したものです。
PDF (190KB)
中国の軍事戦略は時代と共に変化してきた。1980年代、沿海地区の経済発展を軸にその果実を国防の近代化に投入してきた中国にとり、海洋の戦略的重要性が高まったことはその変化の中でも特筆すべきものであった。沿海地区の経済発展によって東部、南部の沿海を防御することの重要性が増すとともに、90年代には国内におけるエネルギー需要の増大から東シナ海、南シナ海における海底資源の確保を念頭に海洋の権益を確保するという目的が明確に示され、同海域での領有権の主張や実効支配の実績作りが進められた。その結果、東南アジア諸国を中心に「中国脅威論」を惹起することになった。以来、中国の経済発展が東アジア諸国に裨益する事実が存在する一方において、中国の海洋における影響力拡大に周辺諸国の懸念が高まりつつある。
ここでは、建国以来の中国の軍事戦略の変化を整理しつつ、その中で中国がいかに海軍建設を進展させてきたかを論じ、そのことがもたらしつつある問題点を明示したい。
1.毛沢東の軍事戦略
19世紀のアヘン戦争以来、欧米列強によって侵食された経験を持つ中国にとって、そうした屈辱の歴史を繰り返さないためにも強固な軍事力は必要不可欠なものと認識された。さらに米ソ冷戦の渦中に社会主義国家として建国した中国にとり、資本主義との最終決戦となる「第三次世界大戦」は「不可避」と位置づけられ、それに備えるべく臨戦態勢が取られるとともに、対米抑止力としての核武装が急がれた。重要な工業施設は安全な内陸奥地に移転する、いわゆる「三線建設」などの措置が取られたのもこの時期である。
その時期の指導者であった毛沢東は、常に外部に敵を想定する「主敵」論に立ち、臨戦態勢で対応することを構想した。本土防衛については、「敵を人民の海に深く誘い入れ、包囲し殲滅する」という人民戦争論で対応し、朝鮮戦争で戦火を交えた米国、さらには「中ソ対立」後のソ連の核戦力に対しては独自開発の戦略核ミサイルで対抗するという「2本足」戦略で対抗した。
この時期の中国の軍事戦略は、対外宣伝的には好戦的印象を与えるものであったが、実際には戦力的劣勢を自覚したきわめて防御的なものであった。こうした防御的姿勢は、鄧小平が実権を掌握したことによって1978年末から始まる「改革・開放」政策の進展にしたがって徐々に変化してくる。「改革・開放」政策では、文革時代(1966~1976)に世界の経済成長から取り残された中国経済をいかに成長軌道に乗せるかが問われ、そのためには独善的な閉鎖・孤立主義的「自力更生」路線を改め、西側に門戸を開き、資本と技術を導入し、製品を西側に輸出するという手法が選択された。しかし、それを実現するためには中国が常に外部に敵を想定する状況、さらに国境を接した周辺国との緊張の継続が適合するはずはなく、1985年の第12回党大会を契機に中国は「独立自主の平和外交」という全方位協調外交に舵を切ることになった。
2.鄧小平の軍事戦略と海軍
この変化を主導した鄧小平には、米ソが核戦力において相互に拮抗する状況を「核の手詰まり」とみなし、「第三次世界大戦は当面回避できる」という判断があり、それは文革時代に肥大化したままの人民解放軍をスリム化し、近代的戦争に対応できる軍隊に変革するための時間的猶予を得られるチャンスと位置づけられた。1985年から2年間で400万の軍隊を300万規模にする100万人削減が実施され、国防大学の設置(85年)、階級制度の復活(88年)など教育、制度面での改革も進めた。この時期、中国が想定した戦争は局地的な戦争であり、「現代的条件下の局地戦争を戦う」ことが軍事戦略の中心テーマとなった。
鄧小平はこうして毛沢東時代の人民戦争論に訣別し、局地的な戦争、つまり国境における領土保全のための戦争を構想するに至るが、それは国境での防御を重視する方向を生み出し、論理的に海上国境を防衛する海軍の役割を再認識させることになった。つまり、沿海中心の経済発展戦略に基づき、国境としての領海の守備が重視されることは、当然ながら海軍への期待と役割拡大をともなうこととなったのである。
3.江沢民の軍事戦略とハイテク化
1989年5月、約30年続いた中ソ対立が解け、中国は北方内陸国境の脅威から解放された。同年の予算から国防費は毎年二桁の伸びを見せるようになり、2009年まで20年連続を記録した。6月の天安門事件で党総書記に抜擢された江沢民は、同年秋には中央軍事委員会主席のポストを鄧小平から譲り受け、軍近代化の責任者となった。この時期、中央軍事委員会で江沢民を補佐した劉華清副主席(上将)は、1992年に党理論誌『救是』に論文「中国の特色をもつ近代的軍隊建設の道を揺るぎなく前進しよう」を発表し、軍近代化の重点は海・空軍であることを明示した。その背景には、1991年初めの湾岸戦争があり、米国が駆使したトマホーク巡航ミサイルやステルス戦闘機などハイテク兵器の威力に中国は強い印象を受けたことが指摘できる。ロシアからキロ級潜水艦やスホイ27戦闘機などが導入され始めたのもこの時期のことであった。
かかる経緯から、この時期の軍事戦略は「ハイテク条件下の局地戦争を戦う」へと発展し、経済発展と軍近代化の関係についても、鄧小平時代の「経済建設の大局にしたがう」という従属的関係から、2002年の第16回党大会における江沢民報告で「国防整備と経済建設の調和のとれた発展」へと変化し、軍近代化と経済建設の関係は並列化されたのであった。
なお、1992年10月の第14回党大会における報告で、江沢民は人民解放軍の役割に「領海の主権と海洋権益の擁護」を新たに追加した。これは同年2月に公布された「中華人民共和国領海及び接続水域法」で、尖閣諸島や南沙諸島を含む東シナ海、南シナ海の全島嶼の領有を明記したことを反映したものであり、中国海軍の役割拡大を政策的にオーソライズしたことになる。
4.胡錦濤の軍事戦略と情報化
胡錦濤は2002年の第16回党大会で総書記に就任したが、中央軍事委員会主席のポストは江沢民が手放さず、胡錦濤が就任したのは2004年9月の第16期第4回中央委総会であった。胡錦濤はそれに先立つ同年7月に党中央政治局集団学習会で「経済建設・国防建設」を取り上げ、国防建設と経済建設とを同時並行させる考え方を明確にした。また、胡錦濤は中央軍事委主席就任と同時に組織改編を行い、海軍、空軍、第二砲兵部隊(戦略ミサイル部隊)の司令員が新たにメンバーに加わった。これによって、陸軍の比重が圧倒的に高かった人民解放軍においても、陸・海・空の統合運用が常識化している世界の軍事趨勢に即した態勢がとられるようになったと言える。
軍事戦略に関しては、江沢民時代に本格的に開始された機械化を継続推進すると同時に、情報化に力点を置く変化が見られた。これは、2001年の9.11テロ以降、米国が遂行したアフガン戦争やイラク戦争において、人工衛星の情報を駆使した戦争遂行に触発されたものと言える。米国では、衛星やインターネット、無人偵察機等、情報通信分野における技術革新が戦争の遂行形態を革命的に進化させ、これを「軍事における革命(RMA)」と称していたが、胡錦濤の中国はその米国に範をとったと言えるだろう。
さらに胡錦濤は第17回党大会における報告で、「経済建設と国防整備を統一的に考え、小康社会を全面的に建設する過程において富国と強軍の統一を実現しなければならない」と述べ、江沢民以来の「国防整備と経済建設の調和のとれた発展」よりも踏み込み、まさに「富国強兵」に舵を切った。
胡錦濤は、建国60周年となった2009年の4月には、海軍建軍60周年の「国際観艦式」を青島で挙行し、国産艦艇の威容を誇示するとともに、さらに10月の国慶節では10年ぶりの軍事パレードを行い、国産AWACS、車載レーダー、無人偵察機など情報面での戦力の近代化の進展ぶりをアピールしたのであった。
5.海軍近代化の意図するもの
これまで、毛沢東から胡錦濤に至る各指導者のもとでの軍事戦略の発展を述べてきたなかで、経済発展と連動して海洋重視、海軍の役割拡大の方向が示されてきたことについても触れてきた。大陸国家である中国にとって、海軍そのものが陸軍の補助兵種に位置づけられ、かつソ連の海軍戦略を手本にしていたため、沿海防御中心の考え方を採ってきた。国内に十分なエネルギー資源を持つソ連にとっては、守るべき海洋資源やシーレーンが存在しなかったこともあり、その影響を受けた中国海軍にも当初は海洋資源やシーレーン防衛の発想がなかったとしても不思議ではない。しかし、中国はソ連のような資源大国ではない。中国が尖閣諸島の領有を主張し始めた背景に東シナ海の海底資源があり、1993年から石油の純輸入国となって現在では米国に次ぐ世界第2位の石油輸入国となっている。海外からのエネルギー輸入に経済成長の持続性が強く関連付けられているのである。
こうした経済的側面と同時に、中国共産党にとっての宿願である台湾との統一をめざし、かつ台湾の「独立」を阻止するため、台湾海峡を中心とした海域における制海権、制空権の確保も人民解放軍に課せられた任務となる。その場合、米国の軍事的介入を阻止することも当然視野に入ってくる。軍事的にも海軍の充実は求められているのである。
中国の海洋戦略をあらわすキーワードは「第一列島線」と「第二列島線」である。日本列島、沖縄を含む南西諸島、フィリピン、さらにインドネシアの大スンダ列島に至る第一列島線は、その内側に中国が主張する排他的経済水域をカバーするものであり、中国にとって絶対的な制海権を確保する対象である。さらに第二列島線は、伊豆諸島から南下し小笠原諸島を経てマリアナ諸島、さらにパプアニューギニアに至るもので、西太平洋における中国海軍の活動の拡大を図るための目標とみなされる。米軍の西太平洋における拠点であるグアムはこの第二列島線上にあり、中国がこの海域まで進出し、米海軍の行動を制約出来れば、台湾有事の際に米軍の介入は困難となり、中国にとって台湾への軍事力行使はきわめて容易になる。いわゆる中国の対米「接近阻止」戦略であり、そのために米空母を標的とする対艦弾道ミサイル「東風21D」の開発も進めている。
6.南シナ海の「聖域」化がもたらす摩擦
2010年以来、中国が南シナ海を、チベットや台湾と並ぶ「中国の核心的利益」と呼ぶようになり注目された。一般的には、ベトナムやフィリピンなどと領有権の主張でぶつかる南沙諸島の確保を念頭におくものと理解されているが、戦略的には異なった見方ができる。中国が南シナ海の海南島に新たな潜水艦基地を作り、そこに新型のタイプ094「晋」級ミサイル原潜が配備されている。つまり、中国は南シナ海をミサイル原潜のための「聖域」にしたいのである。これまで中国はタイプ092「夏」級ミサイル原潜を一隻保有し、山東省青島の潜水艦基地に配備してきたが、作戦任務につくことはなかった。東シナ海、さらに北部の黄海は水深が浅く、かつ韓国、日本に近いこともあり、ミサイル原潜が行動するのに適切な海域ではなかった。さらに北の渤海湾は、完全な中国の「内海」で、「聖域」化は容易なものの、水深が平均で25メートルに過ぎず、潜水艦の活動自体が困難である。結論的に、南シナ海をミサイル原潜の「聖域」とし、これまで地上発射の戦略核ミサイルにのみ依存してきた核抑止力に、新たに非脆弱な核抑止力としてミサイル原潜を展開する構想を実現しようとしているのである。
南シナ海を「聖域」とするためには、この海域における絶対的制海権を中国が確保する必要がある。中国が空母の保有を実現するとすれば、南シナ海に配備するだろうと予測されるのもそのためである。ただし、この海域は日本や韓国、さらに中国にとっても重要な海上輸送ルートに当たり、中国がこの海域で海軍力を強めようとすればするほど、国際的な摩擦を生じることになる。中国の軍事戦略の発展は、東アジア地域に広く影響を与える段階にまで来ているのである。
ここでは、建国以来の中国の軍事戦略の変化を整理しつつ、その中で中国がいかに海軍建設を進展させてきたかを論じ、そのことがもたらしつつある問題点を明示したい。
1.毛沢東の軍事戦略
19世紀のアヘン戦争以来、欧米列強によって侵食された経験を持つ中国にとって、そうした屈辱の歴史を繰り返さないためにも強固な軍事力は必要不可欠なものと認識された。さらに米ソ冷戦の渦中に社会主義国家として建国した中国にとり、資本主義との最終決戦となる「第三次世界大戦」は「不可避」と位置づけられ、それに備えるべく臨戦態勢が取られるとともに、対米抑止力としての核武装が急がれた。重要な工業施設は安全な内陸奥地に移転する、いわゆる「三線建設」などの措置が取られたのもこの時期である。
その時期の指導者であった毛沢東は、常に外部に敵を想定する「主敵」論に立ち、臨戦態勢で対応することを構想した。本土防衛については、「敵を人民の海に深く誘い入れ、包囲し殲滅する」という人民戦争論で対応し、朝鮮戦争で戦火を交えた米国、さらには「中ソ対立」後のソ連の核戦力に対しては独自開発の戦略核ミサイルで対抗するという「2本足」戦略で対抗した。
この時期の中国の軍事戦略は、対外宣伝的には好戦的印象を与えるものであったが、実際には戦力的劣勢を自覚したきわめて防御的なものであった。こうした防御的姿勢は、鄧小平が実権を掌握したことによって1978年末から始まる「改革・開放」政策の進展にしたがって徐々に変化してくる。「改革・開放」政策では、文革時代(1966~1976)に世界の経済成長から取り残された中国経済をいかに成長軌道に乗せるかが問われ、そのためには独善的な閉鎖・孤立主義的「自力更生」路線を改め、西側に門戸を開き、資本と技術を導入し、製品を西側に輸出するという手法が選択された。しかし、それを実現するためには中国が常に外部に敵を想定する状況、さらに国境を接した周辺国との緊張の継続が適合するはずはなく、1985年の第12回党大会を契機に中国は「独立自主の平和外交」という全方位協調外交に舵を切ることになった。
2.鄧小平の軍事戦略と海軍
この変化を主導した鄧小平には、米ソが核戦力において相互に拮抗する状況を「核の手詰まり」とみなし、「第三次世界大戦は当面回避できる」という判断があり、それは文革時代に肥大化したままの人民解放軍をスリム化し、近代的戦争に対応できる軍隊に変革するための時間的猶予を得られるチャンスと位置づけられた。1985年から2年間で400万の軍隊を300万規模にする100万人削減が実施され、国防大学の設置(85年)、階級制度の復活(88年)など教育、制度面での改革も進めた。この時期、中国が想定した戦争は局地的な戦争であり、「現代的条件下の局地戦争を戦う」ことが軍事戦略の中心テーマとなった。
鄧小平はこうして毛沢東時代の人民戦争論に訣別し、局地的な戦争、つまり国境における領土保全のための戦争を構想するに至るが、それは国境での防御を重視する方向を生み出し、論理的に海上国境を防衛する海軍の役割を再認識させることになった。つまり、沿海中心の経済発展戦略に基づき、国境としての領海の守備が重視されることは、当然ながら海軍への期待と役割拡大をともなうこととなったのである。
3.江沢民の軍事戦略とハイテク化
1989年5月、約30年続いた中ソ対立が解け、中国は北方内陸国境の脅威から解放された。同年の予算から国防費は毎年二桁の伸びを見せるようになり、2009年まで20年連続を記録した。6月の天安門事件で党総書記に抜擢された江沢民は、同年秋には中央軍事委員会主席のポストを鄧小平から譲り受け、軍近代化の責任者となった。この時期、中央軍事委員会で江沢民を補佐した劉華清副主席(上将)は、1992年に党理論誌『救是』に論文「中国の特色をもつ近代的軍隊建設の道を揺るぎなく前進しよう」を発表し、軍近代化の重点は海・空軍であることを明示した。その背景には、1991年初めの湾岸戦争があり、米国が駆使したトマホーク巡航ミサイルやステルス戦闘機などハイテク兵器の威力に中国は強い印象を受けたことが指摘できる。ロシアからキロ級潜水艦やスホイ27戦闘機などが導入され始めたのもこの時期のことであった。
かかる経緯から、この時期の軍事戦略は「ハイテク条件下の局地戦争を戦う」へと発展し、経済発展と軍近代化の関係についても、鄧小平時代の「経済建設の大局にしたがう」という従属的関係から、2002年の第16回党大会における江沢民報告で「国防整備と経済建設の調和のとれた発展」へと変化し、軍近代化と経済建設の関係は並列化されたのであった。
なお、1992年10月の第14回党大会における報告で、江沢民は人民解放軍の役割に「領海の主権と海洋権益の擁護」を新たに追加した。これは同年2月に公布された「中華人民共和国領海及び接続水域法」で、尖閣諸島や南沙諸島を含む東シナ海、南シナ海の全島嶼の領有を明記したことを反映したものであり、中国海軍の役割拡大を政策的にオーソライズしたことになる。
4.胡錦濤の軍事戦略と情報化
胡錦濤は2002年の第16回党大会で総書記に就任したが、中央軍事委員会主席のポストは江沢民が手放さず、胡錦濤が就任したのは2004年9月の第16期第4回中央委総会であった。胡錦濤はそれに先立つ同年7月に党中央政治局集団学習会で「経済建設・国防建設」を取り上げ、国防建設と経済建設とを同時並行させる考え方を明確にした。また、胡錦濤は中央軍事委主席就任と同時に組織改編を行い、海軍、空軍、第二砲兵部隊(戦略ミサイル部隊)の司令員が新たにメンバーに加わった。これによって、陸軍の比重が圧倒的に高かった人民解放軍においても、陸・海・空の統合運用が常識化している世界の軍事趨勢に即した態勢がとられるようになったと言える。
軍事戦略に関しては、江沢民時代に本格的に開始された機械化を継続推進すると同時に、情報化に力点を置く変化が見られた。これは、2001年の9.11テロ以降、米国が遂行したアフガン戦争やイラク戦争において、人工衛星の情報を駆使した戦争遂行に触発されたものと言える。米国では、衛星やインターネット、無人偵察機等、情報通信分野における技術革新が戦争の遂行形態を革命的に進化させ、これを「軍事における革命(RMA)」と称していたが、胡錦濤の中国はその米国に範をとったと言えるだろう。
さらに胡錦濤は第17回党大会における報告で、「経済建設と国防整備を統一的に考え、小康社会を全面的に建設する過程において富国と強軍の統一を実現しなければならない」と述べ、江沢民以来の「国防整備と経済建設の調和のとれた発展」よりも踏み込み、まさに「富国強兵」に舵を切った。
胡錦濤は、建国60周年となった2009年の4月には、海軍建軍60周年の「国際観艦式」を青島で挙行し、国産艦艇の威容を誇示するとともに、さらに10月の国慶節では10年ぶりの軍事パレードを行い、国産AWACS、車載レーダー、無人偵察機など情報面での戦力の近代化の進展ぶりをアピールしたのであった。
5.海軍近代化の意図するもの
これまで、毛沢東から胡錦濤に至る各指導者のもとでの軍事戦略の発展を述べてきたなかで、経済発展と連動して海洋重視、海軍の役割拡大の方向が示されてきたことについても触れてきた。大陸国家である中国にとって、海軍そのものが陸軍の補助兵種に位置づけられ、かつソ連の海軍戦略を手本にしていたため、沿海防御中心の考え方を採ってきた。国内に十分なエネルギー資源を持つソ連にとっては、守るべき海洋資源やシーレーンが存在しなかったこともあり、その影響を受けた中国海軍にも当初は海洋資源やシーレーン防衛の発想がなかったとしても不思議ではない。しかし、中国はソ連のような資源大国ではない。中国が尖閣諸島の領有を主張し始めた背景に東シナ海の海底資源があり、1993年から石油の純輸入国となって現在では米国に次ぐ世界第2位の石油輸入国となっている。海外からのエネルギー輸入に経済成長の持続性が強く関連付けられているのである。
こうした経済的側面と同時に、中国共産党にとっての宿願である台湾との統一をめざし、かつ台湾の「独立」を阻止するため、台湾海峡を中心とした海域における制海権、制空権の確保も人民解放軍に課せられた任務となる。その場合、米国の軍事的介入を阻止することも当然視野に入ってくる。軍事的にも海軍の充実は求められているのである。
中国の海洋戦略をあらわすキーワードは「第一列島線」と「第二列島線」である。日本列島、沖縄を含む南西諸島、フィリピン、さらにインドネシアの大スンダ列島に至る第一列島線は、その内側に中国が主張する排他的経済水域をカバーするものであり、中国にとって絶対的な制海権を確保する対象である。さらに第二列島線は、伊豆諸島から南下し小笠原諸島を経てマリアナ諸島、さらにパプアニューギニアに至るもので、西太平洋における中国海軍の活動の拡大を図るための目標とみなされる。米軍の西太平洋における拠点であるグアムはこの第二列島線上にあり、中国がこの海域まで進出し、米海軍の行動を制約出来れば、台湾有事の際に米軍の介入は困難となり、中国にとって台湾への軍事力行使はきわめて容易になる。いわゆる中国の対米「接近阻止」戦略であり、そのために米空母を標的とする対艦弾道ミサイル「東風21D」の開発も進めている。
6.南シナ海の「聖域」化がもたらす摩擦
2010年以来、中国が南シナ海を、チベットや台湾と並ぶ「中国の核心的利益」と呼ぶようになり注目された。一般的には、ベトナムやフィリピンなどと領有権の主張でぶつかる南沙諸島の確保を念頭におくものと理解されているが、戦略的には異なった見方ができる。中国が南シナ海の海南島に新たな潜水艦基地を作り、そこに新型のタイプ094「晋」級ミサイル原潜が配備されている。つまり、中国は南シナ海をミサイル原潜のための「聖域」にしたいのである。これまで中国はタイプ092「夏」級ミサイル原潜を一隻保有し、山東省青島の潜水艦基地に配備してきたが、作戦任務につくことはなかった。東シナ海、さらに北部の黄海は水深が浅く、かつ韓国、日本に近いこともあり、ミサイル原潜が行動するのに適切な海域ではなかった。さらに北の渤海湾は、完全な中国の「内海」で、「聖域」化は容易なものの、水深が平均で25メートルに過ぎず、潜水艦の活動自体が困難である。結論的に、南シナ海をミサイル原潜の「聖域」とし、これまで地上発射の戦略核ミサイルにのみ依存してきた核抑止力に、新たに非脆弱な核抑止力としてミサイル原潜を展開する構想を実現しようとしているのである。
南シナ海を「聖域」とするためには、この海域における絶対的制海権を中国が確保する必要がある。中国が空母の保有を実現するとすれば、南シナ海に配備するだろうと予測されるのもそのためである。ただし、この海域は日本や韓国、さらに中国にとっても重要な海上輸送ルートに当たり、中国がこの海域で海軍力を強めようとすればするほど、国際的な摩擦を生じることになる。中国の軍事戦略の発展は、東アジア地域に広く影響を与える段階にまで来ているのである。
(2011年7月)