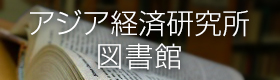中国の外交方針の変遷
政策提言研究
高原 明生 (東京大学大学院教授)
2011年7月
※以下に掲載する文章は、平成23年度政策提言研究「 中国・インドの台頭と東アジアの変容 」第2回研究会(2011年7月7日開催)における報告内容を要約したものです。
PDF (123KB)
1.鄧小平が主導した外交の特徴
本日は中国の外交方針の変遷について語ることになっているが、焦点はここ数年の方針転換であり、毛沢東時代まで振り返る余裕はない。しかし、鄧小平が主導した中国外交の特徴をおさらいすることで、ポイントを把握することは出来る。
鄧小平外交の第一の特徴は、現実的な国際情勢判断に基づいていたことにある。鄧小平は、世界では平和と発展が主な潮流となっており、世界大戦は回避可能だと考えた(毛沢東はそう考えていなかった)。そこで、目下の第一の任務は発展であり、資本主義国との間でも経済的な相互依存関係を築いていった。
第二の特徴は、客観的な自己認識を有していたことである。鄧小平においても大国意識は強かったが、それと同時に中国は小国でもあると認識していた。後に「社会主義の初級段階」にあるとも言われたが、要するに科学技術や工業化が遅れた発展途上国だという自覚が強かった。
第三には、イデオロギーより国家利益を重視したことが挙げられる。国際共産主義運動から次第に足を洗い、平和な国際環境を実現して四つの近代化を追求することを外交の目標に据えた。
そして第四に、「韜光養晦」の外交方針の採用が挙げられる。表現は時代によって異なり、80年代の方針は「同盟せず、覇を称えず、突出せず」というものであった。89年の六四事件、いわゆる第2次天安門事件を経て、90年代には「冷静観察、穏住陣脚(足下を固め)、沈着応付、韜光養晦(鋭気や才能を隠して時を待つ)、善于守拙(劣勢時に利口なまねをしない)、決不当頭(決して先頭に立たず)、有所作為(為すべきを為して業績を上げる)」の28文字に整理された。その核心が「韜光養晦」であり、低姿勢を保つことがいわば外交方針に関する鄧小平の遺訓であった。
2.「韜光養晦」をめぐる綱引き
現在、中国では「韜光養晦」をめぐる論争が表面化している。一方には、鄧小平の教えである「韜光養晦」を守っていかねばならないと主張する者も少なくない。その論拠としては、経済規模では日本を抜いたものの、中国は依然として1人当たりGDPが低い発展途上国であることが挙げられる。また、最近のメディアに登場する軍人の勇ましい発言は中国のイメージを悪化させるのでやめさせるべきであるとか、北朝鮮の核・ミサイル開発や問題行動に中国は厳しく臨むべきであるといった声も、この立場と親和的である。
ところが、「韜光養晦」を超越する時が来たという主張も強くなってきた。すなわち、中国は世界経済を牽引するまでになり、G20でも中心的な役割を期待されている、中国の時代が来たのであって、もっと自己主張を強めてもよいのだとする訴えである。リアリズムに基づき、海外の権益を守る必要性が強まったので軍事力の投射能力を強めるべきだとか、緩衝地帯として有用な北朝鮮への支援を強化すべきだといった声は、こちらの立場と親和的である。
この論争は今も続いているが、実は2009年7月の在外使節会議(大使会議)において、胡錦濤はすでに方針の一部修正を発表している。すなわち、「韜光養晦、有所作為」に四文字を足して、「堅持韜光養晦、積極有所作為」を新外交方針とした。一見すると玉虫色の修正であるが、力点は「為すべきを為し、業績を上げる」ことを「積極」化するところにあった。同時に発表された外交上の戦略目標は、政治の影響力、経済の競争力、イメージの親和力、道義の感化力を強めることであった。また、周辺の地政学的戦略拠点を築く活動を充実、強化せよという指示も出され、恐らくはそれに基づいて09年後半からの北朝鮮支援の梃入れが行われたものと思われる。
しかし、自己主張を強めた結果、2010年は中国外交の“annus horribilis” (ひどい年)になってしまった。それを反省したのか、2011年に入ってからの対米、対日外交はいずれもかなり軟化した。しかし、新外交方針が改められたわけではなく、その運用をめぐる論争は続いていくだろう。
3.新外交方針の背景——多面的な論争、綱引き
外交方針をめぐる論争の背景には、それに関連する諸問題をめぐる意見の不一致が存在する。その一つは、「中国モデル」をめぐる論争である。一方には、「中国モデル」は存在しないとする立場がある。それによれば、中国の発展様式の特徴が「独裁+市場経済+ナショナリズム」だとすれば、それはいわゆる開発独裁と同じであり、ユニークさはない。また、中国の社会制度はまだ改革の途上にあり、他国のモデルになりえないだけでなく、中国社会の現状をみれば問題は山積しており(格差、縁故主義、汚職腐敗、物価、環境汚染、高齢化等)、とてもモデルを称することのできる状況ではないとする。
それに対しては、しかし「中国モデル」は存在し、有効だとする立場も存在する。特に08年秋に米国発の世界金融危機が起き、米国資本主義の象徴である金融機関や自動車会社の国有化が起きると、「アメリカモデル、ワシントンコンセンサス」の天下は終わり、これからは「中国モデル、北京コンセンサス」の時代だと自信を強める者も増えた。中国社会の現状についていえば、生活水準は向上し、かつ国際的な地位も高まっているのは事実であって、近代以降最高の状態にあるのだという。
この論争に絡むのが、「普遍的価値」をめぐる意見の不一致である。一方には、「普遍的価値」は存在し、中国ではまだ実現できていないとする立場がある。鄧小平をはじめ、江沢民も胡錦濤もこの立場を表明してきた。最近では、温家宝が人権の実現を強く訴えている。ところが、いまや「普遍的価値」など存在しないとする立場が宣伝部門内では強くなっている。すなわち、西洋が自分たちの価値を中国に押し付けるためにそう呼んでいるだけであり、「普遍的価値」を唱えることは中国の否定につながるのだという。
4.外交方針をめぐる現在の論争の性質
以上の考察から、今後の中国の政治と外交の方向性に関する深刻な論争が激しく展開されている様子が見て取れる。単純化のそしりを恐れずに整理を試みれば、一方における改革派、国際主義者、穏健派に対し、他方には保守派、国粋主義者、強硬派がいる。そして前者に対し、後者が勢いを増す恐れがある。
もちろん現実は複雑であって、様々な立場が入り乱れ、きれいに二極に分かれるわけではない。しかし、この枠組みは、複雑な現実を整理し、理解する上で少しは役に立つのではないかと考える。
本日は中国の外交方針の変遷について語ることになっているが、焦点はここ数年の方針転換であり、毛沢東時代まで振り返る余裕はない。しかし、鄧小平が主導した中国外交の特徴をおさらいすることで、ポイントを把握することは出来る。
鄧小平外交の第一の特徴は、現実的な国際情勢判断に基づいていたことにある。鄧小平は、世界では平和と発展が主な潮流となっており、世界大戦は回避可能だと考えた(毛沢東はそう考えていなかった)。そこで、目下の第一の任務は発展であり、資本主義国との間でも経済的な相互依存関係を築いていった。
第二の特徴は、客観的な自己認識を有していたことである。鄧小平においても大国意識は強かったが、それと同時に中国は小国でもあると認識していた。後に「社会主義の初級段階」にあるとも言われたが、要するに科学技術や工業化が遅れた発展途上国だという自覚が強かった。
第三には、イデオロギーより国家利益を重視したことが挙げられる。国際共産主義運動から次第に足を洗い、平和な国際環境を実現して四つの近代化を追求することを外交の目標に据えた。
そして第四に、「韜光養晦」の外交方針の採用が挙げられる。表現は時代によって異なり、80年代の方針は「同盟せず、覇を称えず、突出せず」というものであった。89年の六四事件、いわゆる第2次天安門事件を経て、90年代には「冷静観察、穏住陣脚(足下を固め)、沈着応付、韜光養晦(鋭気や才能を隠して時を待つ)、善于守拙(劣勢時に利口なまねをしない)、決不当頭(決して先頭に立たず)、有所作為(為すべきを為して業績を上げる)」の28文字に整理された。その核心が「韜光養晦」であり、低姿勢を保つことがいわば外交方針に関する鄧小平の遺訓であった。
2.「韜光養晦」をめぐる綱引き
現在、中国では「韜光養晦」をめぐる論争が表面化している。一方には、鄧小平の教えである「韜光養晦」を守っていかねばならないと主張する者も少なくない。その論拠としては、経済規模では日本を抜いたものの、中国は依然として1人当たりGDPが低い発展途上国であることが挙げられる。また、最近のメディアに登場する軍人の勇ましい発言は中国のイメージを悪化させるのでやめさせるべきであるとか、北朝鮮の核・ミサイル開発や問題行動に中国は厳しく臨むべきであるといった声も、この立場と親和的である。
ところが、「韜光養晦」を超越する時が来たという主張も強くなってきた。すなわち、中国は世界経済を牽引するまでになり、G20でも中心的な役割を期待されている、中国の時代が来たのであって、もっと自己主張を強めてもよいのだとする訴えである。リアリズムに基づき、海外の権益を守る必要性が強まったので軍事力の投射能力を強めるべきだとか、緩衝地帯として有用な北朝鮮への支援を強化すべきだといった声は、こちらの立場と親和的である。
この論争は今も続いているが、実は2009年7月の在外使節会議(大使会議)において、胡錦濤はすでに方針の一部修正を発表している。すなわち、「韜光養晦、有所作為」に四文字を足して、「堅持韜光養晦、積極有所作為」を新外交方針とした。一見すると玉虫色の修正であるが、力点は「為すべきを為し、業績を上げる」ことを「積極」化するところにあった。同時に発表された外交上の戦略目標は、政治の影響力、経済の競争力、イメージの親和力、道義の感化力を強めることであった。また、周辺の地政学的戦略拠点を築く活動を充実、強化せよという指示も出され、恐らくはそれに基づいて09年後半からの北朝鮮支援の梃入れが行われたものと思われる。
しかし、自己主張を強めた結果、2010年は中国外交の“annus horribilis” (ひどい年)になってしまった。それを反省したのか、2011年に入ってからの対米、対日外交はいずれもかなり軟化した。しかし、新外交方針が改められたわけではなく、その運用をめぐる論争は続いていくだろう。
3.新外交方針の背景——多面的な論争、綱引き
外交方針をめぐる論争の背景には、それに関連する諸問題をめぐる意見の不一致が存在する。その一つは、「中国モデル」をめぐる論争である。一方には、「中国モデル」は存在しないとする立場がある。それによれば、中国の発展様式の特徴が「独裁+市場経済+ナショナリズム」だとすれば、それはいわゆる開発独裁と同じであり、ユニークさはない。また、中国の社会制度はまだ改革の途上にあり、他国のモデルになりえないだけでなく、中国社会の現状をみれば問題は山積しており(格差、縁故主義、汚職腐敗、物価、環境汚染、高齢化等)、とてもモデルを称することのできる状況ではないとする。
それに対しては、しかし「中国モデル」は存在し、有効だとする立場も存在する。特に08年秋に米国発の世界金融危機が起き、米国資本主義の象徴である金融機関や自動車会社の国有化が起きると、「アメリカモデル、ワシントンコンセンサス」の天下は終わり、これからは「中国モデル、北京コンセンサス」の時代だと自信を強める者も増えた。中国社会の現状についていえば、生活水準は向上し、かつ国際的な地位も高まっているのは事実であって、近代以降最高の状態にあるのだという。
この論争に絡むのが、「普遍的価値」をめぐる意見の不一致である。一方には、「普遍的価値」は存在し、中国ではまだ実現できていないとする立場がある。鄧小平をはじめ、江沢民も胡錦濤もこの立場を表明してきた。最近では、温家宝が人権の実現を強く訴えている。ところが、いまや「普遍的価値」など存在しないとする立場が宣伝部門内では強くなっている。すなわち、西洋が自分たちの価値を中国に押し付けるためにそう呼んでいるだけであり、「普遍的価値」を唱えることは中国の否定につながるのだという。
4.外交方針をめぐる現在の論争の性質
以上の考察から、今後の中国の政治と外交の方向性に関する深刻な論争が激しく展開されている様子が見て取れる。単純化のそしりを恐れずに整理を試みれば、一方における改革派、国際主義者、穏健派に対し、他方には保守派、国粋主義者、強硬派がいる。そして前者に対し、後者が勢いを増す恐れがある。
もちろん現実は複雑であって、様々な立場が入り乱れ、きれいに二極に分かれるわけではない。しかし、この枠組みは、複雑な現実を整理し、理解する上で少しは役に立つのではないかと考える。
(2011年7月)