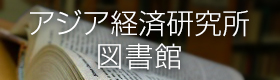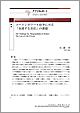論 考: コートジボワール紛争にみる「保護する責任」の課題
アフリカレポート
No.51
PDF(539KB)
■ 論 考: コートジボワール紛争にみる「保護する責任」の課題
■ 佐藤 章
■ 『アフリカレポート』2013年 No.51、pp.1-15
(画像をクリックするとPDFをダウンロードします)
要 約
本稿は、アフリカ開発にとって不可避の課題として認識されている紛争解決と平和構築の問題に関して、とくに国連や欧米諸国などのアフリカ域外の主体によって行われてきた軍事的取り組みの歴史と現状を考察しようとするものである。紛争解決・平和構築を目的として域外主体によって行われてきた軍事的取り組みは、1990年代のソマリアとルワンダでの経験を踏まえて試行錯誤が積み重ねられてきた。これを経て近年では、域外主体がアフリカ諸国の平和構築能力の強化を支援しつつ、国連PKOに代表される域外の軍事要員がアフリカ側と連携する体制が確立されてきている。本稿ではこのような歴史を整理したのち、アフリカの紛争解決・平和構築に深く関わる新しい考え方として注目されている「保護する責任」をめぐる問題を論ずる。具体的には、「保護する責任」に依拠して2011年4月にコートジボワールで行われた国連PKOによる軍事行動を取り上げ、「保護する責任」をめぐり提起されてきた諸論点が、この現実の軍事行動においてどのように現れていたかを検討したい。
はじめに
今年2013年は、第5回目となるアフリカ開発会議(TICAD)が開催される。いうまでもなく開発は、アフリカ諸国にとって独立以来の課題であり、その重要性は今世紀においても減じていない。開発には、よりよい生活ができること(社会開発)、社会生活を営む個々人の健康や、職業的技能・教育が増進されること(人間開発)、経済的な富を増進させること(経済成長)など多面的な課題が含まれるが、これらの課題が実現されるうえでの重要な前提条件が治安の維持と政治的安定である。生命や財産が脅威に晒されていたり、激しい政治対立によって自由な議論ができなかったり、政治信条が異なる者を標的とした暴力が行使されたりするような状況は、開発の諸課題に逆行するものである。このため、武力紛争の解決と平和構築は、アフリカの開発にとって避けて通れない課題となる。
紛争解決と平和構築にかかわるさまざまな取り組みの中で、本稿では軍事要員を用いた取り組み、それも国連や欧米諸国などを中心としたアフリカ域外の主体によるものに焦点をあてたい。軍事要員を用いた取り組みは、停戦監視、治安維持、重要人物や人道援助活動の警護、戦闘員の武装解除・動員解除、選挙実施の支援など多岐にわたり、和平プロセスを円滑に進めるための重要な鍵を握る。アフリカで紛争が多発しはじめた1980年代末から今日までのあいだに、アフリカ域外の主体による軍事要員を用いた取り組みは大きな役割を果たしてきた。現時点から回顧すると、これらの試みは、即座に所定の目標を実現したとは言い難く、むしろ試行錯誤の連続と呼ぶのが適切である。そして、この試行錯誤は現在なお続いている。この試行錯誤の歴史がはたしてどのようなものだったか。また、現在ではどのような取り組みが試みられているのか。このような観点に立って、アフリカの紛争解決と平和構築の問題を考察するのが本稿の目的である。
本稿で具体的に検討してみたいのは、国連平和維持活動(PKO)である「国連コートジボワール活動」(United Nations Mission in Côte d’Ivoire: UNOCI)が2011年4月にコートジボワールで実施した軍事行動についてである。この軍事行動は、「保護する責任」(Responsibility to Protect)という近年浮上している考え方に依拠したものとして国際的にも広く注目を集めた。「保護する責任」は、1990年代に世界各地で生じた紛争下での深刻な人道危機をふまえ、これに対処するための新しい考え方として登場した。この考え方をめぐっては、実際に軍事行動を起こす際に浮上するさまざまな問題が指摘されており、今なお議論が続けられている。また、「保護する責任」の考え方は、後述するとおり、アフリカ連合(African Union: AU)の組織的な目的に取り入れられており、アフリカにおける紛争解決・平和構築をめぐる今後の動きとも深い関わりを持つと考えられる。
このような背景に照らし本稿では、「保護する責任」をめぐって提起されてきた問題が、コートジボワールでのUNOCIの軍事行動においてどのように具体的に現れていたかを検討する。これにより本稿は、アフリカ域外の主体による軍事行動が紛争国の政治情勢に与える影響について具体的な知見を提示し、アフリカ政治研究の立場から「保護する責任」をめぐる議論に対して貢献を試みる。以下、本稿では、大きく2部に分けて考察を行う。まず前半では、1980年代末以降のアフリカでの武力紛争の多発状況(第1節)と、アフリカ域外の主体による軍事行動の試行錯誤の歴史(第2節)を振り返りながら、「保護する責任」の考え方が、アフリカでの実際の軍事行動に適用されることになったことの意義を歴史的に考察する。その考察をふまえ後半では、コートジボワールでのUNOCIの軍事行動(第3節)を整理したのち、その意義を検証する(第4節)。
紛争解決と平和構築にかかわるさまざまな取り組みの中で、本稿では軍事要員を用いた取り組み、それも国連や欧米諸国などを中心としたアフリカ域外の主体によるものに焦点をあてたい。軍事要員を用いた取り組みは、停戦監視、治安維持、重要人物や人道援助活動の警護、戦闘員の武装解除・動員解除、選挙実施の支援など多岐にわたり、和平プロセスを円滑に進めるための重要な鍵を握る。アフリカで紛争が多発しはじめた1980年代末から今日までのあいだに、アフリカ域外の主体による軍事要員を用いた取り組みは大きな役割を果たしてきた。現時点から回顧すると、これらの試みは、即座に所定の目標を実現したとは言い難く、むしろ試行錯誤の連続と呼ぶのが適切である。そして、この試行錯誤は現在なお続いている。この試行錯誤の歴史がはたしてどのようなものだったか。また、現在ではどのような取り組みが試みられているのか。このような観点に立って、アフリカの紛争解決と平和構築の問題を考察するのが本稿の目的である。
本稿で具体的に検討してみたいのは、国連平和維持活動(PKO)である「国連コートジボワール活動」(United Nations Mission in Côte d’Ivoire: UNOCI)が2011年4月にコートジボワールで実施した軍事行動についてである。この軍事行動は、「保護する責任」(Responsibility to Protect)という近年浮上している考え方に依拠したものとして国際的にも広く注目を集めた。「保護する責任」は、1990年代に世界各地で生じた紛争下での深刻な人道危機をふまえ、これに対処するための新しい考え方として登場した。この考え方をめぐっては、実際に軍事行動を起こす際に浮上するさまざまな問題が指摘されており、今なお議論が続けられている。また、「保護する責任」の考え方は、後述するとおり、アフリカ連合(African Union: AU)の組織的な目的に取り入れられており、アフリカにおける紛争解決・平和構築をめぐる今後の動きとも深い関わりを持つと考えられる。
このような背景に照らし本稿では、「保護する責任」をめぐって提起されてきた問題が、コートジボワールでのUNOCIの軍事行動においてどのように具体的に現れていたかを検討する。これにより本稿は、アフリカ域外の主体による軍事行動が紛争国の政治情勢に与える影響について具体的な知見を提示し、アフリカ政治研究の立場から「保護する責任」をめぐる議論に対して貢献を試みる。以下、本稿では、大きく2部に分けて考察を行う。まず前半では、1980年代末以降のアフリカでの武力紛争の多発状況(第1節)と、アフリカ域外の主体による軍事行動の試行錯誤の歴史(第2節)を振り返りながら、「保護する責任」の考え方が、アフリカでの実際の軍事行動に適用されることになったことの意義を歴史的に考察する。その考察をふまえ後半では、コートジボワールでのUNOCIの軍事行動(第3節)を整理したのち、その意義を検証する(第4節)。
1. 1980年代末以降のアフリカでの武力紛争
武力紛争(armed conflict)は、規模、持続期間、争点、関与する主体などにおいて実に多様な形態をとるものであり、操作的な定義の試みがさまざまになされる一方、特定の定義づけをすること自体の持つ問題も指摘されている。このため、武力紛争の「数え方」や「リスト化」は、それ自体がきわめて論争的なものとなる。そのことを留保として示しつつ、ここでは、1980年代末以降のアフリカでの紛争の多発状況を語る際に取り上げられることの多い、代表的な国を一覧に示した(表1)。いずれも、甚大な被害が発生したり、比較的長期にわたるなどし、紛争解決に関わる集中的な取り組みがなされた武力紛争が発生した国々である(国名のあとのカッコ内の数字は、武力紛争の発生期間を西暦年によって示したものである)。サハラ以南アフリカを大きく5つの地域(西、中部、北東・東、大湖地域、南部)に分けて整理したものだが、いずれの地域でも大きな武力紛争があったことが確認できる。1980年代末以降のアフリカの紛争が地域的な広がりをみせていたことがここからわかる。
表1 1980年代末以降に武力紛争を経験した主要なサハラ以南アフリカの国々*
| 西アフリカ |
リベリア (1989-95, 2000-03) シエラレオネ (1991-2002) ギニアビサウ (1998-2000) コートジボワール (2002-2011) マリ (2012-) |
| 中部アフリカ |
チャド (1990, 2005-10) コンゴ共和国 (1993-94, 1997-99) 中央アフリカ (1996-98, 2002-03, 2006-08, 2012-13) |
| 北東・東アフリカ |
ソマリア (1989-) エチオピア(1988-1991) エチオピア-エリトリア(1998-2000) スーダン(南部)(1983-2005) (ダルフール) (2003-) ケニア (2007-08) |
| 大湖地域 |
ルワンダ (1990-94) ブルンジ (1993-2003) ウガンダ、コンゴ民主共和国など(対LRA)(1994-) コンゴ民主共和国 (1996-97, 1998-2002) |
| 南部アフリカ | アンゴラ (1975-2001) モザンビーク (1975-1992) |
(出所)武内[2008, 2009]、EIU Country Report(各国編)等に基づき筆者作成。
* 1980年代末より前から継続していたものも含む。取り上げられることの多い代表的な国を示した。
* 1980年代末より前から継続していたものも含む。取り上げられることの多い代表的な国を示した。
また、この表に掲載した事例では、アンゴラとモザンビークでの紛争が1970年代に、スーダン南部での紛争が1983年に、それぞれ勃発し、1980年代末以降まで継続したものである。これら3例以外は、すべて1980年代末以降に勃発したものだが、勃発はとりわけ1980年代末から1990年代に集中していることが確認できる。2000年代になって新たに勃発した紛争は、コートジボワール、スーダンのダルフール地域、ケニア、マリでの4例にとどまっている。以上の観察からは、アフリカでの武力紛争が、1980年代末から1990年代にかけて急激にその数を増やし、かつ集中的に発生したことがわかる。このことは、紛争解決・平和構築という課題が、いわば唐突な形で浮上したことを意味している。
紛争が常にそうであるとおり、1980年代末からのアフリカの紛争も深刻な人道的惨禍を伴った。ルワンダ内戦の過程で1994年に発生した大虐殺では、わずか2カ月の間に100万人を超える人々が殺害され、それに匹敵する数の人々が難民としての生活を余儀なくされた。コンゴ民主共和国では、2次にわたる9年間の紛争による死者が540万人を数えたともいわれる。死者と難民の数が示すとおり、1980年代末以降のアフリカの紛争は、民間人に深く関わる戦争であった点が特徴である。また、ルワンダ大虐殺の際に、軍人ではない民間人の「普通の人々」が虐殺に加わったことに象徴されるように、この時期の紛争では、貧困や強制によって反乱軍や民兵組織に動員された民間人が、武力行使主体として活動した(武内[2000])。
結果として、1980年代末以降のアフリカの武力紛争には、政府側の軍や反政府勢力といった、内戦における基本的な当事者のみならず、民兵なども加わって、戦闘主体が多様化していく傾向が観察される。とくに、離合集散を繰りかえしながら多数の反政府勢力が活動する状況が広くみられた。加えて、これら国内的主体だけではなく、さまざまな国際的な武力行使の主体が参加することも、この時期のアフリカの紛争の特徴である。国連やアフリカの地域機構による平和維持部隊の展開だけではなく、周辺国による介入、また傭兵や民間軍事企業の関与などもみられた。このようにアフリカの紛争は、その多くの事例において、様々な主体が参加する錯綜した様相を呈することとなった。
1980年代末以降のアフリカの紛争にみられる以上の特徴は、紛争が深刻な惨禍をもたらすうえ、錯綜した構図で展開されるために、和平も困難となる状況があることを示唆している。これが、平和構築、復興、和解といった課題の実現にとって、きわめて困難な状況であることはいうまでもない。
紛争が常にそうであるとおり、1980年代末からのアフリカの紛争も深刻な人道的惨禍を伴った。ルワンダ内戦の過程で1994年に発生した大虐殺では、わずか2カ月の間に100万人を超える人々が殺害され、それに匹敵する数の人々が難民としての生活を余儀なくされた。コンゴ民主共和国では、2次にわたる9年間の紛争による死者が540万人を数えたともいわれる。死者と難民の数が示すとおり、1980年代末以降のアフリカの紛争は、民間人に深く関わる戦争であった点が特徴である。また、ルワンダ大虐殺の際に、軍人ではない民間人の「普通の人々」が虐殺に加わったことに象徴されるように、この時期の紛争では、貧困や強制によって反乱軍や民兵組織に動員された民間人が、武力行使主体として活動した(武内[2000])。
結果として、1980年代末以降のアフリカの武力紛争には、政府側の軍や反政府勢力といった、内戦における基本的な当事者のみならず、民兵なども加わって、戦闘主体が多様化していく傾向が観察される。とくに、離合集散を繰りかえしながら多数の反政府勢力が活動する状況が広くみられた。加えて、これら国内的主体だけではなく、さまざまな国際的な武力行使の主体が参加することも、この時期のアフリカの紛争の特徴である。国連やアフリカの地域機構による平和維持部隊の展開だけではなく、周辺国による介入、また傭兵や民間軍事企業の関与などもみられた。このようにアフリカの紛争は、その多くの事例において、様々な主体が参加する錯綜した様相を呈することとなった。
1980年代末以降のアフリカの紛争にみられる以上の特徴は、紛争が深刻な惨禍をもたらすうえ、錯綜した構図で展開されるために、和平も困難となる状況があることを示唆している。これが、平和構築、復興、和解といった課題の実現にとって、きわめて困難な状況であることはいうまでもない。
2. アフリカ域外の主体による軍事的取り組みの試行錯誤
(1)1990年代前半の取り組みとその問題点
では、このようなアフリカの紛争に対して、国連、各国政府などのアフリカ域外の主体がどのように対応してきたかを次にみていきたい。アフリカで紛争が多発しはじめる1980年代末に先立つ時代には、紛争解決に関わる国連を中心とする取り組みでは、比較的規模の小さい部隊による停戦監視や人道援助活動の支援が中心であった。しかし、このような取り組みのあり方は冷戦終結を境に一変し、国連が中心となって紛争解決・平和構築へ積極的に関与していく方針が打ち出されることになった。この新しい流れを決定づけたのは、ブトロス・ブトロス=ガーリ(Boutros Boutros-Ghali)国連事務総長(当時)が1992年に発表した『平和への課題』という報告書 1 であり、そこでは国連PKOが、軍事的な強制力も適宜使用しながら平和活動に積極的に携わっていくべきだとの考えが提示された。この背景には、冷戦後という新しい時代に対応した国連の新たな役割をめぐる議論、同じく冷戦後の時代に対応した新しい国際的な軍事的秩序(すなわち地政学)をめぐる関心、またすでにいくつか発生していた紛争での悲惨な状況に対して、人道的な関心が国際的に高まったことなどがあったと指摘できる。
このような新しい方針に棹さす形で、アフリカでの紛争解決を目指す軍事的取り組みが、アフリカ域外の主体によって1990年代初頭に積極的に行われた。しかし、その取り組みは試行錯誤の連続となった。最初の事例はソマリアでのものである。1989年に内戦が始まったソマリアでは、1991年にシアド・バーレ(Mahamed Siyaad Barre)政権が打倒されたのちも武装勢力間の対立が続き、中央政府が樹立されない状態が続いた。和平調停が行われるのと並行して、1992年には国連PKOである第1次国連ソマリア活動(United Nations Operation in Somalia I: UNOSOM I)、次いでさらに人員を拡大したアメリカ主導の多国籍軍である統一タスクフォース(United Task Force: UNITAF)が派遣され、人道援助の支援にあたった。
しかしその後、対症療法的に人道援助を続けるのではなく、紛争当事者に武力で働きかけることで積極的に平和を作りだす(平和強制)ねらいのもとに、1993年に第2次国連ソマリア活動(United Nations Operation in Somalia II: UNOSOM II)が派遣された。UNOSOM IIは、首都モガディシュに勢力を誇っていたアイディード(Mohamed Farrah Aidid)将軍率いる勢力の封じ込めを目的としていたが、強硬な軍事的抵抗に遭い、5カ月後には平和強制の任務を断念した。次いでアメリカが、1993年10月に特殊部隊を中心とする1万8000人の兵力を投入し、アイディード将軍の身柄確保に乗り出したが、何人かの米兵が殺害され、その遺体が海岸で引きずりまわされるショッキングな映像が国際プレスを通じて流される結果を招いた。アイディード将軍の身柄確保にも失敗し、アメリカはソマリアから完全撤退した。ソマリアでの試みは、世界最大の軍事大国ですら、積極的な平和の創造・強制が困難であるという厳しい現実を浮き彫りにした。
外部主体による軍事的取り組みの難しさを浮き彫りにした第2の事例は、ソマリアでの試みが失敗した直後のルワンダでの対応である。ルワンダでは、隣国ウガンダに逃れていたルワンダ難民を中心に組織されたルワンダ愛国戦線(Rwandan Patriotic Front: RPF)が1990年に蜂起し、ルワンダ政府との内戦が始まった。1993年に和平合意が締結され、これに基づいて国連ルワンダ支援団(United Nations Assistance Mission for Rwanda: UNAMIR)が派遣された。UNAMIRは、UNOSOM IIで試みられたような武力を用いた強制行動をとる権限は与えられていない、停戦監視を任務とする国連PKOであった。
しかし、当時のルワンダでは、和平合意を不満とする政権側が扇動放送をするなどして緊張が激化する傾向にあった。UNAMIRの司令官が国連本部側に対して、今後の事態の悪化に関して繰りかえし懸念を表明していたにもかかわらず、ソマリアでの強制行動の試みが失敗した直後ということもあって、強制行動を伴う追加的措置の導入は見送られた。このため、1994年4月に大虐殺が発生したとき、強制行動の権限を付与されていないUNAMIRは、結果的にこれを「傍観」することとなった。加えて、PKO兵士にも犠牲者が出て、兵員を派遣していた国々が相次いで撤退を決めたことから、UNAMIRは活動困難な状況に追い込まれてしまった。
ここでフランスがルワンダへの兵員派遣に乗り出した。「トルコ石作戦」(Opération turquoise)と命名されたこの軍事行動は、難民が安全に国外脱出できるよう避難路を設定することを目的としたもので、一定の成功を収めたことが評価されている。しかしながら、フランスが設定した避難路を通って国外に脱出したのは難民だけではなく、虐殺に関与したルワンダのハビャリマナ(Juvénal Habyarimana)政権側の幹部らも含まれていた。このことから、フランスの軍事行動に対しては、難民保護は口実で、むしろ、従来から親仏政権として支援してきたハビャリマナ政権幹部の保護こそが隠された意図だったのではないか、との批判が向けられることとなった。
アフリカ域外の主体によるこのときのルワンダへの対応は、ソマリアとは異なる新たな問題を浮き彫りにしている。まず、直前のソマリアでの失敗を教訓として、現地情勢へ直接に関与しない方針がとられたことにより、駐留した軍事要員(この場合は国連PKO)は、大虐殺という甚大な帰結をみすみす傍観する格好となったことである。もう一つは、大国(この場合はフランス)が独自の考えに基づいて断行した軍事行動は、その国が持つ個別の利害関心を反映した、政治的なものとなりかねないということである。
(2)アフリカ独自の対応の支援と連携強化
ソマリア、ルワンダでの経験を経て、国連ならびに域外国政府が行う紛争解決のための軍事的取り組みは、実効性の面での問題と多大な物的・政治的リスクを抱えることが広く認識されるようになった。この後、アフリカ諸国による停戦監視部隊の成功例 2 も踏まえて浮上したのが、アフリカ諸国側の平和構築能力の向上という方向性である。これは、欧米諸国や国連などの域外主体の兵力が乗り出すだけではなく、アフリカ諸国みずからの兵力によって対応できる体制を支援しようとするもので、具体的には、アメリカやフランスといった国々によって、アフリカ諸国の軍隊の能力強化や軍事演習の実施などの支援が開始されている。
また、これに呼応するかたちで、アフリカ諸国の側でも紛争解決・平和構築に関する機能強化が積極的に取り組まれてきた。なかでも、アフリカ連合(AU)による取り組みにはめざましいものがある。AUの機能強化に関しては、アフリカ統一機構(Organization of African Unity: OAU)時代にはなかった、2つの新しい原則が発足時の基本文書に盛り込まれたことが重要である(Williams 2007; Murithi 2007)。第1は、「非憲法的政権交代」の非難である。AU発足にあたり、「自由で公正な通常の選挙での勝利勢力に権力を委ねることを現職の政府が拒否すること」を、クーデタと同様の「非憲法的政権交代」とすることが定義され、これに該当する政権に対する制裁手続きも定められた 3 。第2は、「戦争犯罪、ジェノサイド、人道に対する犯罪などの重大な状況に鑑みた首脳会議の決定に基づき、連合が加盟国に介入する権利」である 4 。そして、このような安全保障に関わる問題について迅速な意志決定を行うため、AUの機関として、「平和安全保障理事会」(Peace and Security Council: PSC)が設置された 5 。さらにAUは、独自の平和維持部隊の派遣(ダルフール、ソマリア)も開始しており、機能強化の取り組みは着実に具体化されている。
AUによる取り組みは、「アフリカの問題のアフリカによる解決」という歴史的理念を具体化する取り組みとして理解されるものだが、ここで重要なのは、このような方向性のもとでもアフリカ域外の主体による紛争解決への関与は決して否定されなかったことである。このことは、1990年代半ばまでにいったん低調になった、アフリカ域外の主体によるアフリカでの平和維持活動が、もっぱら国連PKOの形で1990年代後半から再び急増し、要員も増加したことに端的に表れている(武内 2008; 清水 2011)。
国連PKOの大規模化は、停戦監視に任務を限定した小規模な部隊という伝統的なあり方とは一線を画する、いわゆる「第2世代PKO」の増加による。「第2世代PKO」は、現地の治安の維持、人道援助活動の保護、武装解除・動員解除・(社会への)再統合(Desarmament, Demobilization, Reintegration: DDR)、選挙支援、難民保護、人権状況の監視、文民の保護などと実に多岐にわたる任務を持ち、また、多くの場合、国連憲章第7章に基づく強制行動をとる権限も付与されている。このような多任務ミッションは、中長期の取り組みが求められる国家の再建・建設を包括的に支援するものであり、当然ながら派遣期間も以前より長い期間を想定したものである。
つまり、アフリカ諸国は、紛争解決に向けたアフリカ域内での主体的な取り組みだけでなく、もっとも重要な域外主体である国連との関係を中心に、アフリカ域外の主体との「連携関係の強化」を同時並行的に追求してきたのである(滝澤 2010)。
(3)「保護する責任」——試行錯誤のあらたな課題——
さてこのように、1990年代に入ってから20年あまりのあいだに、アフリカの武力紛争に対するアフリカ域外の主体による軍事的取り組みは、試行錯誤を経ながら、より実効性のある体制作りにむけて努力が続けられてきた。ただ、それは完成形に至ったわけではなく、現在も試行錯誤が続いているとみるのが妥当である。本稿が焦点をあてるコートジボワールでの2011年の国連PKOによる軍事行動は、域外主体による軍事的取り組みのあり方をめぐる新たな課題を浮き彫りにしたものといえるが、この軍事行動の検討に先立ち、「保護する責任」について、その登場の経緯と主たる論点を整理しておきたい。
ルワンダ大虐殺などのアフリカでの紛争事例、ならびに旧ユーゴスラヴィアでの内戦の中で生じた民間人の虐殺事件などをきっかけとして、武力紛争下における文民の保護をいかに実現するかという問題意識が国際的な場で浮上してきた。1999年9月の国連総会での演説で、コフィ・アナン(Kofi A. Annan)事務総長(当時)が文民の保護に言及したことを嚆矢として国連の場での公式の議論が始まり、その直後には、文民の保護を任務のひとつに明記した初めての国連PKOとして、国連シエラレオネ活動(United Nations Mission in Sierra Leone: UNAMSIL)が活動を開始した。
「保護する責任」という表現そのものは、武力紛争下での文民の保護をめぐる課題を検討するためにカナダ政府が設立した「介入と国家主権に関する国際委員会」(International Commission on Intervention and State Sovereignty: ICISS)が、2001年に発表した報告書のなかで登場した。この報告書での議論も反映するかたちで、2005年の国連総会世界サミットでは、「各々の国家は、集団殺害、戦争犯罪、民族浄化および人道に対する罪から住民を保護する責任を負う」ことが基本的前提として確認され、この前提に基づいて、国家当局が「自国民を保護することに明らかに失敗している場合」は、国際共同体が安保理を通して「第7章を含む国連憲章に則り[中略]集団的行動をとる用意がある」ことが明言された 6 。これは、武力紛争下の文民の保護を誰が行うのかという問題に対して、安保理の決定に基づいて権限を付与された主体が行うことができるとする規範を明文化したものといえる。
これまでにアフリカで生じてきた紛争での人道的被害の甚大さを想起するに、当該国の政府が文民の保護に失敗している事例が広くみられてきたことは間違いない。この問題へ対応可能な論拠を提供している点で、「保護する責任」は、アフリカでの紛争の惨禍を軽減する新しいアプローチの根幹をなしうる考えだといえる。実際、AUがその制定法において、戦争犯罪、ジェノサイド、人道に対する犯罪などに鑑みて加盟国に介入する権利を明記したことは、「保護する責任」の考え方と共通の発想に立つものである。AUが、「保護する責任」という表現の登場前にいち早くこのような考えを取り入れたのも、紛争下の文民の保護に関する実践的な対応を可能にするものとして、大きな利点を認めたがゆえと考えられる。
しかしながら、「保護する責任」の考え方に対しては、さまざまな懸念も提起されている。例えば、「保護する責任」を行使する根拠とされる、国家当局が「自国民を保護することに明らかに失敗している場合」を誰が認定するのかといえば、現在の手続きでは、その任は安保理に委ねられている。しかし、安保理は常任理事国である5大国の権限が大きいため、これらの国々が議論をリードし、自国に都合のよいかたちで軍事行動に乗り出す事態が生じかねない。言い換えれば、大国の介入主義に安保理の「お墨付き」を与えるかたちで運用される可能性がここにはあり、過去に植民地支配を受けた経験をもつ、アフリカ諸国を含む発展途上国側からの慎重な姿勢が向けられるのもこの点である。また、軍事行動は常にキャパシティの限界が存在するものである。事態が深刻だからといって、際限なく部隊の規模を大きくすることはできない。実際に派遣される部隊の能力で応じられる範囲に限界があることを考えると、その限られた対応能力で保護を提供できるところと、できないところとの間に、截然たる格差が生まれることは不可避である。
このように、「保護する責任」の考え方は、この10年あまりのあいだに、国連を中心とする紛争解決の議論において広く共有されるようになったが、その実際の適用をめぐってはさまざまな議論がなされている現状がある。この理念に依拠しながら行われた実際の軍事行動を検証することは、この議論に対して大きく貢献するものと考えられる。またその検証は、アフリカにおける紛争解決の取り組みをさらに実効性のあるものに深化させていくうえでも重要だと考えられる。そこで以下後半では、コートジボワールで行われた国連PKOの軍事行動について考察することにしたい。
では、このようなアフリカの紛争に対して、国連、各国政府などのアフリカ域外の主体がどのように対応してきたかを次にみていきたい。アフリカで紛争が多発しはじめる1980年代末に先立つ時代には、紛争解決に関わる国連を中心とする取り組みでは、比較的規模の小さい部隊による停戦監視や人道援助活動の支援が中心であった。しかし、このような取り組みのあり方は冷戦終結を境に一変し、国連が中心となって紛争解決・平和構築へ積極的に関与していく方針が打ち出されることになった。この新しい流れを決定づけたのは、ブトロス・ブトロス=ガーリ(Boutros Boutros-Ghali)国連事務総長(当時)が1992年に発表した『平和への課題』という報告書 1 であり、そこでは国連PKOが、軍事的な強制力も適宜使用しながら平和活動に積極的に携わっていくべきだとの考えが提示された。この背景には、冷戦後という新しい時代に対応した国連の新たな役割をめぐる議論、同じく冷戦後の時代に対応した新しい国際的な軍事的秩序(すなわち地政学)をめぐる関心、またすでにいくつか発生していた紛争での悲惨な状況に対して、人道的な関心が国際的に高まったことなどがあったと指摘できる。
このような新しい方針に棹さす形で、アフリカでの紛争解決を目指す軍事的取り組みが、アフリカ域外の主体によって1990年代初頭に積極的に行われた。しかし、その取り組みは試行錯誤の連続となった。最初の事例はソマリアでのものである。1989年に内戦が始まったソマリアでは、1991年にシアド・バーレ(Mahamed Siyaad Barre)政権が打倒されたのちも武装勢力間の対立が続き、中央政府が樹立されない状態が続いた。和平調停が行われるのと並行して、1992年には国連PKOである第1次国連ソマリア活動(United Nations Operation in Somalia I: UNOSOM I)、次いでさらに人員を拡大したアメリカ主導の多国籍軍である統一タスクフォース(United Task Force: UNITAF)が派遣され、人道援助の支援にあたった。
しかしその後、対症療法的に人道援助を続けるのではなく、紛争当事者に武力で働きかけることで積極的に平和を作りだす(平和強制)ねらいのもとに、1993年に第2次国連ソマリア活動(United Nations Operation in Somalia II: UNOSOM II)が派遣された。UNOSOM IIは、首都モガディシュに勢力を誇っていたアイディード(Mohamed Farrah Aidid)将軍率いる勢力の封じ込めを目的としていたが、強硬な軍事的抵抗に遭い、5カ月後には平和強制の任務を断念した。次いでアメリカが、1993年10月に特殊部隊を中心とする1万8000人の兵力を投入し、アイディード将軍の身柄確保に乗り出したが、何人かの米兵が殺害され、その遺体が海岸で引きずりまわされるショッキングな映像が国際プレスを通じて流される結果を招いた。アイディード将軍の身柄確保にも失敗し、アメリカはソマリアから完全撤退した。ソマリアでの試みは、世界最大の軍事大国ですら、積極的な平和の創造・強制が困難であるという厳しい現実を浮き彫りにした。
外部主体による軍事的取り組みの難しさを浮き彫りにした第2の事例は、ソマリアでの試みが失敗した直後のルワンダでの対応である。ルワンダでは、隣国ウガンダに逃れていたルワンダ難民を中心に組織されたルワンダ愛国戦線(Rwandan Patriotic Front: RPF)が1990年に蜂起し、ルワンダ政府との内戦が始まった。1993年に和平合意が締結され、これに基づいて国連ルワンダ支援団(United Nations Assistance Mission for Rwanda: UNAMIR)が派遣された。UNAMIRは、UNOSOM IIで試みられたような武力を用いた強制行動をとる権限は与えられていない、停戦監視を任務とする国連PKOであった。
しかし、当時のルワンダでは、和平合意を不満とする政権側が扇動放送をするなどして緊張が激化する傾向にあった。UNAMIRの司令官が国連本部側に対して、今後の事態の悪化に関して繰りかえし懸念を表明していたにもかかわらず、ソマリアでの強制行動の試みが失敗した直後ということもあって、強制行動を伴う追加的措置の導入は見送られた。このため、1994年4月に大虐殺が発生したとき、強制行動の権限を付与されていないUNAMIRは、結果的にこれを「傍観」することとなった。加えて、PKO兵士にも犠牲者が出て、兵員を派遣していた国々が相次いで撤退を決めたことから、UNAMIRは活動困難な状況に追い込まれてしまった。
ここでフランスがルワンダへの兵員派遣に乗り出した。「トルコ石作戦」(Opération turquoise)と命名されたこの軍事行動は、難民が安全に国外脱出できるよう避難路を設定することを目的としたもので、一定の成功を収めたことが評価されている。しかしながら、フランスが設定した避難路を通って国外に脱出したのは難民だけではなく、虐殺に関与したルワンダのハビャリマナ(Juvénal Habyarimana)政権側の幹部らも含まれていた。このことから、フランスの軍事行動に対しては、難民保護は口実で、むしろ、従来から親仏政権として支援してきたハビャリマナ政権幹部の保護こそが隠された意図だったのではないか、との批判が向けられることとなった。
アフリカ域外の主体によるこのときのルワンダへの対応は、ソマリアとは異なる新たな問題を浮き彫りにしている。まず、直前のソマリアでの失敗を教訓として、現地情勢へ直接に関与しない方針がとられたことにより、駐留した軍事要員(この場合は国連PKO)は、大虐殺という甚大な帰結をみすみす傍観する格好となったことである。もう一つは、大国(この場合はフランス)が独自の考えに基づいて断行した軍事行動は、その国が持つ個別の利害関心を反映した、政治的なものとなりかねないということである。
(2)アフリカ独自の対応の支援と連携強化
ソマリア、ルワンダでの経験を経て、国連ならびに域外国政府が行う紛争解決のための軍事的取り組みは、実効性の面での問題と多大な物的・政治的リスクを抱えることが広く認識されるようになった。この後、アフリカ諸国による停戦監視部隊の成功例 2 も踏まえて浮上したのが、アフリカ諸国側の平和構築能力の向上という方向性である。これは、欧米諸国や国連などの域外主体の兵力が乗り出すだけではなく、アフリカ諸国みずからの兵力によって対応できる体制を支援しようとするもので、具体的には、アメリカやフランスといった国々によって、アフリカ諸国の軍隊の能力強化や軍事演習の実施などの支援が開始されている。
また、これに呼応するかたちで、アフリカ諸国の側でも紛争解決・平和構築に関する機能強化が積極的に取り組まれてきた。なかでも、アフリカ連合(AU)による取り組みにはめざましいものがある。AUの機能強化に関しては、アフリカ統一機構(Organization of African Unity: OAU)時代にはなかった、2つの新しい原則が発足時の基本文書に盛り込まれたことが重要である(Williams 2007; Murithi 2007)。第1は、「非憲法的政権交代」の非難である。AU発足にあたり、「自由で公正な通常の選挙での勝利勢力に権力を委ねることを現職の政府が拒否すること」を、クーデタと同様の「非憲法的政権交代」とすることが定義され、これに該当する政権に対する制裁手続きも定められた 3 。第2は、「戦争犯罪、ジェノサイド、人道に対する犯罪などの重大な状況に鑑みた首脳会議の決定に基づき、連合が加盟国に介入する権利」である 4 。そして、このような安全保障に関わる問題について迅速な意志決定を行うため、AUの機関として、「平和安全保障理事会」(Peace and Security Council: PSC)が設置された 5 。さらにAUは、独自の平和維持部隊の派遣(ダルフール、ソマリア)も開始しており、機能強化の取り組みは着実に具体化されている。
AUによる取り組みは、「アフリカの問題のアフリカによる解決」という歴史的理念を具体化する取り組みとして理解されるものだが、ここで重要なのは、このような方向性のもとでもアフリカ域外の主体による紛争解決への関与は決して否定されなかったことである。このことは、1990年代半ばまでにいったん低調になった、アフリカ域外の主体によるアフリカでの平和維持活動が、もっぱら国連PKOの形で1990年代後半から再び急増し、要員も増加したことに端的に表れている(武内 2008; 清水 2011)。
国連PKOの大規模化は、停戦監視に任務を限定した小規模な部隊という伝統的なあり方とは一線を画する、いわゆる「第2世代PKO」の増加による。「第2世代PKO」は、現地の治安の維持、人道援助活動の保護、武装解除・動員解除・(社会への)再統合(Desarmament, Demobilization, Reintegration: DDR)、選挙支援、難民保護、人権状況の監視、文民の保護などと実に多岐にわたる任務を持ち、また、多くの場合、国連憲章第7章に基づく強制行動をとる権限も付与されている。このような多任務ミッションは、中長期の取り組みが求められる国家の再建・建設を包括的に支援するものであり、当然ながら派遣期間も以前より長い期間を想定したものである。
つまり、アフリカ諸国は、紛争解決に向けたアフリカ域内での主体的な取り組みだけでなく、もっとも重要な域外主体である国連との関係を中心に、アフリカ域外の主体との「連携関係の強化」を同時並行的に追求してきたのである(滝澤 2010)。
(3)「保護する責任」——試行錯誤のあらたな課題——
さてこのように、1990年代に入ってから20年あまりのあいだに、アフリカの武力紛争に対するアフリカ域外の主体による軍事的取り組みは、試行錯誤を経ながら、より実効性のある体制作りにむけて努力が続けられてきた。ただ、それは完成形に至ったわけではなく、現在も試行錯誤が続いているとみるのが妥当である。本稿が焦点をあてるコートジボワールでの2011年の国連PKOによる軍事行動は、域外主体による軍事的取り組みのあり方をめぐる新たな課題を浮き彫りにしたものといえるが、この軍事行動の検討に先立ち、「保護する責任」について、その登場の経緯と主たる論点を整理しておきたい。
ルワンダ大虐殺などのアフリカでの紛争事例、ならびに旧ユーゴスラヴィアでの内戦の中で生じた民間人の虐殺事件などをきっかけとして、武力紛争下における文民の保護をいかに実現するかという問題意識が国際的な場で浮上してきた。1999年9月の国連総会での演説で、コフィ・アナン(Kofi A. Annan)事務総長(当時)が文民の保護に言及したことを嚆矢として国連の場での公式の議論が始まり、その直後には、文民の保護を任務のひとつに明記した初めての国連PKOとして、国連シエラレオネ活動(United Nations Mission in Sierra Leone: UNAMSIL)が活動を開始した。
「保護する責任」という表現そのものは、武力紛争下での文民の保護をめぐる課題を検討するためにカナダ政府が設立した「介入と国家主権に関する国際委員会」(International Commission on Intervention and State Sovereignty: ICISS)が、2001年に発表した報告書のなかで登場した。この報告書での議論も反映するかたちで、2005年の国連総会世界サミットでは、「各々の国家は、集団殺害、戦争犯罪、民族浄化および人道に対する罪から住民を保護する責任を負う」ことが基本的前提として確認され、この前提に基づいて、国家当局が「自国民を保護することに明らかに失敗している場合」は、国際共同体が安保理を通して「第7章を含む国連憲章に則り[中略]集団的行動をとる用意がある」ことが明言された 6 。これは、武力紛争下の文民の保護を誰が行うのかという問題に対して、安保理の決定に基づいて権限を付与された主体が行うことができるとする規範を明文化したものといえる。
これまでにアフリカで生じてきた紛争での人道的被害の甚大さを想起するに、当該国の政府が文民の保護に失敗している事例が広くみられてきたことは間違いない。この問題へ対応可能な論拠を提供している点で、「保護する責任」は、アフリカでの紛争の惨禍を軽減する新しいアプローチの根幹をなしうる考えだといえる。実際、AUがその制定法において、戦争犯罪、ジェノサイド、人道に対する犯罪などに鑑みて加盟国に介入する権利を明記したことは、「保護する責任」の考え方と共通の発想に立つものである。AUが、「保護する責任」という表現の登場前にいち早くこのような考えを取り入れたのも、紛争下の文民の保護に関する実践的な対応を可能にするものとして、大きな利点を認めたがゆえと考えられる。
しかしながら、「保護する責任」の考え方に対しては、さまざまな懸念も提起されている。例えば、「保護する責任」を行使する根拠とされる、国家当局が「自国民を保護することに明らかに失敗している場合」を誰が認定するのかといえば、現在の手続きでは、その任は安保理に委ねられている。しかし、安保理は常任理事国である5大国の権限が大きいため、これらの国々が議論をリードし、自国に都合のよいかたちで軍事行動に乗り出す事態が生じかねない。言い換えれば、大国の介入主義に安保理の「お墨付き」を与えるかたちで運用される可能性がここにはあり、過去に植民地支配を受けた経験をもつ、アフリカ諸国を含む発展途上国側からの慎重な姿勢が向けられるのもこの点である。また、軍事行動は常にキャパシティの限界が存在するものである。事態が深刻だからといって、際限なく部隊の規模を大きくすることはできない。実際に派遣される部隊の能力で応じられる範囲に限界があることを考えると、その限られた対応能力で保護を提供できるところと、できないところとの間に、截然たる格差が生まれることは不可避である。
このように、「保護する責任」の考え方は、この10年あまりのあいだに、国連を中心とする紛争解決の議論において広く共有されるようになったが、その実際の適用をめぐってはさまざまな議論がなされている現状がある。この理念に依拠しながら行われた実際の軍事行動を検証することは、この議論に対して大きく貢献するものと考えられる。またその検証は、アフリカにおける紛争解決の取り組みをさらに実効性のあるものに深化させていくうえでも重要だと考えられる。そこで以下後半では、コートジボワールで行われた国連PKOの軍事行動について考察することにしたい。
3. 国連コートジボワール活動(UNOCI)の軍事行動
(1)和平プロセスと選挙後危機
本節ではコートジボワール内戦の前史を確認したのち、UNOCIの軍事行動の目的、経過、帰結をコートジボワールの和平プロセスとの関連で述べる。1960年の独立以来、サハラ以南アフリカにはまれな「安定と発展の代名詞」と評されてきたコートジボワールは、独立以来君臨したF・ウフェ=ボワニ(Félix Houphouët-Boigny)大統領の死(1993年)を契機に、政治的に不安定化するようになった。後継のコナン=ベディエ(Henri Konan Bédié)大統領は強権化を進め、最大のライバルであるワタラ(Alassane Dramane Ouattara)元首相に対して民族差別・排外主義を動員した執拗な弾圧を続けた。1999年12月に、待遇への不満を訴えた兵士反乱の収拾に失敗してベディエ政権が崩壊すると、ゲイ(Robert Guéi)元参謀総長を首班とする軍事政権が樹立された。翌2000年10月に実施された大統領選挙の際には、ゲイ首班による不正操作への抗議行動をきっかけに、数百人の死者を出す大規模な騒乱が発生した。その後、この選挙で当選したバボ(Laurent Gbagbo)大統領のもとで、主要政治家の対話再開と国民和解が進められたものの、2002年9月には、軍事政権の残存勢力を主体とした反乱軍の挙兵により、内戦が始まった。在留自国民保護を名目に介入したフランス軍の継続駐留によって、北部に拠点を置いた反乱軍の南進は抑止され、戦線は早期に膠着した。
本来の目的である政権奪取に失敗した反乱軍が和平を志向したこともあり、この内戦では2003年1月という比較的早い時期に和平合意(マルクーシ合意)が成立した。同時期に西アフリカ諸国経済共同体(Economic Community of West African States: ECOWAS)が軍事ミッションを派遣し、翌2004年4月にはこれを母体としてUNOCIが発足した 7 。これらの国際的な部隊の監視下で、大規模な武力衝突の再発はおおむね抑止されたものの、最初の数年間の和平プロセスは大きく停滞した。その主たる原因は、マルクーシ合意が定めた大統領権限の縮小に反発したバボ大統領が、非協力的な姿勢をとったことにある。転機となったのは、2007年3月の新しい和平合意(ワガドゥグ合意)で、これにより実権を回復した大統領は、和平プロセスに前向きな姿勢を示すようになった。以後、国土分断の解消、行政要員の再配置、武装解除・動員解除・(社会への)再統合(DDR)、選挙プロセスという重要な和平プログラムが進展し、2010年10月にようやく大統領選挙の実施にこぎ着けた。
和平プロセスの集大成としての重要な位置づけを帯びたこの大統領選挙では、まず2010年10月に第1回投票が実施され、過半数を獲得した候補者がいなかったため、同年11月に、上位を占めた2名——現職のバボと挑戦者のワタラ元首相——の間で決選投票が行われた。独立選挙管理委員会(Commission électorale indépendante: CEI。以下、「選管」とする)による開票で当選とされたのはワタラである。選管発表は、和平プロセス下での選挙に関するすべての認定権限を持つ国連事務総長特使から承認され 8 、アフリカ諸国からも一致して支持された。しかしバボは、選管発表を受け入れずに勝利宣言を行い、就任式と組閣を強行した 9 。これに対抗してワタラも就任式と組閣を行い、コートジボワールは「2人の大統領、2つの政府」が並び立つ状況に入った。バボはアフリカ諸国からの退陣要請を拒み、退陣を求める国内の運動を武力で弾圧した。AUによる調停が行き詰まった2011年3月半ばに、ワタラは大統領令を発出して新たな正規軍である「コートジボワール共和国軍」(Forces républicaines de Côte d’Ivoire: FRCI。以下、「ワタラ軍」とする)を創設し、3月29日にバボ打倒を目指した軍事行動を開始した 10 。
2011年3月30日に国連安保理は決議1975を採択し、国連憲章第7章に基づき、UNOCIが「差し迫った物理的暴力の危機に晒されている文民の保護」のために、「必要なすべての手段を用いる」権限を再確認し、全面的な支持を強調した 11 。「差し迫った物理的暴力の危機に晒されている文民の保護」という任務は、2004年のUNOCI派遣当初から定められていたものだが、今回これが再確認されたのは、退陣を拒むバボ大統領が、抗議行動を行う民間人や国連施設に対して重火器を使用するのをやめさせるためであった。この決議に則りUNOCIは、2011年4月4日と11日の2度にわたり、フランス軍の支援のもとにバボの軍事拠点に空爆を行い、戦車やロケットランチャーなどの重火器を破壊した。11日の空爆の直後にバボはワタラ軍によって逮捕された。これにより4カ月半にわたって続いた選挙後危機は終結した 12 。
(2)UNOCIの軍事行動の政治史上の意義
UNOCIの軍事行動の当時、バボは、国際的に完全に孤立しながらも政権を放棄する姿勢をまったくみせておらず、保有する重火器を使ってさらに抵抗を続けることは十分に予想できることであった 13 。したがって、UNOCIの軍事行動は、文民の保護という公式の任務に適合的なタイミングで行われたといえる。その一方、UNOCIの軍事行動が実施されたのは、「2人の大統領」の対立が軍事的対立へと転化し、事実上の内戦が展開されていた時点でもあった。この内戦は、2002年に始まった内戦の和平プロセスのなかに「入れ子」のように起こった新たな内戦であるが、2011年3月31日に最大都市アビジャンでの市街戦が始まったのち、ワタラ軍が独力でバボ逮捕に至らなかったことから10日あまりにわたり膠着状態が続き、この間、数百万のアビジャン住民が電気・水道などのライフラインを途絶される人道危機の中にあった。UNOCIの軍事行動は、この内戦の一方の当事者であるバボ側の軍事力を無力化したことで、結果的にこの膠着状態を打破した。すなわち、UNOCIはワタラを支持して参戦したわけではなかったのだが、その軍事行動のタイミングから、ワタラ側の軍事的勝利が決定づけられたのである。この意味でUNOCIは、コートジボワール政治史の帰趨を決定づける、政治的な役割を果たしたといえる。この点は、文民の保護ならびに「保護する責任」を理念とする軍事行動における「規範意識とその実行の齟齬」(清水 2011: 117)に関連して、コートジボワールの事例が提起する重要な論点であると考えられる。
同時に、UNOCIの軍事行動は、国際的に広く認められた選管発表の通りに大統領選挙の結果を確定したことで、政治情勢が和平プロセスの行程から逸脱するのを抑止する役割も果たした。この点で重要なのが、2011年3月30日の安保理決議1975において、バボを含む複数の幹部が「平和と和解ならびにUNOCIその他の国際的な主体の活動を妨害し、人権・国際人道法の深刻な違反を行う者」と名指しされ、制裁を発動されていたことである 14 。この制裁は資産凍結と海外渡航の禁止を内容とするものであって、バボら対象者の拘束を勧奨するものではなかった。だが、この制裁の発動は、和平プロセスに深く関与してきた国連が、もはやバボを和平の当事者としてではなく、和平の妨害者と認定する意思を端的に表明したものであった。この意味で、この制裁は、「バボ抜きの和平プロセス」を容認するものであり、UNOCIの軍事行動の結果としてバボが拘束されたとしても、そのことで和平プロセスが隘路に陥ることをあらかじめ防ぐものであったといえる。
本節ではコートジボワール内戦の前史を確認したのち、UNOCIの軍事行動の目的、経過、帰結をコートジボワールの和平プロセスとの関連で述べる。1960年の独立以来、サハラ以南アフリカにはまれな「安定と発展の代名詞」と評されてきたコートジボワールは、独立以来君臨したF・ウフェ=ボワニ(Félix Houphouët-Boigny)大統領の死(1993年)を契機に、政治的に不安定化するようになった。後継のコナン=ベディエ(Henri Konan Bédié)大統領は強権化を進め、最大のライバルであるワタラ(Alassane Dramane Ouattara)元首相に対して民族差別・排外主義を動員した執拗な弾圧を続けた。1999年12月に、待遇への不満を訴えた兵士反乱の収拾に失敗してベディエ政権が崩壊すると、ゲイ(Robert Guéi)元参謀総長を首班とする軍事政権が樹立された。翌2000年10月に実施された大統領選挙の際には、ゲイ首班による不正操作への抗議行動をきっかけに、数百人の死者を出す大規模な騒乱が発生した。その後、この選挙で当選したバボ(Laurent Gbagbo)大統領のもとで、主要政治家の対話再開と国民和解が進められたものの、2002年9月には、軍事政権の残存勢力を主体とした反乱軍の挙兵により、内戦が始まった。在留自国民保護を名目に介入したフランス軍の継続駐留によって、北部に拠点を置いた反乱軍の南進は抑止され、戦線は早期に膠着した。
本来の目的である政権奪取に失敗した反乱軍が和平を志向したこともあり、この内戦では2003年1月という比較的早い時期に和平合意(マルクーシ合意)が成立した。同時期に西アフリカ諸国経済共同体(Economic Community of West African States: ECOWAS)が軍事ミッションを派遣し、翌2004年4月にはこれを母体としてUNOCIが発足した 7 。これらの国際的な部隊の監視下で、大規模な武力衝突の再発はおおむね抑止されたものの、最初の数年間の和平プロセスは大きく停滞した。その主たる原因は、マルクーシ合意が定めた大統領権限の縮小に反発したバボ大統領が、非協力的な姿勢をとったことにある。転機となったのは、2007年3月の新しい和平合意(ワガドゥグ合意)で、これにより実権を回復した大統領は、和平プロセスに前向きな姿勢を示すようになった。以後、国土分断の解消、行政要員の再配置、武装解除・動員解除・(社会への)再統合(DDR)、選挙プロセスという重要な和平プログラムが進展し、2010年10月にようやく大統領選挙の実施にこぎ着けた。
和平プロセスの集大成としての重要な位置づけを帯びたこの大統領選挙では、まず2010年10月に第1回投票が実施され、過半数を獲得した候補者がいなかったため、同年11月に、上位を占めた2名——現職のバボと挑戦者のワタラ元首相——の間で決選投票が行われた。独立選挙管理委員会(Commission électorale indépendante: CEI。以下、「選管」とする)による開票で当選とされたのはワタラである。選管発表は、和平プロセス下での選挙に関するすべての認定権限を持つ国連事務総長特使から承認され 8 、アフリカ諸国からも一致して支持された。しかしバボは、選管発表を受け入れずに勝利宣言を行い、就任式と組閣を強行した 9 。これに対抗してワタラも就任式と組閣を行い、コートジボワールは「2人の大統領、2つの政府」が並び立つ状況に入った。バボはアフリカ諸国からの退陣要請を拒み、退陣を求める国内の運動を武力で弾圧した。AUによる調停が行き詰まった2011年3月半ばに、ワタラは大統領令を発出して新たな正規軍である「コートジボワール共和国軍」(Forces républicaines de Côte d’Ivoire: FRCI。以下、「ワタラ軍」とする)を創設し、3月29日にバボ打倒を目指した軍事行動を開始した 10 。
2011年3月30日に国連安保理は決議1975を採択し、国連憲章第7章に基づき、UNOCIが「差し迫った物理的暴力の危機に晒されている文民の保護」のために、「必要なすべての手段を用いる」権限を再確認し、全面的な支持を強調した 11 。「差し迫った物理的暴力の危機に晒されている文民の保護」という任務は、2004年のUNOCI派遣当初から定められていたものだが、今回これが再確認されたのは、退陣を拒むバボ大統領が、抗議行動を行う民間人や国連施設に対して重火器を使用するのをやめさせるためであった。この決議に則りUNOCIは、2011年4月4日と11日の2度にわたり、フランス軍の支援のもとにバボの軍事拠点に空爆を行い、戦車やロケットランチャーなどの重火器を破壊した。11日の空爆の直後にバボはワタラ軍によって逮捕された。これにより4カ月半にわたって続いた選挙後危機は終結した 12 。
(2)UNOCIの軍事行動の政治史上の意義
UNOCIの軍事行動の当時、バボは、国際的に完全に孤立しながらも政権を放棄する姿勢をまったくみせておらず、保有する重火器を使ってさらに抵抗を続けることは十分に予想できることであった 13 。したがって、UNOCIの軍事行動は、文民の保護という公式の任務に適合的なタイミングで行われたといえる。その一方、UNOCIの軍事行動が実施されたのは、「2人の大統領」の対立が軍事的対立へと転化し、事実上の内戦が展開されていた時点でもあった。この内戦は、2002年に始まった内戦の和平プロセスのなかに「入れ子」のように起こった新たな内戦であるが、2011年3月31日に最大都市アビジャンでの市街戦が始まったのち、ワタラ軍が独力でバボ逮捕に至らなかったことから10日あまりにわたり膠着状態が続き、この間、数百万のアビジャン住民が電気・水道などのライフラインを途絶される人道危機の中にあった。UNOCIの軍事行動は、この内戦の一方の当事者であるバボ側の軍事力を無力化したことで、結果的にこの膠着状態を打破した。すなわち、UNOCIはワタラを支持して参戦したわけではなかったのだが、その軍事行動のタイミングから、ワタラ側の軍事的勝利が決定づけられたのである。この意味でUNOCIは、コートジボワール政治史の帰趨を決定づける、政治的な役割を果たしたといえる。この点は、文民の保護ならびに「保護する責任」を理念とする軍事行動における「規範意識とその実行の齟齬」(清水 2011: 117)に関連して、コートジボワールの事例が提起する重要な論点であると考えられる。
同時に、UNOCIの軍事行動は、国際的に広く認められた選管発表の通りに大統領選挙の結果を確定したことで、政治情勢が和平プロセスの行程から逸脱するのを抑止する役割も果たした。この点で重要なのが、2011年3月30日の安保理決議1975において、バボを含む複数の幹部が「平和と和解ならびにUNOCIその他の国際的な主体の活動を妨害し、人権・国際人道法の深刻な違反を行う者」と名指しされ、制裁を発動されていたことである 14 。この制裁は資産凍結と海外渡航の禁止を内容とするものであって、バボら対象者の拘束を勧奨するものではなかった。だが、この制裁の発動は、和平プロセスに深く関与してきた国連が、もはやバボを和平の当事者としてではなく、和平の妨害者と認定する意思を端的に表明したものであった。この意味で、この制裁は、「バボ抜きの和平プロセス」を容認するものであり、UNOCIの軍事行動の結果としてバボが拘束されたとしても、そのことで和平プロセスが隘路に陥ることをあらかじめ防ぐものであったといえる。
4. コートジボワールにおける「保護する責任」の評価
(1)「大国の介入主義」か
コートジボワールで実施されたUNOCIの軍事行動は、「差し迫った物理的暴力の危機に晒されている文民の保護」のために「必要なすべての手段を用いる」という安保理決議に基づいて実施されたものであり、文民の保護を掲げる「保護する責任」の考えに則って行われた軍事行動だったといえる。本節では、このUNOCIの軍事行動において、「保護する責任」をめぐって提起されてきた問題が具体的にどのように現れたかを、大国の介入主義をめぐる問題と、アフリカ域外の主体による軍事行動の政治性をめぐる問題に焦点をあてて、検討してみたい。
まず、「保護する責任」に則る軍事行動が、大国の介入主義の性格を持ちかねないとする懸念についてみてみたい。UNOCIの軍事行動の場合に、「大国」として問題となるのは具体的にはフランスである。安保理決議1975は、フランスがイニシアチヴをとって採択が行われたものであり、フランスは周知のとおり安保理の常任理事国である。さらにフランスは、UNOCIの軍事行動に協力して空爆にも参加した。フランスはコートジボワールに多大な経済的な権益を有し、フランス軍の常駐基地を置いてもいる。紛争の早期終結がフランスにとって大きな利益であったことは間違いない。
大国の介入主義かどうかの判断に関わるアフリカ諸国の認識についてみると、まずAUは、選挙後危機の発生直後から、バボの勝利宣言の正当性を認めず、彼が政権の座にとどまっていることは非憲法的政権交代にあたるとして非難し、退陣勧告を出していた 15 。また、コートジボワールも加盟するECOWASは、AUと同じくバボの正当性を認めず、退陣勧告を出しただけでなく、自らが軍隊を派遣してバボの排除に乗り出す意志があることを早期から表明していた 16 。実際にECOWASは、AUによる調停が行き詰まった2011年3月に、ECOWASの部隊派遣の承認を求める提議を国連安保理に対して行っている 17 。
このようなアフリカ諸国の態度は、UNOCIが軍事行動を行うこと、またその帰結として当然予想されるバボの失脚を容認する環境を醸成したといえる。現に、その後もフランスの行動を介入主義として批判する意見は、失脚したバボ側の支持者からのものを除いて出されなかった。安保理での検討会合でも、UNOCIの軍事行動が結果的に政権交代をもたらしたことについては批判がなされたものの、フランスの行動を介入主義として批判する指摘はなかった 18 。今回のUNOCIの軍事行動に関しては、アフリカ諸国が介入主義として批判するような事態は起こってはいない。したがって、今回のUNOCIの軍事行動については、少なくとも現段階では大国の介入主義が批判される状況にはないことが確認できる。
(2)域外主体による軍事行動の持つ政治性
次に、アフリカ域外の主体による軍事行動の政治性に関わる問題についてみてみたい。UNOCIがバボ側の武力を完全に破壊した2011年4月11日に至るまでほぼ2週間のあいだ、コートジボワールの最大都市アビジャンは、バボ側とワタラ側が戦闘を続ける状態にあった。このなかで400万人あまりの同市の居住者は、停電、断水に苦しみ、生活必需品の調達もできずに家に閉じこもる状態を余儀なくされており、深刻な人道危機に陥っていた。この意味でUNOCIの軍事行動は、民生上の苦難の根本原因であった戦闘を終結させたところに大きな意義を持ったといえる。
しかしながら、アビジャン住民を危機的な状況に陥らせた原因は、そもそも交戦当事者であるバボ側、ワタラ側の双方にあった。「保護する責任」を行使する条件となる「国家当局が自国民を保護することに明らかに失敗している場合」に照らせば、自国民保護にあたるべき「国家当局」とは、政権に居座ったバボ側と、正統な政権として国際的に認定されたワタラ側の双方であったと考えることができる。この考えにしたがえば、文民の保護の実現には、バボ、ワタラ双方に働きかけて停戦を実現するという選択肢もあったことになる。だが、現実にはUNOCIの軍事行動は、双方に対してではなく、一方のバボ側のみを対象にして実施された。その結果としてワタラ政権の樹立に向けた流れが促進されたという意味で、UNOCIの軍事行動が重大な政治的帰結をもたらしたものであったことは間違いない。
実際のところ、決議1975が採択されたときの安保理の討議では、UNOCIの軍事行動によって結果的に政権交代がもたらされることへの危惧を表明する意見が出されていた。それは、国連PKOが「政権交代のエージェント」として行動したとなれば、それは明らかに安保理決議の定めを逸脱するものであり、中立性を保つべき国連PKOの活動に将来的に支障をもたらしかねないとする趣旨の批判であった 19 。UNOCIがバボ側の重火器を無力化する行動を取りながらも、バボの身柄拘束までは行わなかったのは、この批判を考慮した行為として解釈できるものである。とはいえ、UNOCIの軍事行動なしにはワタラ側がバボを拘束できていなかったのは客観状況として明らかであり、UNOCIの軍事行動が政権交代に深く関わるものであったことは否定しがたい。軍事行動ののちにおこなわれた安保理での検討会合でも、UNOCIがコートジボワールでの政権交代に事実上関与したことを問題視する意見が出されている 20 。UNOCIの軍事行動は、その帰結に照らして評価すれば、明白な政治性を持つものだったといえる。
域外主体による軍事行動の政治性をめぐっては、ここではもう一つ、個々の軍事行動の持つ対応能力に関連して浮上する問題を指摘しておきたい。「保護する責任」の考えに依拠した軍事行動は、保護されるべき対象に応じて際限なく大規模化できるものではない。安保理決議に根拠をもつ軍事行動の場合には、すでに展開している部隊の「活動能力と展開地域の範囲内で」これを行うとする旨が決議に明記されている。UNOCIの場合にも決議1975にこのことが明記されており、実際の軍事行動も、駐留拠点に近いアビジャンでのみで行われた。しかしながら、これとほぼ同じ時期に、コートジボワール西部では、主にワタラ軍によって深刻な人権侵害が行われていた 21 。この事実は、文民の保護を任務とする国連PKOが派遣されている国においても、展開地域と活動能力に応じて、対応可能な地域とそうでない地域の差が明確に表れることを示している。コートジボワールの場合には、その差は、ワタラ側の行為に対しては歯止めがなされず、バボ側に対しては強硬な軍事的攻撃がなされるという、強い政治的な意味あいを帯びた結果として表れることになった。ここから浮かびあがるのは、個々の軍事行動が持ちうる対応能力にはおのずから制約があるため軍事行動は結果的に選択的に行われることとなり、これによって、意図的なものではないにもかかわらず、そこに不可避的に政治的な意味が生じてしまうということである。「保護する責任」という理念は、そもそも普遍的な価値志向を持つものでありながら、実際の軍事行動に体現された時の姿は、不均質でまだら模様なものとなってしまうのである。
コートジボワールで実施されたUNOCIの軍事行動は、「差し迫った物理的暴力の危機に晒されている文民の保護」のために「必要なすべての手段を用いる」という安保理決議に基づいて実施されたものであり、文民の保護を掲げる「保護する責任」の考えに則って行われた軍事行動だったといえる。本節では、このUNOCIの軍事行動において、「保護する責任」をめぐって提起されてきた問題が具体的にどのように現れたかを、大国の介入主義をめぐる問題と、アフリカ域外の主体による軍事行動の政治性をめぐる問題に焦点をあてて、検討してみたい。
まず、「保護する責任」に則る軍事行動が、大国の介入主義の性格を持ちかねないとする懸念についてみてみたい。UNOCIの軍事行動の場合に、「大国」として問題となるのは具体的にはフランスである。安保理決議1975は、フランスがイニシアチヴをとって採択が行われたものであり、フランスは周知のとおり安保理の常任理事国である。さらにフランスは、UNOCIの軍事行動に協力して空爆にも参加した。フランスはコートジボワールに多大な経済的な権益を有し、フランス軍の常駐基地を置いてもいる。紛争の早期終結がフランスにとって大きな利益であったことは間違いない。
大国の介入主義かどうかの判断に関わるアフリカ諸国の認識についてみると、まずAUは、選挙後危機の発生直後から、バボの勝利宣言の正当性を認めず、彼が政権の座にとどまっていることは非憲法的政権交代にあたるとして非難し、退陣勧告を出していた 15 。また、コートジボワールも加盟するECOWASは、AUと同じくバボの正当性を認めず、退陣勧告を出しただけでなく、自らが軍隊を派遣してバボの排除に乗り出す意志があることを早期から表明していた 16 。実際にECOWASは、AUによる調停が行き詰まった2011年3月に、ECOWASの部隊派遣の承認を求める提議を国連安保理に対して行っている 17 。
このようなアフリカ諸国の態度は、UNOCIが軍事行動を行うこと、またその帰結として当然予想されるバボの失脚を容認する環境を醸成したといえる。現に、その後もフランスの行動を介入主義として批判する意見は、失脚したバボ側の支持者からのものを除いて出されなかった。安保理での検討会合でも、UNOCIの軍事行動が結果的に政権交代をもたらしたことについては批判がなされたものの、フランスの行動を介入主義として批判する指摘はなかった 18 。今回のUNOCIの軍事行動に関しては、アフリカ諸国が介入主義として批判するような事態は起こってはいない。したがって、今回のUNOCIの軍事行動については、少なくとも現段階では大国の介入主義が批判される状況にはないことが確認できる。
(2)域外主体による軍事行動の持つ政治性
次に、アフリカ域外の主体による軍事行動の政治性に関わる問題についてみてみたい。UNOCIがバボ側の武力を完全に破壊した2011年4月11日に至るまでほぼ2週間のあいだ、コートジボワールの最大都市アビジャンは、バボ側とワタラ側が戦闘を続ける状態にあった。このなかで400万人あまりの同市の居住者は、停電、断水に苦しみ、生活必需品の調達もできずに家に閉じこもる状態を余儀なくされており、深刻な人道危機に陥っていた。この意味でUNOCIの軍事行動は、民生上の苦難の根本原因であった戦闘を終結させたところに大きな意義を持ったといえる。
しかしながら、アビジャン住民を危機的な状況に陥らせた原因は、そもそも交戦当事者であるバボ側、ワタラ側の双方にあった。「保護する責任」を行使する条件となる「国家当局が自国民を保護することに明らかに失敗している場合」に照らせば、自国民保護にあたるべき「国家当局」とは、政権に居座ったバボ側と、正統な政権として国際的に認定されたワタラ側の双方であったと考えることができる。この考えにしたがえば、文民の保護の実現には、バボ、ワタラ双方に働きかけて停戦を実現するという選択肢もあったことになる。だが、現実にはUNOCIの軍事行動は、双方に対してではなく、一方のバボ側のみを対象にして実施された。その結果としてワタラ政権の樹立に向けた流れが促進されたという意味で、UNOCIの軍事行動が重大な政治的帰結をもたらしたものであったことは間違いない。
実際のところ、決議1975が採択されたときの安保理の討議では、UNOCIの軍事行動によって結果的に政権交代がもたらされることへの危惧を表明する意見が出されていた。それは、国連PKOが「政権交代のエージェント」として行動したとなれば、それは明らかに安保理決議の定めを逸脱するものであり、中立性を保つべき国連PKOの活動に将来的に支障をもたらしかねないとする趣旨の批判であった 19 。UNOCIがバボ側の重火器を無力化する行動を取りながらも、バボの身柄拘束までは行わなかったのは、この批判を考慮した行為として解釈できるものである。とはいえ、UNOCIの軍事行動なしにはワタラ側がバボを拘束できていなかったのは客観状況として明らかであり、UNOCIの軍事行動が政権交代に深く関わるものであったことは否定しがたい。軍事行動ののちにおこなわれた安保理での検討会合でも、UNOCIがコートジボワールでの政権交代に事実上関与したことを問題視する意見が出されている 20 。UNOCIの軍事行動は、その帰結に照らして評価すれば、明白な政治性を持つものだったといえる。
域外主体による軍事行動の政治性をめぐっては、ここではもう一つ、個々の軍事行動の持つ対応能力に関連して浮上する問題を指摘しておきたい。「保護する責任」の考えに依拠した軍事行動は、保護されるべき対象に応じて際限なく大規模化できるものではない。安保理決議に根拠をもつ軍事行動の場合には、すでに展開している部隊の「活動能力と展開地域の範囲内で」これを行うとする旨が決議に明記されている。UNOCIの場合にも決議1975にこのことが明記されており、実際の軍事行動も、駐留拠点に近いアビジャンでのみで行われた。しかしながら、これとほぼ同じ時期に、コートジボワール西部では、主にワタラ軍によって深刻な人権侵害が行われていた 21 。この事実は、文民の保護を任務とする国連PKOが派遣されている国においても、展開地域と活動能力に応じて、対応可能な地域とそうでない地域の差が明確に表れることを示している。コートジボワールの場合には、その差は、ワタラ側の行為に対しては歯止めがなされず、バボ側に対しては強硬な軍事的攻撃がなされるという、強い政治的な意味あいを帯びた結果として表れることになった。ここから浮かびあがるのは、個々の軍事行動が持ちうる対応能力にはおのずから制約があるため軍事行動は結果的に選択的に行われることとなり、これによって、意図的なものではないにもかかわらず、そこに不可避的に政治的な意味が生じてしまうということである。「保護する責任」という理念は、そもそも普遍的な価値志向を持つものでありながら、実際の軍事行動に体現された時の姿は、不均質でまだら模様なものとなってしまうのである。
結論
以上本稿では、2011年4月にUNOCIがコートジボワールで実施した軍事行動を取り上げ、文民の保護ないし「保護する責任」をめぐるこれまでの議論で浮上した論点に照らして、検証を行ってきた。本稿の考察からは、以下2つの結論を導き出すことができる。
まず第1の結論は、選挙結果を受諾せず政権の座に居座ったバボに対して、アフリカの地域機構(具体的にはAUとECOWAS)が独自に政治的圧力をかけたことが、UNOCIの軍事行動に一定の国際的な正統性を付与したという点である。ECOWASとAUが取ったこのような姿勢を追い風として、UNOCIは、軍事行動がもたらし得る政治的帰結に対して想定される批判に縛られることなく、行動を起こすことができた 22 。この意味でUNOCIの軍事行動は、UNOCI単独の行動というよりは、アフリカの地域機構からの間接的な授権も受けることで実現したものと評価できる。言い換えれば、UNOCIの軍事行動は、国連、AU、ECOWASの連携の上に成立しており、1990年代後半以降積み重ねられてきた「連携関係の強化」(滝澤2010)の所産といえる。今回のUNOCIの軍事行動は、アフリカの紛争解決・平和構築に関する試行錯誤の歴史のうえに成立したものなのである。
結論の第2は、UNOCIの軍事行動には、払拭しがたい政治性が見出される点である。バボ側の重火器を無力化しさえすれば、アビジャンでの戦闘状態を解消できるというのは、軍事作戦の構想としてはきわめて「効率的」であろうし、実際にそれによって多数のアビジャン市民が窮地を脱したことはたしかである。しかし、「保護する責任」の理念的な考えに立てば、「国家当局」として文民を保護する責任を有したのはバボ側とワタラ側の双方であった。バボ側だけを攻撃対象とするのは、「保護する責任」の考え方そのものから導き出されたものではない。ここには、文民の保護ないし「保護する責任」をめぐって指摘される、「規範意識とその実行の齟齬」(清水 2011: 117)が的確に合致する状況がみられる。UNOCIの軍事行動が政治性を持ったことは、軍事行動の政治的帰結に対してアフリカ諸国が広く支持を与えているという第1の結論で指摘した点とは、別の問題として考えておくべきであろう。「保護する責任」を掲げた軍事行動が政権交代という大きな転換をもたらした事例は、コートジボワールだけではなく、同時期のリビアでもみられたことであった。この2つの事例が示しているのは、「保護する責任」の考えが、強力な軍事力の行使を許す、じつに強力な「力」を備えていることである。この強大な「力」をどのように適切な管理するかは、今後も重要な課題となるであろう。
まず第1の結論は、選挙結果を受諾せず政権の座に居座ったバボに対して、アフリカの地域機構(具体的にはAUとECOWAS)が独自に政治的圧力をかけたことが、UNOCIの軍事行動に一定の国際的な正統性を付与したという点である。ECOWASとAUが取ったこのような姿勢を追い風として、UNOCIは、軍事行動がもたらし得る政治的帰結に対して想定される批判に縛られることなく、行動を起こすことができた 22 。この意味でUNOCIの軍事行動は、UNOCI単独の行動というよりは、アフリカの地域機構からの間接的な授権も受けることで実現したものと評価できる。言い換えれば、UNOCIの軍事行動は、国連、AU、ECOWASの連携の上に成立しており、1990年代後半以降積み重ねられてきた「連携関係の強化」(滝澤2010)の所産といえる。今回のUNOCIの軍事行動は、アフリカの紛争解決・平和構築に関する試行錯誤の歴史のうえに成立したものなのである。
結論の第2は、UNOCIの軍事行動には、払拭しがたい政治性が見出される点である。バボ側の重火器を無力化しさえすれば、アビジャンでの戦闘状態を解消できるというのは、軍事作戦の構想としてはきわめて「効率的」であろうし、実際にそれによって多数のアビジャン市民が窮地を脱したことはたしかである。しかし、「保護する責任」の理念的な考えに立てば、「国家当局」として文民を保護する責任を有したのはバボ側とワタラ側の双方であった。バボ側だけを攻撃対象とするのは、「保護する責任」の考え方そのものから導き出されたものではない。ここには、文民の保護ないし「保護する責任」をめぐって指摘される、「規範意識とその実行の齟齬」(清水 2011: 117)が的確に合致する状況がみられる。UNOCIの軍事行動が政治性を持ったことは、軍事行動の政治的帰結に対してアフリカ諸国が広く支持を与えているという第1の結論で指摘した点とは、別の問題として考えておくべきであろう。「保護する責任」を掲げた軍事行動が政権交代という大きな転換をもたらした事例は、コートジボワールだけではなく、同時期のリビアでもみられたことであった。この2つの事例が示しているのは、「保護する責任」の考えが、強力な軍事力の行使を許す、じつに強力な「力」を備えていることである。この強大な「力」をどのように適切な管理するかは、今後も重要な課題となるであろう。
参考文献
〈日本語文献〉
井上実佳[2011]「アフリカの安全保障と国連——国連平和維持活動(PKO)における地域機構との関係を中心に——」日本国際連合学会編『(「国連研究」第12号)安全保障をめぐる地域と国連』pp.17-40。
川端正久[2010]「アフリカにおける紛争解決と安全保障」川端正久・武内進一・落合雄彦編『紛争解決——アフリカの経験と展望——』ミネルヴァ書房 pp.3-35。
佐藤 章[2011]「コートジボワールの選挙後紛争とワタラ新政権の課題」『アジ研 ワールド・トレンド』第193号 pp.48-57。
清水奈名子[2011]『冷戦後の国連安全保障体制と文民の保護——多主体間主義による規範的秩序の模索——』日本経済評論社。
滝澤美佐子[2006]「人間の安全保障と国際介入——破綻国家ソマリアの事例から——」(望月克哉編『人間の安全保障の射程』アジア経済研究所 pp.108-149)。
——[2010]「紛争解決における国連とアフリカの地域機構」(川端正久・武内進一・落合雄彦編『紛争解決——アフリカの経験と展望——』ミネルヴァ書房 pp.169-194)。
武内進一[2000]「アフリカの紛争——その今日的特質についての考察——」(武内進一編『現代アフリカの紛争——歴史と主体——』アジア経済研究所 pp.3-52)。
——[2008]「アフリカの紛争と国際社会」(武内進一編『戦争と平和の間——紛争勃発後のアフリカと国際社会——』アジア経済研究所 pp.3-56)。
——[2009]『現代アフリカの紛争と国家——ポストコロニアル家産制国家とルワンダ・ジェノサイド——』明石書店。
〈外国語文献〉
ISS (Institute for Security Studies)[2011]“Country Analysis: Côte d’Ivoire Update,” Peace and Security Council Report , No.21, April, pp.7-12.
Murithi, Tim[2007]“The Responsibility to Protect, As Enshrined in Article 4 of the Constitutive Act of the African Union,” African Security Review , 16(3), pp.14-24.
Williams, Paul D.[2007]“From Non-intervention to Non-indifference: The Origins and Development of the African Union’s Security Culture,” African Affairs , 106/423, pp.253-279.
〈ECOWAS関連文章・資料〉
N° 193/2010, 24 décembre 2010 (Abuja - Nigeria), Session extraordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement sur la Côte d’Ivoire, Communiqué final.
N° 043/2011, 25 March 2011 (Abuja - Nigeria) Resolution A/RES.1/03/11 of the Authority of Heads of State and Government of ECOWAS on the Situation in Côte d’Ivoire.
井上実佳[2011]「アフリカの安全保障と国連——国連平和維持活動(PKO)における地域機構との関係を中心に——」日本国際連合学会編『(「国連研究」第12号)安全保障をめぐる地域と国連』pp.17-40。
川端正久[2010]「アフリカにおける紛争解決と安全保障」川端正久・武内進一・落合雄彦編『紛争解決——アフリカの経験と展望——』ミネルヴァ書房 pp.3-35。
佐藤 章[2011]「コートジボワールの選挙後紛争とワタラ新政権の課題」『アジ研 ワールド・トレンド』第193号 pp.48-57。
清水奈名子[2011]『冷戦後の国連安全保障体制と文民の保護——多主体間主義による規範的秩序の模索——』日本経済評論社。
滝澤美佐子[2006]「人間の安全保障と国際介入——破綻国家ソマリアの事例から——」(望月克哉編『人間の安全保障の射程』アジア経済研究所 pp.108-149)。
——[2010]「紛争解決における国連とアフリカの地域機構」(川端正久・武内進一・落合雄彦編『紛争解決——アフリカの経験と展望——』ミネルヴァ書房 pp.169-194)。
武内進一[2000]「アフリカの紛争——その今日的特質についての考察——」(武内進一編『現代アフリカの紛争——歴史と主体——』アジア経済研究所 pp.3-52)。
——[2008]「アフリカの紛争と国際社会」(武内進一編『戦争と平和の間——紛争勃発後のアフリカと国際社会——』アジア経済研究所 pp.3-56)。
——[2009]『現代アフリカの紛争と国家——ポストコロニアル家産制国家とルワンダ・ジェノサイド——』明石書店。
〈外国語文献〉
ISS (Institute for Security Studies)[2011]“Country Analysis: Côte d’Ivoire Update,” Peace and Security Council Report , No.21, April, pp.7-12.
Murithi, Tim[2007]“The Responsibility to Protect, As Enshrined in Article 4 of the Constitutive Act of the African Union,” African Security Review , 16(3), pp.14-24.
Williams, Paul D.[2007]“From Non-intervention to Non-indifference: The Origins and Development of the African Union’s Security Culture,” African Affairs , 106/423, pp.253-279.
〈ECOWAS関連文章・資料〉
N° 193/2010, 24 décembre 2010 (Abuja - Nigeria), Session extraordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement sur la Côte d’Ivoire, Communiqué final.
N° 043/2011, 25 March 2011 (Abuja - Nigeria) Resolution A/RES.1/03/11 of the Authority of Heads of State and Government of ECOWAS on the Situation in Côte d’Ivoire.
(さとう・あきら/アジア経済研究所)
脚 注
- An Agenda for Peace: Preventing Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping , Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992, A/47/277-S/24111 (17 June 1992).
- 1997年に中央アフリカ共和国に派遣されたバンギ協定監視アフリカ・ミッション(Mission interafricaine de la surveillance des Accords de Bangui: MISAB)がこの例である。
- AU制定法成立にあわせて2000年7月にOAUが採択した宣言AHG/Decl.5において定められている。
- これはAUの制定法に明記された(Constitutive Act of African Union, Article 4(h))。AU制定法が成立した2000年7月は、「保護する責任」という言葉そのものがまだ使われはじめていない時期であるが、AU制定法に明記された内容は、「保護する責任」の考えと共通したものである。「保護する責任」という言葉の登場については、次項で述べる。
- AUの安全保障面での取り組みに関しては、川端[2010]、井上[2011]を参照。
- この文での引用は同サミット成果文書の第138段落ならびに第139段落の文言である。訳文は清水[2011: 108]に基づく。
- ECOWASの軍事ミッションとフランス軍に対しては、2003年2月4日の安保理決議1464(S/RES/1464)により、国連憲章第7章下での活動が認められた。UNOCIの創設は、2004年2月27日の安保理決議1528(S/RES/1528)によって決定され、同じく国連憲章第7章下での活動権限が与えられた。
- 国連事務総長特使の持つこの権限は、2007年7月16日付け安保理決議1765で明記されたもので(S/RES/1765, para.6)、和平プロセスのすべての当事者を拘束するものである。
- バボは選管発表を不服とし、投票に不正があったとして憲法裁判所に提訴した。憲法裁判所は、コートジボワール国内法において選挙結果を最終的に承認する権限を有する機関である。憲法裁判所はバボの訴えに沿い、複数の県での投票(およそ数十万票)をすべて無効とする判断を示し、無効分を控除した得票ではバボが上回っているとして、バボの当選を発表した。しかし、法手続きのうえでは、憲法裁判所が投票の無効を判断した場合には再選挙が実施されなければならず、これを抜きにして当選を発表した憲法裁判所の決定は法的根拠を欠くものである。詳しくは、佐藤[2011]を参照。
- FRCIは旧反乱軍を主体に構成された。
- S/RES/1975, para.6.
- その後、ワタラは2011年5月6日に改めて就任宣誓を行い、5月21日には国連事務総長らも臨席して、首都ヤムスクロで大規模な就任式典が挙行された。ワタラ軍によるバボ派残党の掃討作戦も5月中に完了した。6月1日の組閣によってワタラ政権は本格的に始動し、現在に至っている。なお、2011年11月23日に国際刑事裁判所(International Criminal Court: ICC)は、バボ前大統領に対して、選挙後危機の期間中における、「政府治安部隊ならびにバボ派民兵と傭兵によって、アビジャンをはじめとする国内各地でなされた、殺人・レイプ等の性的暴力・処刑・その他の非人間的行為からなる、人道に対する罪の間接的共同遂行者としての個人的責任」の容疑で逮捕状を発行した。現在、バボはハーグに収監されている。
- たとえば、2011年4月7日にはバボ側の傭兵がアビジャンの日本大使公邸を襲撃した。同公邸はバボが潜伏した大統領公邸に近く、バボ側の狙いは防御拠点の構築にあったと考えられる。在留する外交官を危険に晒してでも抵抗を続けるバボ側の強硬姿勢を端的に示す事件である。
- S/RES/1975, para.12, Annex I.
- AUの平和安全保障理事会(PSC)は2010年12月4日の会合で、選管の開票結果を受け入れないバボ大統領の行為が「非憲法的政権交代」に該当するとの認識をいち早く示し、AU加盟国としての資格停止措置と非難声明を行った(PSC/PR/BR (CCLI), 4 December 2010 (African Union Peace and Security Council, 251ST Meeting, Press Statement))。
- ECOWAS, N° 193/2010, 24 décembre 2010, para.6, 10. 実際にECOWASはこの最終声明にしたがい、2010年12月28日と2011年1月18日に、加盟国の参謀総長会議を開催して軍事行動の計画と兵站・展開の準備について議論しており、そこでブルキナファソ、セネガル、ナイジェリアなどが兵員拠出の意思を表明している(ISS 2011: 10)。
- ECOWAS, No 043/2011, 25 March 2011, Resolution A/RES.1/03/11.
- Security Council, SC/10223, 13 April 2011.
- Security Council, SC/10215, 30 March 2011.
- Security Council, SC/10223, 13 April 2011.
- 西部の都市デュエクエ(Duékoué)周辺で、少なくとも1500人がワタラ軍によって殺害されたことが報告されている。この当時、西部にはUNOCIの大規模な部隊は駐留していなかった。西部での事件に関与した責任者の処罰は、国連などからワタラ大統領に対して強く要請されてきている。ワタラ大統領は対応を約束しているものの、具体的な動きは進んでいるとはいえず、そのことでさらにワタラに対して国際的な批判が向けられている。ワタラ大統領がこの問題への対応に及び腰なのは、ワタラ軍が自らにとって重要な政権基盤であることによっている。この点に関しては佐藤[2011]で詳細に論じた。
- この点は、フランスが、1994年のルワンダでの軍事行動ののち、旧政権派幹部の逃亡という政治的帰結を招いたことで国際的な批判を浴びたことと好対照をなす。