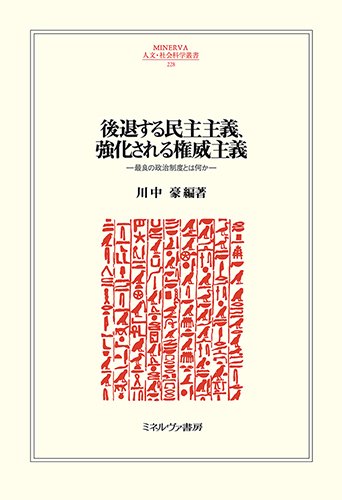IDEスクエア
コラム
第4回 「世界最大の民主主義国」インドの不都合な真実(前編)
PDF版ダウンロードページ:http://hdl.handle.net/2344/00050467
2018年8月
書籍紹介
ヴィカース・スワループ『6人の容疑者 (上)(下)』(子安亜弥訳、RHブックス・プラス、2012年)
「実話系映画」への違和感
実話であることを売りにした映画というのを、この頃よく見かける。しかし、作品の内容、出演者の顔ぶれ、日本映画か外国映画かなどにかかわりなく、あまり観ようという気が起こらない。
それはなぜかというと、一つには、「感動の実話」とか「衝撃の実話」とかといった、実話系映画におなじみの過剰で陳腐な宣伝文句に鼻白んでしまうからである。そもそも、感動したり衝撃を受けたりするかどうかは観る側の勝手であり、映画を観る前から感動やら衝撃やらを一方的に押し付けられたのでは、たまったものではないと軽い反感さえ覚えてしまう。ところが、この手のフレーズは実話系映画の宣伝でよく使われるだけでなく、最近になって活躍の場をさらに広げており、「奇跡の実話」や「真実の物語」という副題の付いた日本映画も公開されている。
実話であることを売りにした映画に二の足を踏んでしまうのには、もう一つ理由がある。映画の内容のどこまでが事実に即していて、どこからが脚色(場合によっては、完全なる創作)なのかがどうしても気になり、モヤモヤした気持ちのまま映画を観なければならないからである。例えば、主人公を聖人君子のように過度に美化したり、実在しない人物を悪役として登場させたりして、単純極まりない勧善懲悪のストーリーに仕立てているのではないかとか、これほど極端ではないにしても、特定の視点から偏った描き方をしているのではないかとか、もっと卑近な例をあげれば、映画のなかで俳優が演じる登場人物の方が実在の人物よりもはるかに容姿端麗なのではないかとか、引っかかるポイントはいろいろとある。
このように書くと、私がフィクションの要素やフィクションという形態そのものを毛嫌いしていると誤解する読者がいるかもしれない。しかし、すぐ後で述べるように、そんなことはまったくない。ここで私が問題にしているのは、作品にフィクションの要素を盛り込みつつ、事実と脚色の境界を曖昧にしておきながら、その一方で、実話であることを売りにするという、実話系映画の作品としての在り方と営業戦略であり、それにどうしても違和感を覚えてしまうのである。
現実と虚構のあいだ
事実に基づいて現実を映し出さなければならない(ということになっている)ドキュメンタリー映画に対して、製作者が自分の主張に都合のいいように現実をねじ曲げて描いていると批判の声が上がることは少なくない。また、新聞やテレビなどのメディアの報道にも、同様の批判が向けられることがある1 。
この点を踏まえれば、事実と脚色の境界が曖昧になりがちな実話系映画では、同様の問題はさらに起こりやすいと考えるのが自然である。さらに、事実誤認ではないかという批判が出た場合、「いやぁ、あの部分は脚色なんですよ」と逃げを打つことができるという意味でも、実話系映画にはより大きな「自由度」があるといえるだろう。そのため、実話であると声高に宣伝しておきながら、脚色という小さな嘘を積み重ねた結果、現実から乖離したストーリー――つまり、感動的で衝撃的で奇跡的な真実の物語!――という大きな嘘をついているのではないかとついつい疑ってしまいたくなる。
これはたとえていうなら、天然果汁ジュースであると謳っているのに、実際には果汁がほんの少ししか入っていない清涼飲料水を飲まされているようなものである。ちなみに、清涼飲料水等については、果汁または果肉の使用量に応じて、商品名、パッケージ、記載方法に関する規定が設けられており、このような誤解を招く表記は日本では違法である(詳しくは、消費者庁のホームページの「無果汁の清涼飲料水等についての表示」を参照)。一方、実話であると称する映画について、作品内容の「実話度」に応じて同様の規制が設けられているという話は、寡聞にして知らない。
現実を浮き彫りにする虚構の物語
実話系映画にフィクションの要素が少なからず盛り込まれているように、完全なフィクションであると自ら称しているストーリーにも、程度の差こそあれ、現実を反映している部分が必ずといっていいほどある。それは、誰もが知っているような実際の出来事や実在する人物を作品のなかに取り入れるというだけでなく、ストーリーの作り手本人の個人的体験を下敷きにしたり、日常生活のなかで実際に接した人たちを登場人物の造形に利用したりと実に様々である2 。
そして、このような現実の要素を巧みに換骨奪胎しながら、想像力を働かせて自由に――時には、実際にはありえない超現実的な描写を取り入れつつ――ストーリーを展開できるというフィクションの利点が十分に活かされた時、虚構の物語であるはずのフィクションが、私たちの頭の中にある現実のイメージよりも現実味を帯びるという、一見すると奇妙なことが起こりえる 3。つまり、フィクションというのは、虚構の物語であると同時に現実の物語でもあり、世の中の有り様やそこに生きる人々の姿を鮮やかに浮かび上がらせることができるのである。
その具体例として、現代のインドを舞台にした、『6人の容疑者』という小説を取り上げることにしよう。特に、小説というフィクションのなかに現実の要素がどのように取り入れられ、それがいかにリアリティを生み出しているかという点に焦点を当てる4 。
ちなみに、著者のヴィカース・スワループの本業は作家ではなく外交官であり、数ヶ国での勤務の後、在大阪インド総領事、外務省報道官を経て、2017年からは大使としてカナダに赴任している。デビュー作の『ぼくと1ルピーの神様』(子安亜弥訳、RHブックス・プラス、2009年)は、小説それ自身としてよりも、大ヒット映画『スラムドッグ$ミリオネア』の原作としてむしろよく知られているといってよいだろう(ただし、映画には原作の小説とは異なる点がある)。

By Vikas Swarup (Vikas Swarup) [Public domain], via Wikimedia Commons
『6人の容疑者』は、スワループにとって2作目の長編小説である。著者のような立場にある人が、完全なるフィクションとはいえ、これほど赤裸々な内容の本を出版して大丈夫なのかと心配になるほど、現代のインドが抱える様々な社会問題を抉り出している。それでいて、風刺とユーモアというスパイスが随所にほどよく効いていて、エンターテイメントとしても文句のつけようのない見事な小説である。
残念ながら、2012年12月に出版元が破産したため、『6人の容疑者』は『ぼくと1ルピーの神様』とともに現在絶版になっている。ヘイト・スピーチまがいの本や「日本はこんなにスゴイ(と外国人もいっている)!」と何の臆面もなく連呼しまくる本が堂々と書店に並ぶ一方で、こんなに面白い小説(日本語訳も非常に優れている)が絶版のままになっているという現状には、ただ呆然とするばかりである。果たして悪いのは、出版社なのか、書店なのか、読者なのか……。
著者プロフィール
湊一樹(みなとかずき)。アジア経済研究所地域研究センター研究員。専門は南アジアの政治経済。最近の著作に、「非政党選挙管理政府制度と政治対立――バングラデシュにおける民主主義の不安定性」(川中豪編著『後退する民主主義、強化される権威主義』ミネルヴァ書房、2018年)がある。
注
- ドキュメンタリー映画に対するこのような批判の例として、小川さやか「批評:ドキュメンタリー映画『ダーウィンの悪夢』の舞台から」(『アフリカレポート』No.45、44-48ページ、2007年)、「イルカ漁批判の映画『ザ・コーヴ』、どう評価? 『有益』『魅力ない』賛否くっきり」(日本経済新聞電子版、2010年7月5日)を参照。また、メディアの報道に対する批判の例として、地下鉄サリン事件をめぐる報道が善悪二元論的な単純化された構図でなされていたと指摘する、村上春樹『アンダーグラウンド』(講談社文庫、1999年)を参照。
- 一例をあげると、現代中国を代表する作家の一人である余華(ユイ・ホア)のエッセイ集『ほんとうの中国の話をしよう』(飯塚容訳、河出文庫、2017年)を読むと、小説『兄弟(上)(下)』(泉京鹿訳、文春文庫、2010年)には、文化大革命から改革開放という激動の時代を経てきた作者の個人的体験がいろいろな場面で活かされていることがわかる。
- 超現実的な描写によるリアリティの追及という点については、ノーベル文学賞の有力候補と目されている閻連科(イエン・リエンコー)の小説『炸裂志』(泉京鹿訳、河出書房新社、2016年)と同書に収められている「神実主義とは何か――外国語版あとがき」を参照。また、「過酷な現実見つめ、物語紡ぐ 中国人作家2氏に聞く」(日本経済新聞夕刊、2017年12月19日)も参照。
- フィクションでありながら、インドの現実を鋭く描写している映画も数多くある。昨年の夏に日本でも公開された、『裁き』という映画はその一例である。この映画については、大場正明「インドの理不尽な裁判を舞台にインドの分断を描く『裁き』」(『ニューズウィーク日本版』ウェブ版、2017年7月7日)を参照。また、『裁き』のストーリーのなかで重要な位置づけにある、手作業で汚物処理に従事する人たち(「指定カースト」と呼ばれる旧不可触民)の現状については、Sheeva Dubey and Dhamma Darshan Nigam (2018) "Seven Manual Scavengers Died in Seven Days. Why Is There Still Silence?" The Wire, 9 January 2018を参照。
- 第1回 韓流アイドルは今日も全国を走る
- 第2回 リメイク版「101回目のプロポーズ」にみる中国結婚事情
- 第3回 抹茶が結びつける日台の縁
- 第5回 「世界最大の民主主義国」インドの不都合な真実(後編)
- 第4回 「世界最大の民主主義国」インドの不都合な真実(前編)
- 第6回 第90回アカデミー賞授賞式とベトナム女優
- 第7回 ベトナムにおける映画作りの現実――『草原に黄色い花を見つける』の成功によせて
- 第8回 韓国IMF危機の「リアル」――映画『国家不渡りの日』
- 第9回 いま、大地の子たちが伝えてくれること――一心とビクトルの物語
- 第10回 ベトナム映画「子を背負う父」を観て
- 第11回 経済学者松原隆一郎とその祖父――大正・昭和を駆けた、ある起業家の生涯をたどって
- 第12回 「匈奴ロック」がやってくるヨーウェ、ヨーウェ、ヨー!――ロックバンドThe Huが表象するモンゴル
- 第13回 『梨泰院クラス』の復讐法にみる韓国株式会社の現在
- 第14回 映画『ベトナムを懐う』を思う――TVニュースのある報道を知って――
- 第15回 ベトナムの女性トップ水泳選手――東京五輪アスリート候補の闘い
- 第16回 テレビドラマ「愛の不時着」の背景
- 第17回 「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」考――日本企業と台湾企業が手を組んで生み出した新しいエンターテイメント
- 第18回 世界を魅了するカザフスタンの美声――ディマシュ・クダイベルゲン
- 第19回 新型コロナ感染症禍とベトナムの芸能人